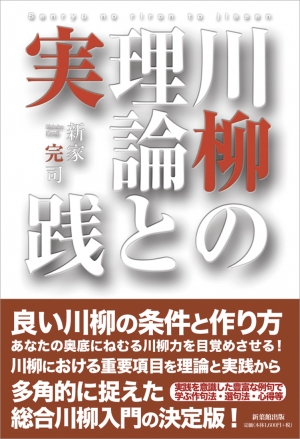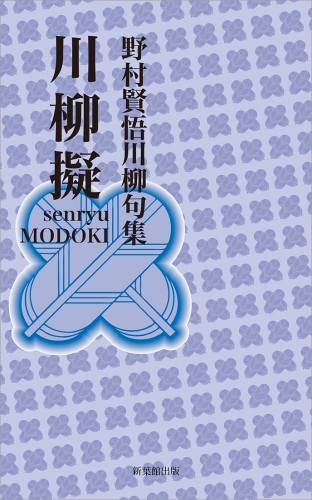たまには、しっとりと古典もいいかも。むずかしいことはさておき、徒然草の現代語訳を和歌山弁で少々やっちゃいました。第十二段、第百七段、第百十二段、第百十六段、第百十七段から、一部。ちなみに徒然草は第二百四十三段まであるのね。兼好法師という人は少々変わっていて、ウガチの眼がそこここに顔をだす。いま生きておられたら、かれに川柳作家になることを強くおススメします。(第百七段はオモシロイので、ここだけ原文付き。たいへんな怨み節?、兼好はよほど女性にひどい目に遭ったのね、笑。)
たまには、しっとりと古典もいいかも。むずかしいことはさておき、徒然草の現代語訳を和歌山弁で少々やっちゃいました。第十二段、第百七段、第百十二段、第百十六段、第百十七段から、一部。ちなみに徒然草は第二百四十三段まであるのね。兼好法師という人は少々変わっていて、ウガチの眼がそこここに顔をだす。いま生きておられたら、かれに川柳作家になることを強くおススメします。(第百七段はオモシロイので、ここだけ原文付き。たいへんな怨み節?、兼好はよほど女性にひどい目に遭ったのね、笑。)
…‥‥‥‥‥‥………‥‥‥‥‥‥………‥‥‥‥‥‥………‥‥‥‥‥‥……
第12段
「よう気の合う人とこころを開いて話をするのはうれしいことやが。そうでない相手と話をするのはひとりぼっちでいるのとおなじことやん」
第107段
(原文)
かく人にはぢらるる女、如何ばかりいみじきものぞと思ふに、女の性(しょう)は皆ひがめり。人我(にんが)の相深く、貪欲(とんよく)甚だしく、ものの理(ことわり)を知らず、ただ、迷ひの方に心も早く移り、詞(ことば)も巧みに、苦しからぬ事をも問ふ時は言はず、用意あるかと見れば、又あさましき事まで、問はず語りに言ひ出(いだ)す。深くたばかり飾れる事は、男の知恵にもまさりたるかと思へば、その事、あとよりあらはるるを知らず。すなほならずして拙きものは女なり。その心に随ひてよく思はれん事は、心憂かるべし。されば、何かは女のはづかしからん。もし賢女(けんぢょ)あらば、それもものうとく、すさまじかりなん。ただ迷ひを主(あるじ)として、かれに随ふ時、やさしくも、おもしろくも覚ゆべき事なり。
「こんなふうに男に強く意識されている女という存在、どんだけええもんかと思うと、(実際はまるで逆)女の本性はゆがみきっとるねん。利己主義で、欲望が激しく、ものの道理をわきまえへんし、やたらと悟りの妨げとなるものに飛びついて、口が達者で、(そのくせ)とくに遠慮のいらんことでもこちらが聞くと黙り込む。そこで、何か気配りしているのかと思うと、とんでもないことまで聞きもしないのに自分からしゃべりだすし。本心を隠し外見を飾ることでは、男よりもはるかに頭が回るけど、じきにばれてしまうことに気づかない。(ほんまに女というもんは)素直さに欠けた、くだらない存在よ。(だから)そんな女の心に合わせてよく思われようとすれば、うんざりするのは当然や。なんで女なんかに気ぃ遣う必要などあるだろう。もし賢女というもんがいるとしたら、(逆に)女らしさがなくて、ぞっとするに違いないねん。(女というもんは)その色香に支配されて彼女の言いなりになっているときだけ、優しくて、魅力ある存在に思えてくるようなシロモンに過ぎん」
第112段
「日暮れて途遠しやねん。俗世のことにかまけんとこ。義理なんか立てようと思ったらあかん。俗縁を断ち切るんがええ。薄情とか無情とか言われてもかまへん。あれもせなこれもせなと気に病むのは、ええことない」
第116段
「そうかい。女の子の名前は千草とつけたんかい。ええ名前やんか。奇をてらわずあっさりしていて。この頃はなんでもかんでもむずかしい名前をつければええと思ってる人が多いからなあ。この傾向は、才智を世間に顕示してるみたいでほんまにいやみなもんやで」
第117段
「ともだちとするに悪いもんが七つあるんよ。身分が高く尊い人、若い人、無病でからだの強い人、酒好きの人、勇猛な武士、うそをつく人、欲の深い人や。反対にええ友には三つある。モノをくれるともだち、医者、それと知恵のあるともだちや」
 Loading...
Loading...