 俳句では、〈二物衝撃(取り合わせ)〉はよく言われること。たとえば、羊羹をオシャレな洋皿にのせて出されると、視覚的に羊羹にいつもとはちがう新しいあじわいが生まれる(ような気がする)。取り合わせることによって、異なったあじわいを引きだすことができるのである。俳句も、一句の中に二つの事物(主に季語と、まったく異なったモノやコト)を取り合わせることで新しい情趣を生みだすことができる。その効果を、〈二物衝撃〉という。
俳句では、〈二物衝撃(取り合わせ)〉はよく言われること。たとえば、羊羹をオシャレな洋皿にのせて出されると、視覚的に羊羹にいつもとはちがう新しいあじわいが生まれる(ような気がする)。取り合わせることによって、異なったあじわいを引きだすことができるのである。俳句も、一句の中に二つの事物(主に季語と、まったく異なったモノやコト)を取り合わせることで新しい情趣を生みだすことができる。その効果を、〈二物衝撃〉という。
〈二物衝撃〉の句は比較的詠みやすいので、季語をいろいろな事物と取り合わせて妙味を引きだすことが以前から試みられてきた。衝撃ということばが示すように、意外な取り合わせに読者が驚きながらも得心したとき、季語に新たな情趣が加わる。情景の提示や補完が季語の(カビの生えたような)情趣の範囲内での作句であるのに対し、〈二物衝撃〉はそれらのありきたりを超え、さらに発展・展開させていくものといえる。(対象となる季語だけを見つめ、その状態を詠んだ俳句は〈一物仕立て(いちぶつじたて・いちもつじたて)〉と言われる。)
つぎに、〈二物衝迫〉について。このことばをはじめて目にしたのは、故・尾藤三柳師のご著書だったのではないか。衝迫の直截の意味は、〚心の中にわきおこる強い欲求。衝動〛。現代川柳では、この技法で深層心理や心象までにんげんの内面に迫っている。この技法の中の暗喩をどう読みとるかが、現代川柳をあじわううえで重要なことになる。
尾藤三柳師は俳句の〈二物衝撃〉を〈二物衝迫(川柳)〉と言い換えられたようだが、その理由。もう分かっていただけたと思うが、〈二物衝撃〉は一方に季語があることが前提。川柳では季語はいらない(季語とは言わない)ので、技法としては似ているがそのまま俳句の〈二物衝撃〉ということばをあてはめるのはおかしいということ。ゆえに師は〈二物衝迫〉とされたのだろう。
 Loading...
Loading...























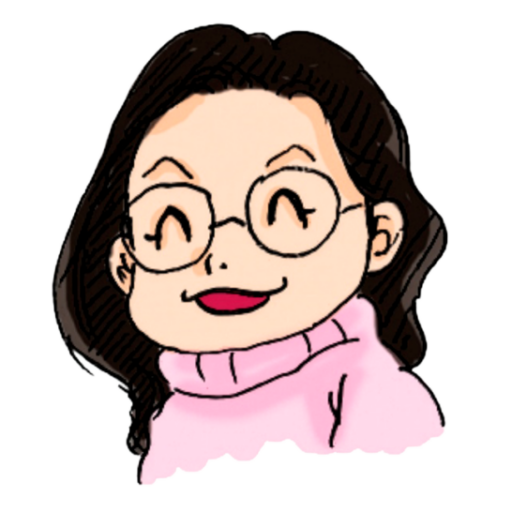



















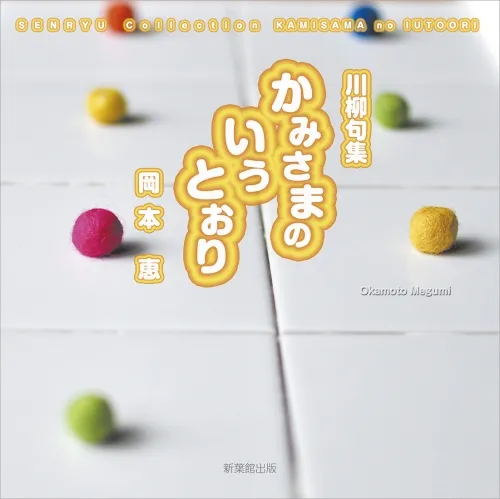
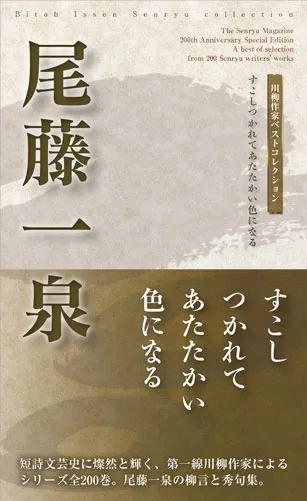
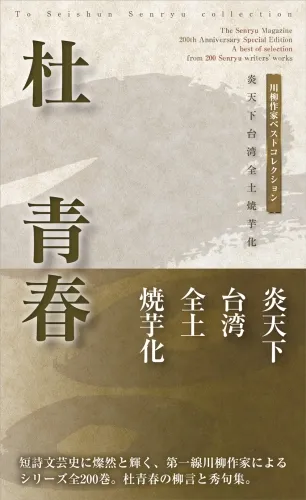
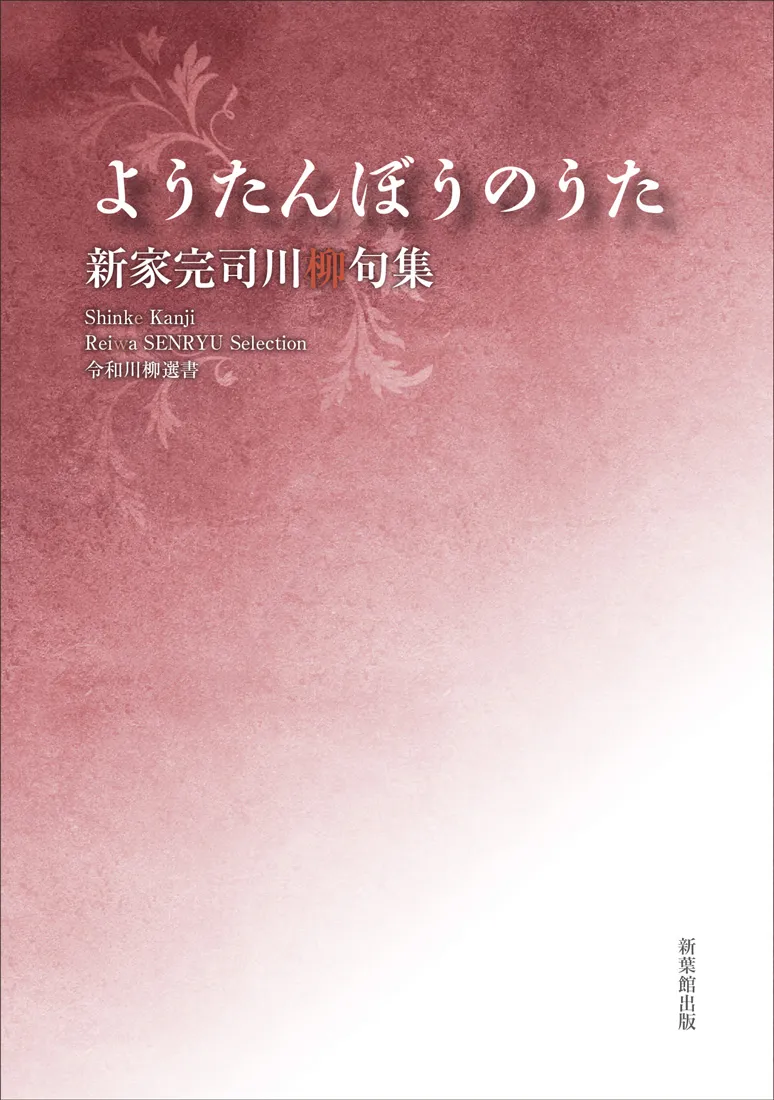
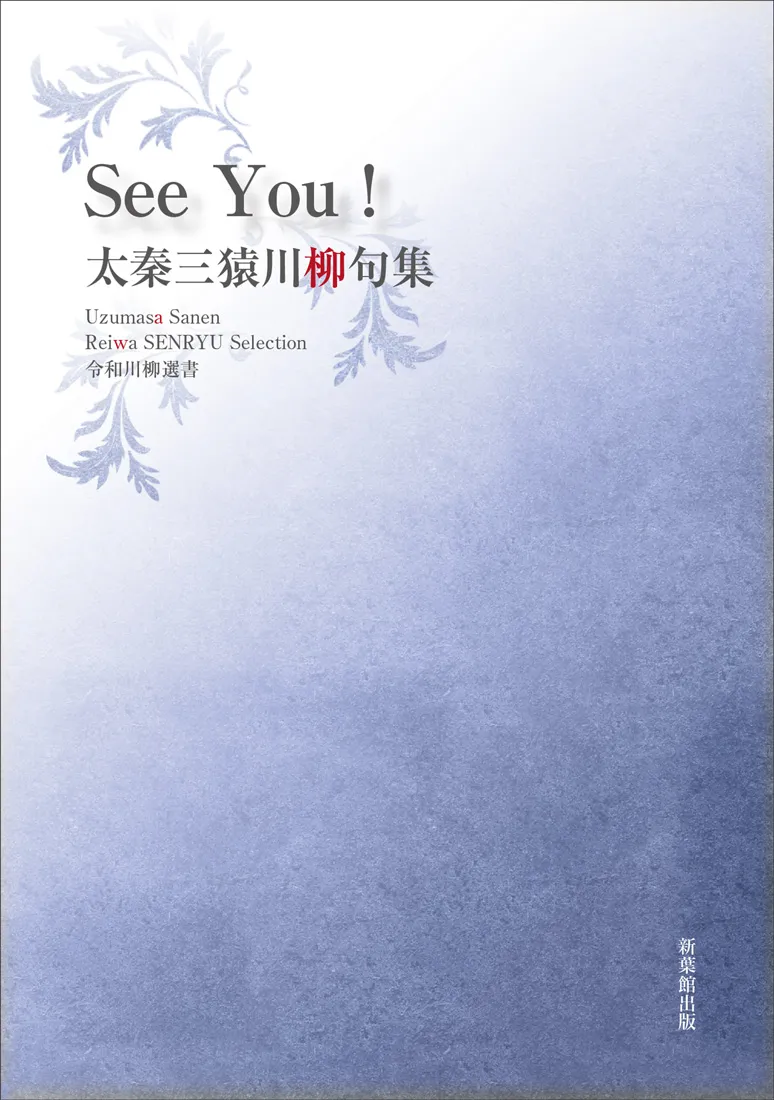
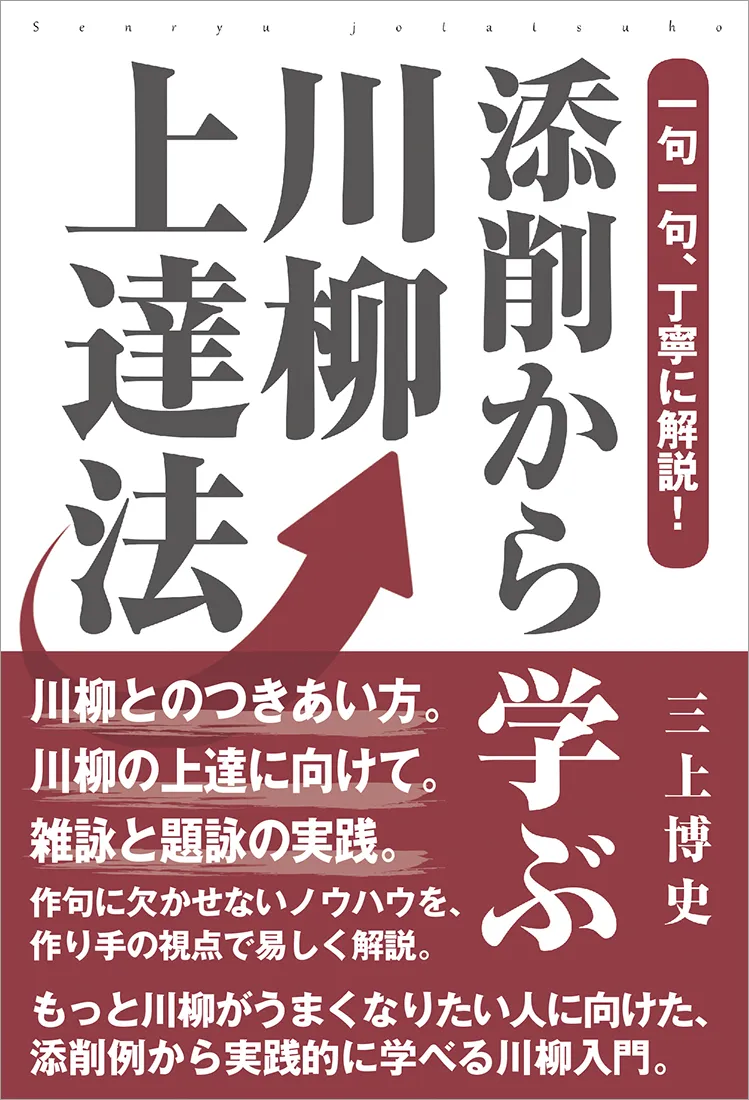
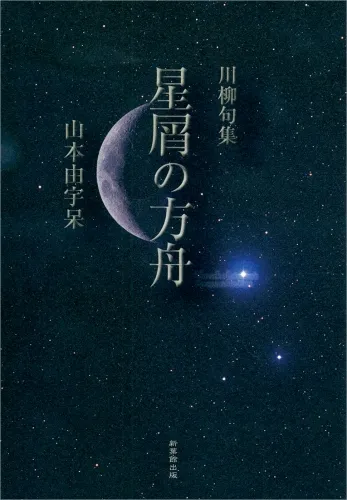
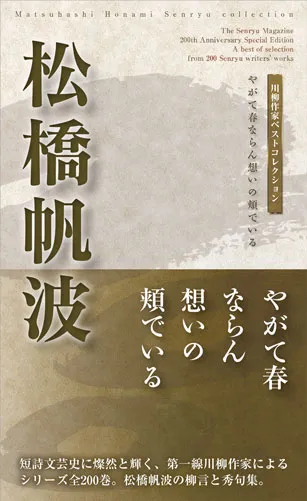
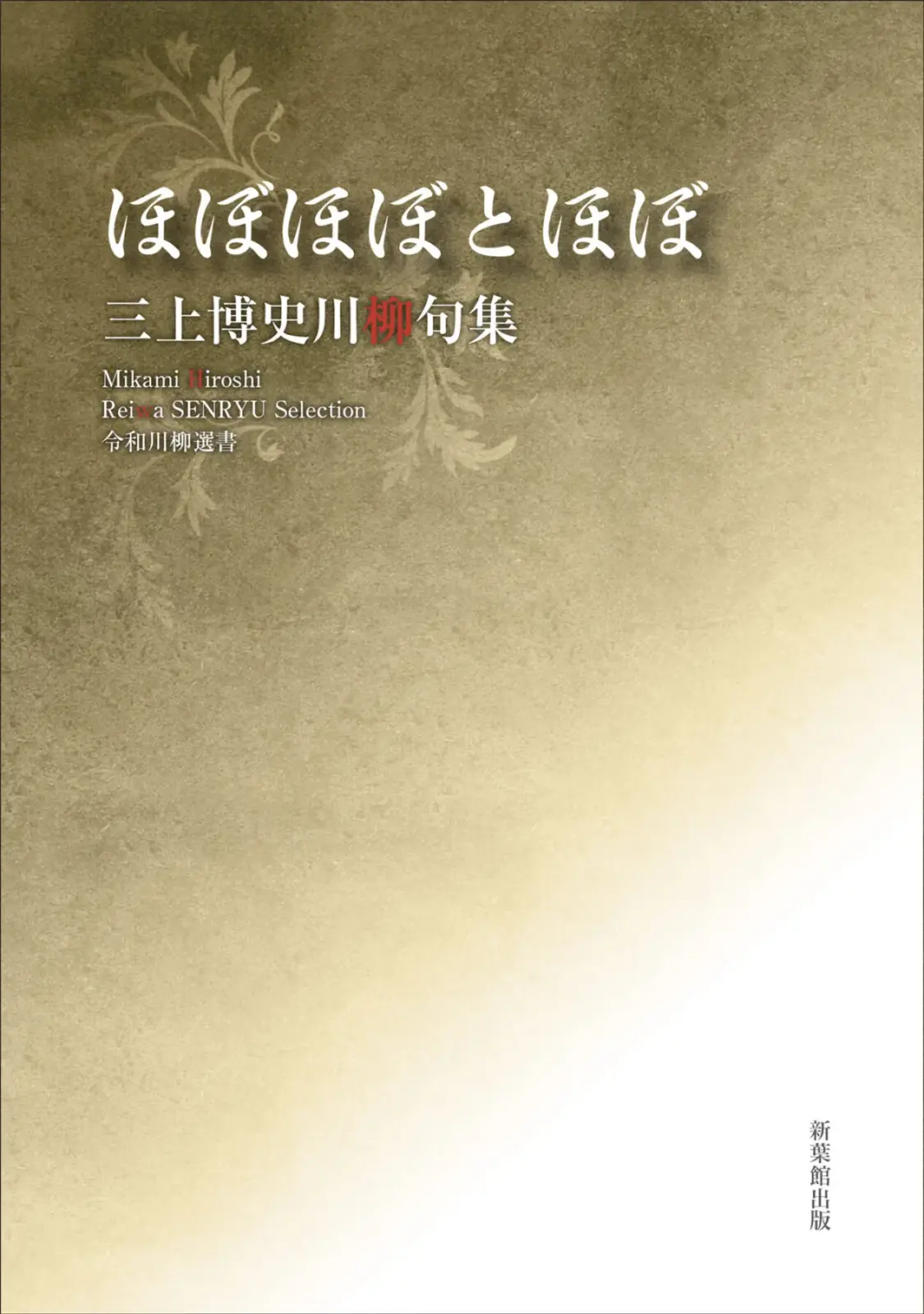
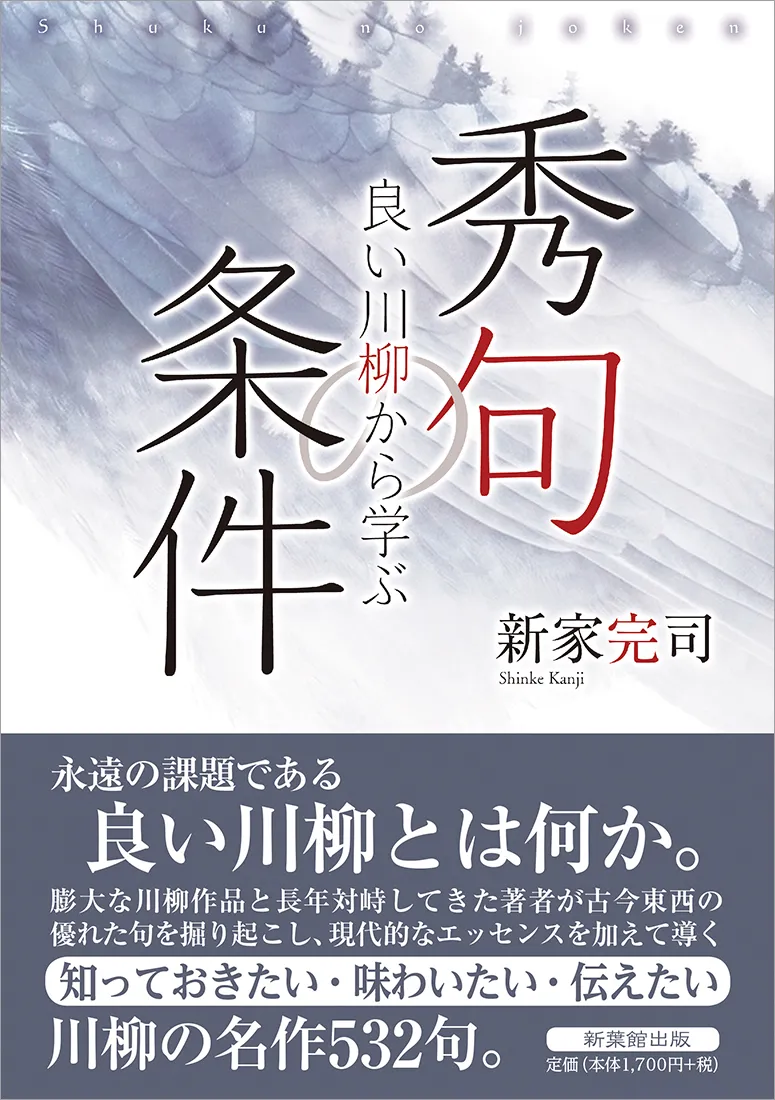














「二物衝迫」って、あまり聞きませんね。
そのあたりの解説を楽しみにしております。
江畑 哲男さま
少々お待ちください。(ちょっと仕事があるのね)
本日の内には書き込みます。