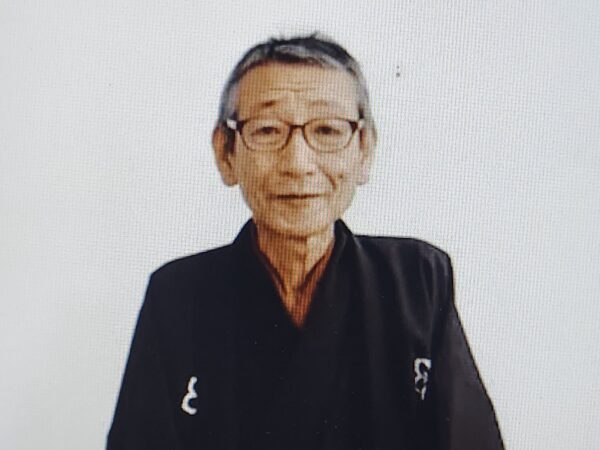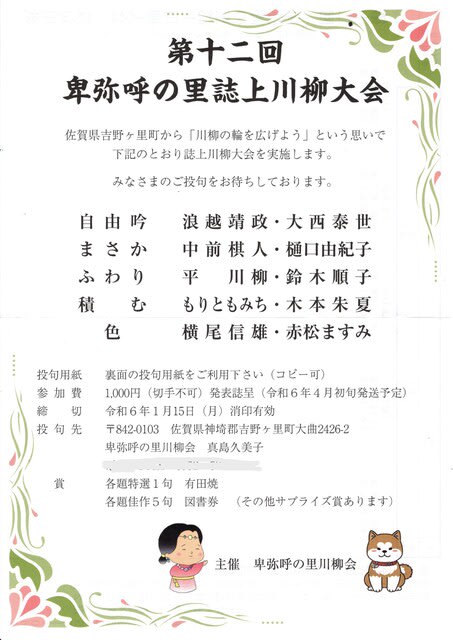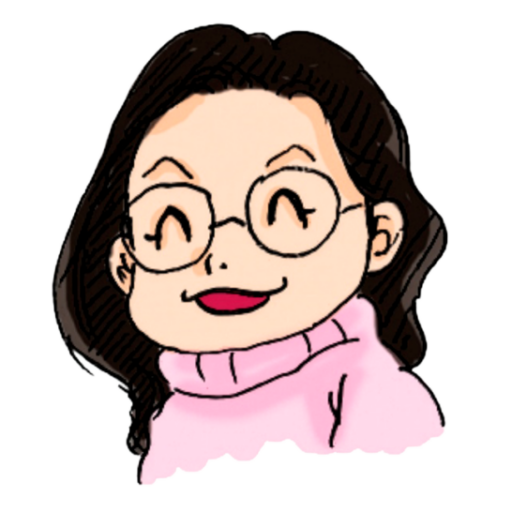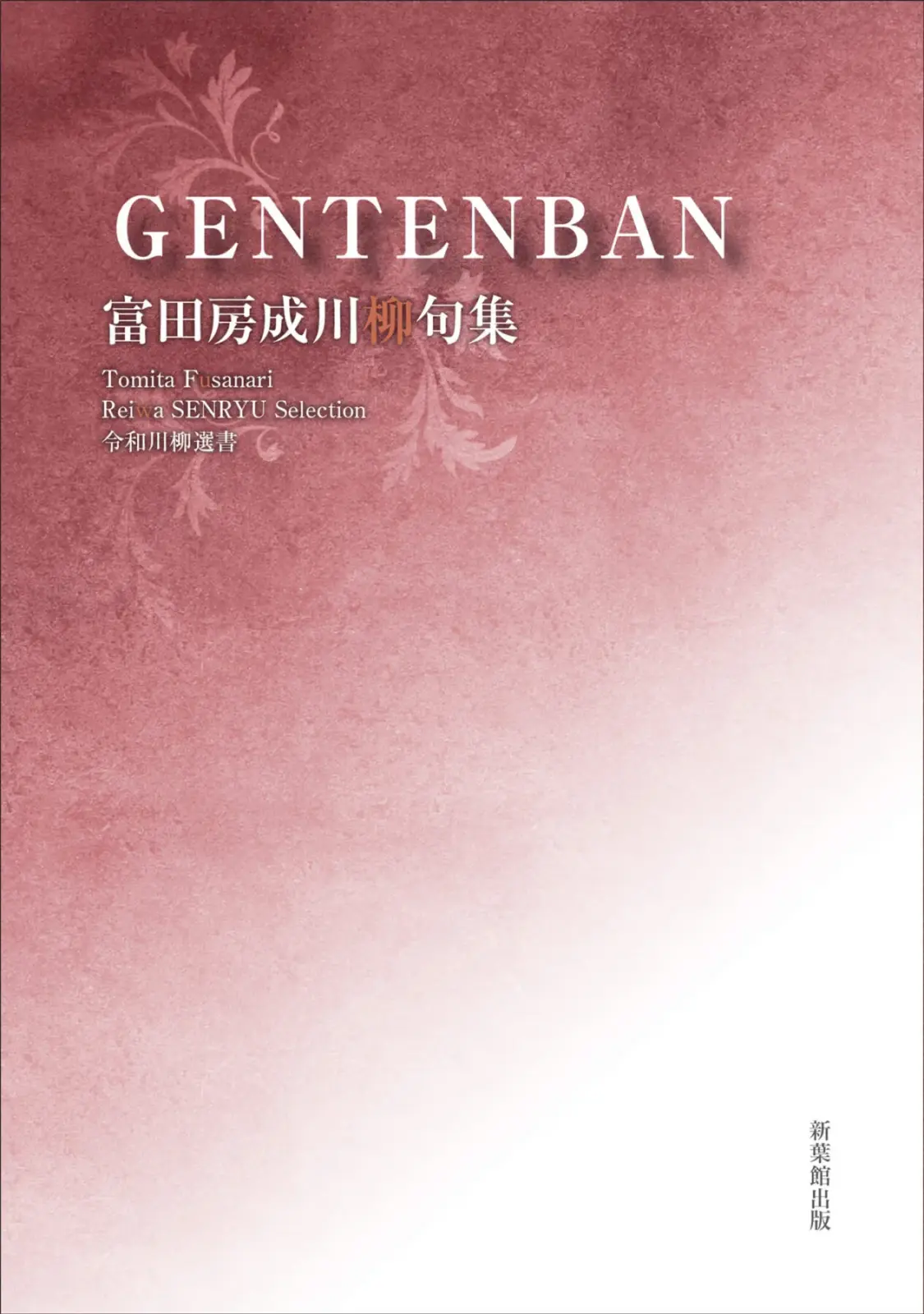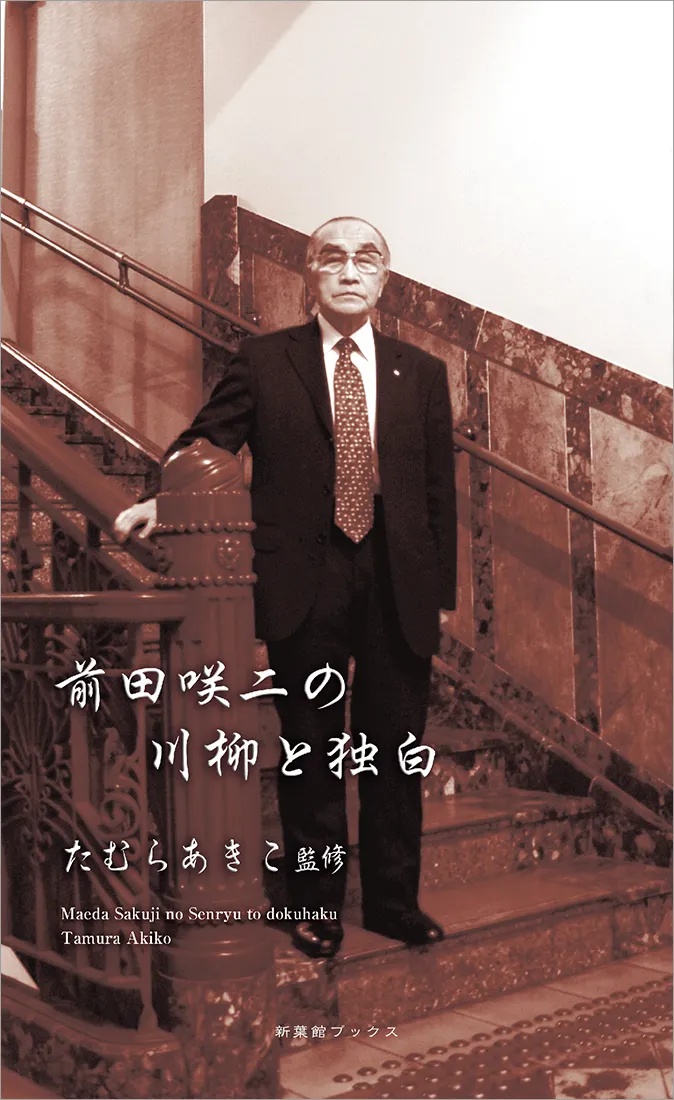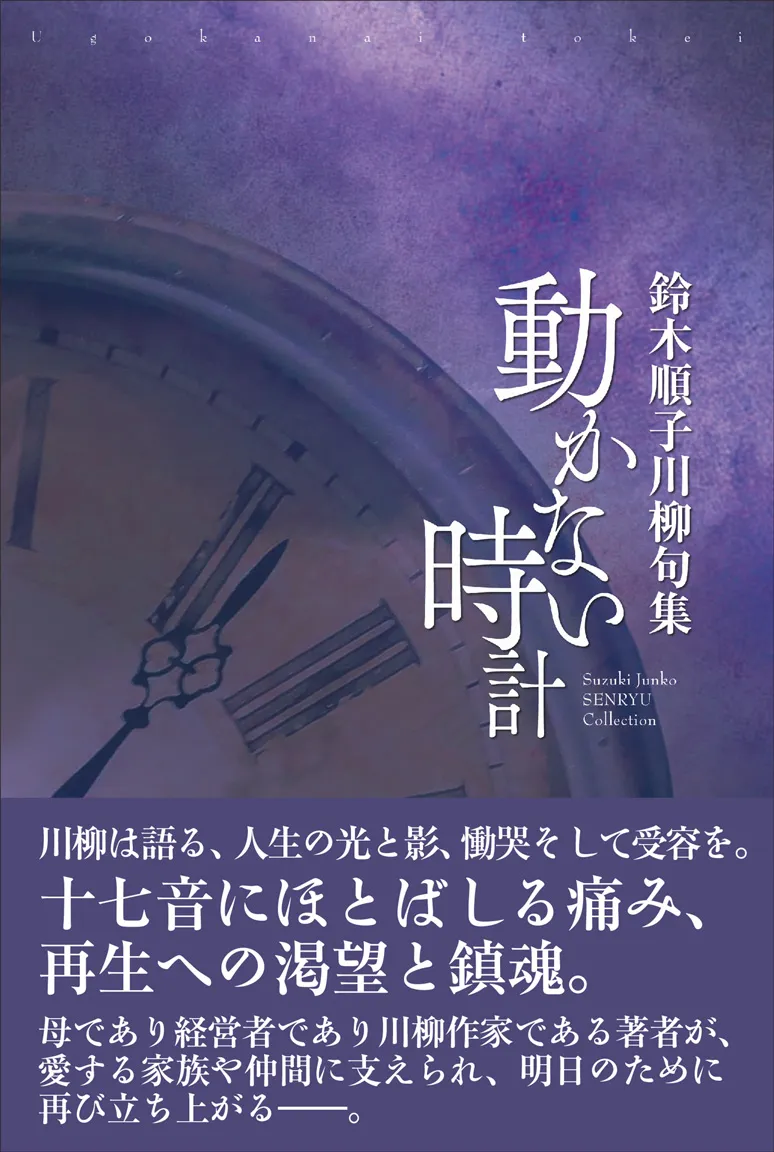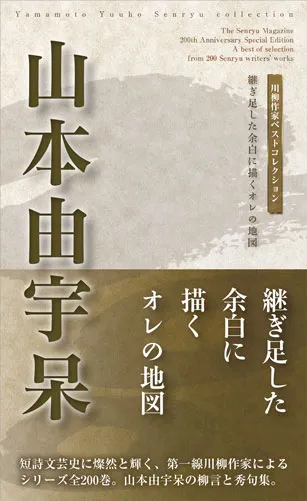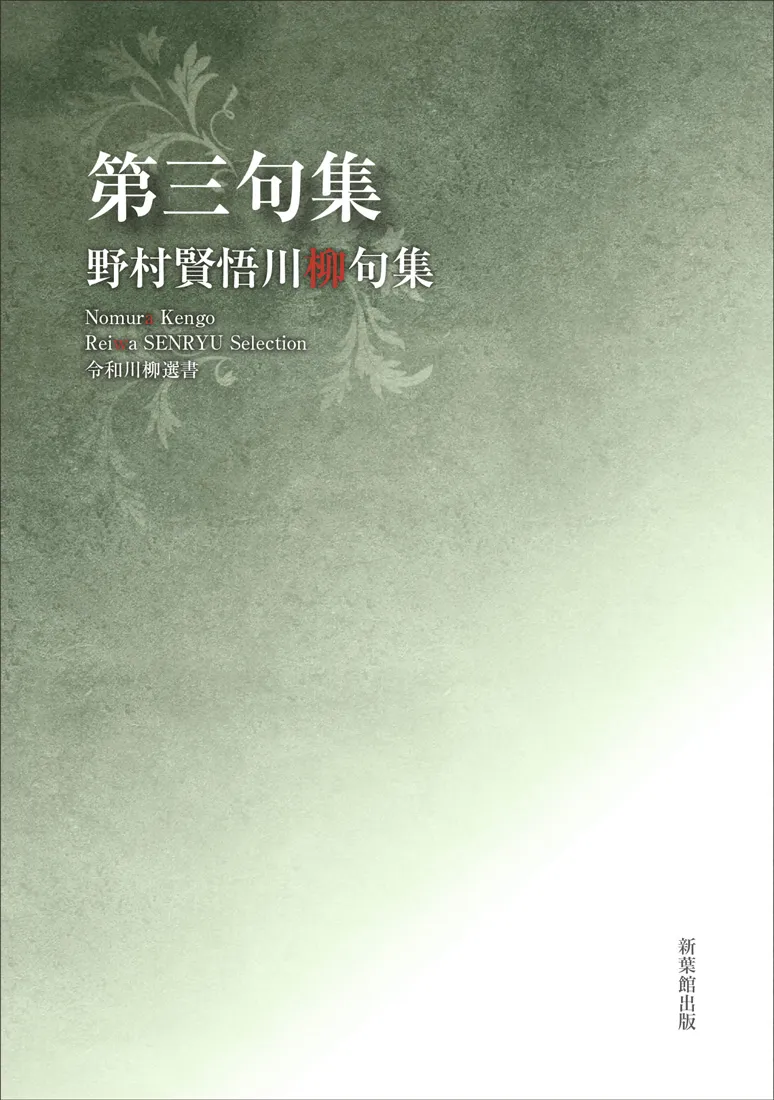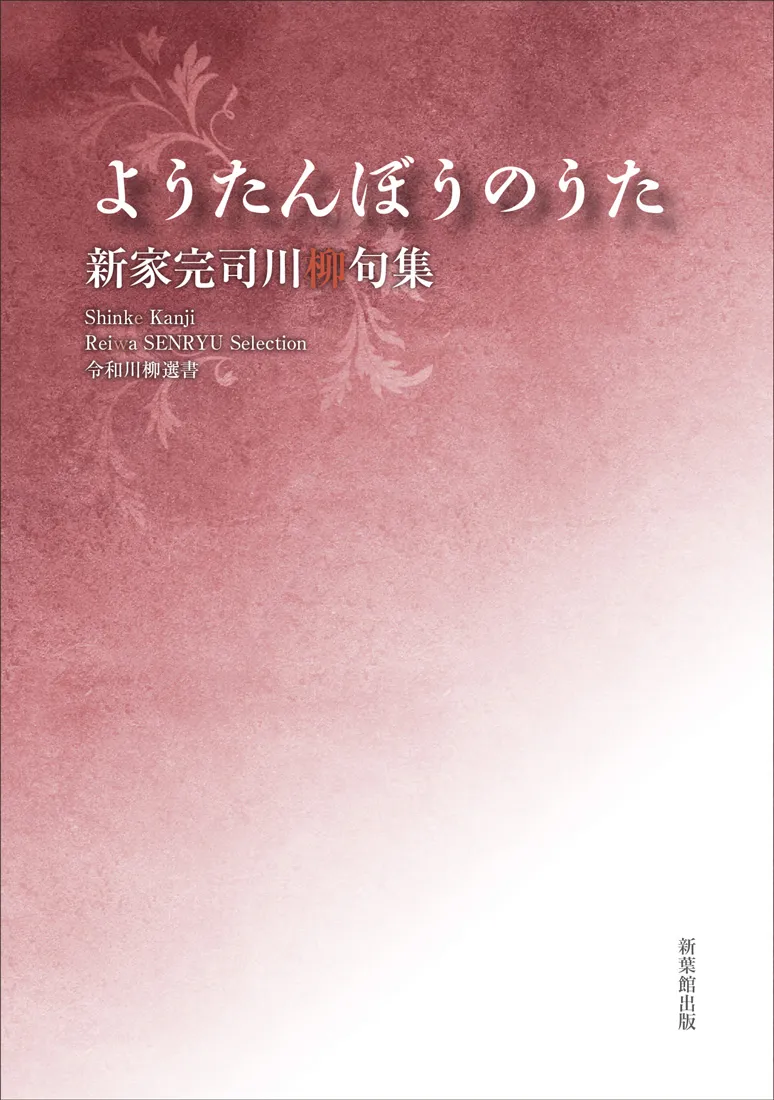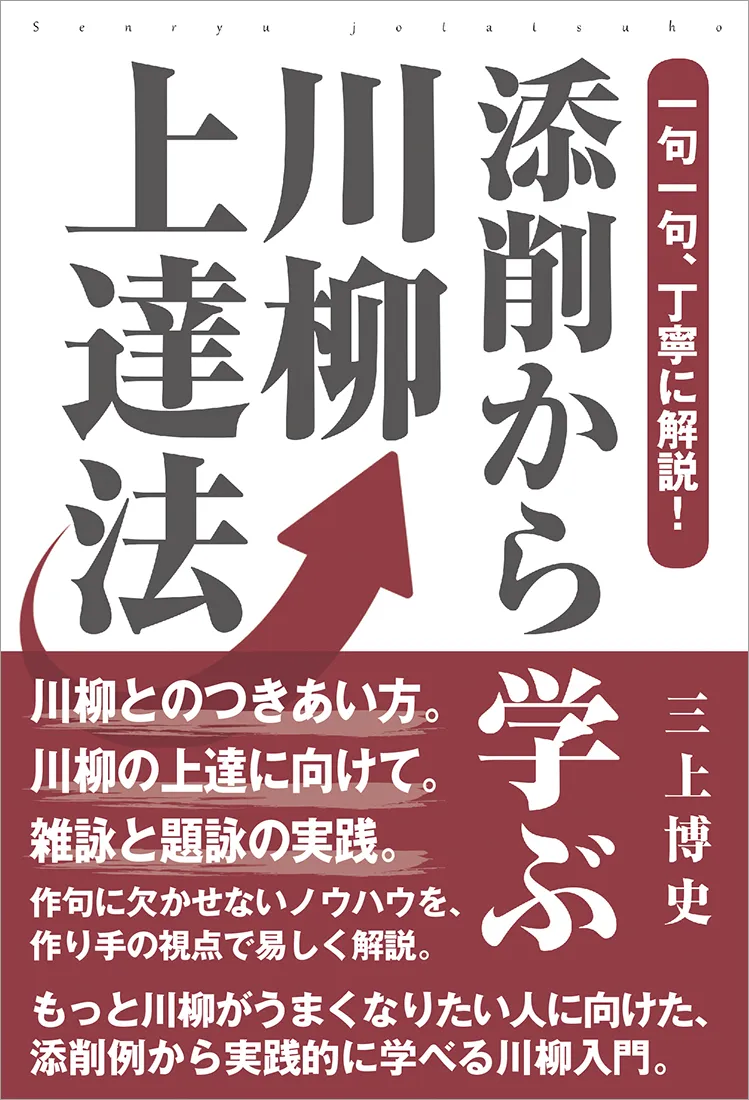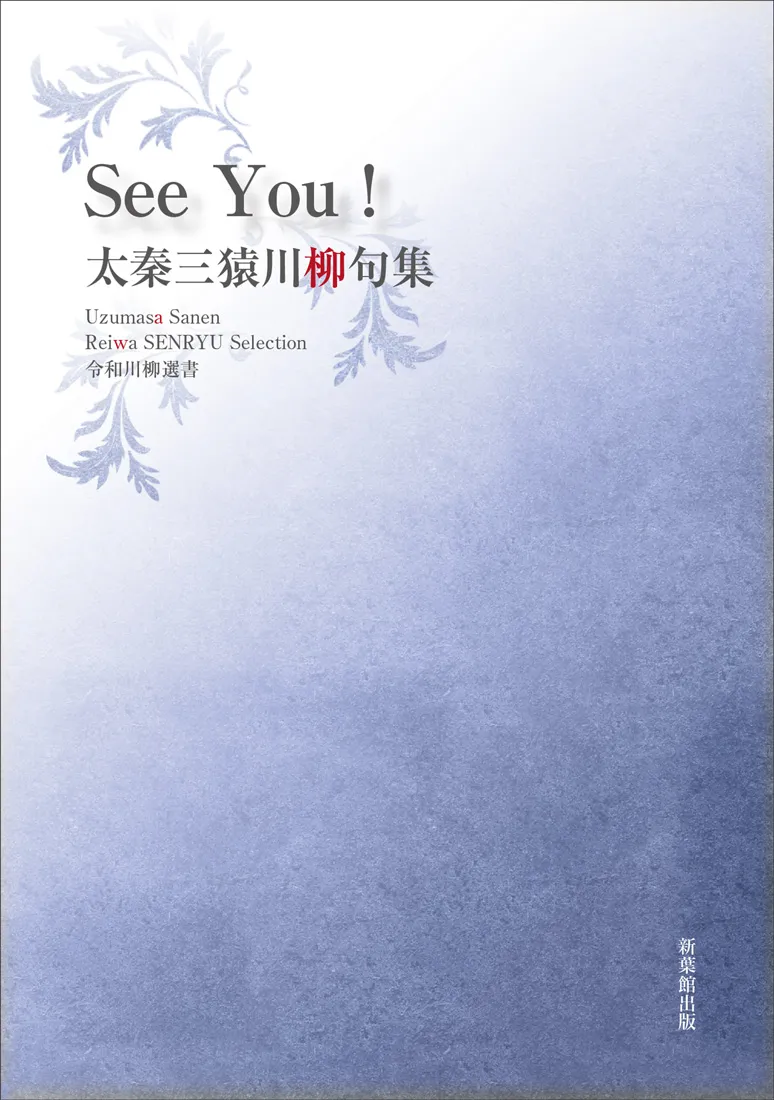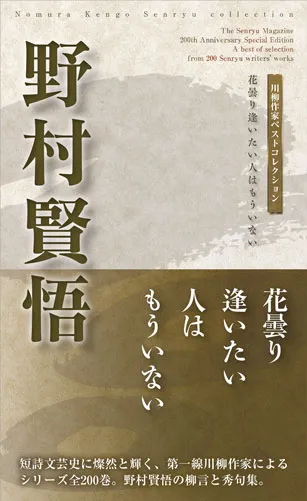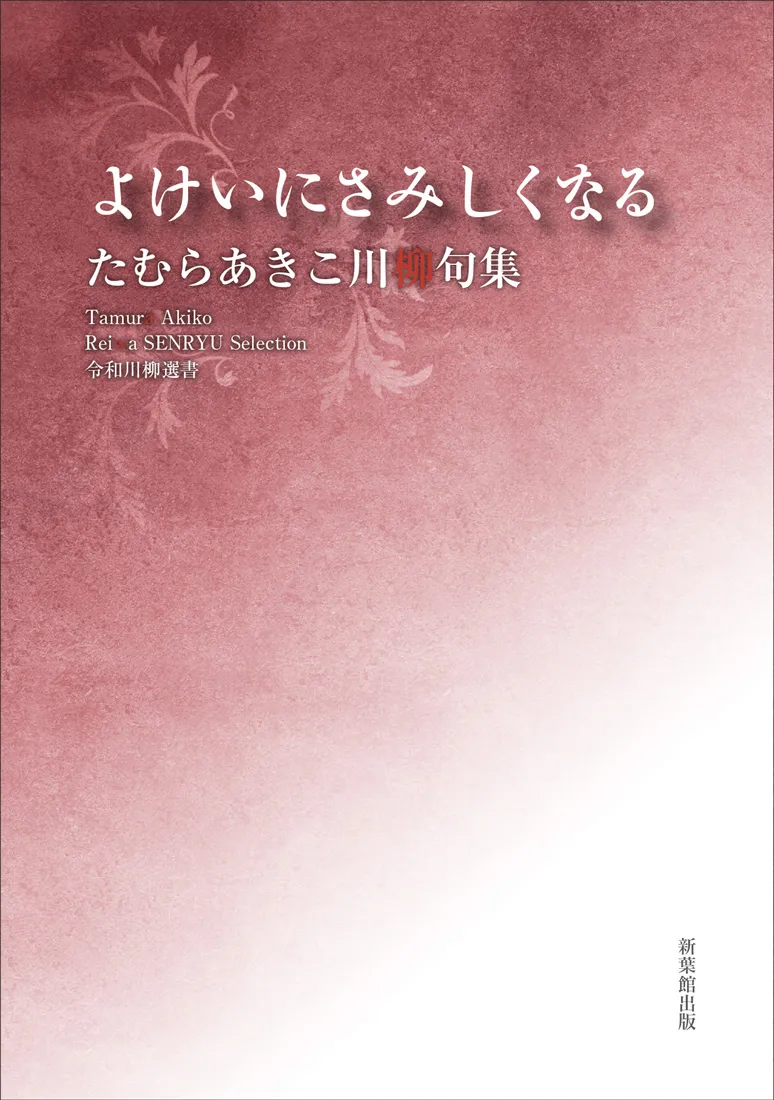学童疎開
大江山の近くに、ニッケルを掘り出す鉱山が有り、そこに働いている、昨日まで日本の捕虜だったアメリカ人が、私達の住むお寺の寮へ押しかけて来るか分らない。皆女の子だからきっと悪さをされるだろう。そうなる前に死んだら何も起らないはずだ、というのが先生が私に言った説明だった。私がそれを同年の寮友に言って歩く役であった。
「負けたかてええ、お母ちゃんとこに帰れる、ほれ戦争終ったし、着物かて着られるやん。早よ帰りたいなあー。」
先生の部屋から戻って来ると、下級生は、自分の命が風前の灯であることも知らず、楽しくて、うれしくて仕方がないといった様子だった。
六年生の面々はお互い顔を見合せても言葉も無く、いつ先生の号令が掛かるかとびくびくしながら、先生の行動に付いて行くしか仕方がないと、諦めていた…と言うより、日本の乙女として死ねるという、今思えば日本人として洗脳された戦時中の女子として、立派な行動で死ぬことのできる、心のたかぶりに、遠い父母のことなど思う余裕などまるでなかった。
日本人として辱めを受けない為の一番いいことだと、心ははっきりと決まって行った。
どれ位の時間が過ぎていたのか、気が付けば疎開の子のことを心配して、駆け付けてくれた村人達が、先生から今までの話を聞き出し、居合わせた者は皆声を上げて泣いてくれた。また先生に呼ばれた私達も、こっそりと「よかったね」と言ってもらい抱き合って泣いた。
あの時村の人が来てくれなかったら私達はどうなっていただろう。今思っても恐ろしいばかりである。
先生も村の人達も言葉少なにお喋りをし、後はシーンと静まり返っていた。近くの森の蝉だけは、何も知らない様に日暮近くまで鳴き続けていた。
皆んなが自分のする事も忘れた様にポカンとした顔をして、これから何をするのか分らない姿だった。
この最後のおべべを、先生は記念写真として一枚撮って下さっていた。いずれ後に、各家庭の遺族へ届けられる為の一枚であったはずではなかったか。この写真が疎開中に撮ってもらった唯一の記念として、今も大切にアルバムの中に有る。
…… (写真は本文とは関係ありません)
‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥
すべては風化してゆく。私たちは自らの体験、辿った道をなんらかの方法で記録、伝えていかなければならないのかもしれない。事実をたんたんと書き残すこと。そこから何を読み取るか、何を反省のよすがとするか、判断は読む人に任せる。篤子さんの文章には作為がない。深く心打たれるものがある。(たむらあきこ)
 Loading...
Loading...