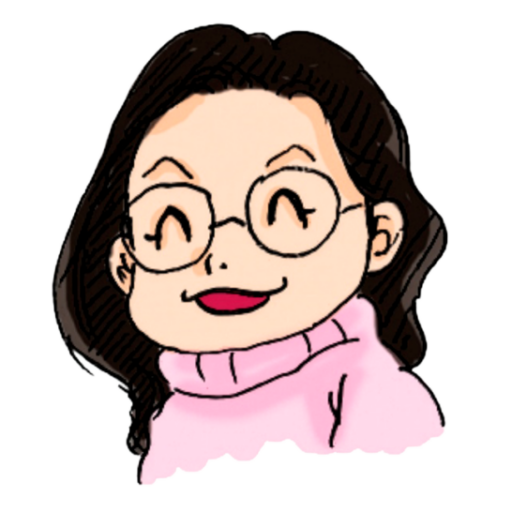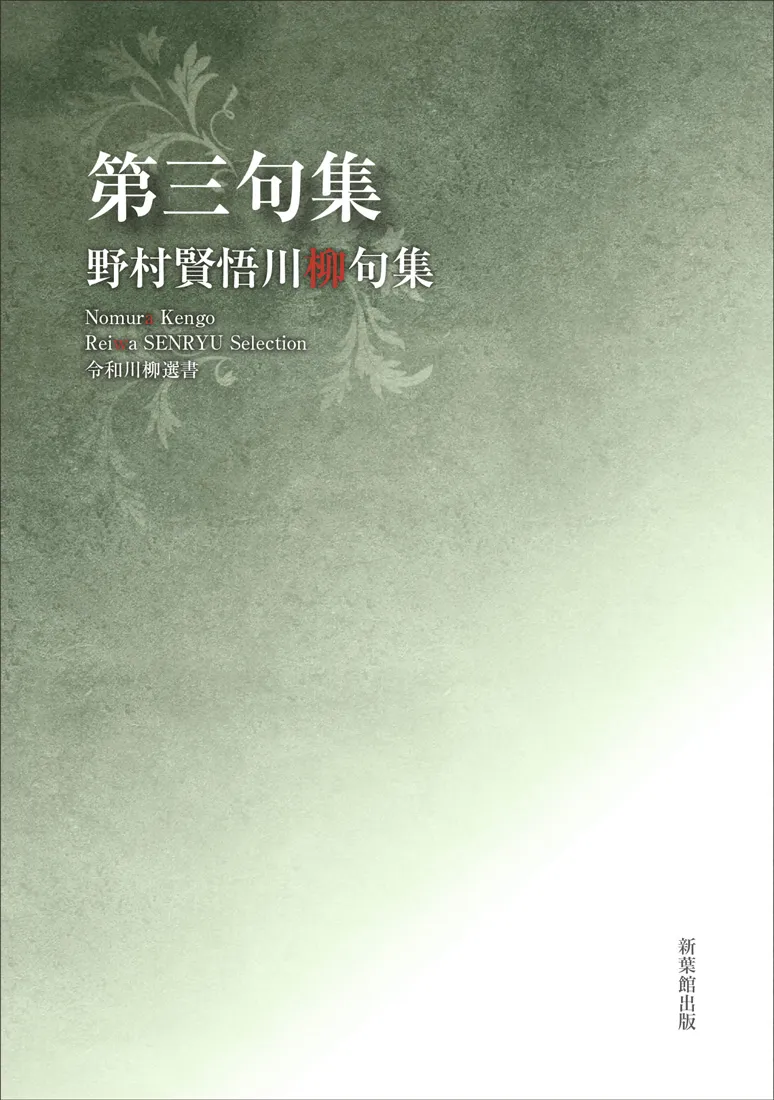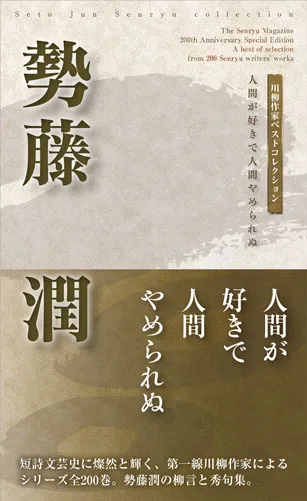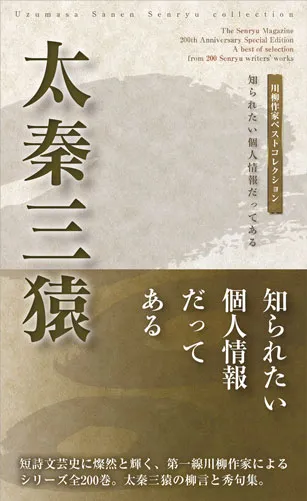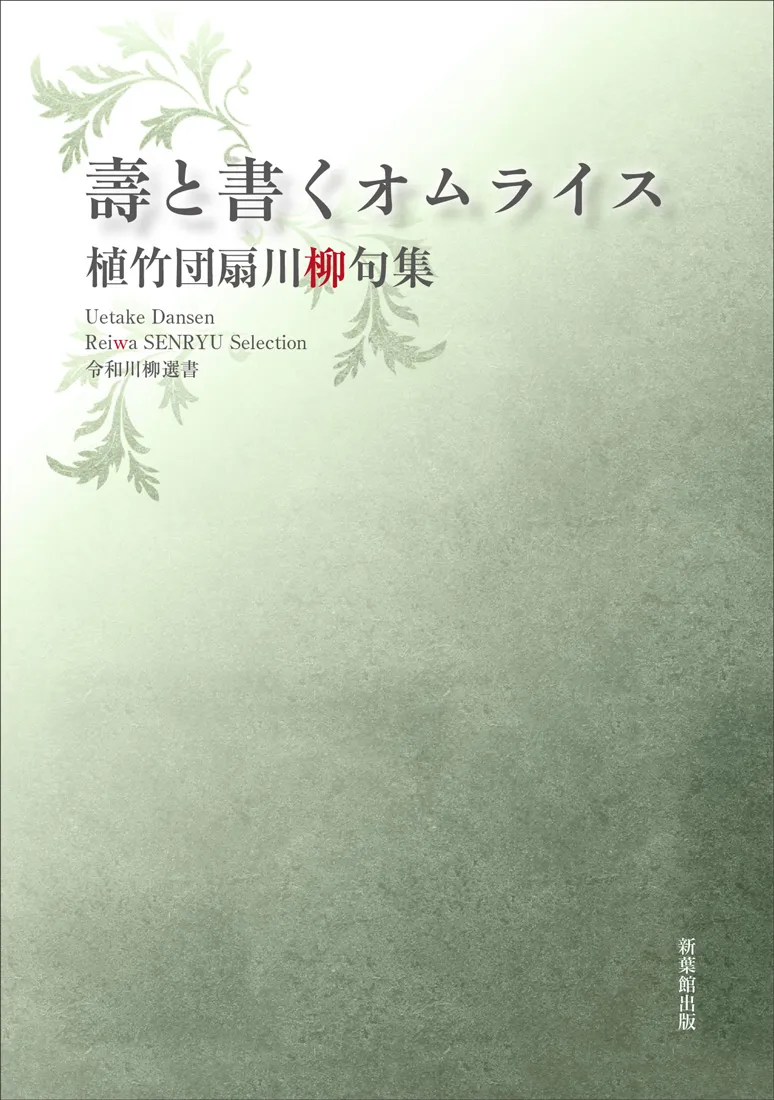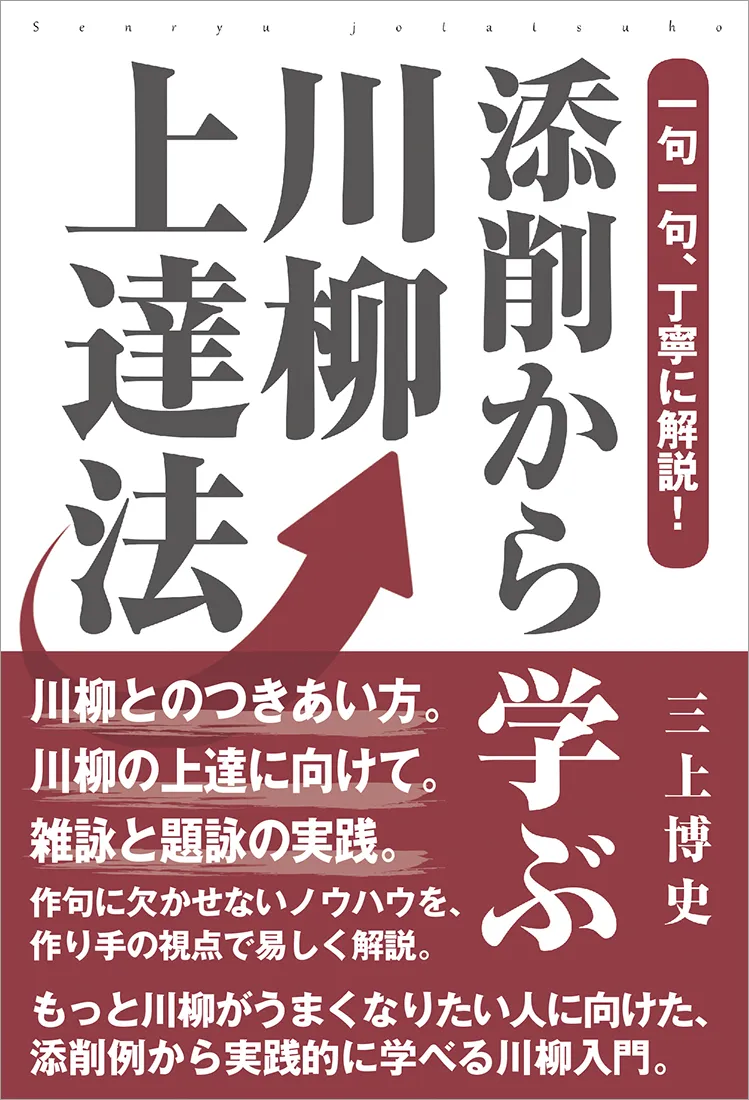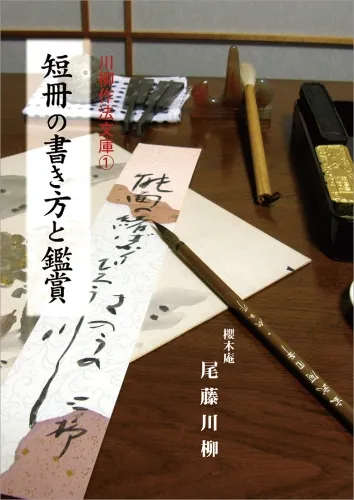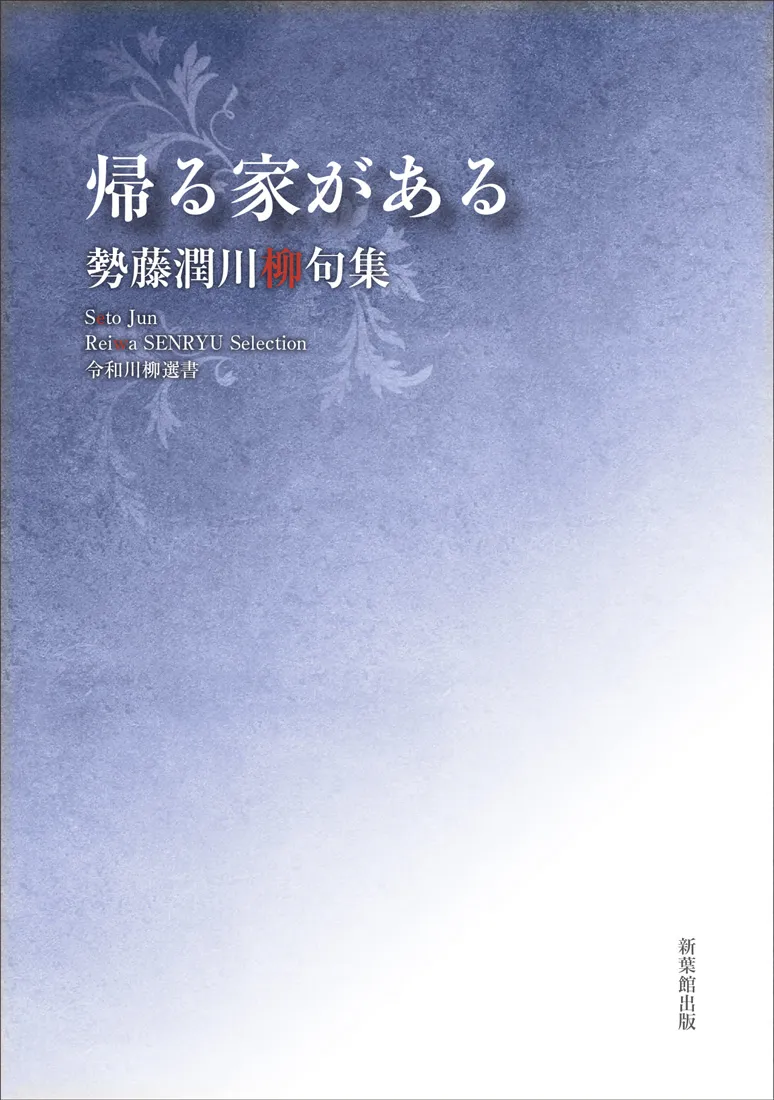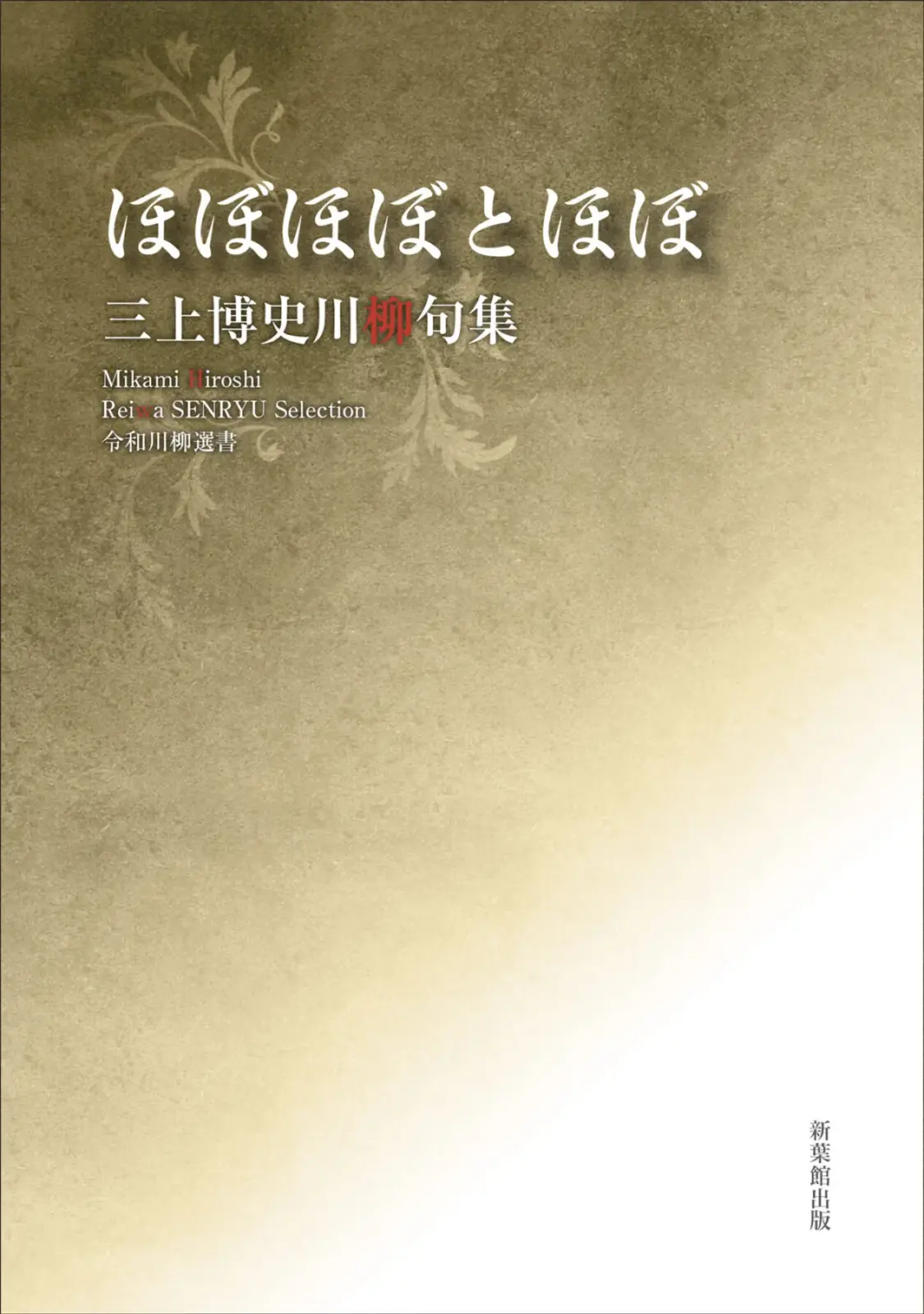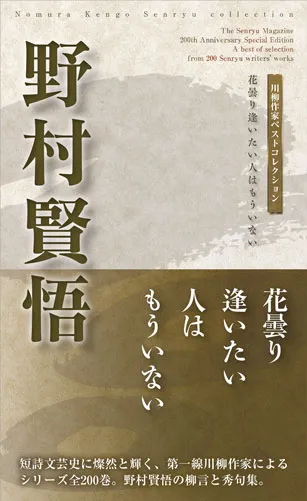遺骨の“処理”に悩んでいる人が増えてきたと言われているのね。自分が死んでしまったら管理してくれる身内がいないなどで、先祖代々の墓を撤去してしまう“墓じまい”も珍しくなくなったとか。墓を持たないことを前提として遺骨を海や山などにまく、いわゆる“散骨”も多くなってきたというのね。現代ならではの状況だと捉えられているが、日本において“散骨”そのものは決して珍しいものではなかったというのね。(写真:散骨島)
遺骨の“処理”に悩んでいる人が増えてきたと言われているのね。自分が死んでしまったら管理してくれる身内がいないなどで、先祖代々の墓を撤去してしまう“墓じまい”も珍しくなくなったとか。墓を持たないことを前提として遺骨を海や山などにまく、いわゆる“散骨”も多くなってきたというのね。現代ならではの状況だと捉えられているが、日本において“散骨”そのものは決して珍しいものではなかったというのね。(写真:散骨島)
下記は、『万葉集』(7世紀後半〜8世紀後半)に収載されている挽歌(ばんか)で、“散骨”を詠み込んでいる。
秋津野(あきづの)を人の懸(か)くれば朝撒きし君が思ほえて嘆きはやまず(巻7・1405)
(秋津野のことが話題にのぼると、今朝、そこに散骨したあなたのことが思い起こされて嘆きはやみません。)
玉梓(たまづさ)の妹(いも)は玉かもあしひきの清き山辺(やまへ)に撒けば散りぬる(巻7・1415)
(玉梓の使いを介してやりとりした彼女は玉(木の実)だったんだなあ。あの清い山辺に撒いたら木の実のように散らばったんだもの。)
玉梓の妹は花かもあしひきのこの山陰(やまかげ)に撒けば失(う)せぬる(巻7・1416)
(玉梓の使いを介してやりとりした彼女は花だったんだなあ。この山蔭に撒いたら幻のように消えてしまったんだもの。)
これらの歌からは、撒いた“骨”そのものへの忌避感などはまったく感じられないのね。後の二つの歌では、“骨”を“玉”、そして“花”にまでなぞらえて詠んでいるのね。
死はどんなかたちであれ、人間を含むすべての生きものに平等に訪れる。現代において葬儀や墓はとくに大事なものではないと考えて、簡略化するようになったのね。遠方に住んでいて不便だからなどと“墓じまい”することを、一概によくないと決めてかかることもないだろう。将来の日本にどのような価値基準が存在するか、我われには想像もつかないことなのだから。
 Loading...
Loading...