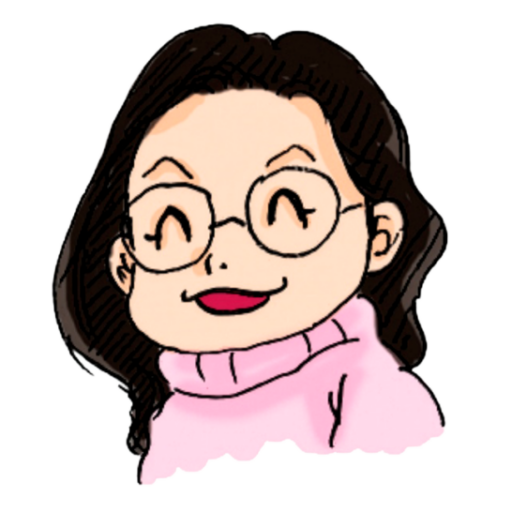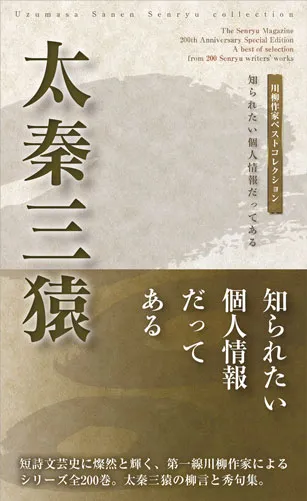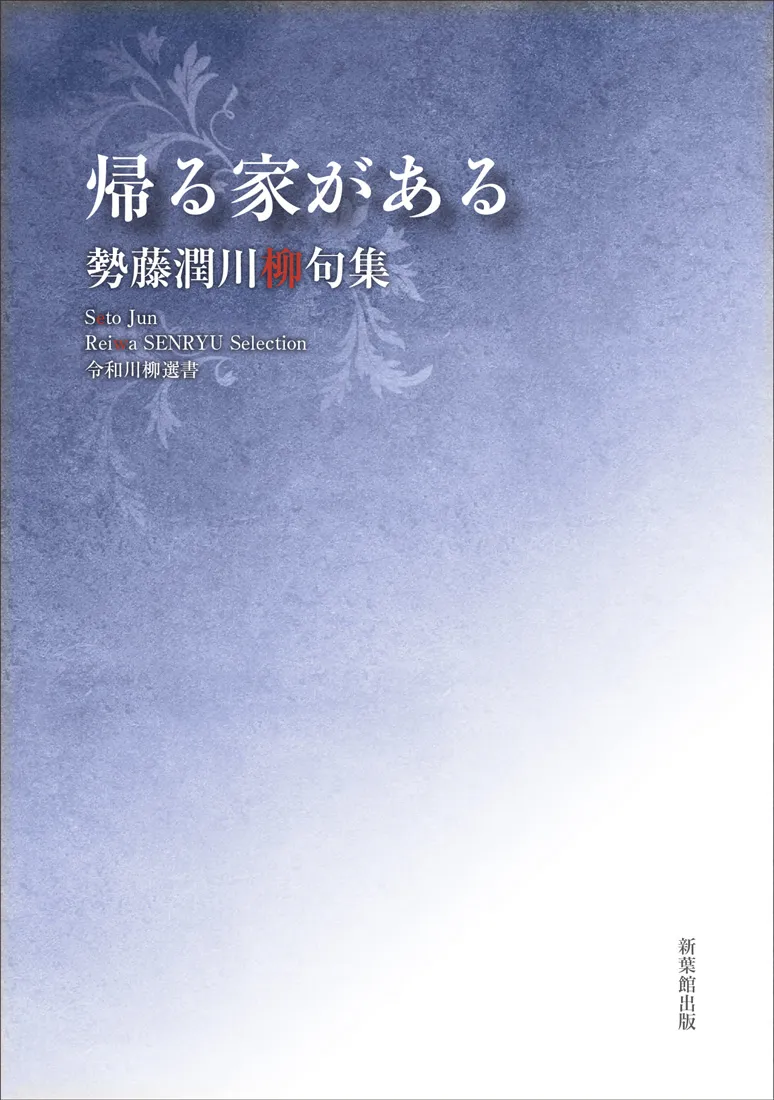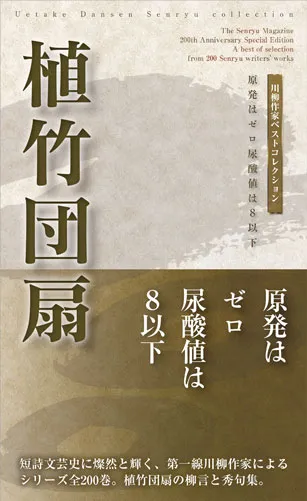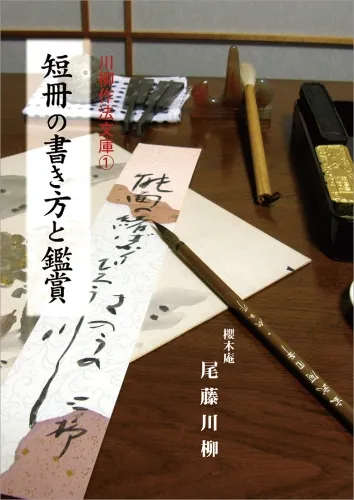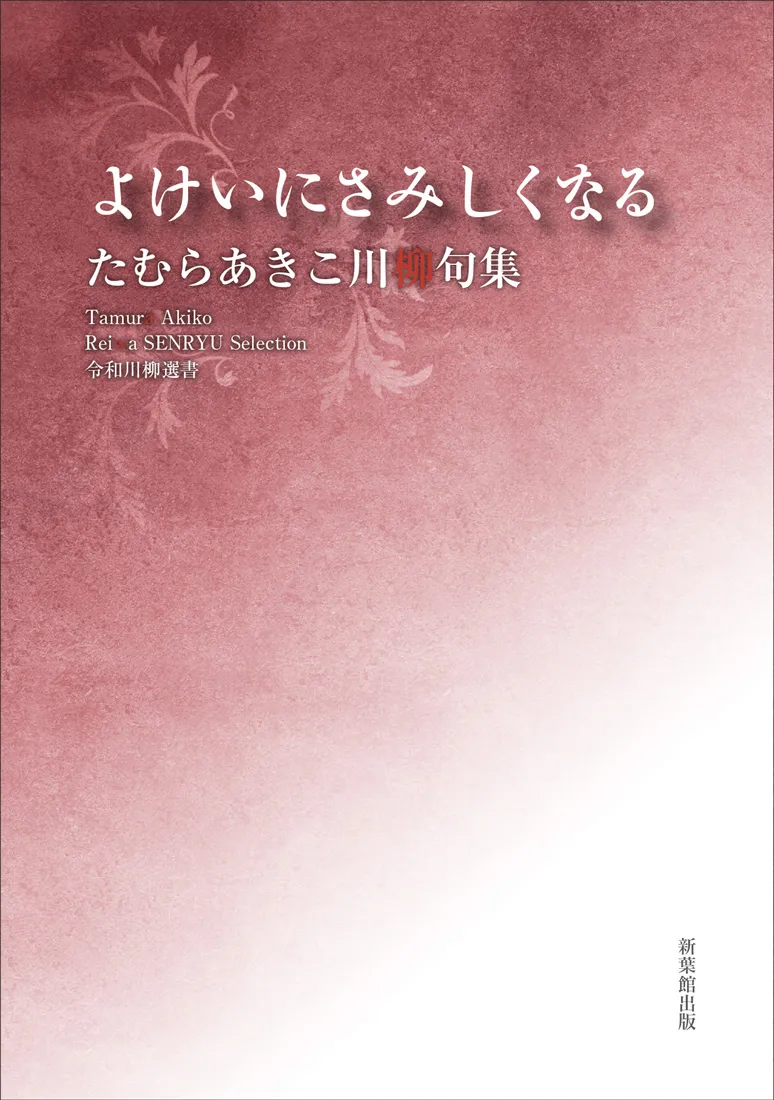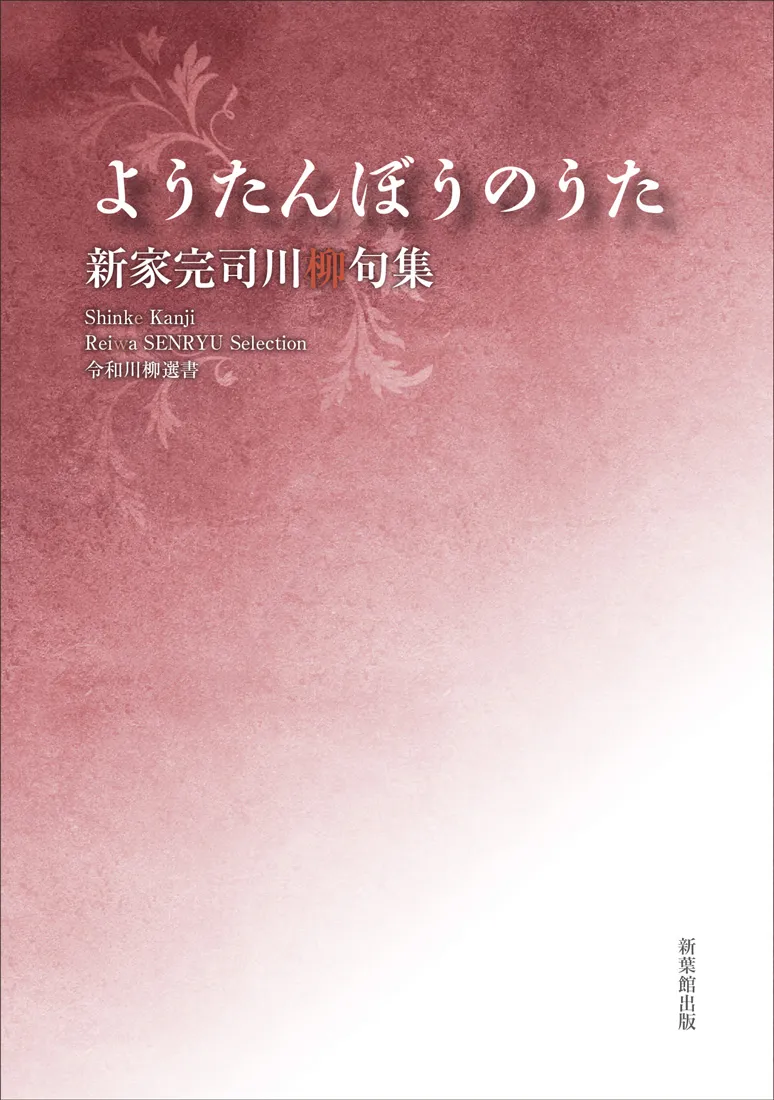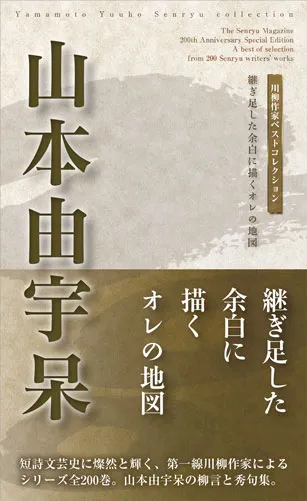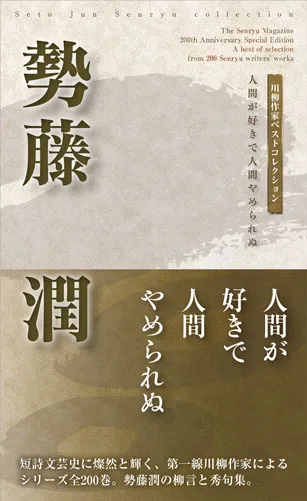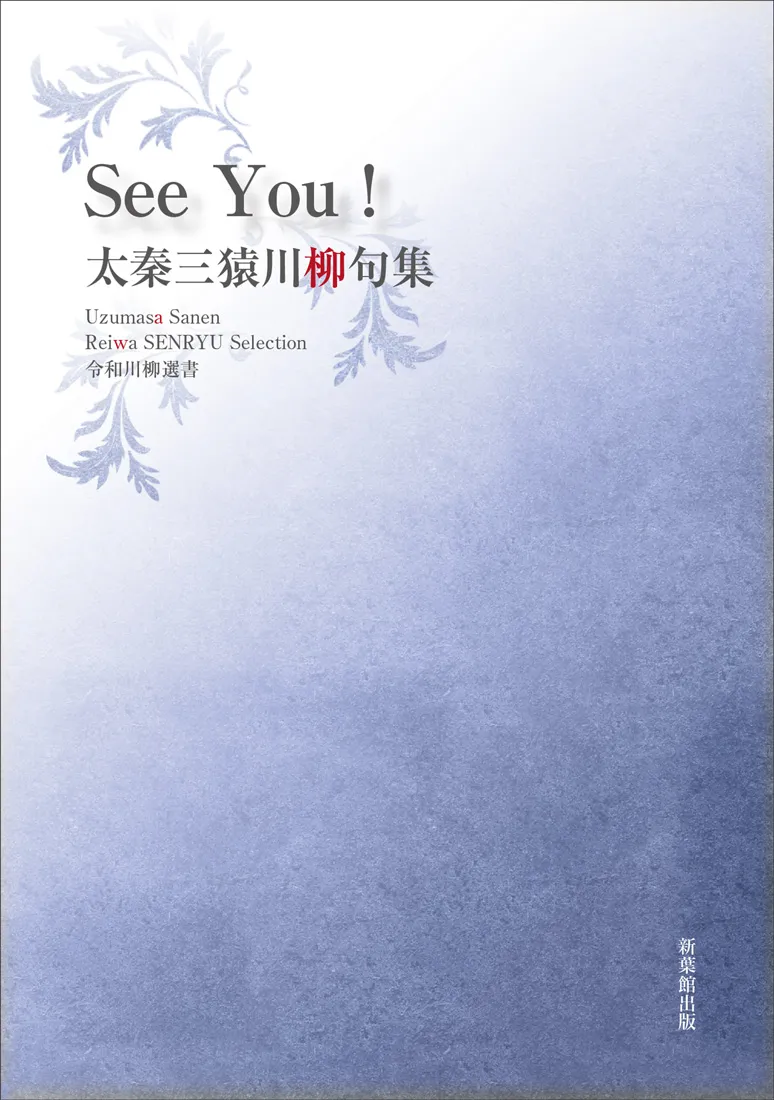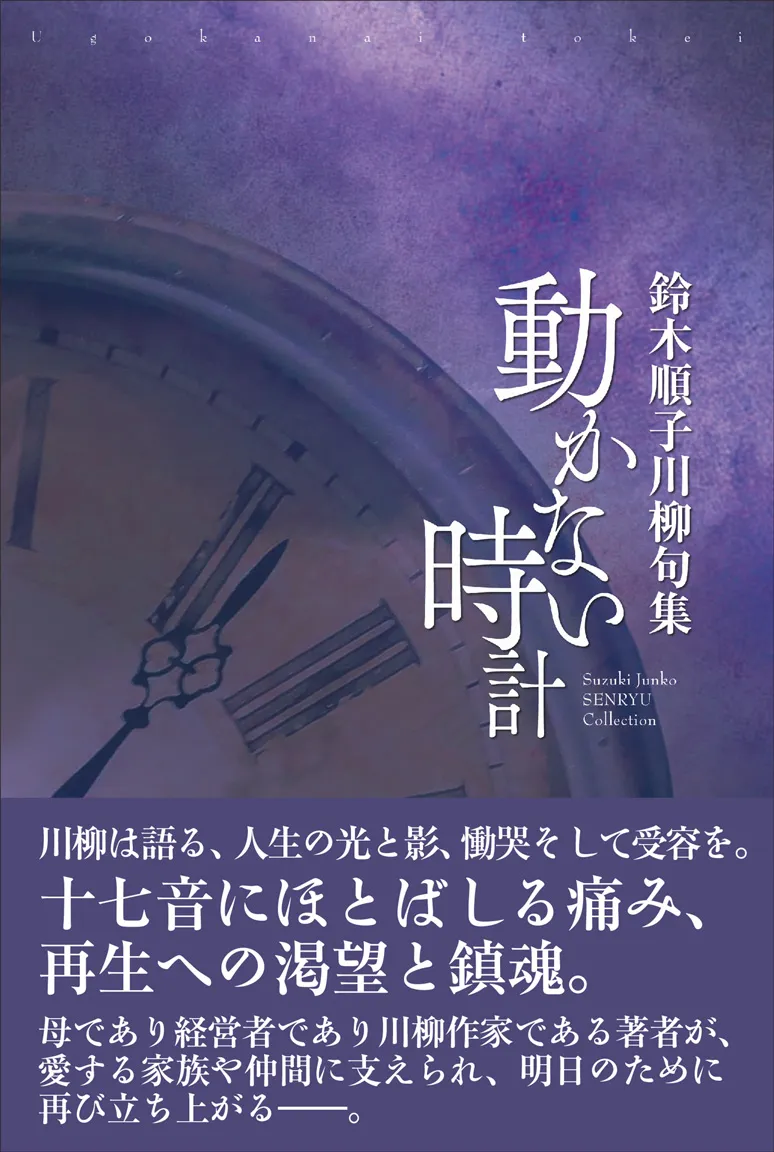「やまと路」鑑賞 たむらあきこ
 ため息がガタンゴトンと春の底 古川 洋子
ため息がガタンゴトンと春の底 古川 洋子
「ガタンゴトン」はこころが何かにぶつかる音。このオノマトペ(電車)の比喩は面白い。「春の底」も、愁いに占領された作者のこころの位置を表していてよく分かる句。
とんがってもみよう砕けてもみよう 古川 洋子
ふと口をついて出た、呟きのような句。こころを自然体にしようといっている。怒りで尖ることもあれば、辛くて砕けるような思いもある。それもこれも人生。よい経験をさせていただいたと最後は肯定的に受け止めることができれば。
復興の五分咲きなんてもどかしい 吉井テイ子
大震災のあとの「復興」の遅さを桜の「五分咲き」に喩える。時季的に桜をもってきた。
むなしさがふと贅沢のど真ん中 吉井テイ子
既視感のある内容を詠んでいるのだが、纏め方が巧い。暮らしに必要以上の「贅沢」は要らない。日本には〈清貧〉という美学がある。『清貧の思想』(中野孝次)は92年のベストセラーだが、その内容は、西行・兼好・芭蕉などの風雅の暮らしを論じたもの。一切を捨てきったあとの心の充実を説くその論は、むしろ古風な伝統のうえにある。こころを満たしてくれるものは決してカネで手に入るものではない。
信じよう自分の中の補正力 徳重美恵子
「補正力」がよい。「自分」の言行に判断を下すのは何より「自分」が積んできた経験。他人の言もだが、まず「自分の中」の正直な声を聴くことだろう。そのうえで改めるべきは改める。長く関わったものについても、切るべきは切る。宗教などについてもいえることかもしれない。
体温をほどく弱々しい帽子 阪本きりり
「(体温を)ほどく」がよい。「帽子」は柔らかく編まれたものなのだろう。脱ぎ捨てた途端にカタチが崩れ「体温」がぬけてゆく。そのカタチの弱々しさは作者の弱さでもあるようだ。
その先は言わぬマグマが火を上げる 細田 貴子
こころの「マグマ」は、「その先」を言わないからこそ煮え滾る。「マグマ」を詠んだ句は多いが、さらに「火を上げる」とまで詠んでいる句を初めて見た。どれほどの凄まじい怒りなのか。
ブレーキを常に自分にかけている 大村 三郎
おとなは「自分」を抑制することができる。抑制することができるからこそおとななのだろう。そのおとなの中でも「ブレーキ」を「常に」かけている作者は、揉め事がもう煩わしいだけなのかもしれない。
うなずいたばかりに重い荷を背負う 仲村 周子
簡単なことを頼まれたつもりで軽く「うなずいた」のであろう作者。後悔したのだろうが、よくあること。ただ誰かが損得抜きに担わなければならない「荷」もある。そのときはボランティアのつもりで。
ノーという返事ゆっくり消化する 福田 道子
まさかの「ノー」が返ってきた。作者の驚きが出ている。何故なのか、じっくり考えて腑に落ちたのだろうか。人の心を自由にはできない。結局自分の甘さが身に沁みて分かったということだろうか。
調律のきかなくなった遠い耳 福田 道子
〈聴こえ〉が悪くなるのは分かるが「調律のきかなくなった」とは。上がったり下がったりして聞こえるのだろうか。経験者にしか分からない句。
点滅を繰り返してる老いた母 菱木 誠
思い出したり、また忘れたりを繰り返すのが老人というもの。記憶のカケラを引き寄せながら、ついには忘却ということになる。
図書館を丸のみしたい本の虫 山田紀代美
「図書館を丸のみしたい」とはいかにも大仰であるが、ユーモアがあってよい。誰もが思い付かないようなことを言ってのけるのも、川柳の愉しさ。
不協和音へ飯茶碗ゆれている 西澤 知子
よくある「(家庭内)不協和音」。家族で囲む食卓もそんなときは空気が澱んでいることだろう。温かい家庭だとしても、いつも和音というわけにはいかない。
まだ生きるためのバトルへ爪を研ぐ 五味 尚子
「生きる」ことへは否応もなく「バトル」がつき纏う。「バトル」であるからには、やられたらやり返す「爪」を研いでおかなくてはならない。
ばれたかな背中がちょっとうそ寒い 池田みほ子
「ばれたかな」と、黙っていたことへの間の悪さ。「背中」が冷たい視線を感じ取っている。
風向きが変わって浮いている私 植野美津江
懸命に述べた意見も結局は一蹴されたようだ。「浮いている」と自身を客観視。
盃を差し劍幕を手懐ける 土田 欣之
差す「盃」に相手の「剣幕」も漸く収まったか。あとはさりげなくこちらの意に従わせていく。酒のチカラを借りての懐柔。
 Loading...
Loading...