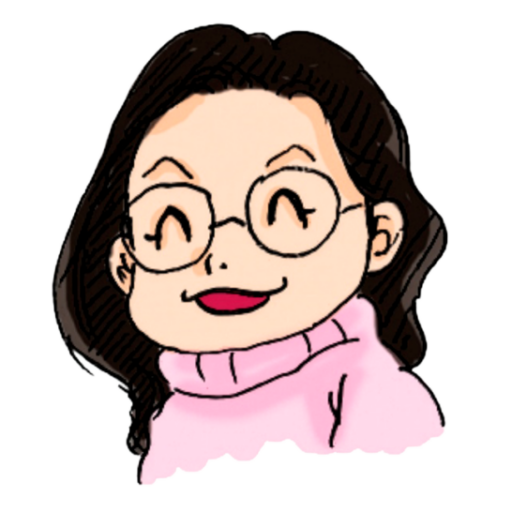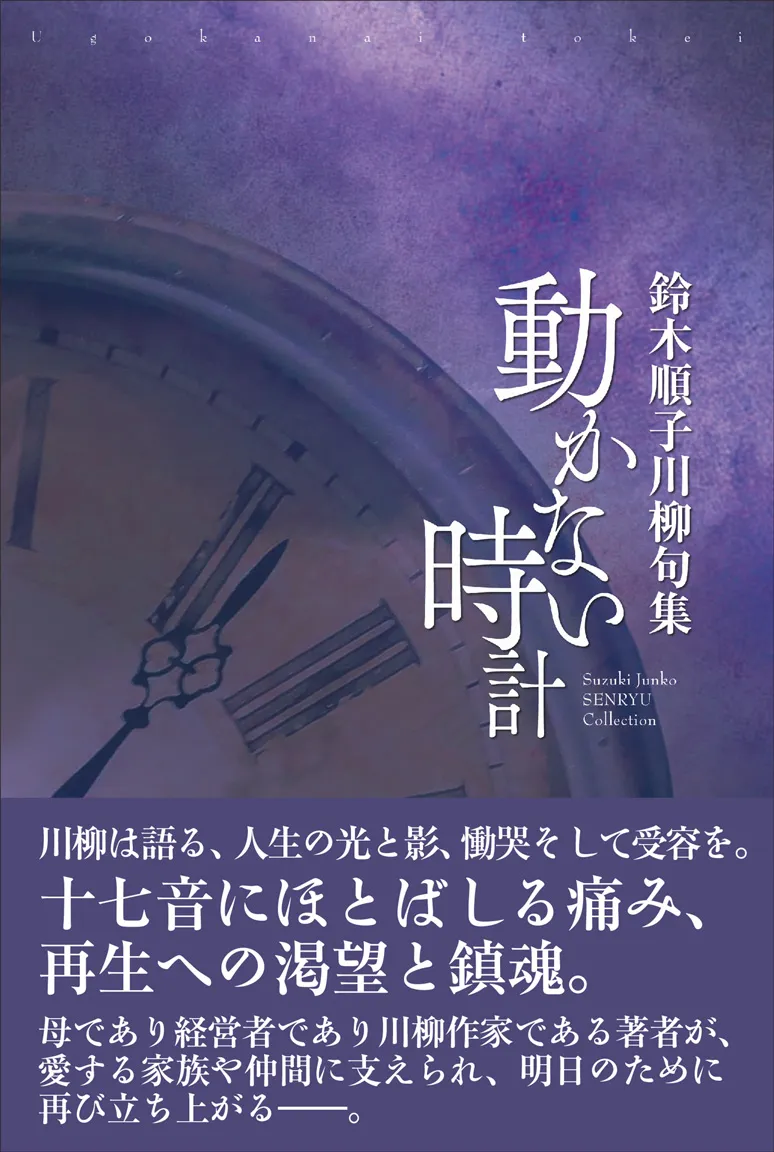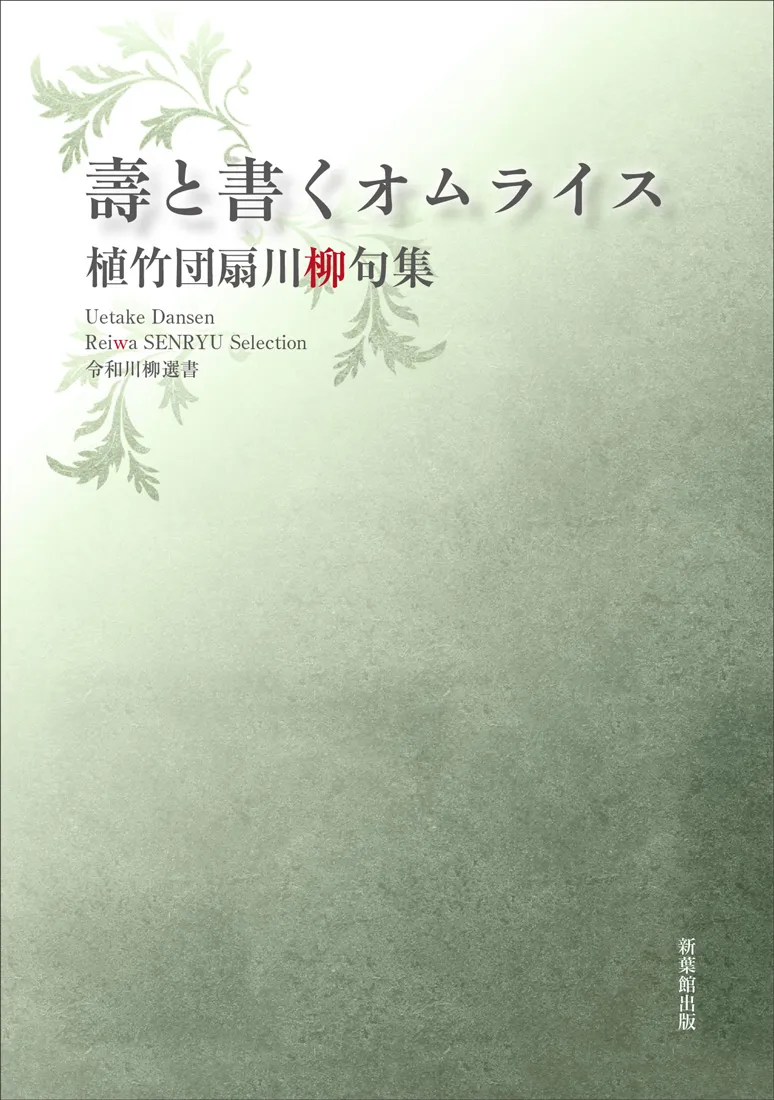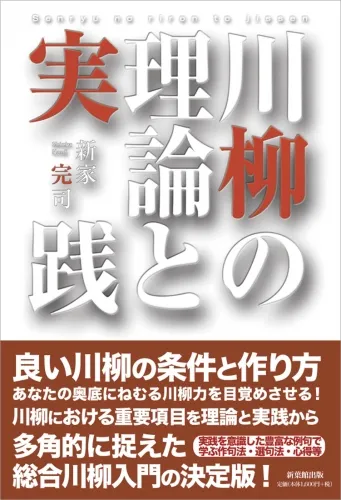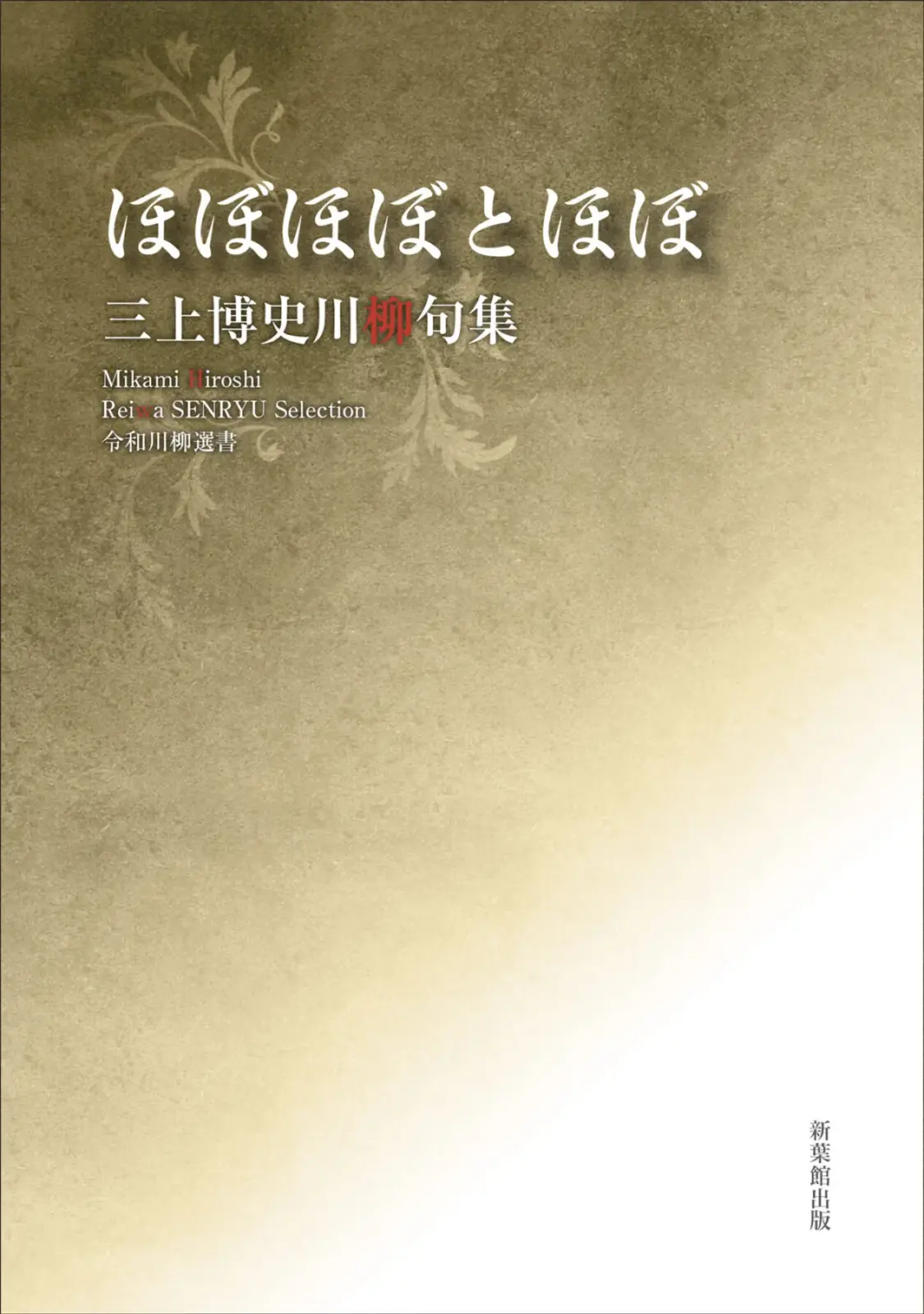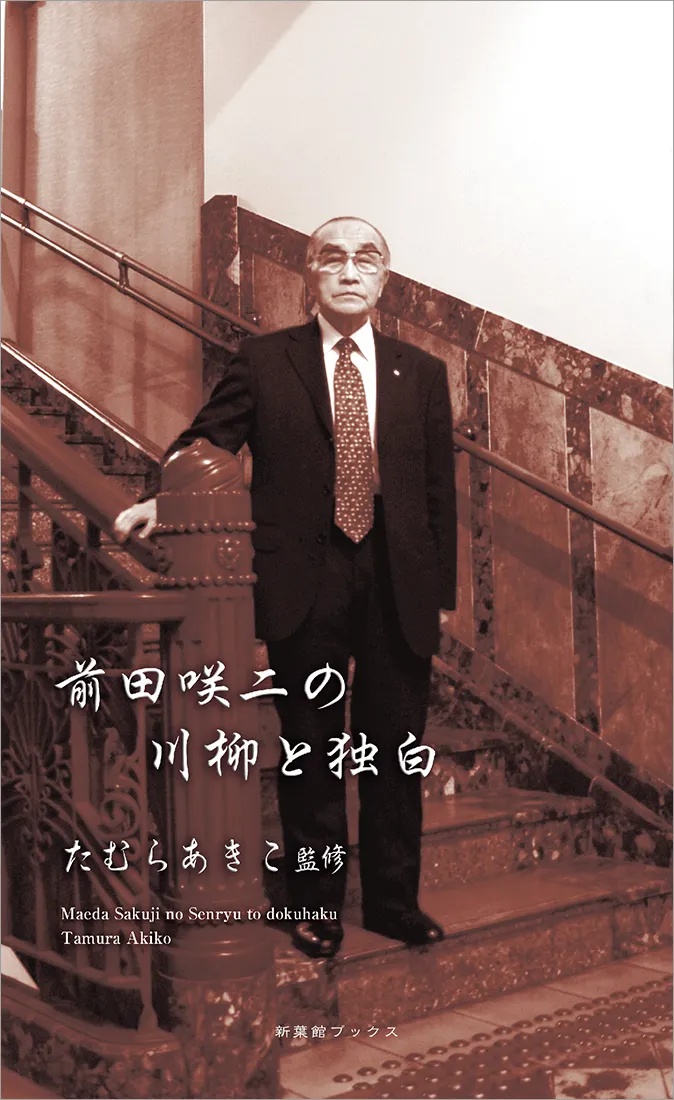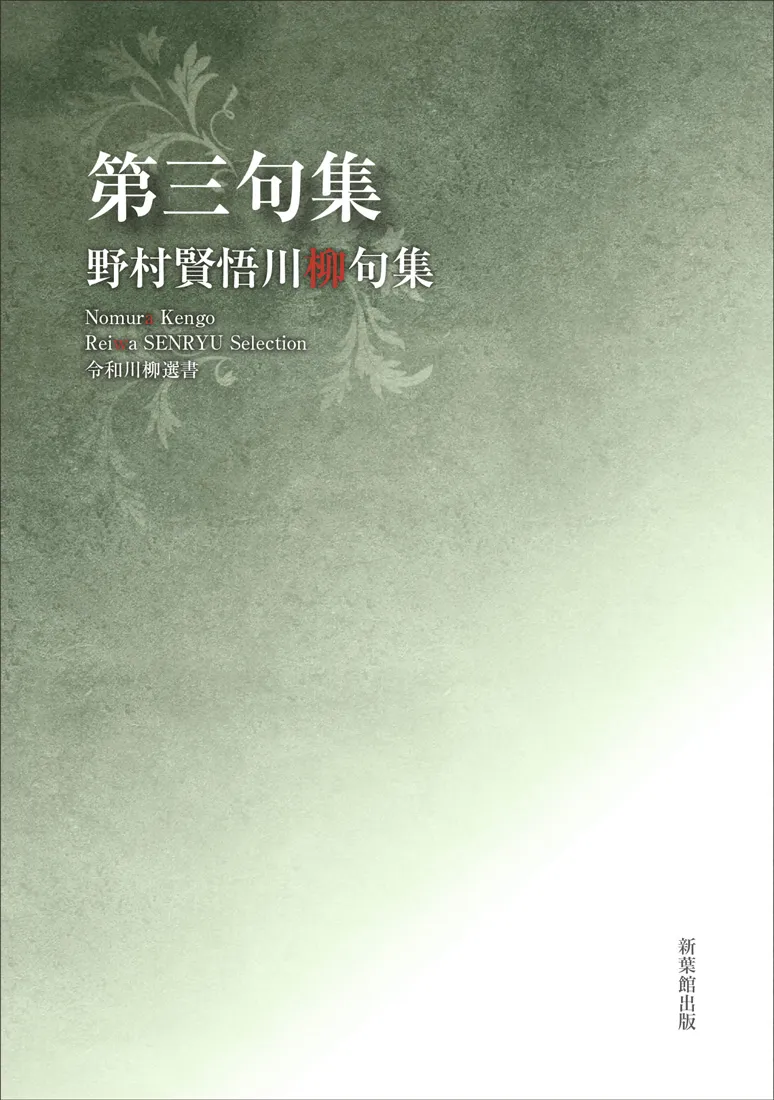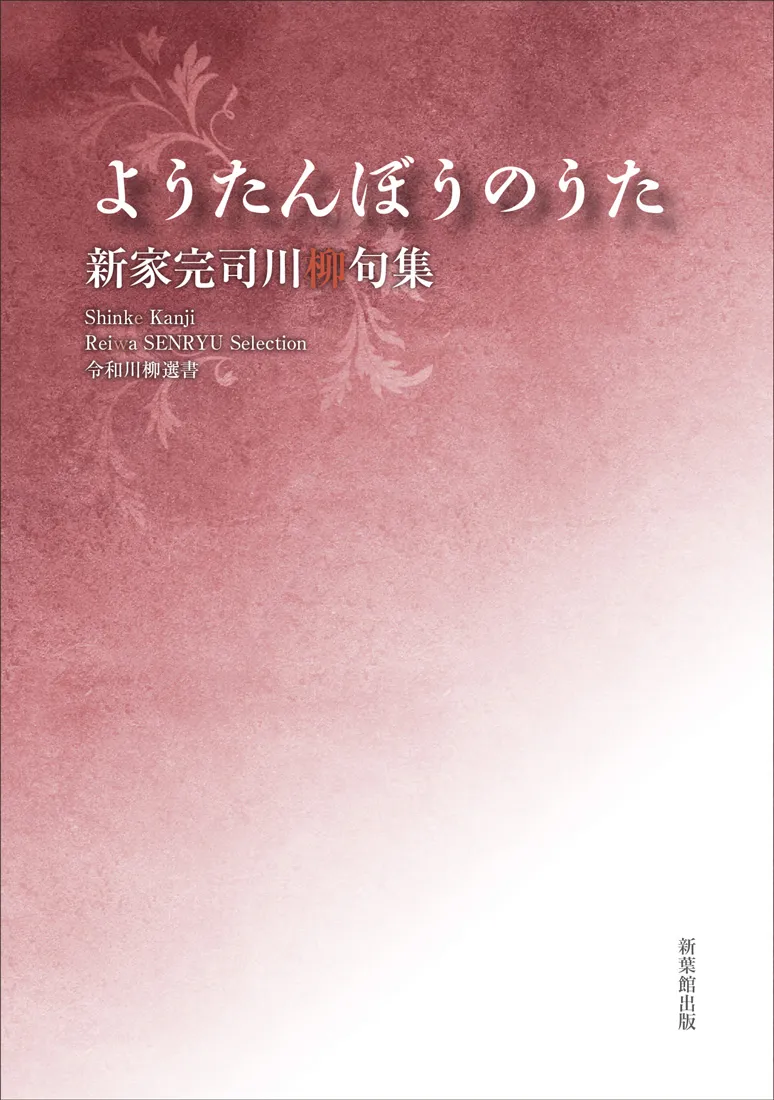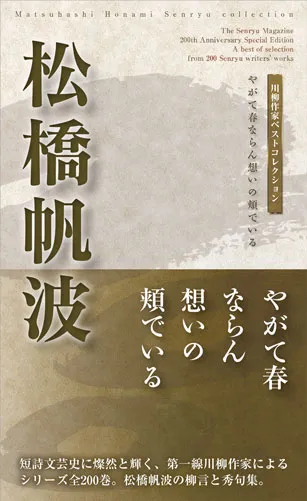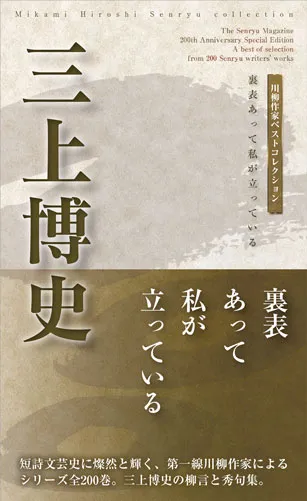本日は『たむらあきこ吟行千句』で、句の下部につける吟行地についての説明を少々まとめた。これから推敲にかかる。個人が嘱目吟(吟行の句)で千句(じつは、1,158句)をまとめるのは、たぶん句数としては短詩型文学史上(あえて文芸とはいいません)初めてではないだろうか。ちなみに、『おくのほそ道』では芭蕉の句はわずか51句(50句ともいわれる)。これからは、あきこも紀行文をつけて詠んでいきたい。
本日は『たむらあきこ吟行千句』で、句の下部につける吟行地についての説明を少々まとめた。これから推敲にかかる。個人が嘱目吟(吟行の句)で千句(じつは、1,158句)をまとめるのは、たぶん句数としては短詩型文学史上(あえて文芸とはいいません)初めてではないだろうか。ちなみに、『おくのほそ道』では芭蕉の句はわずか51句(50句ともいわれる)。これからは、あきこも紀行文をつけて詠んでいきたい。
一昨日21日に新葉館出版さんには上記以外の原稿を送付済み。お忙しいと思いますが、今回もよろしくお願いいたします。
…‥‥‥‥‥‥………‥‥‥‥‥‥………‥‥‥‥‥‥……
 『おくのほそ道』(おくのほそみち)は、元禄文化期に活躍した俳人松尾芭蕉の紀行及び俳諧。元禄15年(1702年)刊。日本の古典における紀行作品の代表的存在であり、芭蕉の著作中で最も著名で「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也」という序文より始まる。
『おくのほそ道』(おくのほそみち)は、元禄文化期に活躍した俳人松尾芭蕉の紀行及び俳諧。元禄15年(1702年)刊。日本の古典における紀行作品の代表的存在であり、芭蕉の著作中で最も著名で「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也」という序文より始まる。
作品中に多数の俳句が詠み込まれている。「奥の細道」とも表記されるが、中学校国語の検定済み教科書ではすべて「おくのほそ道」の表記法をとっている。
おくのほそ道(奥の細道)は、芭蕉が崇拝する西行の500回忌にあたる1689年(元禄2年)に、門人の河合曾良を伴って江戸を発ち、奥州、北陸道を巡った旅行記である[1]。全行程約600里(2400キロメートル)、日数約150日間で東北・北陸を巡って[1]、元禄4年(1691年)に江戸に帰った。
「おくのほそ道」では、このうち武蔵から、下野、陸奥、出羽、越後、越中、加賀、越前、近江を通過して旧暦9月6日美濃大垣を出発するまでが書かれている[2][* 1]。曾良の随行日記も、没後数百年を経て曾良本と共に発見されている。
ほとんどの旅程で曾良を伴い、桜の花咲くころの元禄2年3月27日(新暦1689年5月16日)に江戸深川にあった芭蕉の草庵である採荼庵さいとあんを出発し(行く春や鳥啼魚の目は泪)、船に乗り千住に渡り、日光街道の草加、日光へ道を取って下野国の城下町黒羽へ行く。黒羽では大いに歓迎されたこともあり、おくのほそ道の旅程では最長となる十数日間滞在する地となった[1]。 ここからさらに北へ向かい白河関を越えて奥州に入る。須賀川、飯坂、仙台と渡り歩き、日本三景の一つに数えられる松島では、その美しい風景に感動するあまり句を詠めず、曾良が詠んだ句「松島や 鶴に身をかれ ほととぎす」が収載されている[* 2]。平泉は、おくのほそ道の折り返し地点にあたり、藤原三代の栄華をしのび、「夏草や兵どもが夢のあと」の句を詠んだ[1]。 ここから奥羽山脈を越えて出羽国に入って山寺(立石寺)に立寄り、「閑しずかさや 岩にしみ入る 蝉の聲こえ」の句を残す[1]。 日本三大急流のひとつに数えられる最上川を下り、出羽三山の最高峰である月山にも登り、6月半ばにおくのほそ道の最北の地となった象潟きさかたに到達する。当時の象潟は、松島に劣らぬ景勝地で「松島は笑ふが如く、象潟はうらむが如し」と、その美しい多島風景を評した[1]。 ここから、再び折り返して日本海岸沿いに南下して新潟へ向かい、出雲崎では「荒波や 佐渡によこたふ 天河」と佐渡島を望む日本海の荒波の情景を詠んだ[1]。 さらに海岸を南下して富山、金沢、福井と北陸道を経て、美濃路(美濃国の脇街道)の大垣で「蛤の ふたみにわかれて 行秋ぞ」の句を詠み、結ばれている[1]。 (Wikipediaより、一部)
 Loading...
Loading...