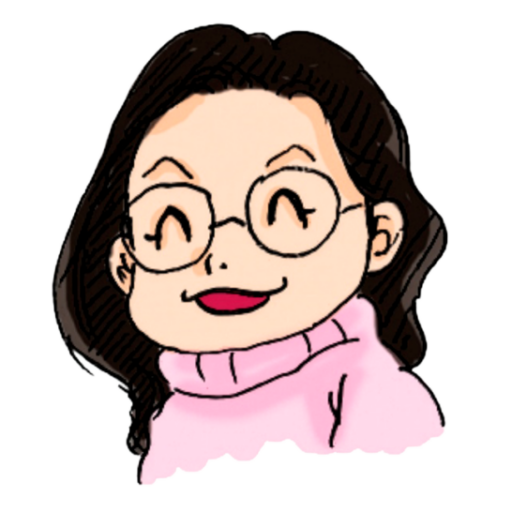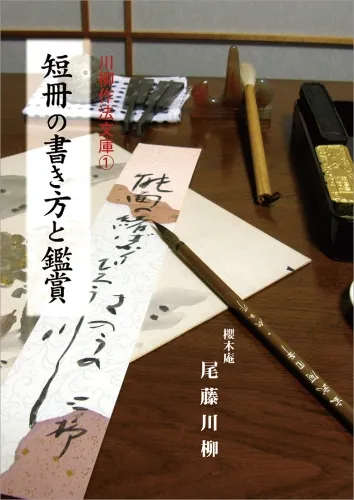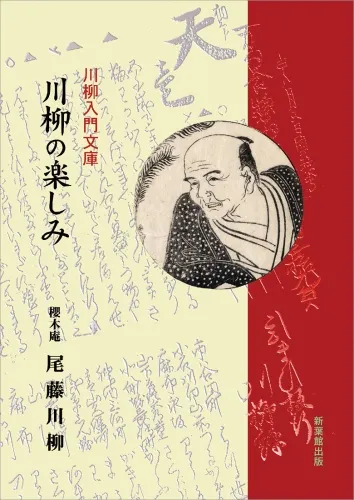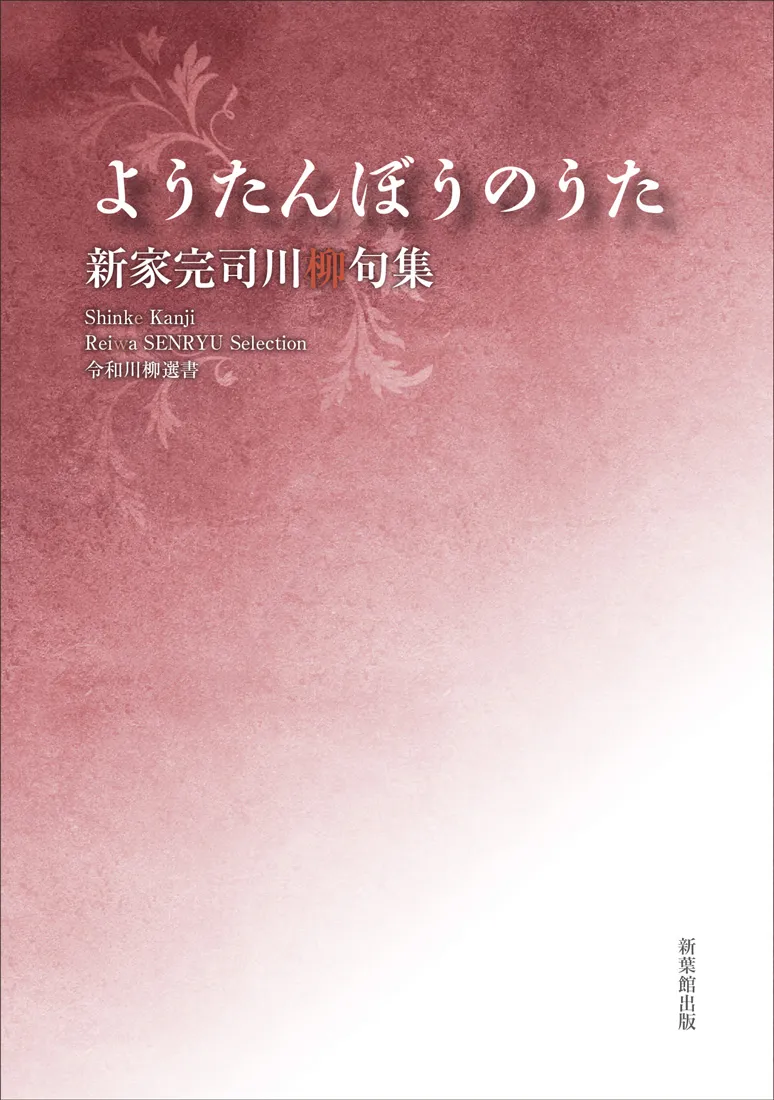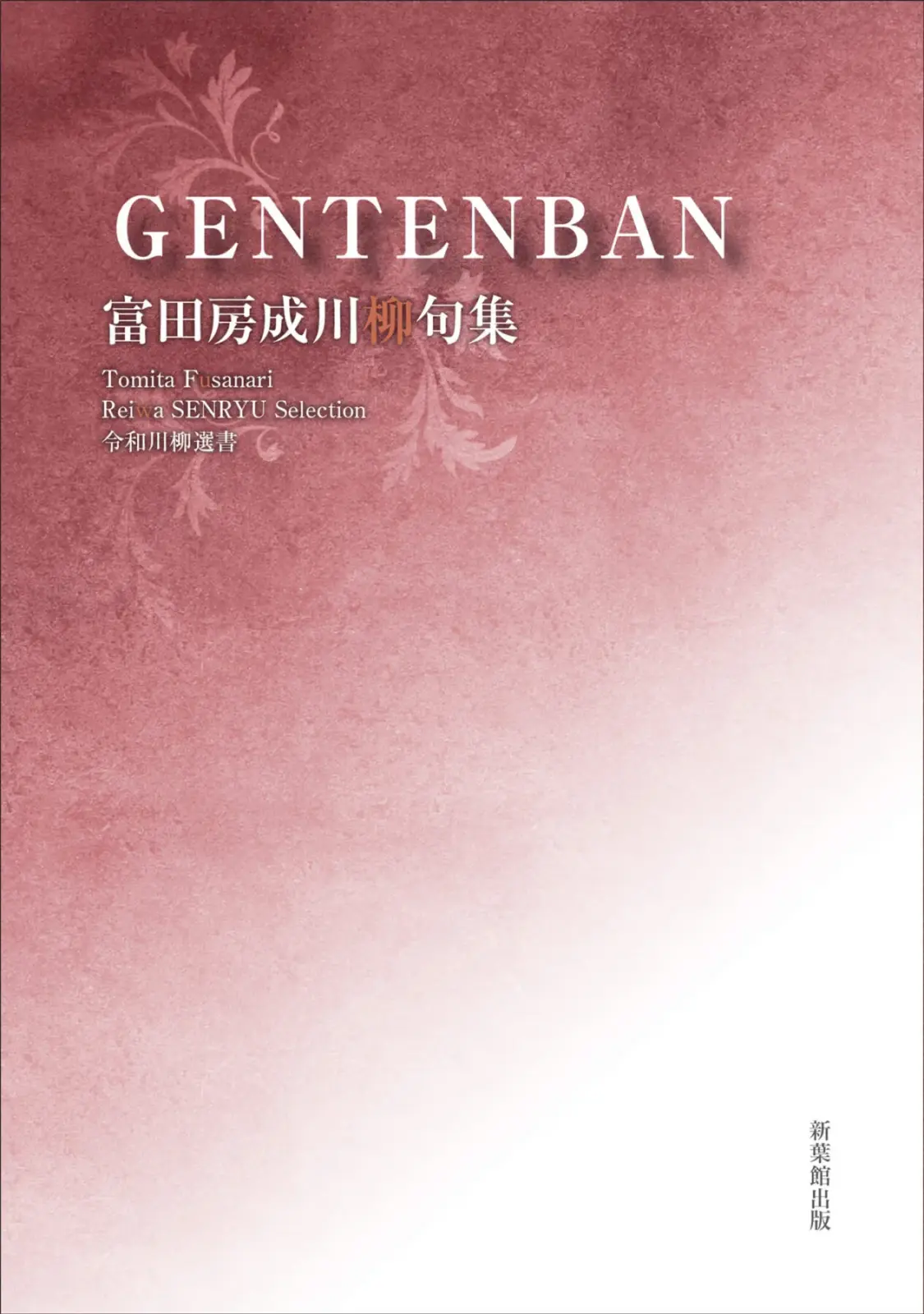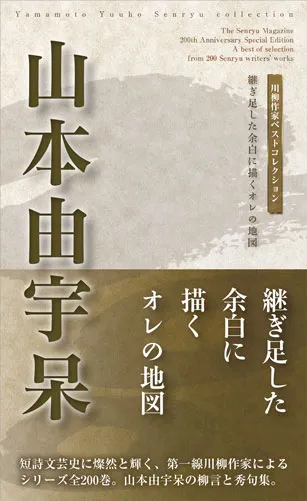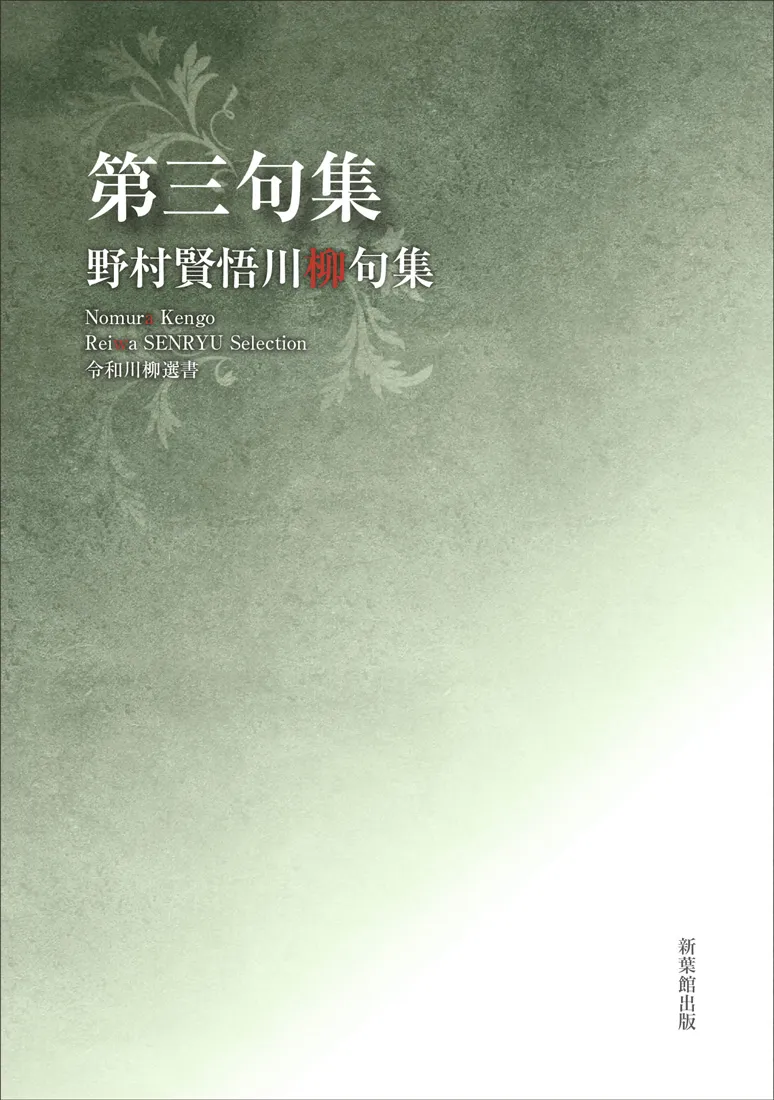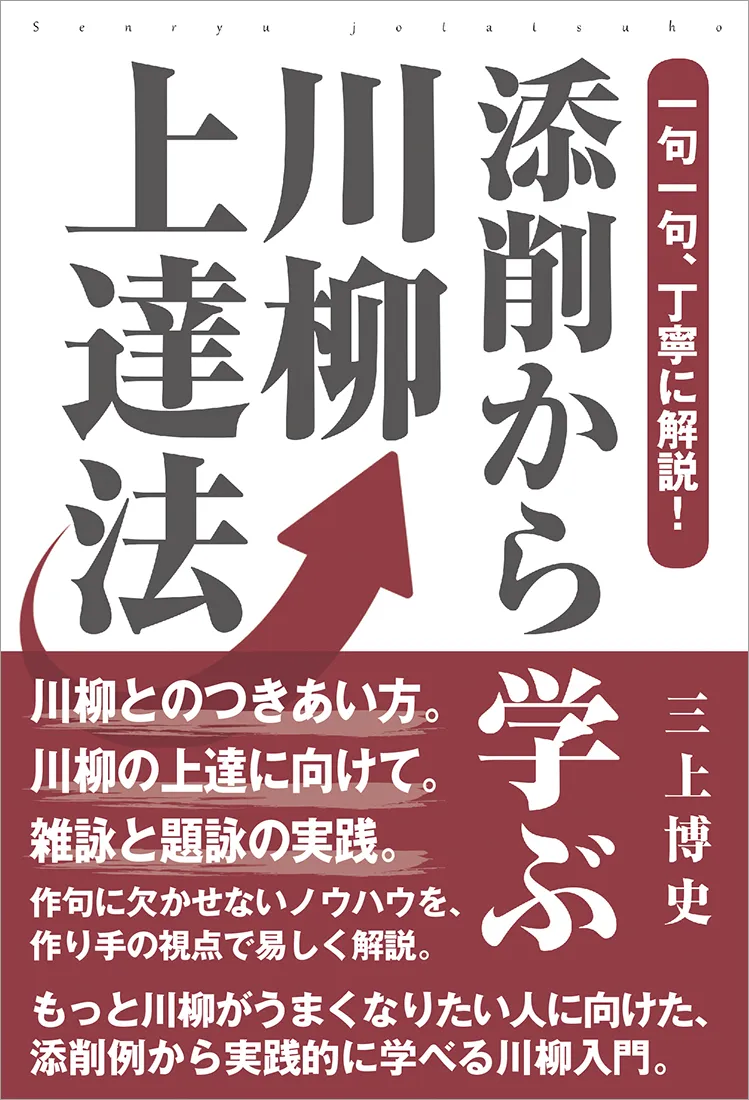句点や読点がピシリとおさまって文脈にそれぞれの場面をつくってゆくことを考えると、句読点とは文章をつづるうえでの魔法の一つかもしれない。川柳ほか短詩型文芸に句読点は、あえてつかわない。詩はあんがい句読点をいとわないようである。短歌や俳句に句読点がつかわれることがまったくないわけではなく、これからは川柳にもしばしば出現するかもしれない。そこに短詩型文芸だからこその効果がないとはいえない。
句点や読点がピシリとおさまって文脈にそれぞれの場面をつくってゆくことを考えると、句読点とは文章をつづるうえでの魔法の一つかもしれない。川柳ほか短詩型文芸に句読点は、あえてつかわない。詩はあんがい句読点をいとわないようである。短歌や俳句に句読点がつかわれることがまったくないわけではなく、これからは川柳にもしばしば出現するかもしれない。そこに短詩型文芸だからこその効果がないとはいえない。
句読点をつかわない(従来の)俳句は、切れ字を句読点の代わりに用いているのではないだろうか。句読点も切れ字も、間(ま)をはさむ。そこに一拍(数拍)の休符、沈黙をうみだす。ことばがないところにことばに代わる表現をうむのである。切れ字では、句のそとに効果が生まれる。《蛤(はまぐり)のふたみに別れ行(ゆく)秋ぞ》(芭蕉)の「ぞ」から始まるものがあるように。
ギリシア以来のヨーロッパの修辞学では、これをアポジオペーシスといって、〈頓挫〉もしくは〈頓絶〉ととらえるらしい。切れ字は、そこまでではない余韻をのこすのである。日本語は仮名をつかいはじめて膠着性が強まったといわれるが、その膠着性をスッキリさせたいという要求にこたえたのが、切れ字という断絶力だった。
切れ字のように修辞的残像すなわち余韻をのこすことが、短詩型文芸における〈省略〉につながるのである。その表現世界にどのような修辞的残像を取り込めるかが肝要。切れ字では空間を限り時間を飛ばし、ちょっとした余情の空間をつくりあげる。日本語の本質にある不決定性、いわゆる曖昧表現こそ修辞的残像をつくってきたそもそもの要因と考えてもよい。
《川柳や要らぬものから脱いでゆく 》(三柳)はブログ仲間の表題から拾わせていただいたもので、これがすぐれた川柳であるかどうかは問題にしない。内容に腑に落ちるところがあり、ここしばらく気になっていたので取り上げさせていただいた。「要らぬものから脱いでゆく」すなわち〈省略〉の要ということが、ふだんわたしが川柳について考えていることと被るのである。ある高名な?柳人の句集を送っていただいたことがあるのだが、数ページを読みきれず絶句した。日を置いて二度、よりていねいに最後まで読ませていただいたのだが。結論からいうと、煌びやかな修辞まみれの内容のない句集だった。
《川柳や要らぬものから脱いでゆく 》、脱ぎ切ったところにスッと立ちあがってくるのが川柳、一行詩なのである。修辞に目がくらむのではなく、しっかり目を見開いて読み切らなければならないということだろう。
 Loading...
Loading...