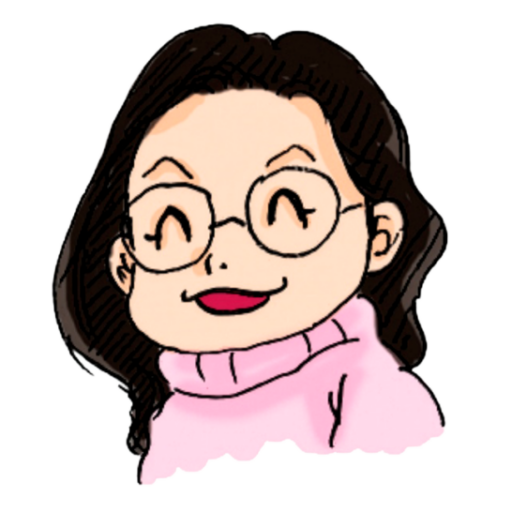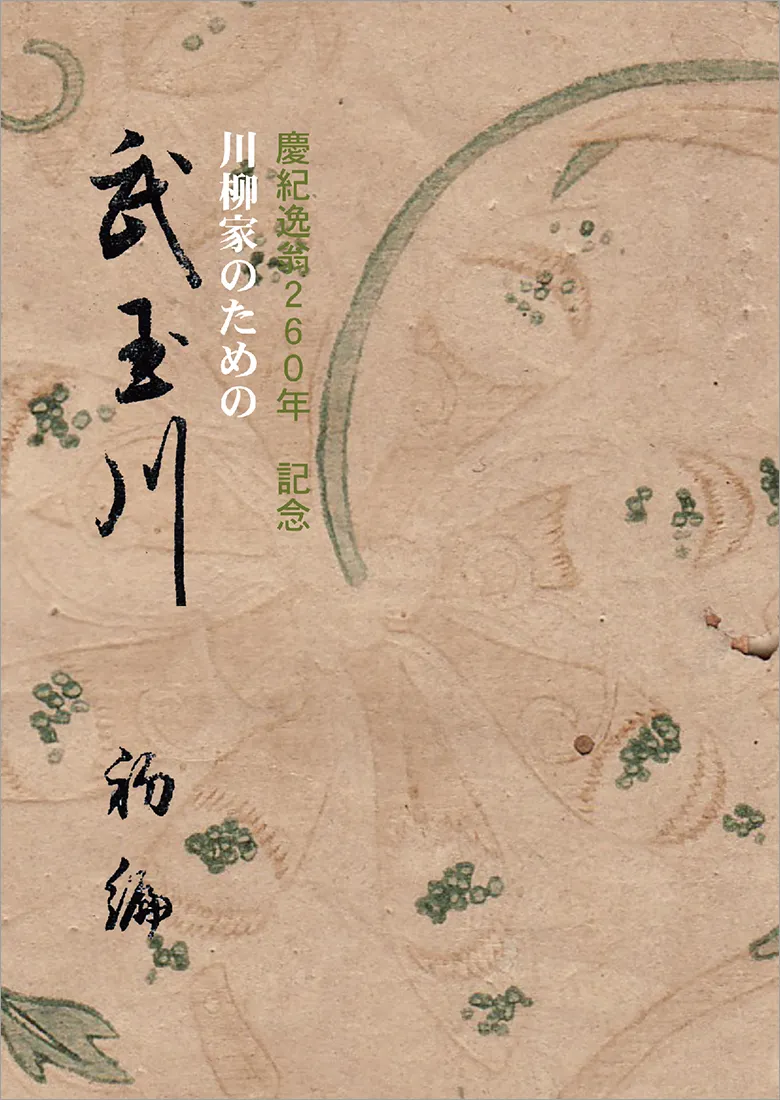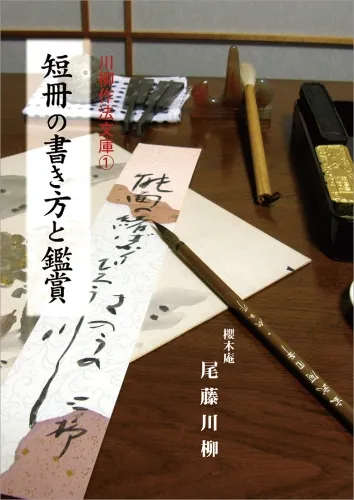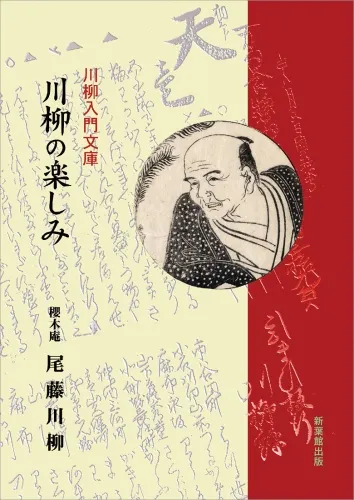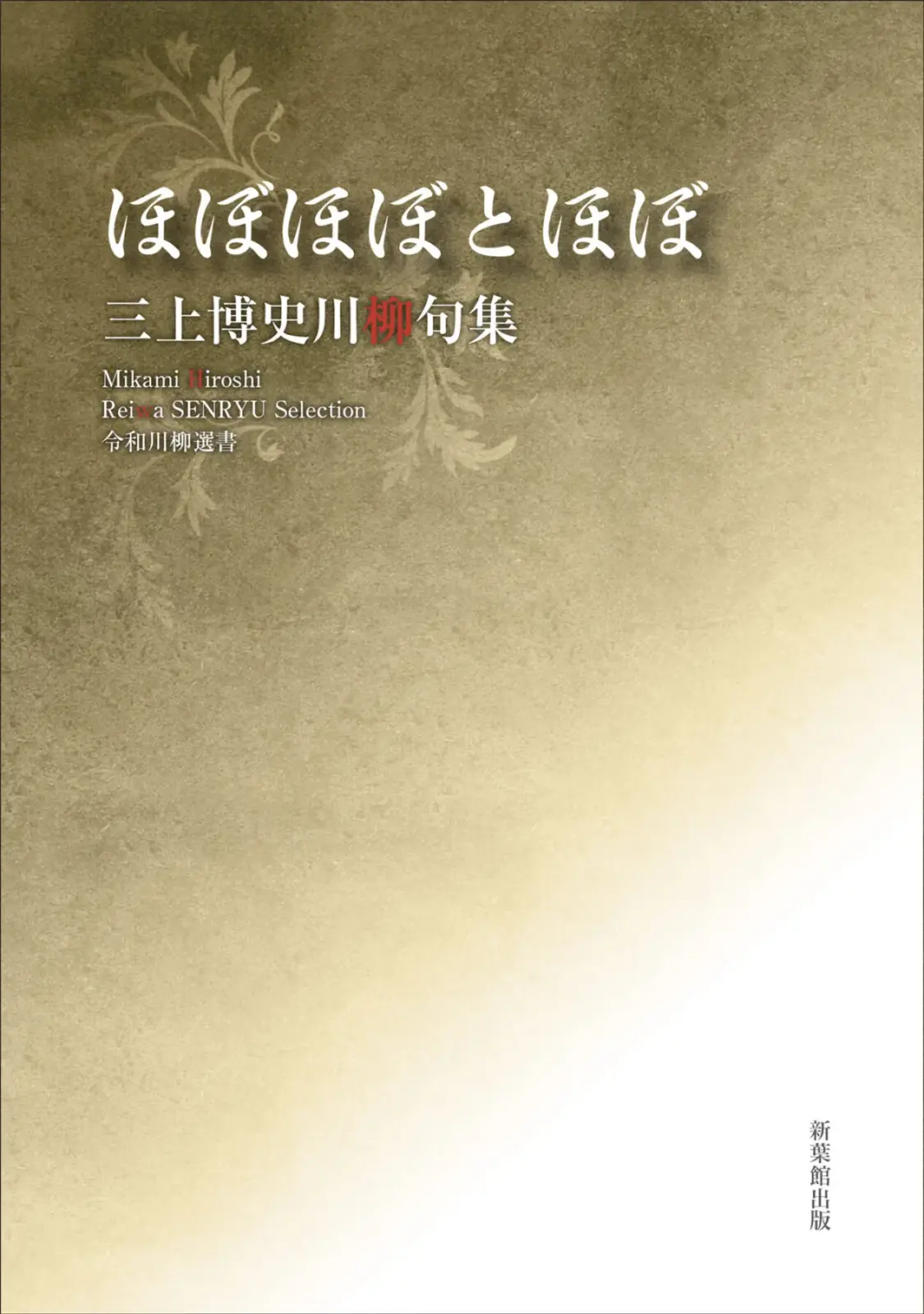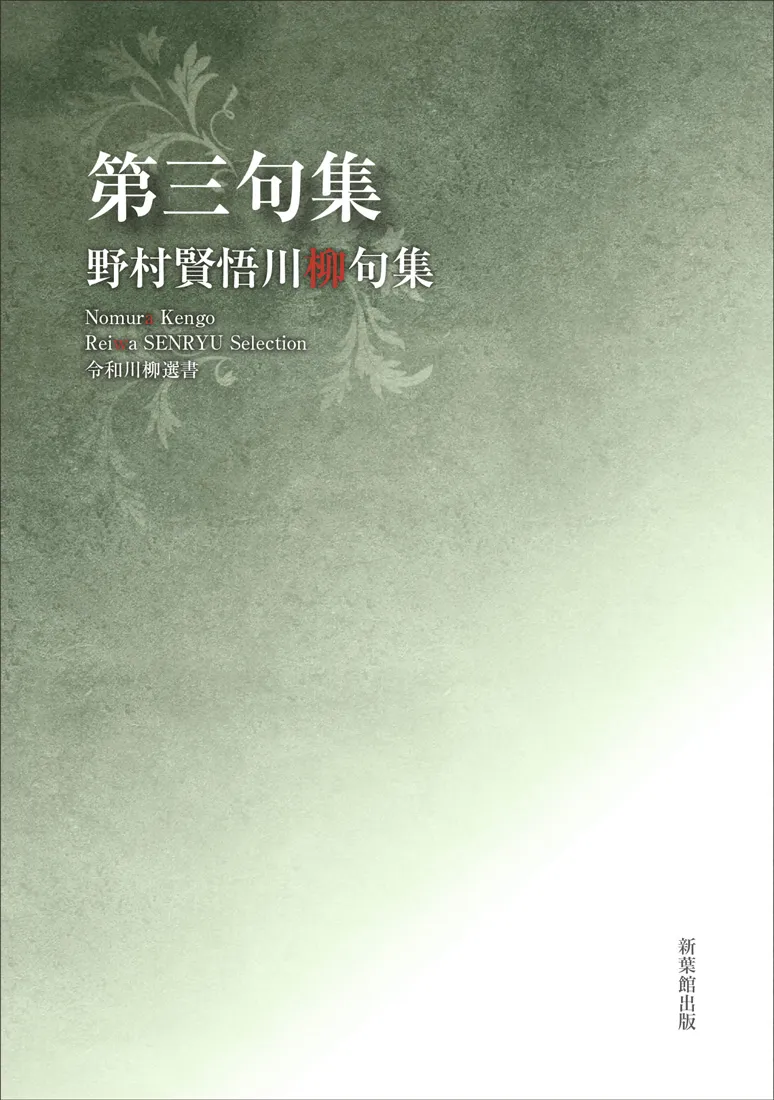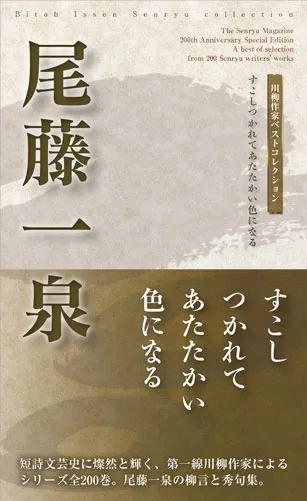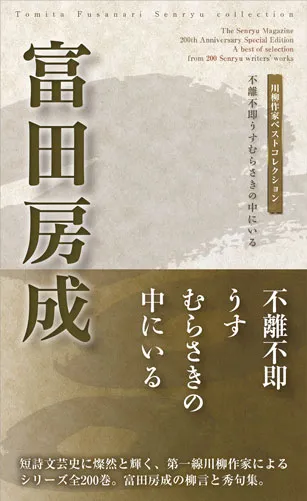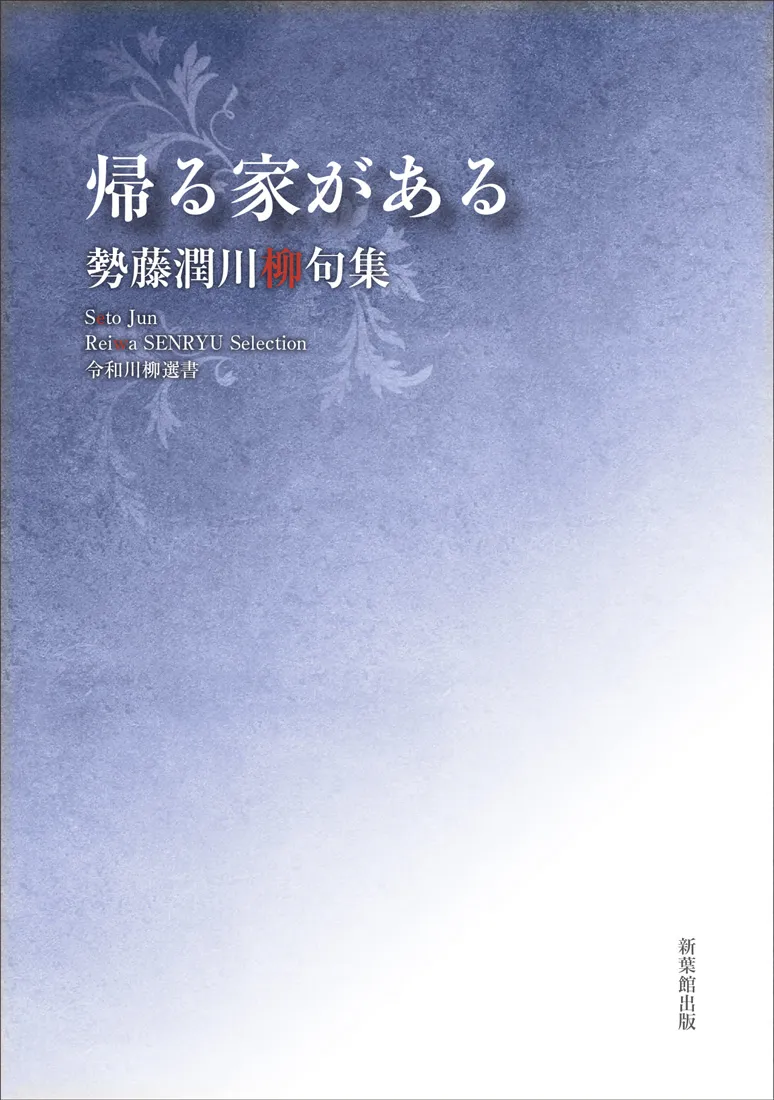今日は、小堀さんのご葬儀。故人のご遺志で家族葬と、奥様から伺っている。昭和25(1950)年9月6日生まれなので、明日73歳を迎えられるその一日前なのね。
今日は、小堀さんのご葬儀。故人のご遺志で家族葬と、奥様から伺っている。昭和25(1950)年9月6日生まれなので、明日73歳を迎えられるその一日前なのね。
早朝自宅マンション(集合住宅)ベランダのカーテンを開けると、快晴。(正午過ぎのいまは、東の方(伊勢)の空が曇っているのね。) 訃報をいただいた一昨日から、小堀さんを知る数人の方々と電話でお話しして、沈痛な気持ちを分かち合った。
難しい学術書などよりやはり詩がいちばん分かるということで、朝から読んでは、とくに分かりやすい詩を選んで写している。あきこの理解の届く範囲でということだが、下記は抄出22篇。優しかった小堀さんを偲びながら。(13時20分、また晴れてきている。)
…‥‥‥‥‥‥………‥‥‥‥‥‥………‥‥‥‥‥‥………‥‥‥‥‥‥……
雨が上がり、薄っぺらな雲が北へ北へと急いで流れる。
わずかに見え初めた青空、もう一度会いたい人たちの浮かんでいるところ。
魂の影が薄くなり、やがて誰の呼びかけにも答えなくなる。
魂が御霊(みたま)となるか、神となるか。
誰が祭るか、何を奉るかによるのだろう、豊穣の秋に。
深いみどりの山々のうしろで、うす紅の夕空が予言している。
明日は逢えると。
自然薯の切りくずを鉢植えにしていたら、子供の釣竿をつたって二階までつるが伸びた。
青々としげった葉が、少しずつ枯れてゆく。
実りの季節、眠りのときが来た、ということか。
記憶の分身、親子とはそういう意味にすぎない。
去ることもまた、記憶の開放にすぎないと言えばあまりに切ないか。
この世の者にも、隠れた者にも、十六夜の月光が明るい。
窓ガラスに月光がきらっと映った。
会いに出かける時間か、酒神たちに。
人が去ったあとに残っているもの、風にかき消されそうなもの。
数知れない魂の軌跡が夜の宇治橋の上にある、星降るように。
じつに、ほんとうにばらばらに散らかった人生だなと振り返る。
いつ止むともしれない雨音を聴きながら、片付けるいとまのなかった人生を肯定する。
ぼうっとでも死期を悟ったら、口に出せないことは目で熱く念願するだけだ。
そこに湧き上がってくる言葉の一片でも、あなたに残し得たら、至福というしかない。
柿の実のつややかに熟れてゆく色の美しさ。
さわやかな秋風に吹かれていると、このまま石になってしまってもよいと思う。
いつかあなたがこの石の慕わしさに気付いてくれる日のあることを願って。
あつたの杜の木漏れ日をひとつふたつと拾いつつ、神の御前(みまえ)に額突く。
すずしい秋風が通りすぎ、今日一日が清まったやろ、と小鳥たちが囀っている。
巧妙な刹那主義に生きている人は振り返らない。
危険はいつも前からやってくると信じているからだろうか。
未来はどこまでも自分の生の時間と信じているからだろうか。
小川の清明な音と囀る鳥の声は、この世のものでないように聴こえる。
いずれ影さえ残らない身を祝福している秋の、晴れた早朝。
「君がため捨つる命は惜しまねど心にかかる国の行末」。
この歌をうべなう者の腸(はらわた)は、生涯腐りません。
海援隊長龍馬は慶応三年十一月十五日、三十三歳になった日、暗殺されました。
小春日和の雲出川左岸にすすき野は広がり、風は山から海へ吹く。
心地よい風景の中で、またしても問わねばならぬ、日本は亡ぶかと。
大都会の一票と限界集落の一票とは平等ではない。
山林田野を荒したのは、都会の経済論理を正しいとしたからだ。
冬の雨が降る、山では雪か。
肌刺す夜風が私を歩ませる。
街かどの暗闇に、私に似た眼差しの者がうずくまっていた、さようならと告げた。
十二月の十六夜の月明りの中に、声をかけたい人たちが立っている。
身も心も洗われるような月光の中に、御祖(みおや)たちもまた、月を眺めている。
五十鈴川の水が手にあたり、指を通りすぎる。
時の流れが私たちの体を通りすぎるように、流れて止まないものが私の今を清めてゆく。
一転して、寒風吹きすさぶ朝となった。
先生、墓石の下は凍っていませんか。
冬空は青く、無風で、白雲が静止している。
死に場所を捜したくなる日和。
祖霊に語りかけたくなる真昼の明るさ。
本当は書くべきことなど、この世にありはしない。
言葉そのものが文学であったと万葉集という石文が伝える。
夜を雨がひとしきり叩いて春はくるのだろう。
 Loading...
Loading...