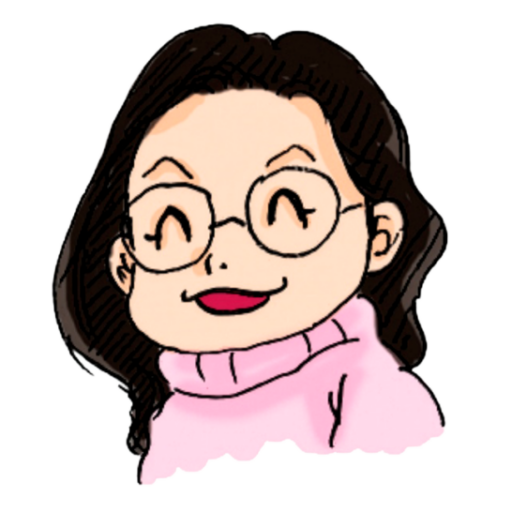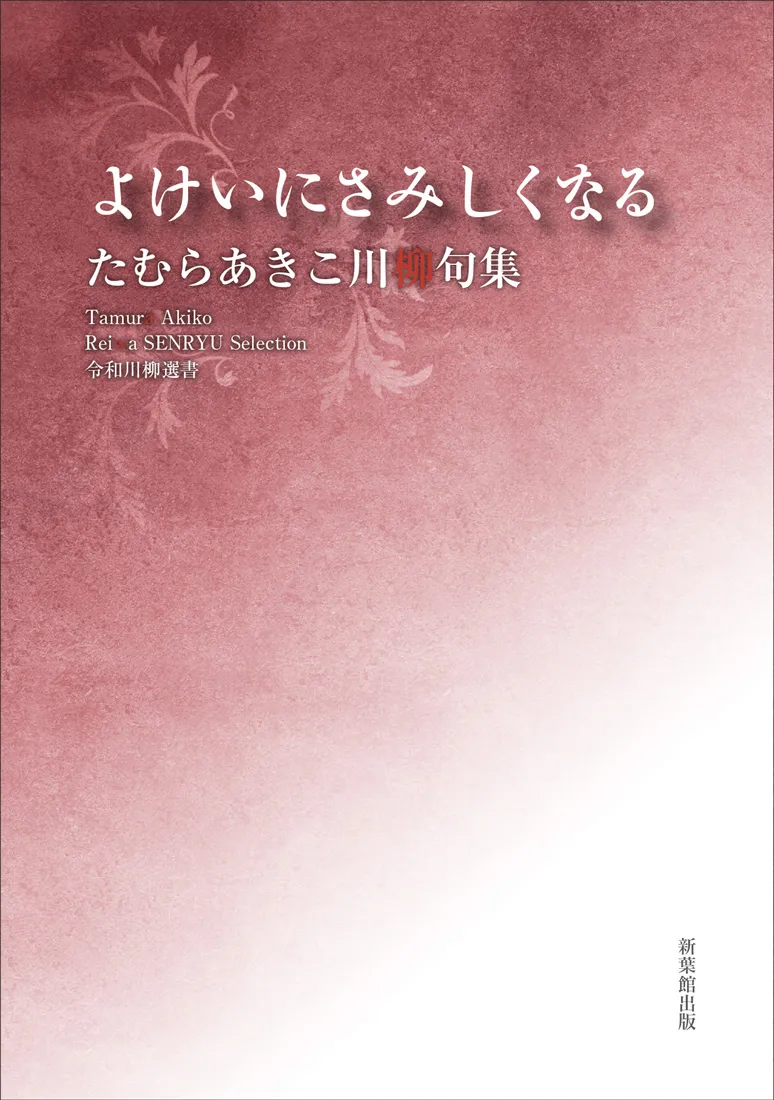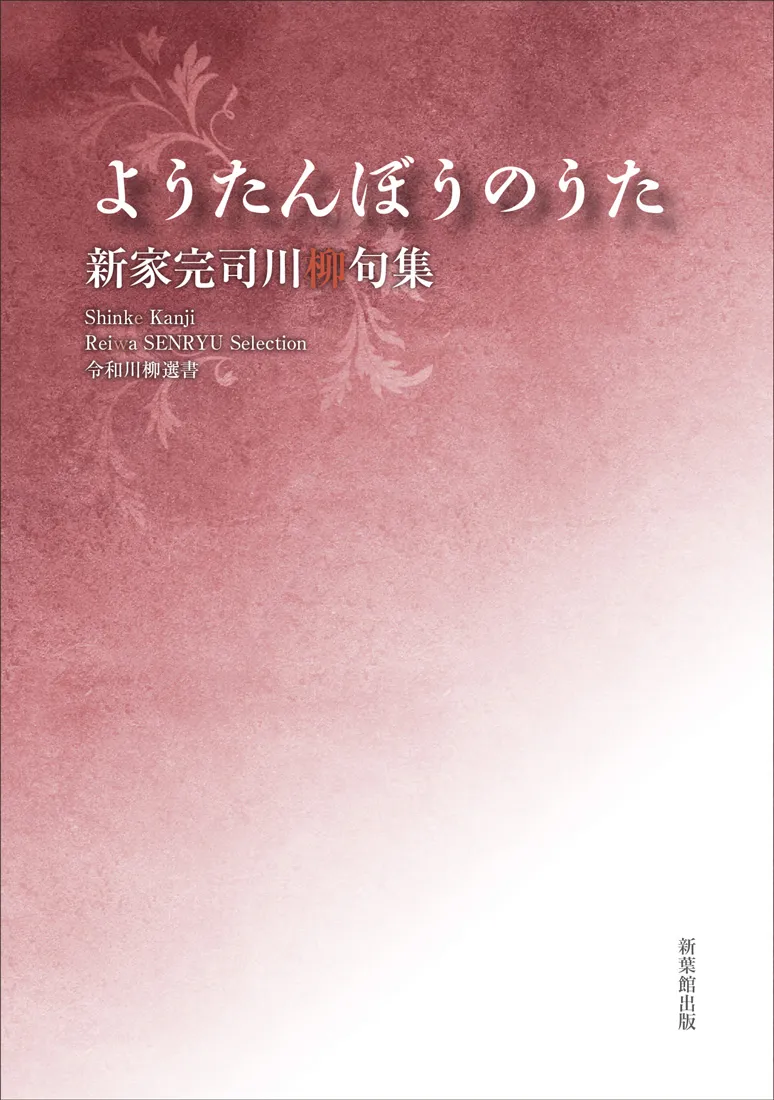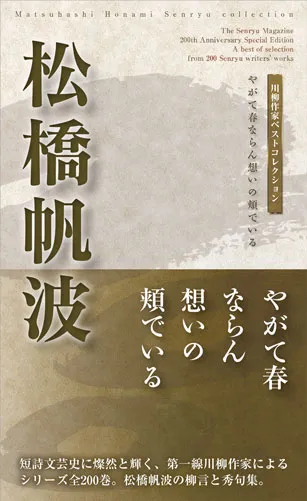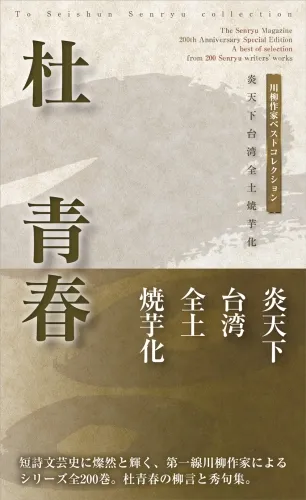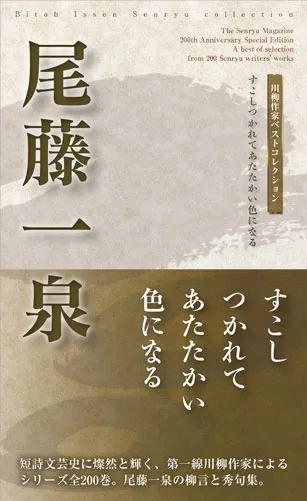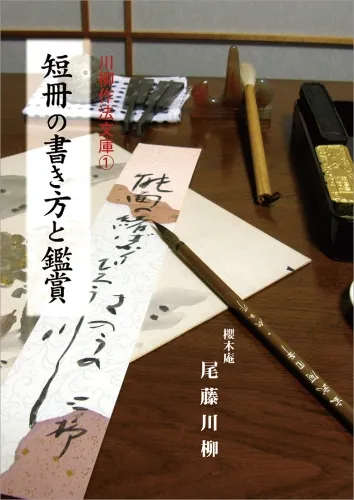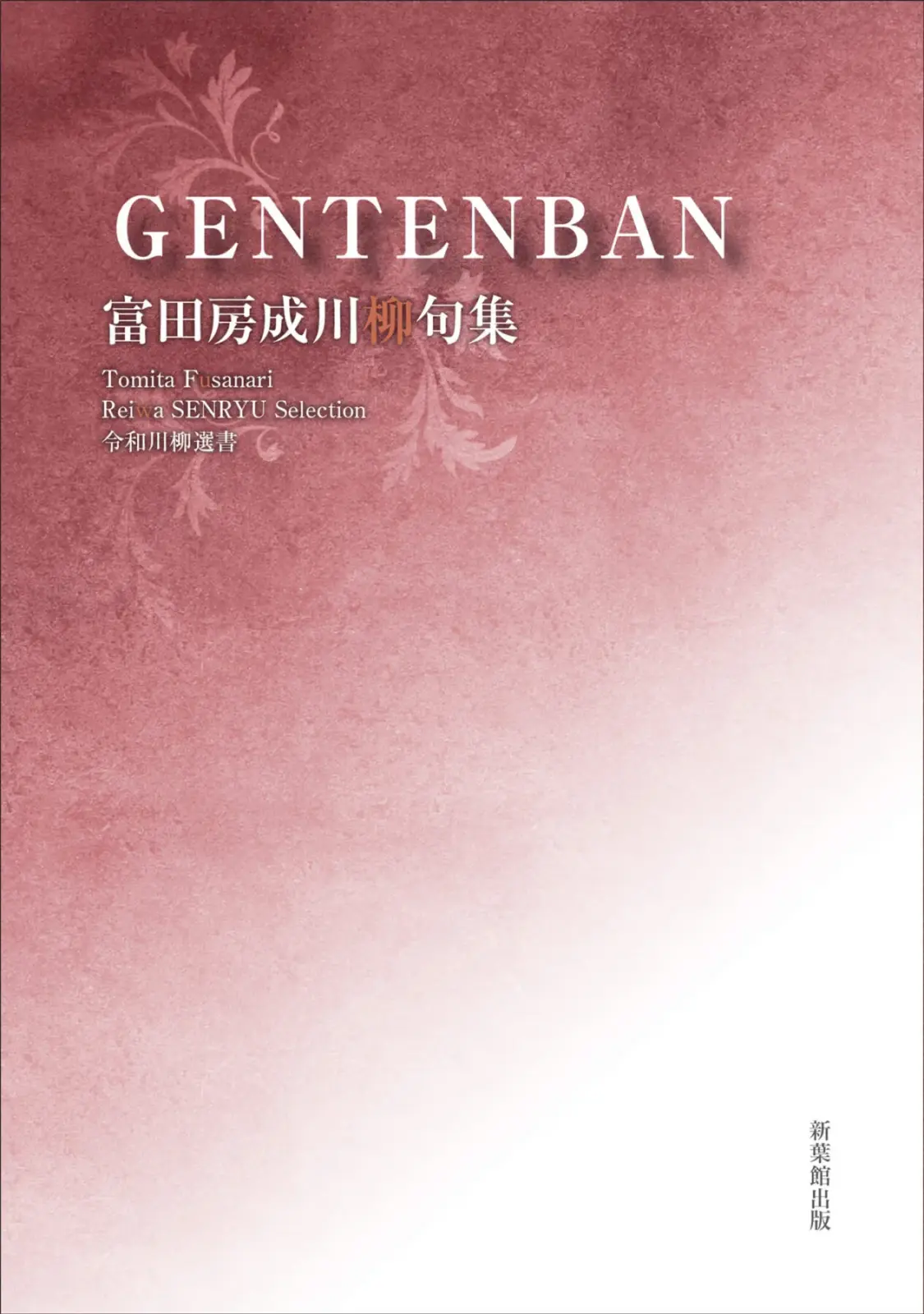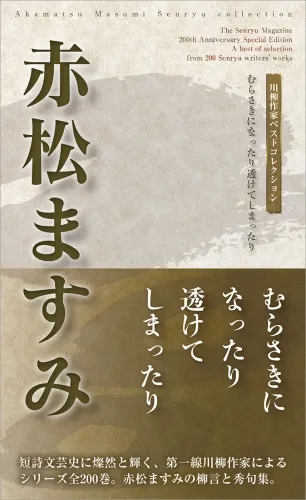彼(か)の人の眠りは、徐(しず)かに覚めて行った。まっ黒い夜の中に、更に冷え圧するものの澱(よど)んでいるなかに、目のあいて来るのを、覚えたのである。
彼(か)の人の眠りは、徐(しず)かに覚めて行った。まっ黒い夜の中に、更に冷え圧するものの澱(よど)んでいるなかに、目のあいて来るのを、覚えたのである。
した した した。耳に伝うように来るのは、水の垂れる音か。ただ凍りつくような暗闇の中で、おのずと睫(まつげ)と睫とが離れて来る。
‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥
上記は、折口信夫(おりくち・しのぶ)の幻想的小説『死者の書』の冒頭。この一冊の感想をどう書けばよいのか。今回の 二上山吟行の遠い動機であり、わたしの読書歴の中でも「とっておき」がまさにこの小説なのである。この作品については凝縮された〈詩〉ということができるだろう。
とくに長い作品ではなく、霧の中にいるような儚い感触でありながら、そこに〈ものがたり〉の真髄があるようにも思える。
『死者の書』の舞台は、麓に当麻寺のある二上山。ここに大津皇子伝承や中将姫伝説がのこっている。
「した した した」と雫が垂れる塚穴の岩床でめざめたのは、死者(※大津皇子)である。死者は射干玉(ぬばたま)の闇の中で「徐(しず)かに」記憶を呼び戻す。物語の冒頭、幽明さだかならぬ境界をゆらめく記憶の断片が、明け方の霧の中に森の木々がうっすら見えてくるように始まる。
『死者の書』の舞台であるこの地域は日本で最も古い神の伝承をもつ。若くして自害(※Wikipedia)に追い込まれた大津皇子の無念がわだかまる地。この地を数時間歩いただけでも、どことなく死のにおいが漂ってくる。
うつそみの人にあるわれや明日よりは二上山を弟世(いろせ)とわが見む 大伯皇女
大津皇子のたましいに語りかけ、また慰めるべく近鉄南大阪線当麻寺駅から鳥谷口古墳(※大津皇子の本当の墓ではないかという説がある)までの道を歩いた。途中せせらぎの音。かの時代に想いを馳せ、姉・大伯皇女の想いに想いをを重ねるつもりで歩いてきたのである。
 Loading...
Loading...