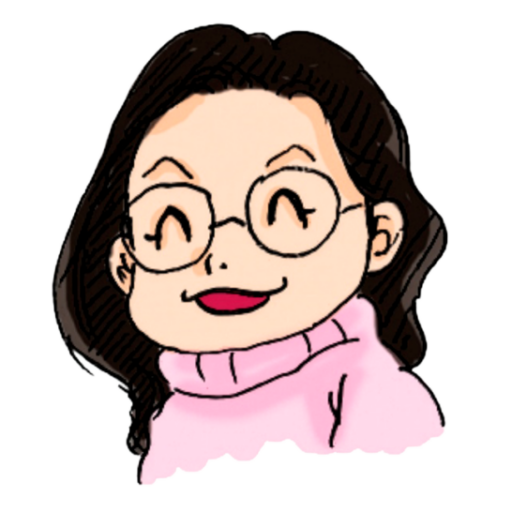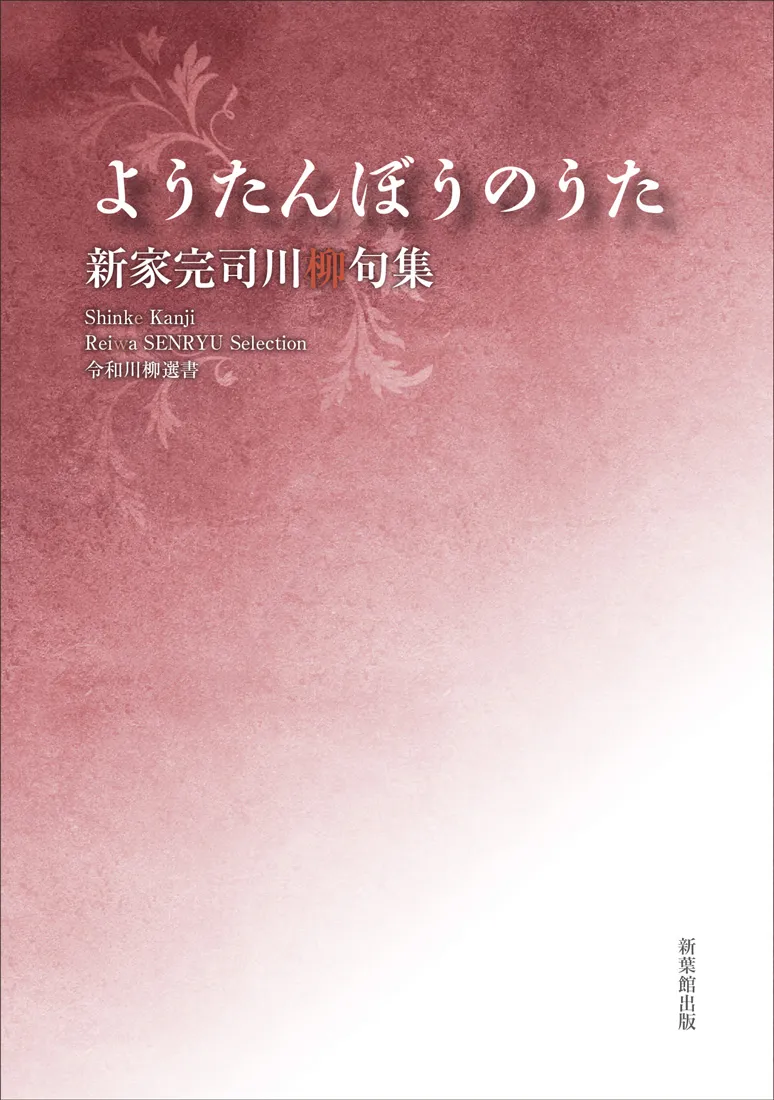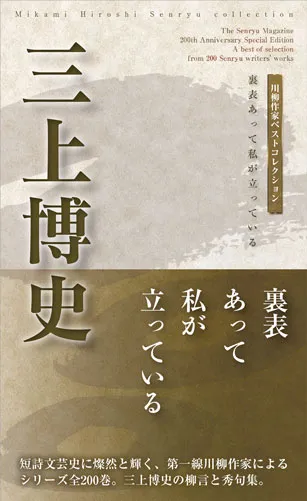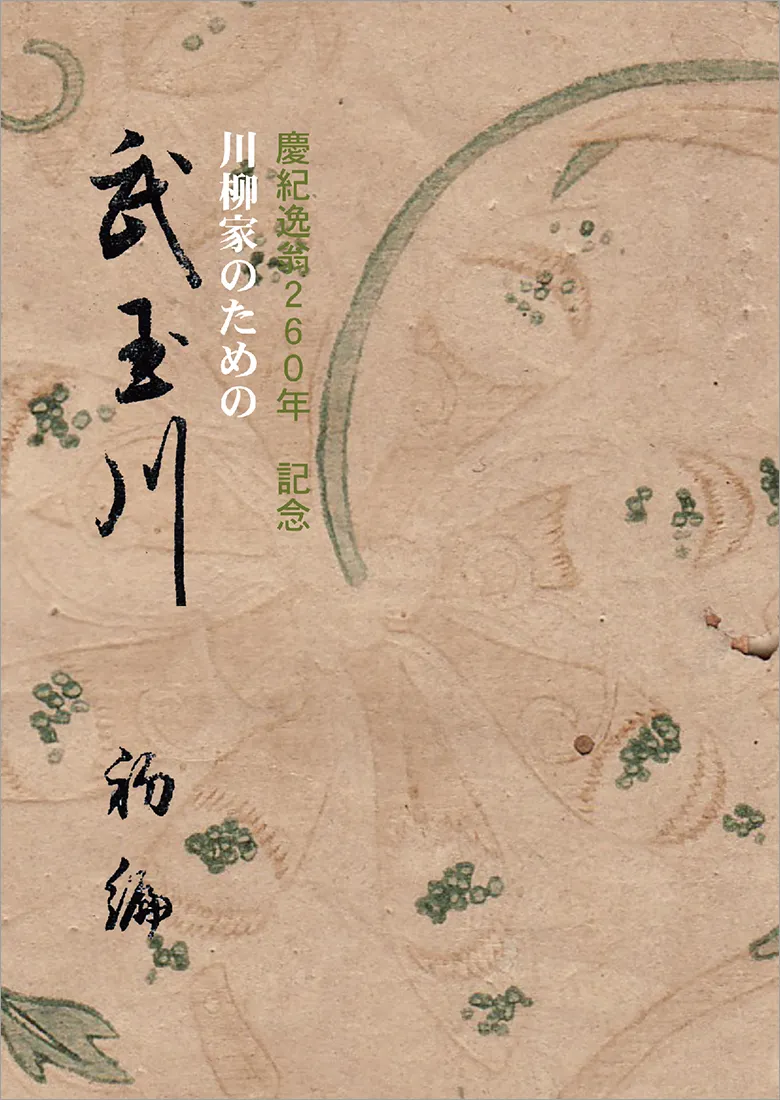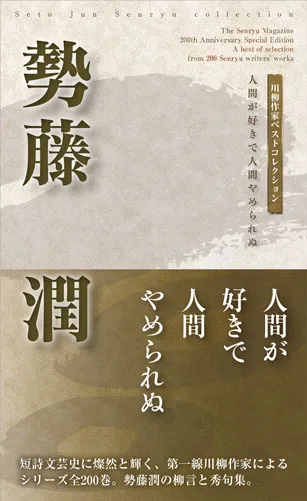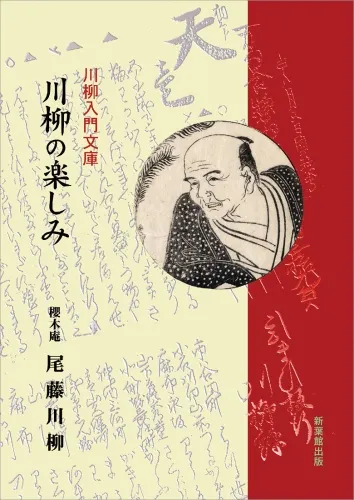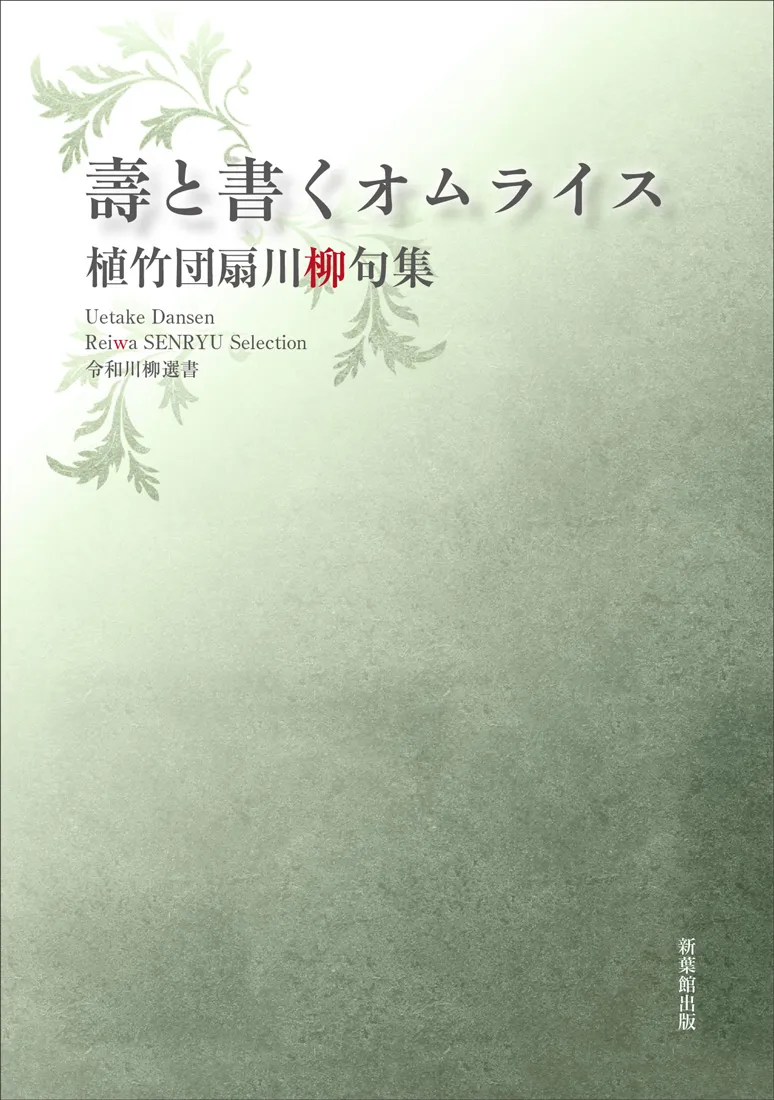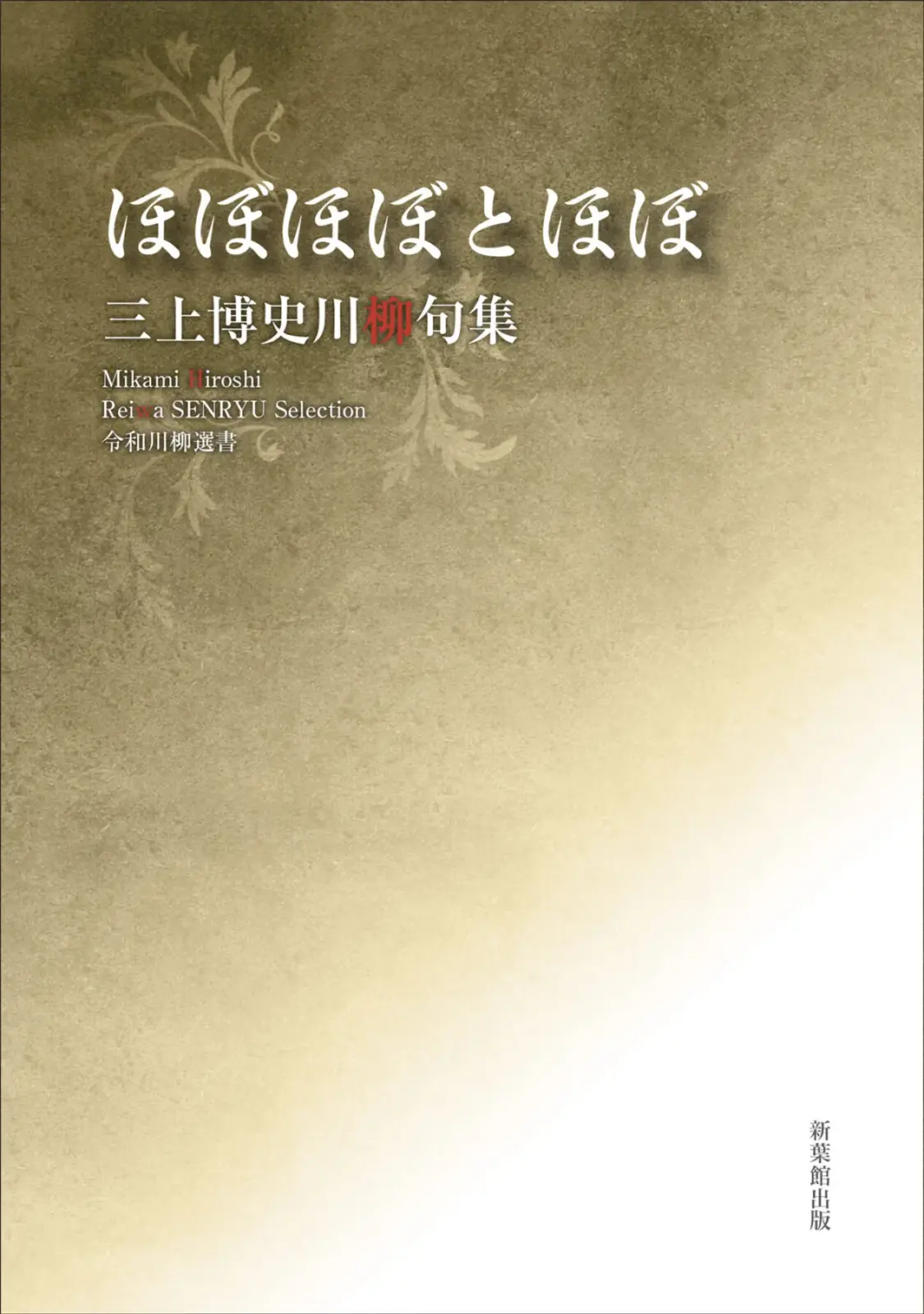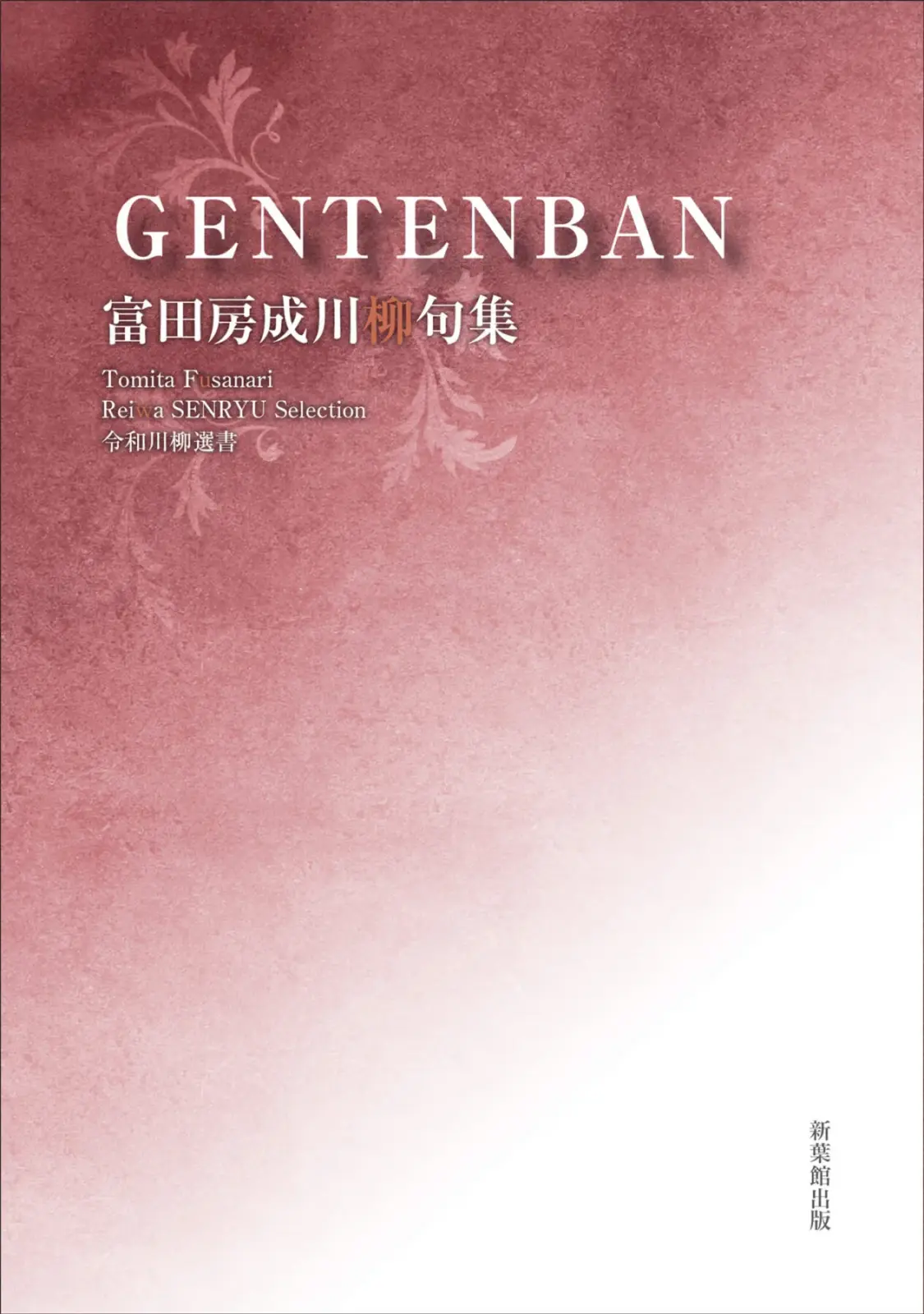わたくしの妬心がわたくしを炙る
わたくしの妬心がわたくしを炙る
「妬心」は嫉妬心。嫉妬が自らの身を焼くということを、「炙(あぶ)る」という動詞に置き換えて詠んでいる。じわじわと焼かれるということで、「炙る」。
享年のことを叫んでいる墓石
夭折の人の墓に参るほど悲しいことはない。病死、事故死、また自死。石の下から「まだ死にたくはなかった、ほんとうはもっと生きていたかった」との叫び声が聞こえてくるようだ。
一閃の恋がいのちを朱に染める
「恋」とは「いのち」の一瞬の閃きのようなもの。理屈ではない何かに突き動かされるのだろう。わずかに指を折るほどしかないわたしの「恋」もそうしたものだった。
いつも何か足りずに指を噛んでいる
衣食住足りていても「いつも何か」足りない、その「何か」とはなんだろう。ひたすら川柳を詠むことでその「何か」を埋めているのかもしれない。
わたくしの中に妬心という日陰
「妬心」、嫉妬心というものが誰のこころにも巣食っている。暗くじめじめして、あたかも「日陰」のようなものであると。
 Loading...
Loading...