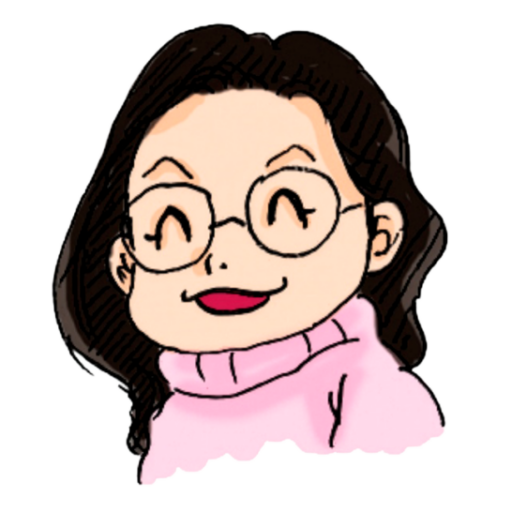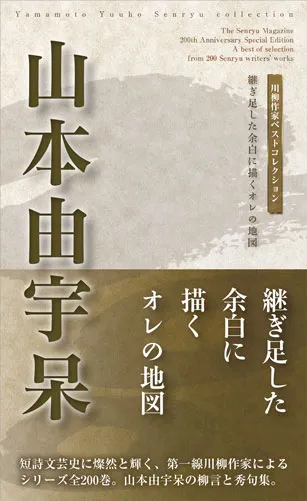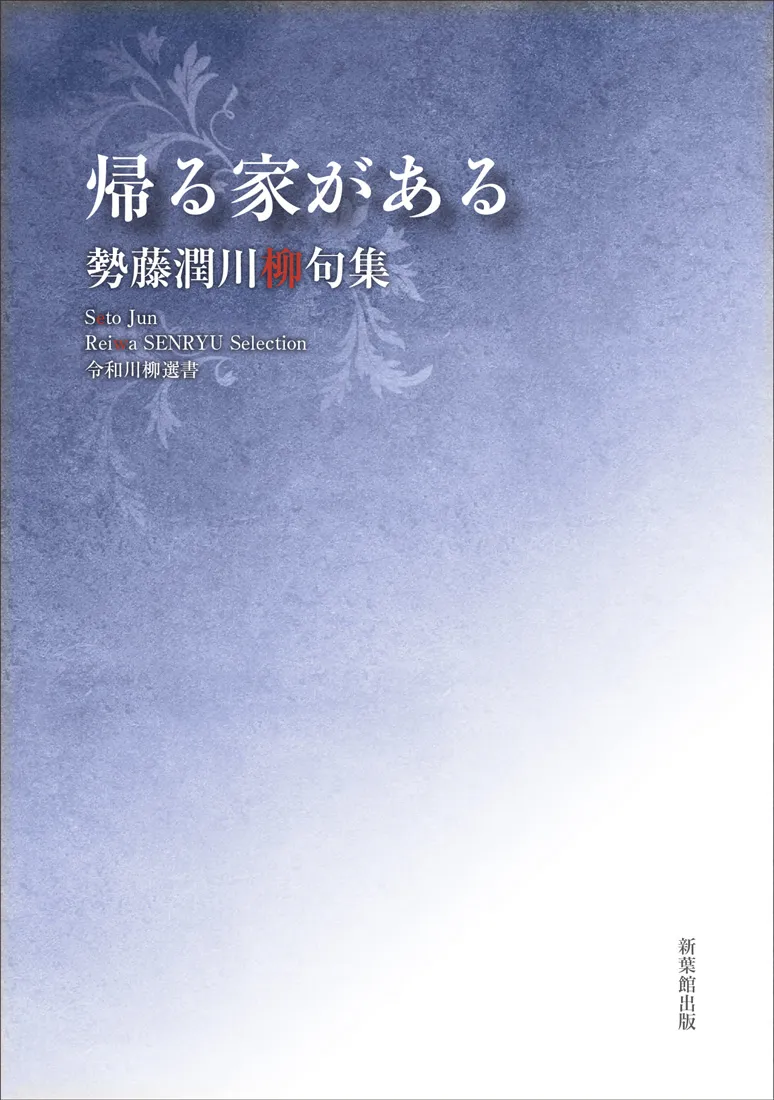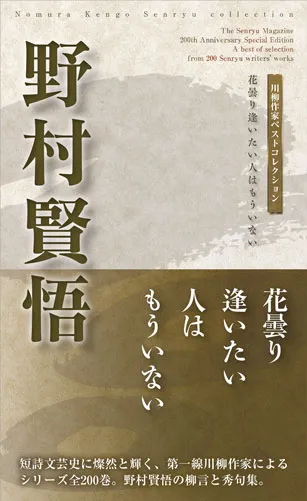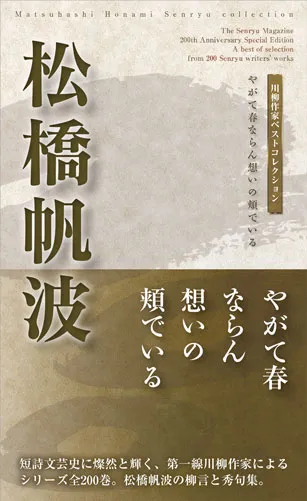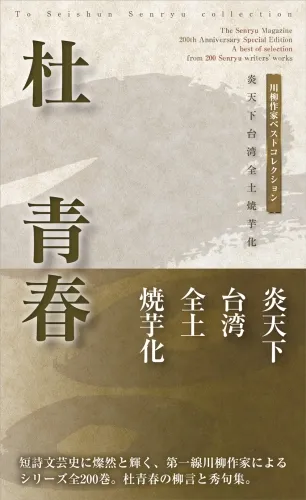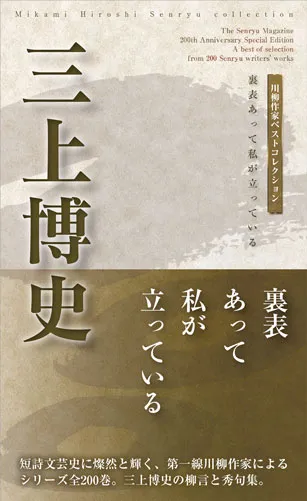灯台下暗し、ということか。行ってみればさほど遠くもないのに、紀南はずっと心理的に遠かった。串本にはずいぶん前に短歌の会や詩の会で行ったことがあるのだが、その先の新宮となると遥か竜宮(?)のように遠い地のような気がしていた。
灯台下暗し、ということか。行ってみればさほど遠くもないのに、紀南はずっと心理的に遠かった。串本にはずいぶん前に短歌の会や詩の会で行ったことがあるのだが、その先の新宮となると遥か竜宮(?)のように遠い地のような気がしていた。
6月25日の鈴鹿市民川柳大会の翌日、近鉄白子駅から津経由でJRに乗りかえ、那智勝浦に向かったのだが、列車の車窓から見る熊野灘(くまのなだ)は想像以上に美しかった。風光明媚に癒される以上の感銘を受けた。海岸線に沿って走るので、車内に津波が来たときの対応がどうとなど書かれていたのは目新しいことだった。
風景の美を考えるとき、浮かぶのはほぼ半世紀前のノーベル文学賞受賞作家川端康成の「美しい日本の私ーその序説」。文学賞受賞に際しての講演内容だが、当時何度も掲載の新聞を読み返したことを覚えている。
川端はまず、道元や明恵の古歌に心惹かれることを、それぞれの詩句を挙げて自然と融合した日本人の心と説明。月を見て月に話しかける心情など、自然を見つめ、それを友とした古(いにしえ)の日本人の心や宗教観を語った。35歳で自殺した芥川龍之介の遺書の中の〈末期(まつご)の眼〉という言葉に関連させ、人間の末期の眼には自然はいっそう美しく映じるものだということ、さらに「自分の死後も自然はなほ美しい」、日本人にとっては生と同様に死も自然との合一、自然への回帰であるというようなことも語っていた。ひと言でいえば日本的な美意識である「もののあはれ」の心情がこれに通底する。
いま聖地熊野をくり返し吟行しようとするわたしにも、不断に日本的な「もののあはれ」の心情が添っているといえる。
 Loading...
Loading...