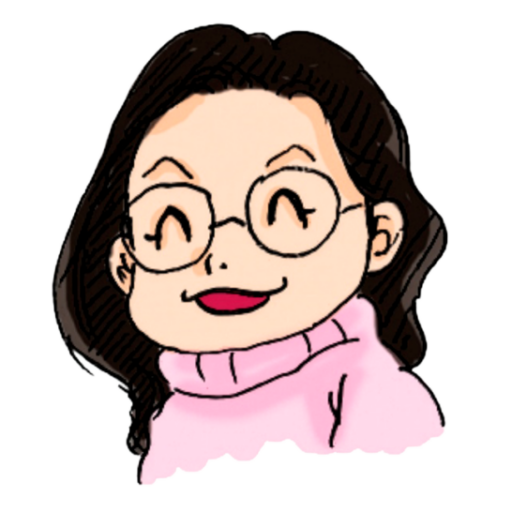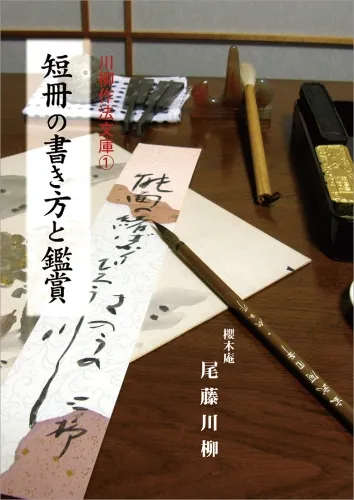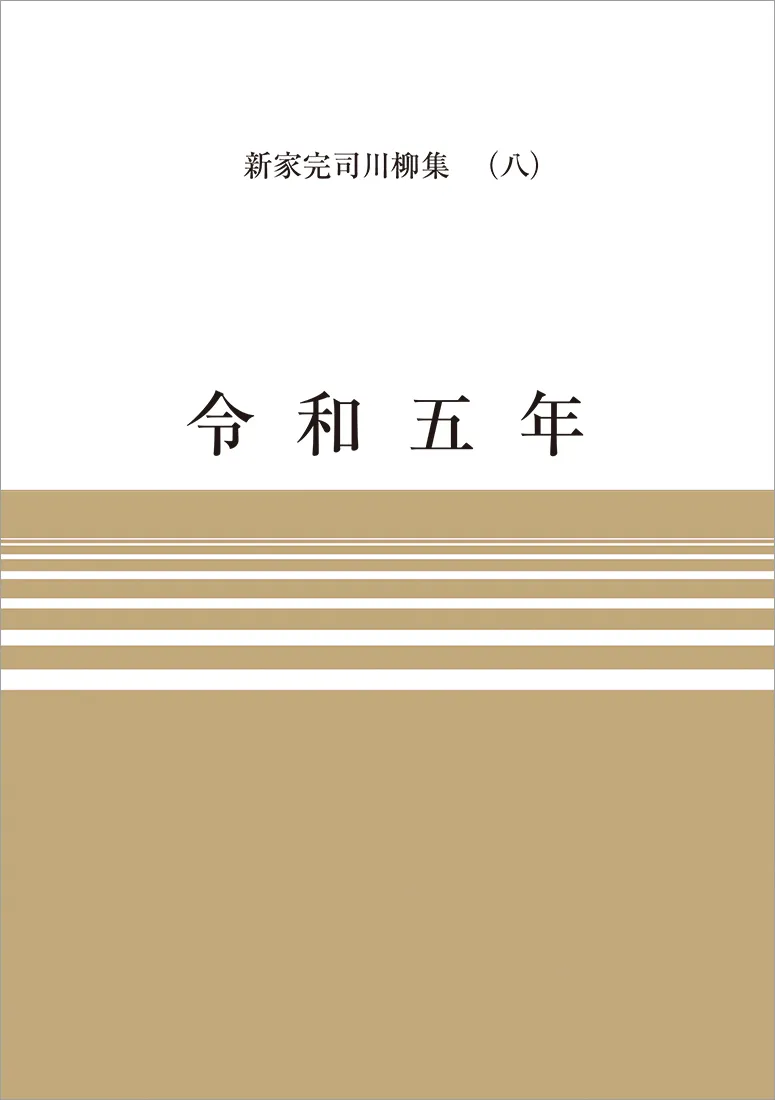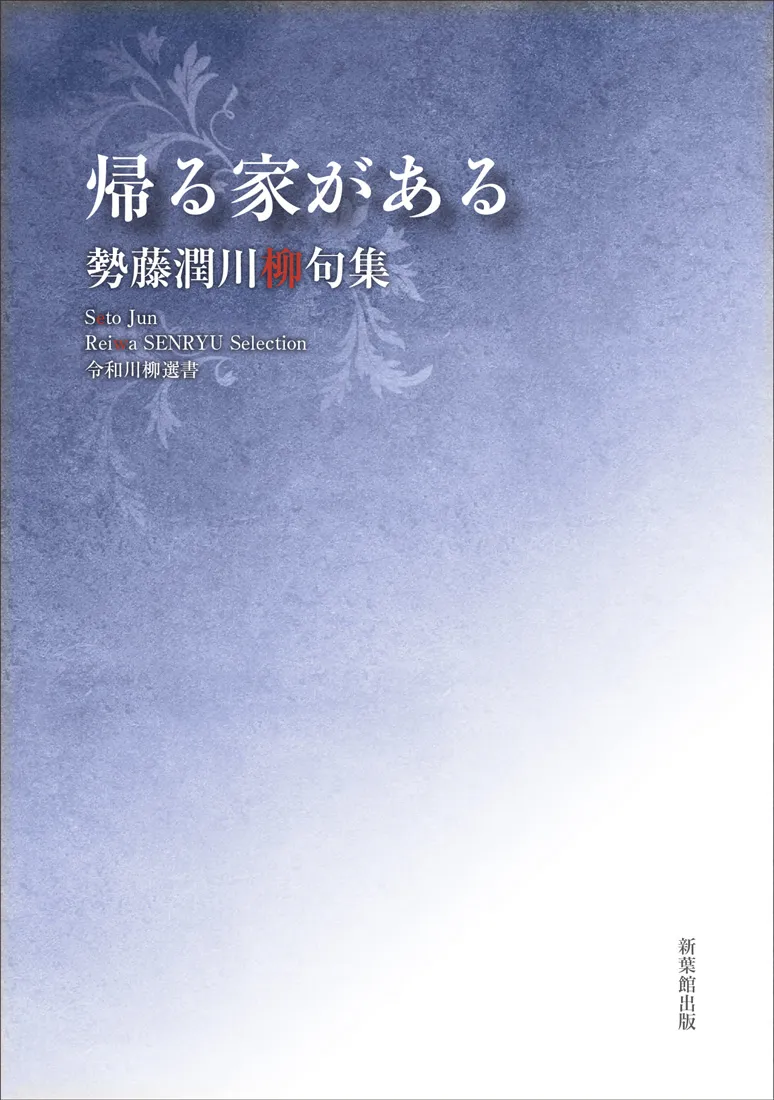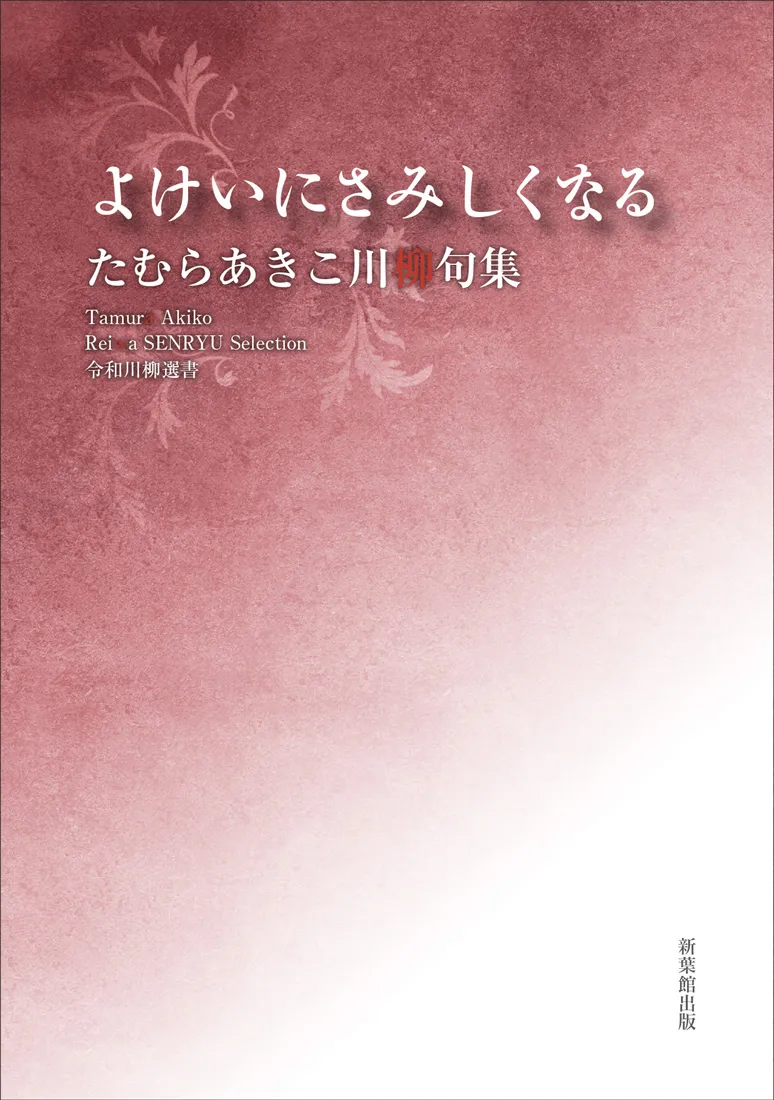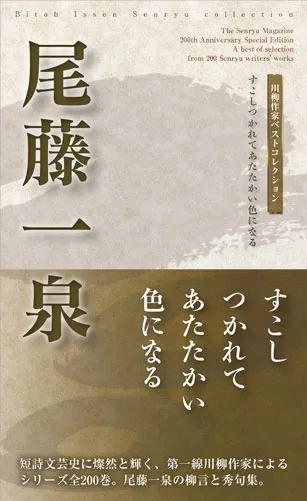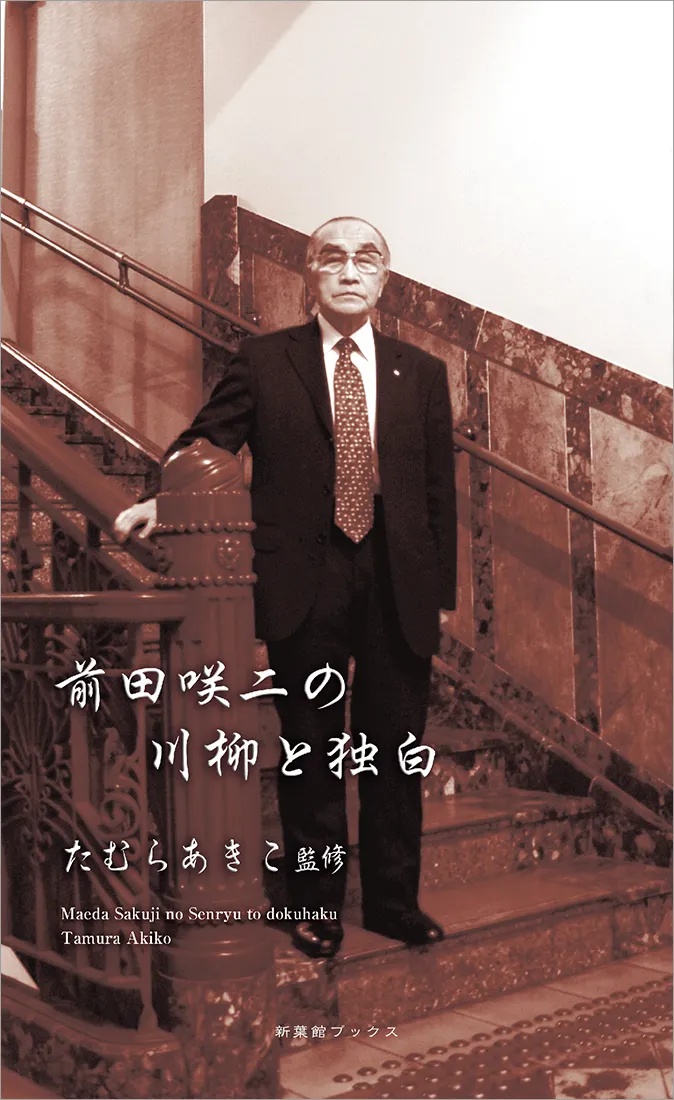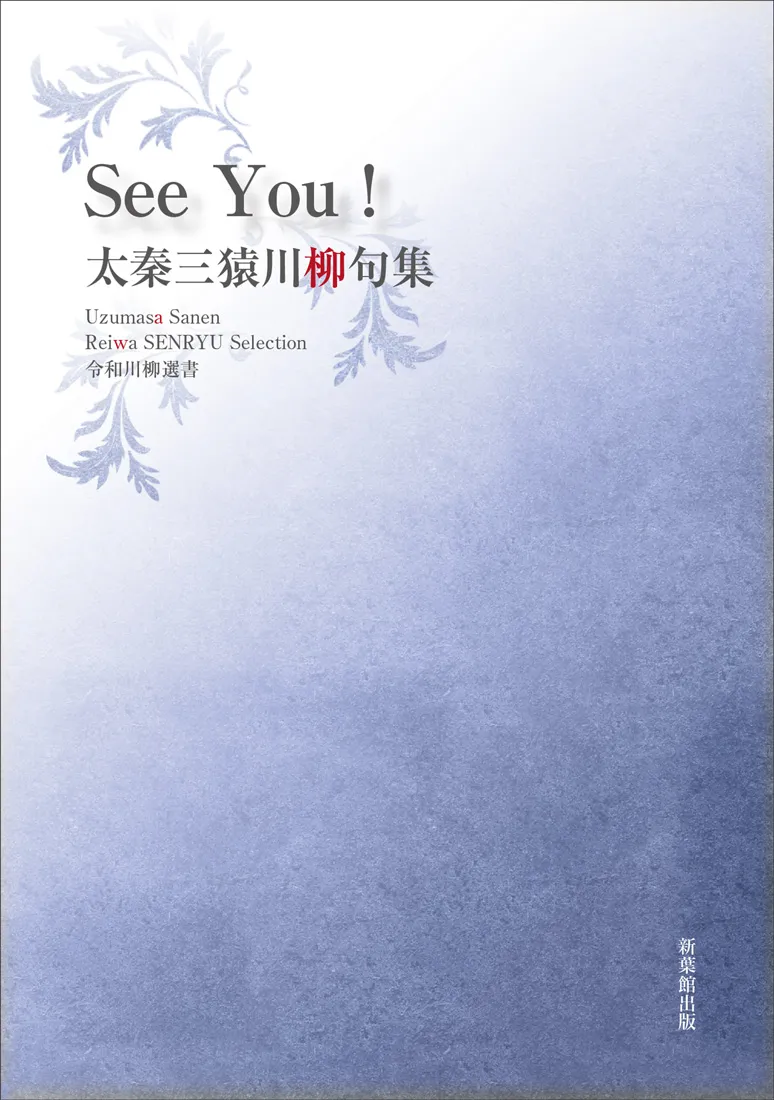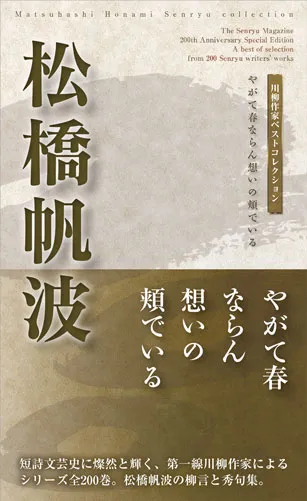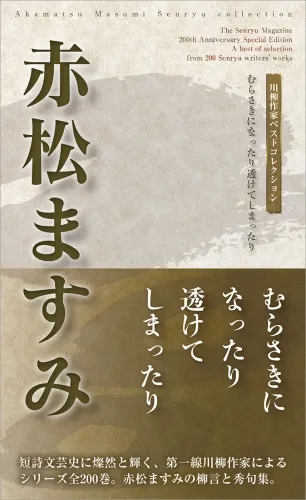敦煌莫高窟 第158窟 涅槃像 中唐 (8世紀)
「やまと路」鑑賞 たむらあきこ
人の輪にうなずくだけの首がある 徳重美恵子
我々は大小の「人の輪」に帰属して暮らしている。世捨て人ででもなければその中で折り合いを付けながら生きている。その折り合いが面倒になってくるのが老(おい)というものか。「うなずくだけの首」と自身を客観視している。
ひとつずつ持たされている涅槃の日 阪本きりり
作者はすでに「末期の眼」とも言うべき眼をもっている。若くして諦観を生きておられる。自らの「涅槃(ねはん)の日」を脳裡に描いて生きてこられたのかどうか。「涅槃」は〈消滅〉、即ち〈死〉の意。
いつもの処にいつもの人がいる暮らし 植野美津江
「暮らし」の安心とは、「いつもの処に」「いつもの人がいる」ということ。そんな安堵が明日を生きる力を与えてくれる。
フィナーレだ冬の底へと傾いて 太田のりこ
「(フィナーレ)だ」とは、終焉が近いことへの断定なのだろうか。こころが「冬の底(へ)」と、暗い方向へ傾くのである。せめてそこに些かでも救いがあることを祈りたい。心象句。
天敵も見かた変えればパートナー 木嶋 盛隆
「天敵」というのは寧ろ縁のある「パートナー」なのだと。そう考えれば憎しみも和らぐ。発想を転換すればよいのだ。いずれはみな海に還ってゆく仲間なのだからと。
葉牡丹の心変わりを責めている 山下怜依子
どこか惹かれる句。「葉牡丹」はオトコの暗喩だろう。色鮮やかな硬い葉を観賞する「葉牡丹」。名の由来は葉を牡丹の花に見立てたとか。暖地では色づかないらしい。
お互いの我慢で持った砂の城 池田みほ子
「我慢で持った」、努力で持たせた家庭が詰るところ「砂の城」に過ぎない、というところに穿ちがある。価値観が変わり、結婚を選択しない若者が増えている。家庭が詰るところ跡形もなく崩れるだけの「砂の城」なら、独りで生きるのも一つの選択肢かと。
台本のないままに年改まる 齋藤 保子
〈「台本のない」明日〉を少し捻って「(台本のない)ままに」と時間的な経過も詠み込んでいる。過去、現在、未来とも人生に確かな「台本」などはない。
年金暮らしへ飛べない鳥になっている 北谷 詔子
「飛べない鳥」とは年金生活者の実感。多くは「年金」の少なさに喘いでいる。十分な「年金」を受け取っていると思われる方々はほんの一握り。
嘘の世を本音で渡る傷だらけ 土田 欣之
「嘘の世」であるから「本音」で生きる真っ正直な者には嘲笑が返ってくるかも知れない。結局は長いものに巻かれて生きるしかないのかと。せめて柳人は川柳の中に「本音」を詠み込んでいこう。
アルバムのこの辺りから独り者 菱木 誠
この切り取り方は巧い。来し方の残された「アルバム」。「この辺り」前後のドラマを仄めかす。「独り者」が不仕合せとは限らない。どう転んでも一度きりの人生。
無人駅風とタッチをして降りる 上田 幸一
「無人駅」で降りるときのそこはかとない浮遊感。駅前に店の灯などもなく、あってもごく寂れている。恰も〈虚無〉への入口のような「無人駅」。
街灯に照らし出される疲労感 佐藤 辰雄
「疲労感」が「照らし出される」という表現が巧い。実感句。
薄い目で母は涙を溜めていた 福尾 圭司
「(薄い目)で」と断定の助動詞「だ」の連用形、あとに一呼吸入る。殆ど目を閉じて、その目に涙が膨らんでいるのである。日本のかつての母は声を出すわけでもなく、こういう泣き方をした。
月光は真うしろブランコが揺れる 阪本 高士
「真うしろ」の「月光」を意識。「月光」に隈どられた自身の影を眺めている。頭を過るものがとくにあるわけではない。誰かが乗り捨てていった「ブランコ」が揺れている。心象句とすれば「ブランコ」は(「揺れる」)作者のこころの暗喩。
手土産に包んでくれるアドバイス 菅納みちほ
「手土産」に呉れるのは「アドバイス」であると。相談に出かけた先は友人の家か、それとも親族か。「包んでくれる」に、よく考えてご覧、とする相手の温かい心が滲む。
ジュージューと年輪一つまたひとつ 古川 洋子
「ジュージュー」というオノマトペと「年輪」との二物衝迫。生きるとは「年輪」を重ねるとは、恰も鉄板の上で自らの肉(現身)を焼き締めていくようなことだと。
センターラインひいて暮らしている遠い 西澤 知子
「センターライン」は作者の身のうちを貫いて伸びるもの。過去、現在、未来を貫く、真っ直ぐな一本の線である。そこから「(ああ)遠い」という溜息。来し方も遥か、この先もまだまだありそうだと。
 Loading...
Loading...