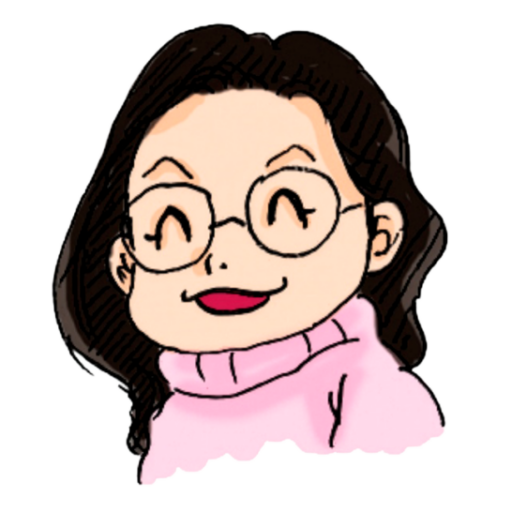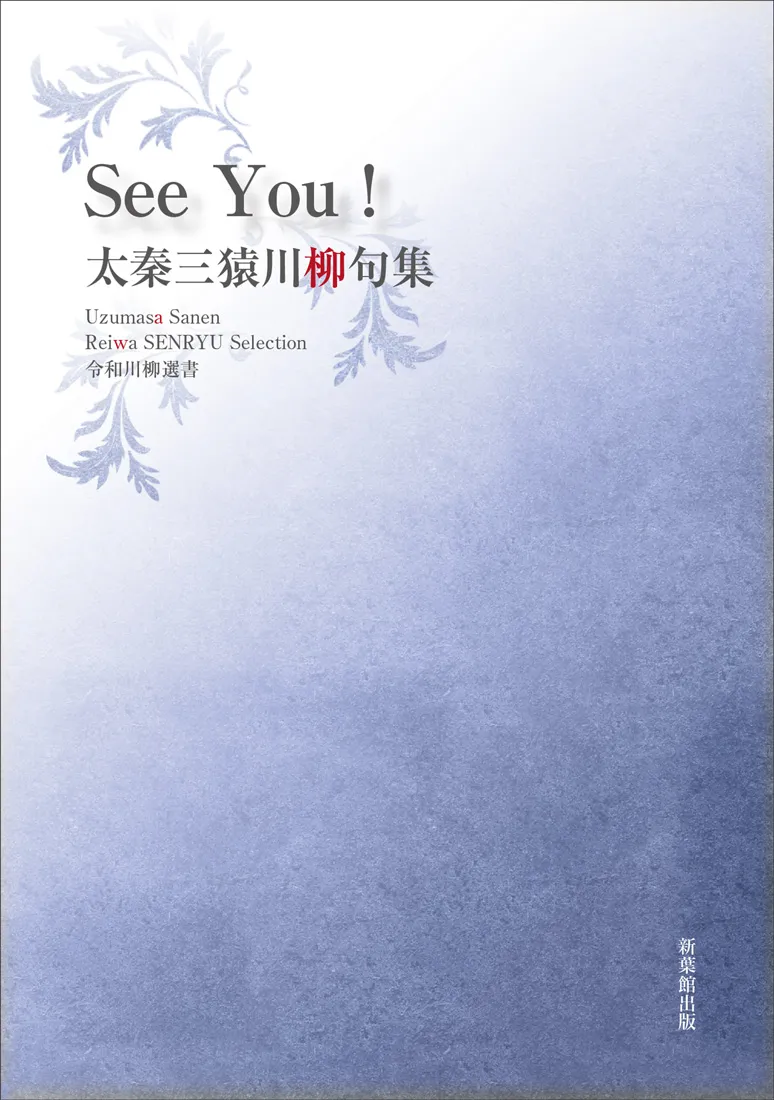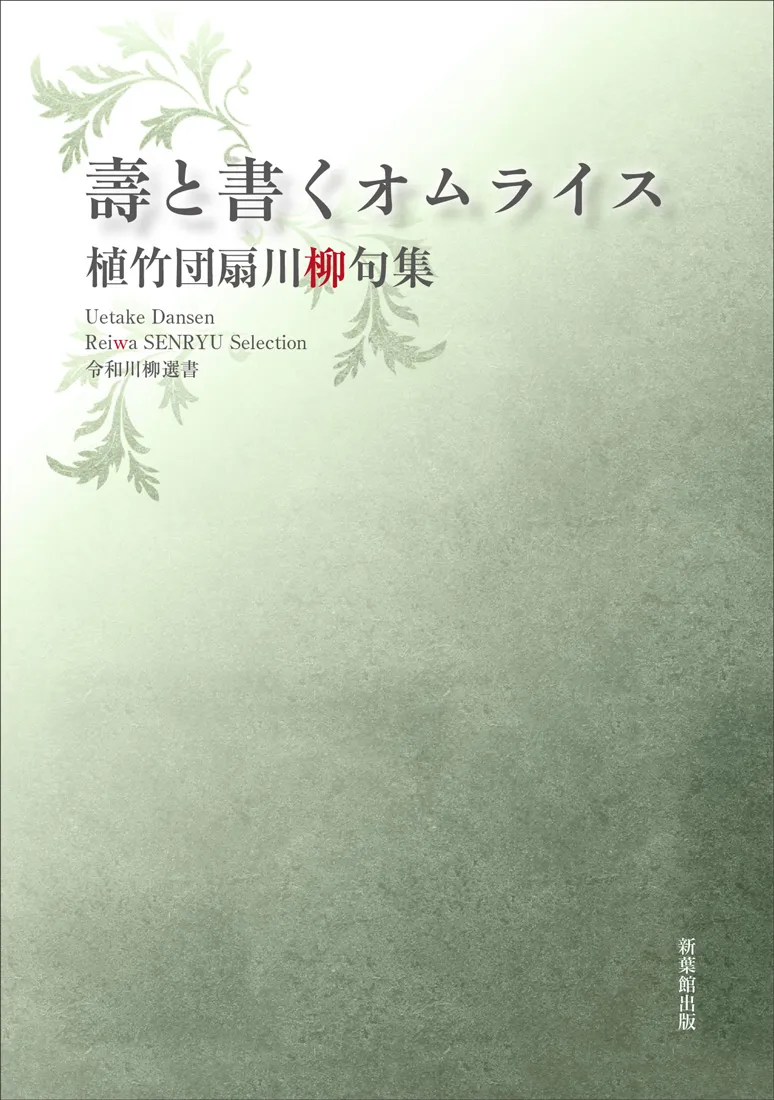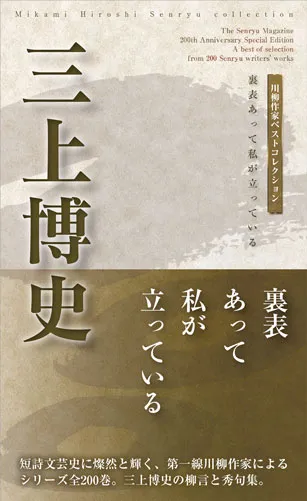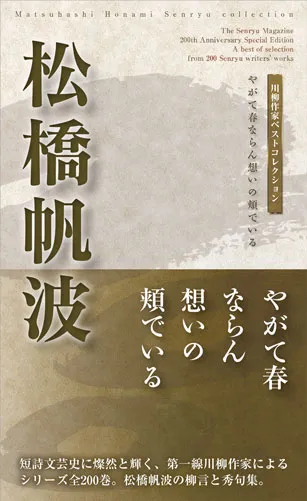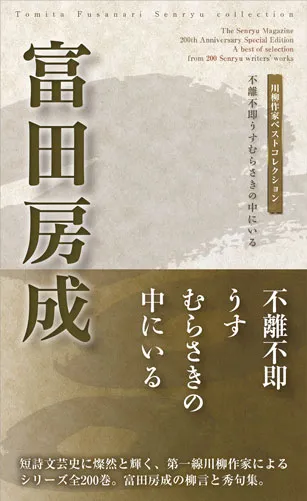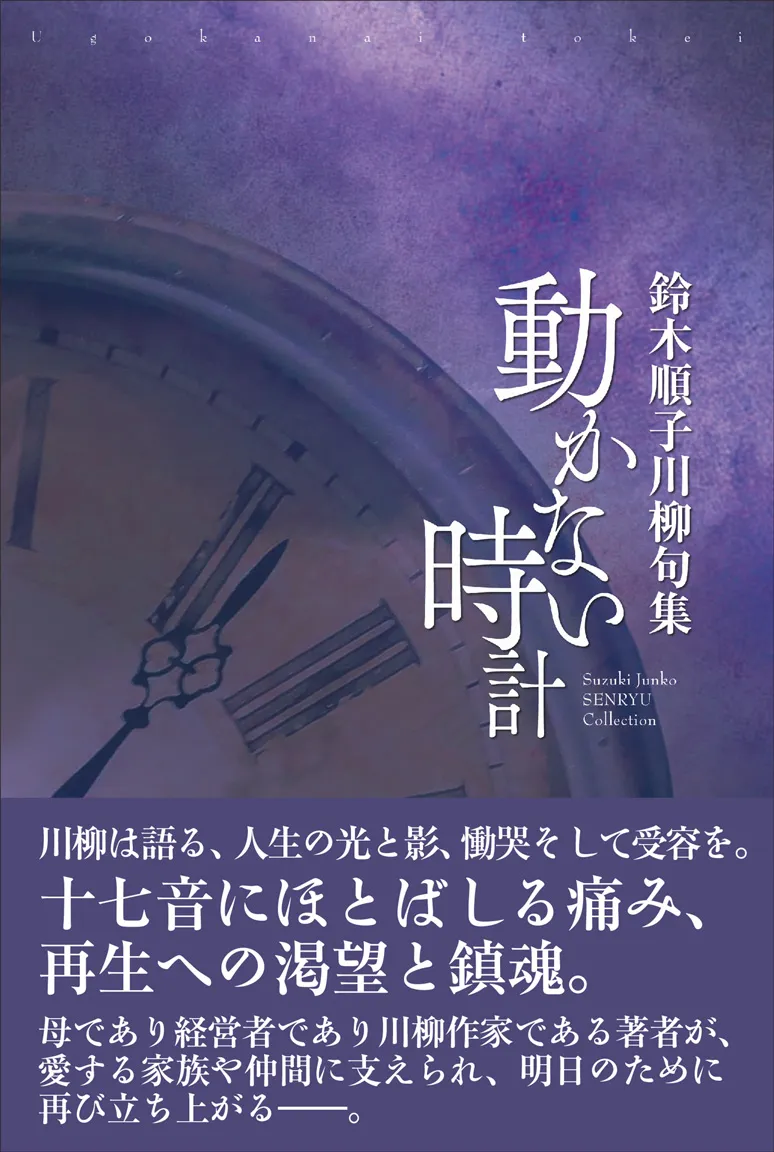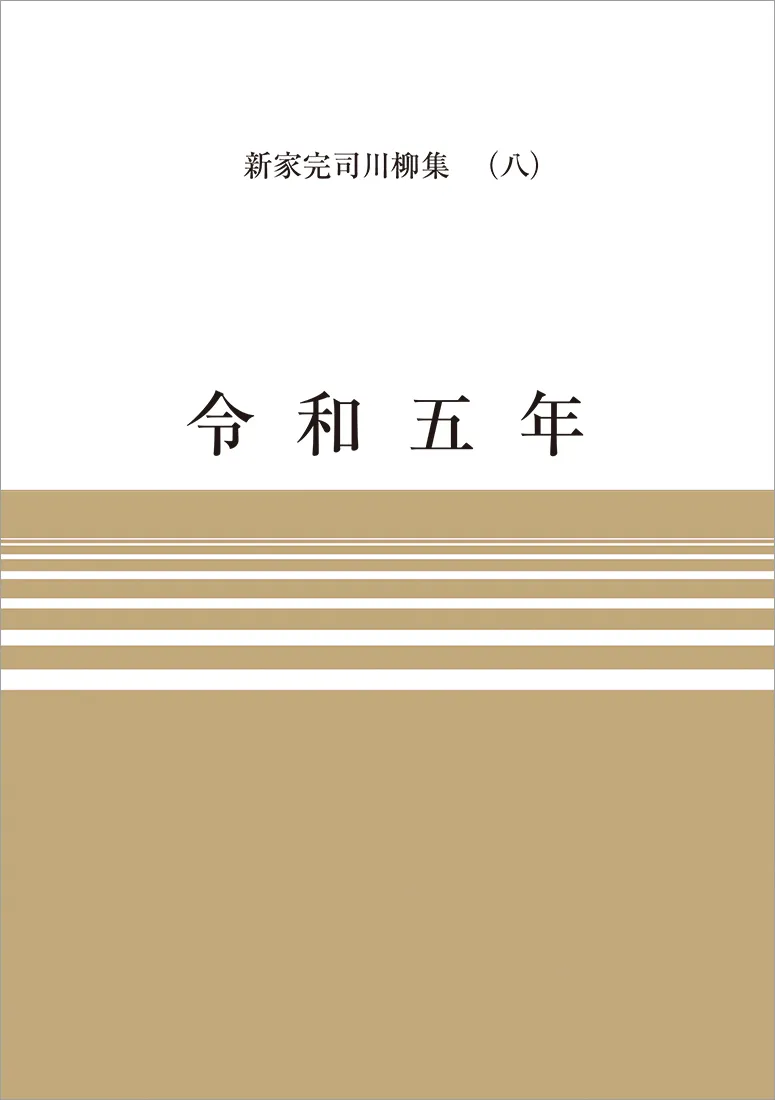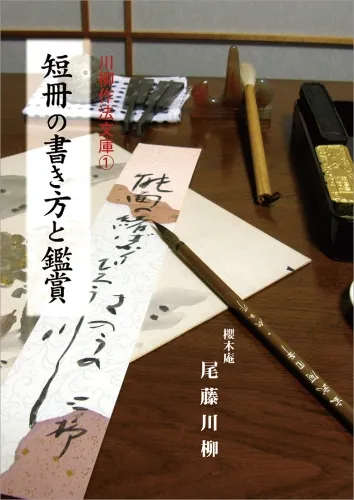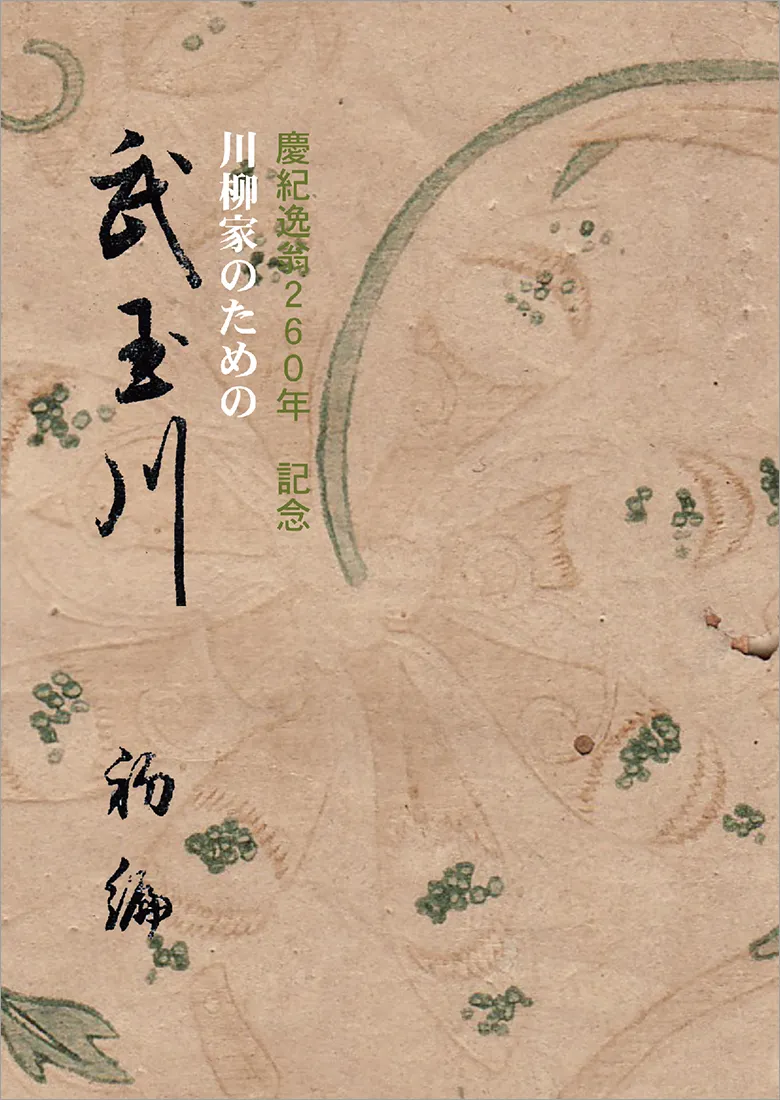昼食後うとうとと眠ってしまったようだ。夢。先ほどまでいた幼い息子はどこへ行ってしまったのか。捜すのをあきらめて、(なぜか)大きなミカンを捥(も)ごうとしていた。足もとが危ういので躊躇しているうちに、目が覚めた。
下記は、いわゆる革新川柳「川柳カード」創刊号からの5句。鑑賞文はあきこ。
 死の横を流れた水を飲んでいる 湊 圭史
死の横を流れた水を飲んでいる 湊 圭史
我われが口にする水道水。浄水施設を通ってきた水だが、元はひどく汚れている。動物の死骸、排泄物ほかが溶け込んでいる。それを処理、塩素消毒したものが蛇口から出てくる。「死」はすでにその中に溶け込んでいるが、例えば死者の湯灌(ゆかん)のあとの水、「死の横を流れた水」も当然入っている。
足首に蛍が産んだ子とありぬ 広瀬ちえみ
新生児の足首に付ける、母の名を記したタグ。すでに成人して母を見送ったあとも、子であることの証のタグを人生の入口で付けられた身体の部分として、自らの足首を意識する。「蛍が産んだ子」とは作者のこと。あの世の母のたましい(「蛍」)と作者のたましいがいまも目に見えぬタグで繋がっているように思うのだ。
たましいを楷書で書いてしまいけり 清水かおり
「たましい」の平仮名の4文字は、草書で書くべきもののような気がする。「たましい」の在りようはどこかおぼろげな睡蓮の白さに似て、また少しずつかたちも変わってゆく。草書で書くべきところを「楷書」で書いてしまってから、そぐわないものを感じている。(自身の)「たましい」を端正に書いた、端然と生き(てしまっ)たということの隠喩かとも思ったが。それでは川柳を詠むことはないだろう。
天ぷらの揚がる音して終わりけり 筒井 祥文
この句は、聴覚にまず訴える。「天ぷらの揚がる」ジューッという音でこの世の生を終わった、他界したという。生き様(死に様)の隠喩として、まず類(たぐい)を見ない。川柳の手練(だ)れである作者の、安定した巧さ。
母通るぎこちなく死の傘をさし 石部 明
病床で自身の「死」が近づいてきたと悟った作者の心象句。「ぎこちなく…」は近くまで迎えにきたあの世の「母」への、息子である作者の「死」をまだ受け入れかねているという心情の表象。
 Loading...
Loading...