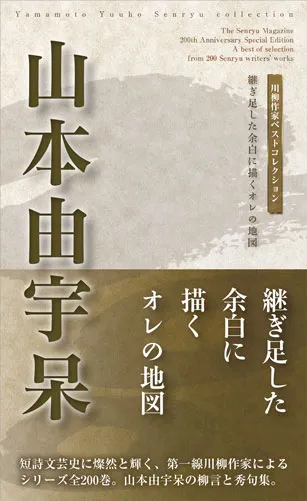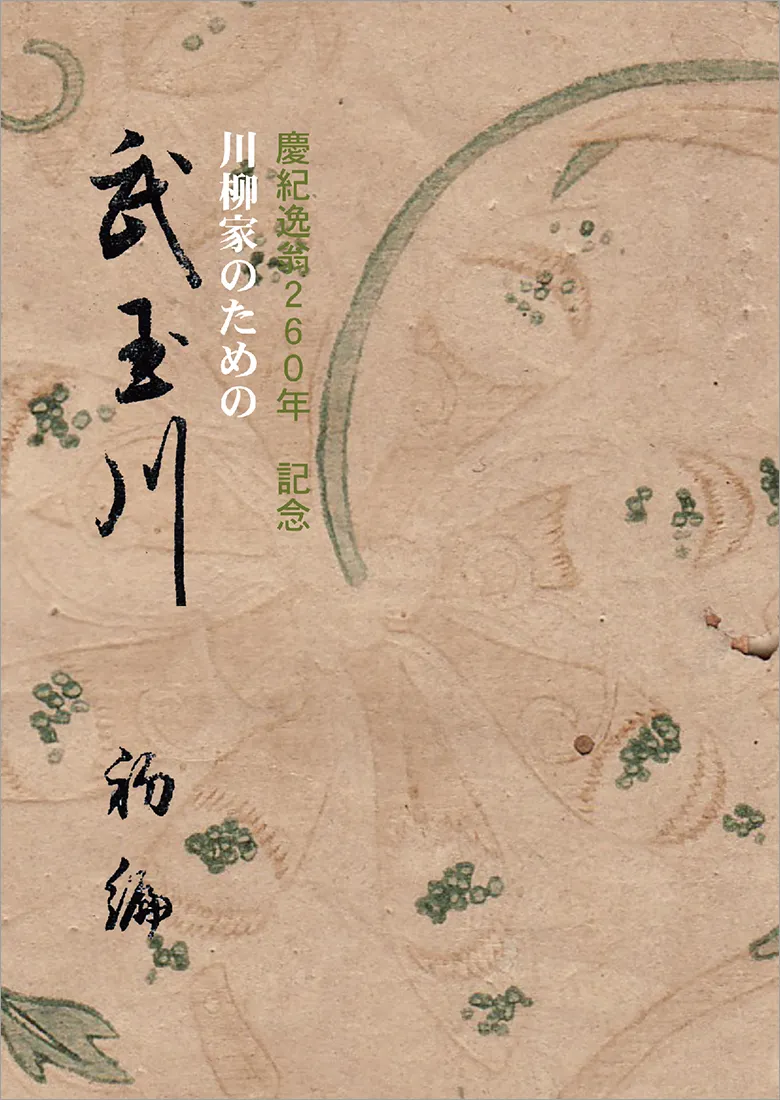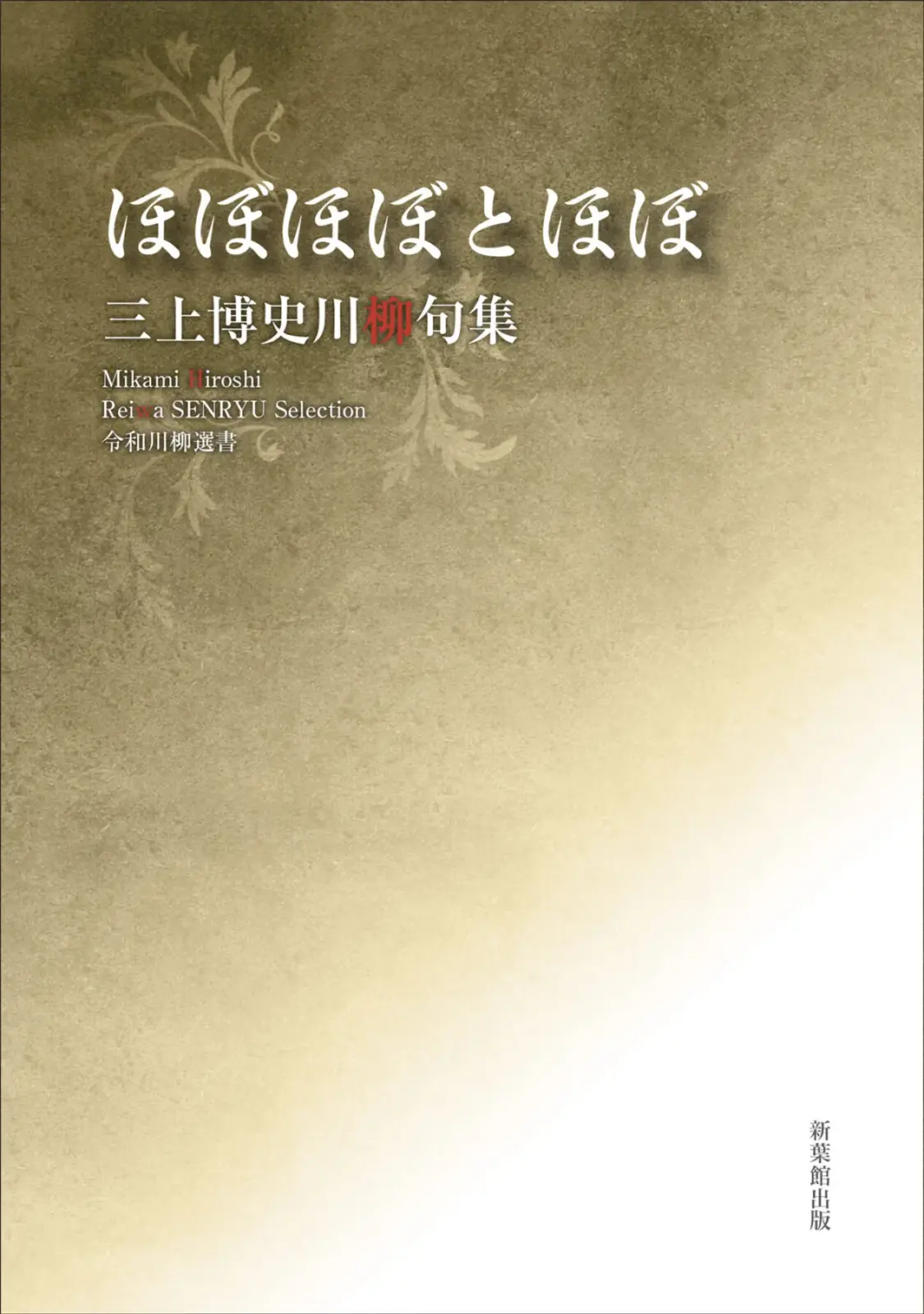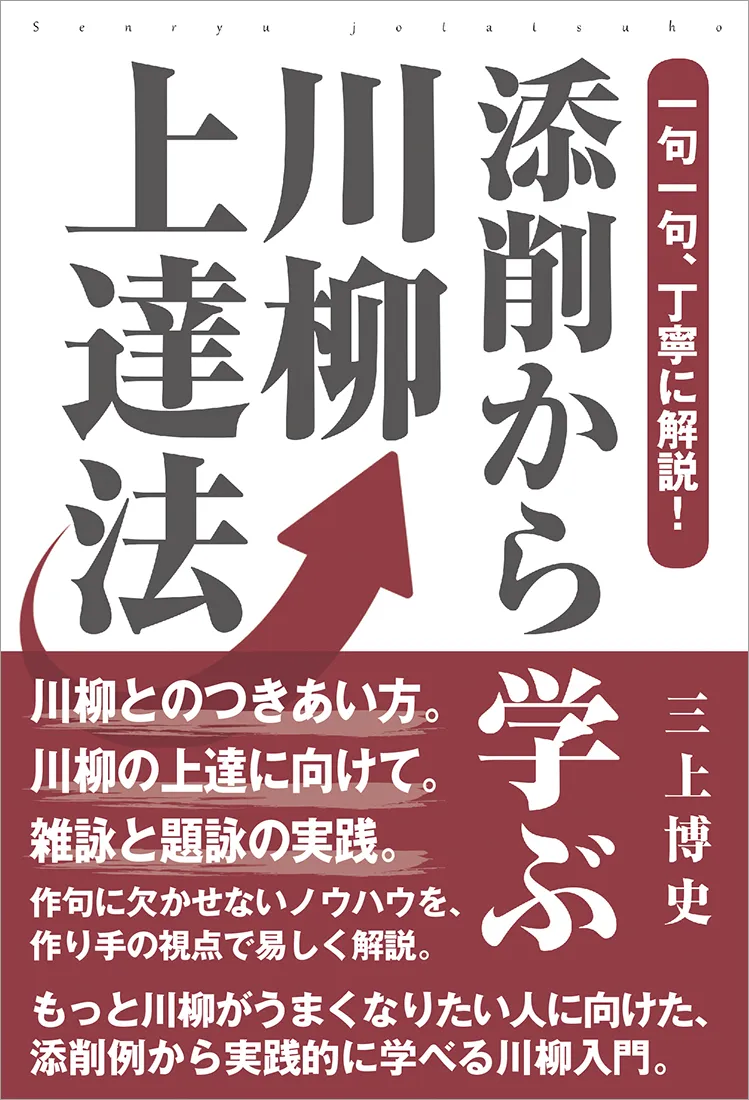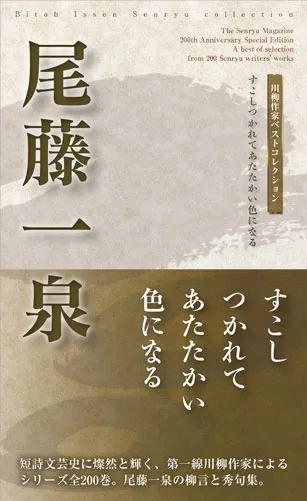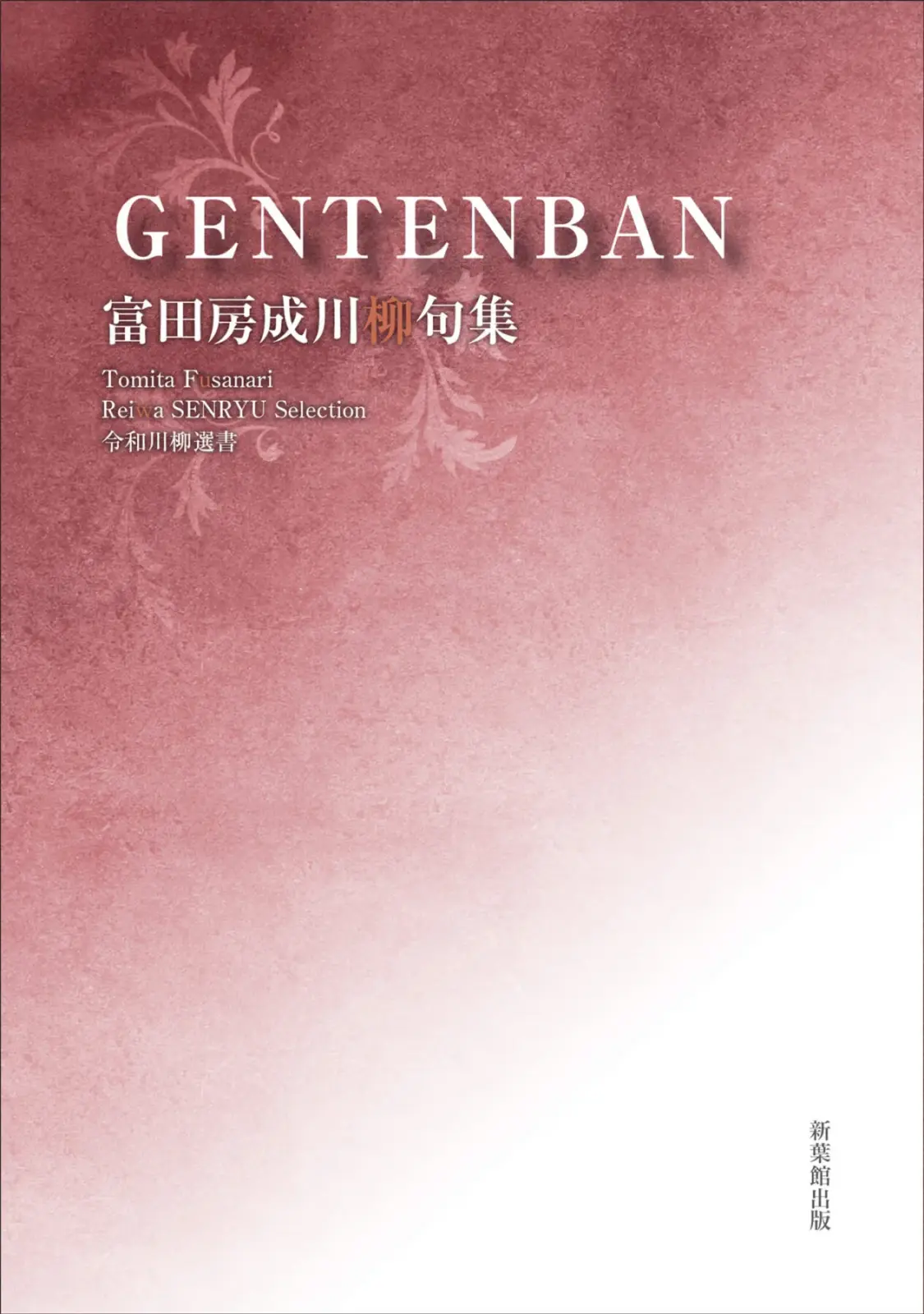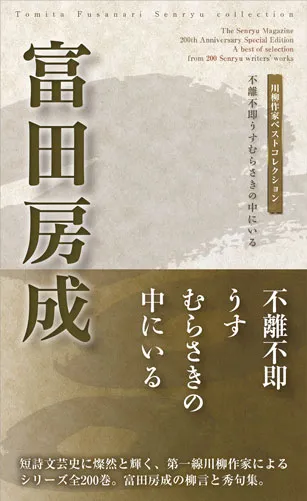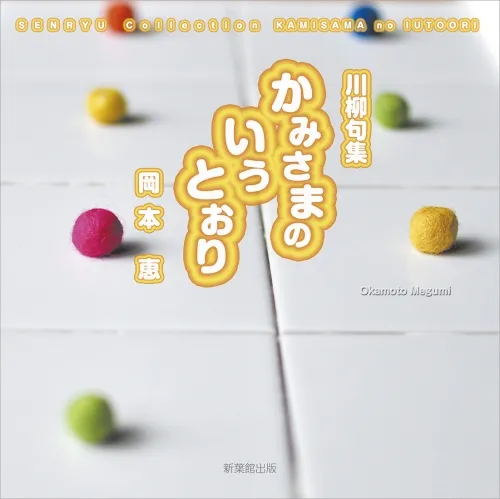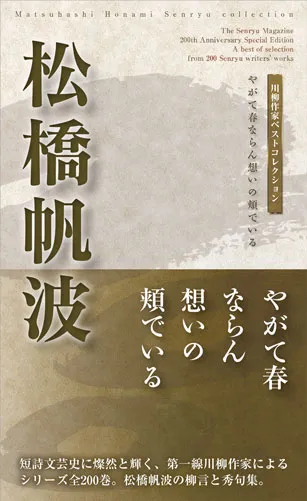東京・浅草仲見世の老舗舞扇(まいせん)店「荒井文扇堂」の四代目店主で、浅草での歌舞伎公演「平成中村座」復活に貢献した浅草観光連盟副会長の荒井修さんが二十二日午前零時十分、肺がんのため死去した。六十七才。 2016年2月23日東京新聞夕刊。
荒井さんとは二度お話をしたことがある。一度目は仲見世をぶらぶらしていて「扇」の看板が目に留まって立ち寄った折である。おそらく6~7年ほど前と思う。我が家には噺家さんの使用する「扇」が一本あった。それは、何かの機会に団体で寄席見物したお袋が籤に当たって入手したものだった。だから、舞扇と高座の扇のつくりの違いは30年以上前から知っていた。この日もそこそこの品を購入した。二度目は敬愛する内田博柳さんに案内されて立ち寄った時である。もう、年金生活者になってからだから、以前より安価なものを求めた。団扇は空桶亭傍迷惑(からおけていはためいわく)から涼風亭団扇(すずかぜていだんせん)の名でたまにごく狭い世間に迷惑を掛けている。
記事に出会って驚いて、博柳さんに連絡をとったが出られず後でお電話を頂戴した。記事の中でも紹介されていた、観光連盟会長の富士慈美さん(同い年の67歳)と葬儀などの準備で奔走中であったとのこと、川柳家博柳さんは浅草でそういう地位と役割を果たし続けている方である。荒井さんや富士さんが何月のお生まれか存じ上げないが、団扇もこの8月で同い年に到達する。
団扇の勤めていた駒込学園は、西の延暦寺が創設した比叡山高校に対して、東の寛永寺が創設した勧学講院が前身である。浅草寺は戦後独立したがもともとは天台宗の寺院である。幼い頃からの「江戸といったら一番は浅草」と思っていたイメージに自然に連鎖してか、信州からの上京の停車場は新宿なのに、上野浅草方面のほうに愛着がある。
東京新聞は、24日にも「勘三郎さん支えた浅草の盟友」「浅草から惜しむ声」「オピニオンリーダー」「修ちゃんいたから繁栄」などの大見出しで報道した。火の消えかけた浅草を復興させた立役者は、こんな若手だったのだ。(活躍は40代から?)そして女性の力であったことも有名である。浅草や台東に団扇は「本物の保守」を感じる。京都に蜷川革新府政が誕生したころ、京都から来た後輩の女子大生に「蜷川さんは素敵な革新だね」と言ったら「蜷川はん革新ちゃいます、保守だっせ(あれこれは大井坂弁かな)」と言い返されたことを懐かしく思い出す。歴史や文化を大切に守り抜くことが、新しい価値を生み出す力であると本当に思う。「ああ、それなのに最近の保守政党の政治家さんといったら・・・・」とここで高座を降りるのも演出法。妻ご飯と呼んでいる日曜日の朝食。
 Loading...
Loading...