昨日の続き。大辞林だけでなく、広辞苑にも「強行採決」という言葉はなかった。「強行採決」に適当な英訳がないという評論をどこかで読んだころ、実際の英字新聞(日本国内発行)の一面トップ記事を読んで、なるほどと大きく頷いた遠い遠い記憶がある。
本文中に”kyouko saiketu”とアルファベットで表記した後、長々しい英文の説明が付記されていたのだ。直訳は簡単であろう、強行という意味の英語と、採決という意味の英語を並べて複合語を作れば済むのだから。ところがそれでは意味が通じない。それは、英字新聞の読者に「強行採決」という概念がないからである。
和英辞典に「強行採決」の翻訳(直訳ではない)が掲載され始めたのは、いつのころであろうか。柔道の「一本」や「技あり」などが国際語となったことには誇りを感じるが、強行採決が国際語にならなかったことは良かったと思う。
さて、「強行採決」の翻訳語のひとつ(steamrolling)であるが、steamは蒸気rolling
はローラーでのばすことと訳すのが適当と思われる。道路に砂利を引いて押し固めた後に、コールタールを撒いて蒸気を当て乍ら押し潰す、あの作業を指していると思われる。
押し潰されるのは民意であり、今回の法案の性格からすれば「民の命」といっても差支えないと思う。民意と一致していれば、強行の必要はないのだから。
道普請に使う用語を「議会用語」にあてた翻訳者に天晴と賛辞を贈りたい。要するに「強行採決」は議会にはそぐわない用語であり概念であるということである。
安保法案が違憲か合憲か、法案に反対か賛成か、採決に反対か賛成か、大いに論議が闘わされるべきだと思う。意見の違いを明らかにするためではなく、互いの意見を尊重して
守り合うためである。
だから、政治に関わる問題にわざと口をつぐんだり、持論を隠して権力におもねるような態度があるとするならば、批判されるべきであると思う。
 Loading...
Loading...














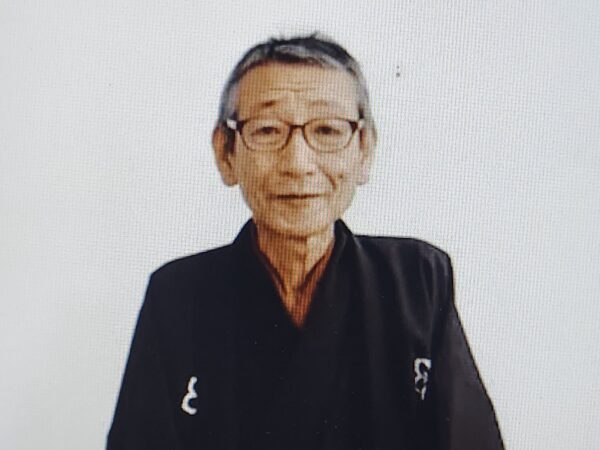
























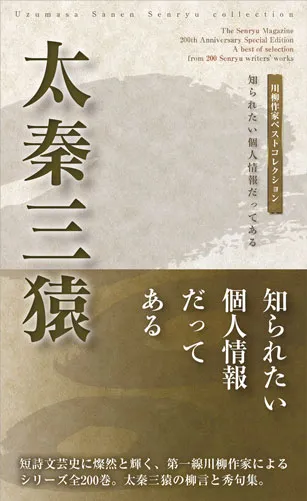
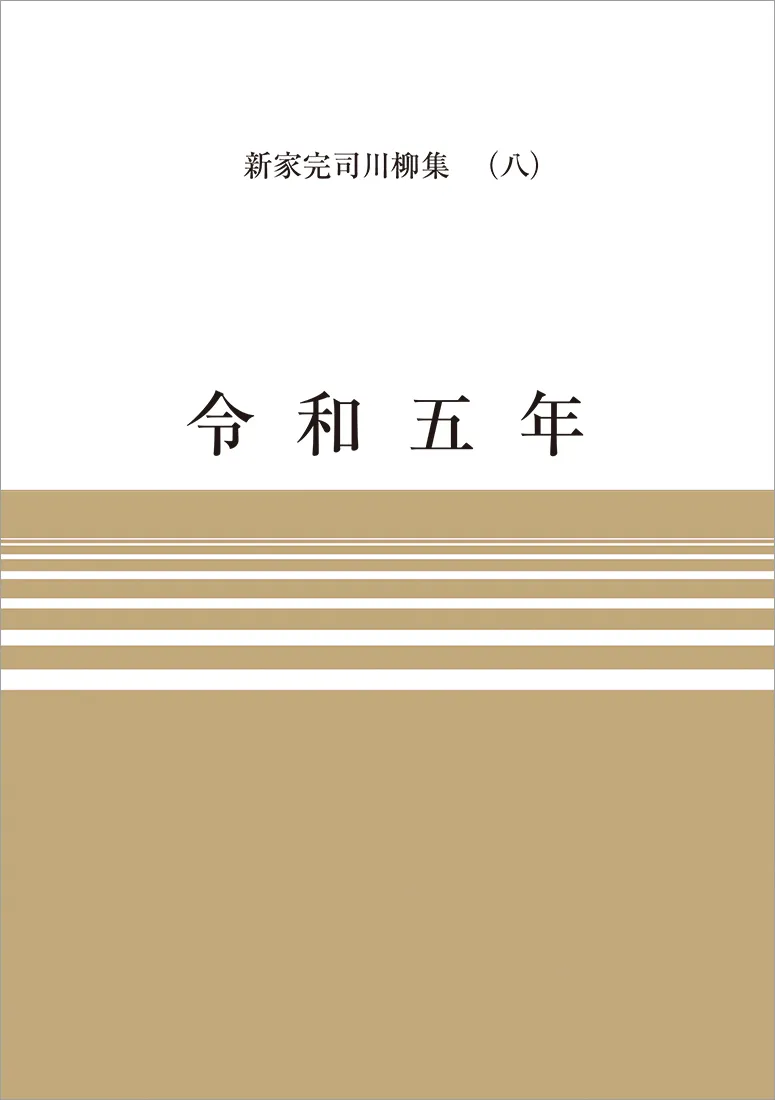
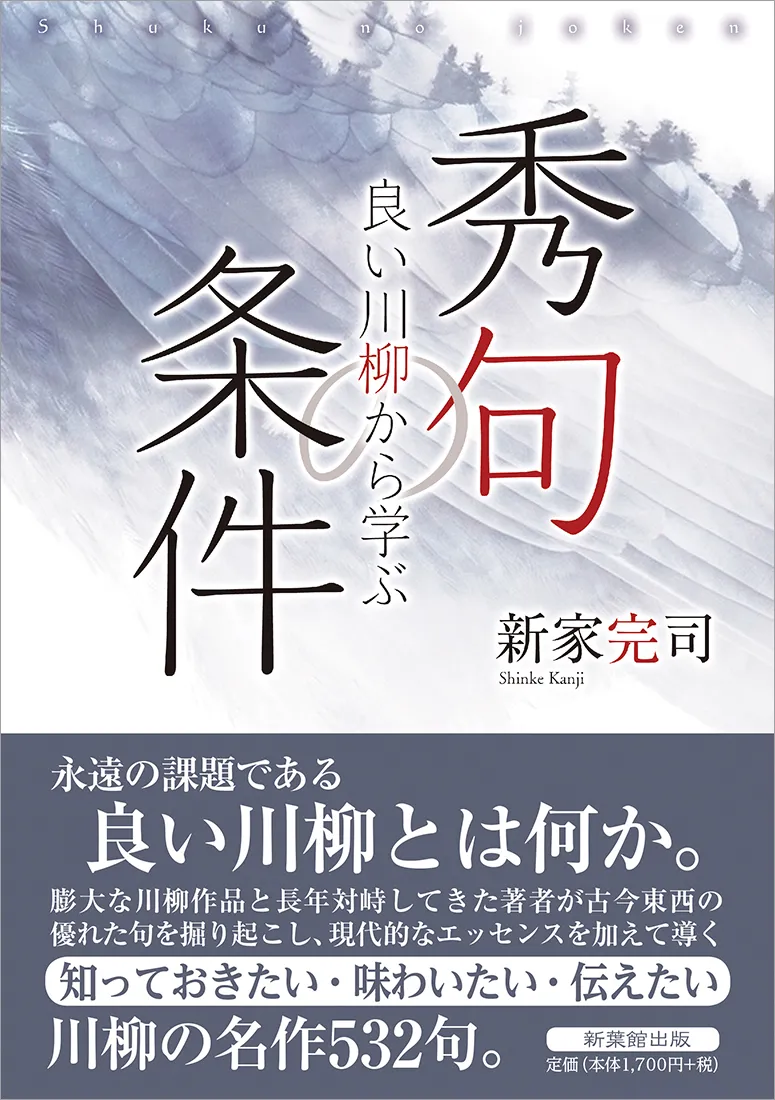
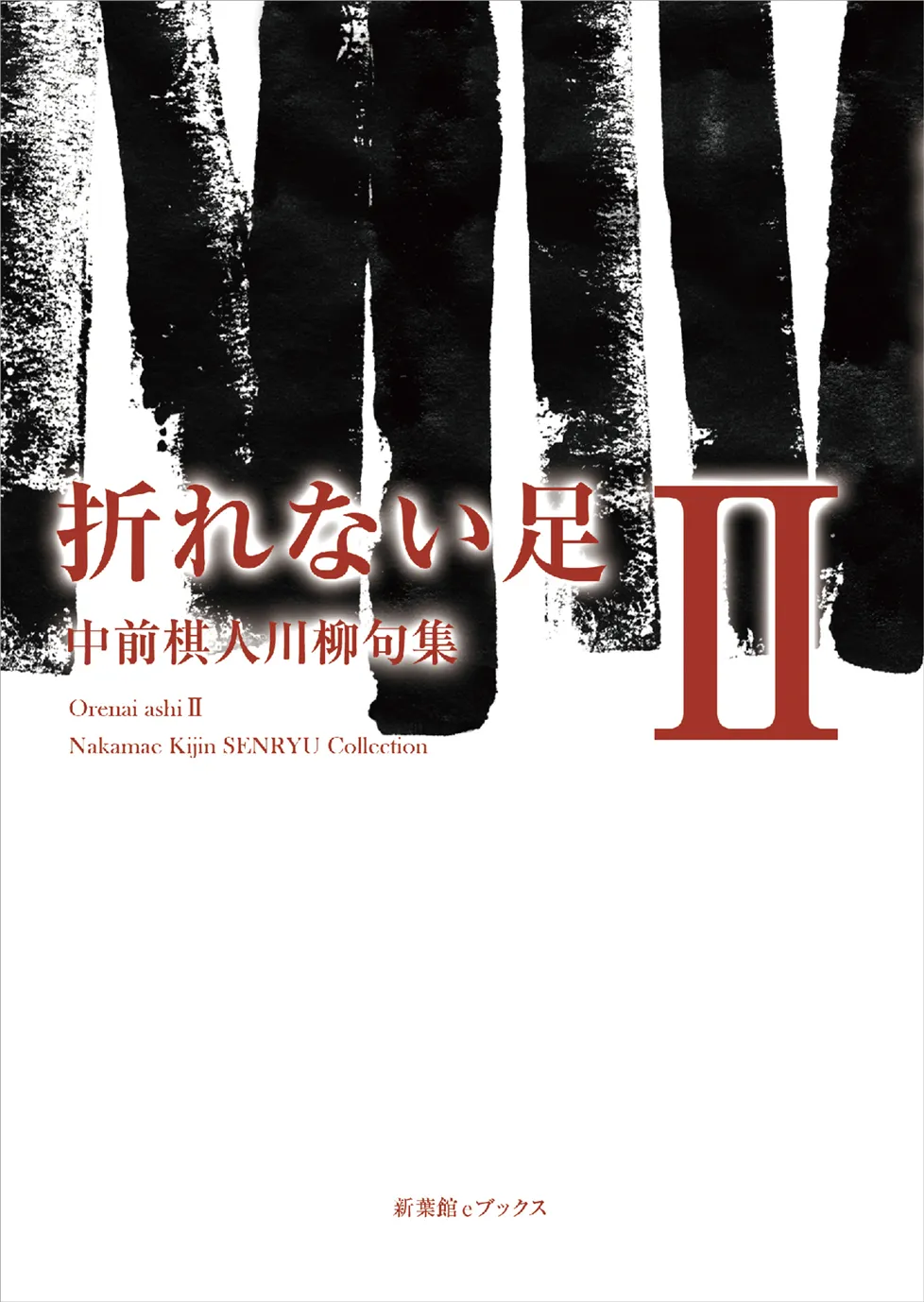
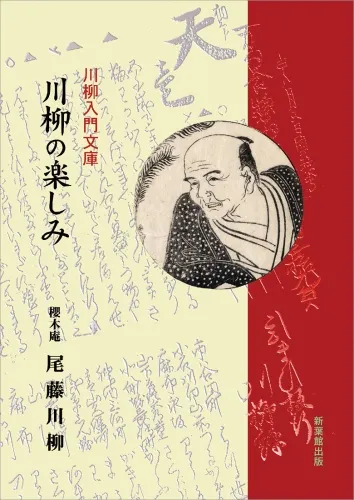
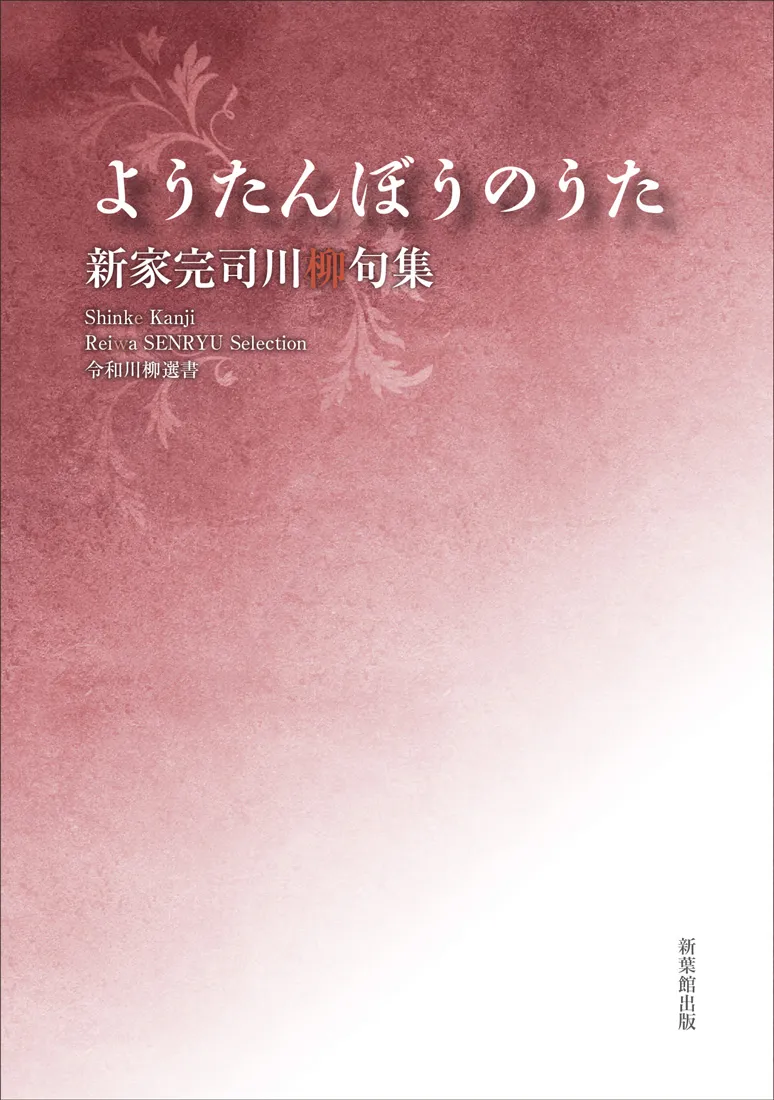
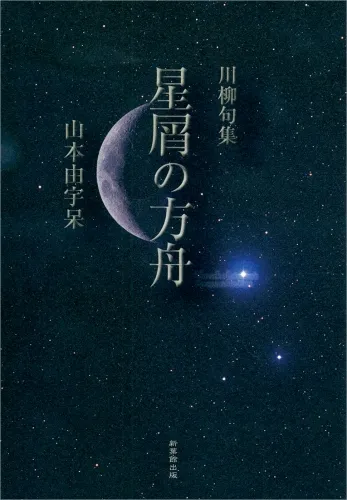
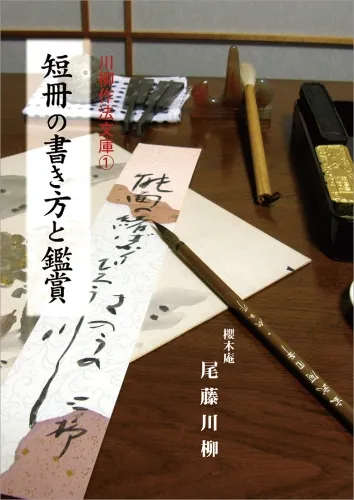
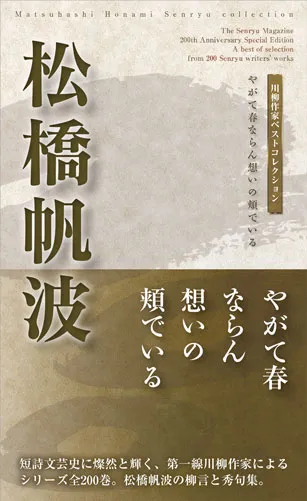
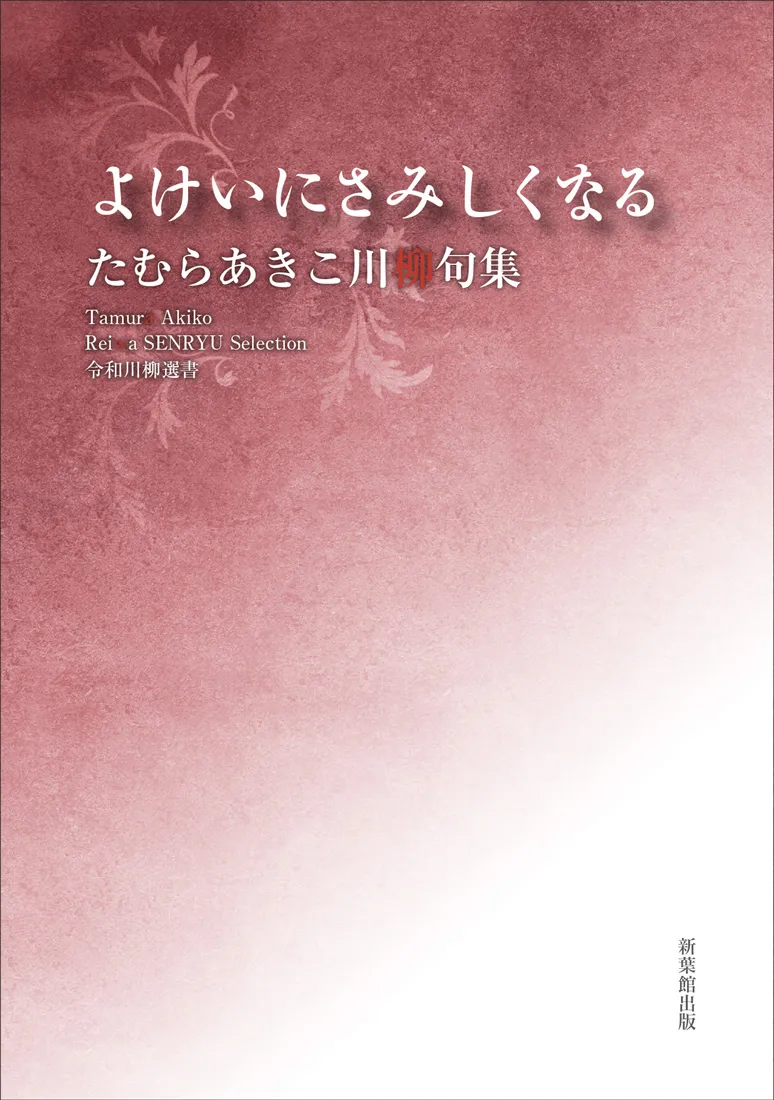














植竹団扇様
「強行採決」の英語にない理由、やっとわかりました。民主主義の国には必要ない言葉なのでした。ごり押しの日本はしょっちゅう出てきます。民意と議会がずれているからなのです。
あのゴリ押しは、何としても止めなければ。金子兜太しの毛筆太字で「アベ政治を許さない」を澤地久枝氏の提案でこの書を掲げている写真を持って各駅で一斉に掲げました。
わたしも「佐貫駅」で一枚もらってきました。
いろいろわかりやすくの解説ありがとうございました。暑いですから体調に気を付けましょう。
コメント有難う御座いました。意見の違いもさることながら、安倍さんの国民を見下した態度や発言に腹が立ちますね。たとえ話もしかりです。団扇は町会の副会長を長いことやっています。冬には拍子木を叩いて町内を回りますし、いざという時の避難のために、高齢者・障がい者のみなさんの名簿も区から預かっています。そういう助け合いと、「地球の裏側まで自衛隊を出して殺し合いをするための法案」を同じように論じるとは言語道断ですね。
若い人たちが発言しだしたのは、日本の希望ですね。18歳選挙権へも積極的反応が増えてきました。言いたいことを言うようになって、腹膨る思いも解消してきました。