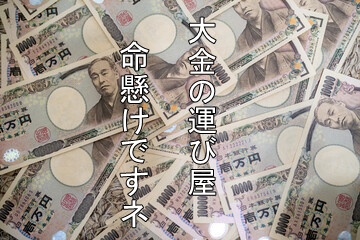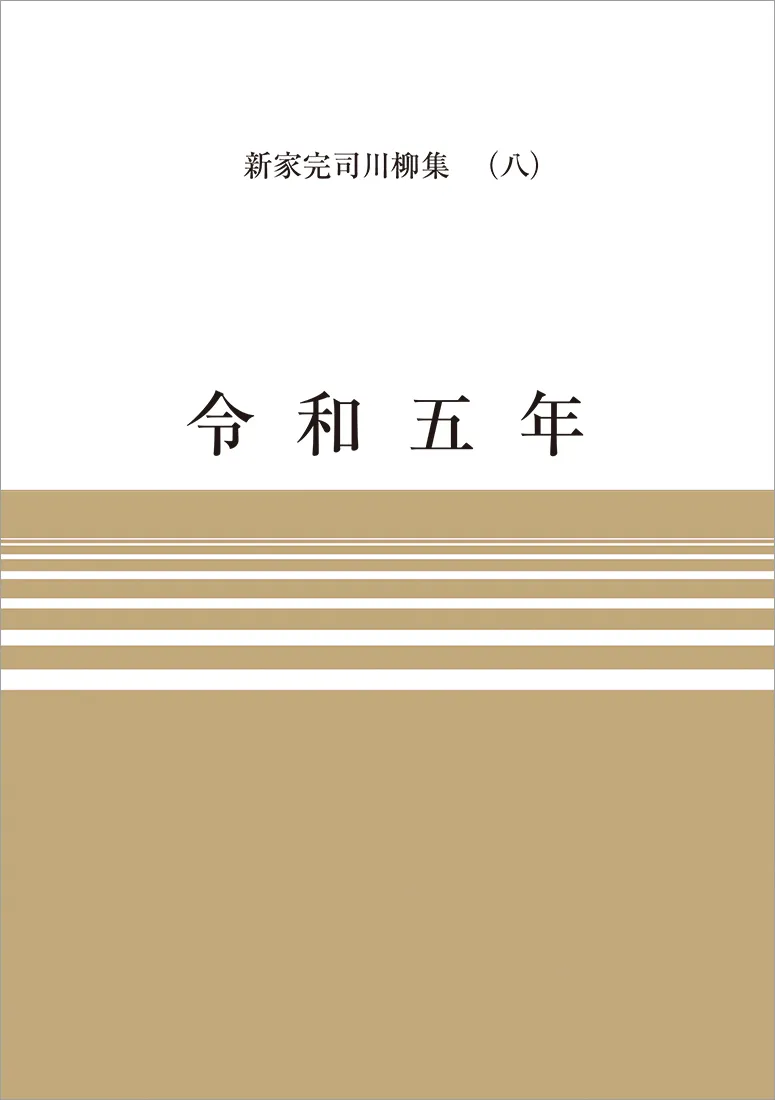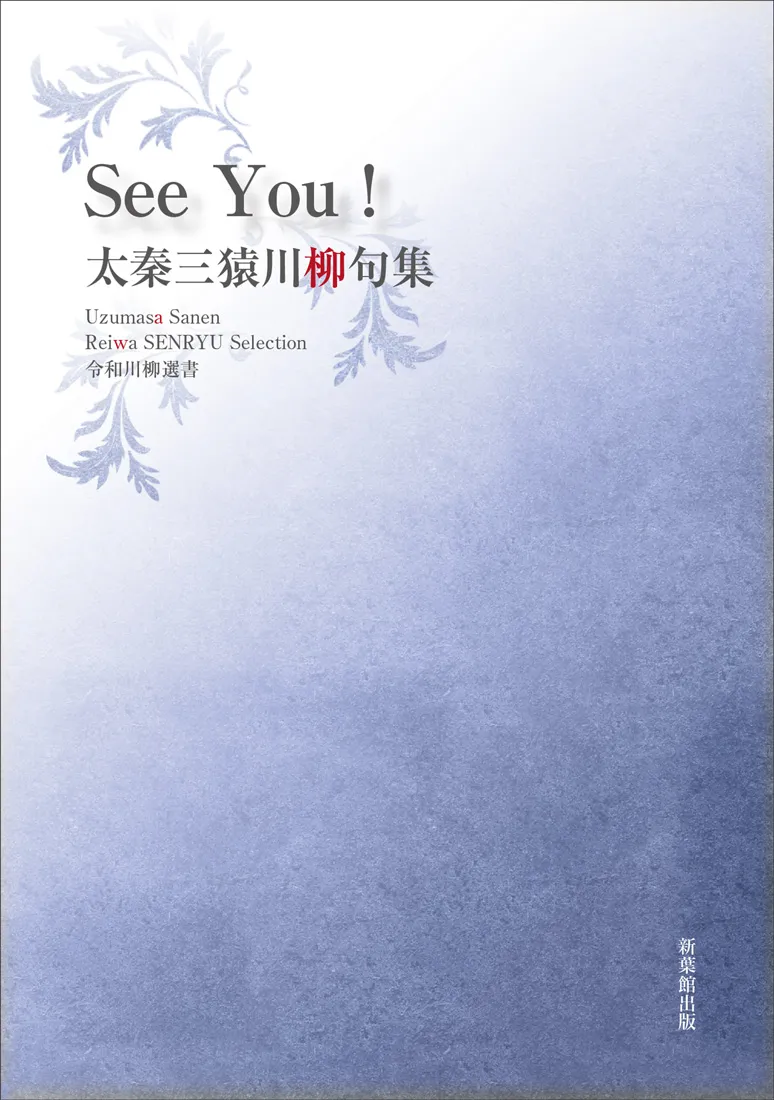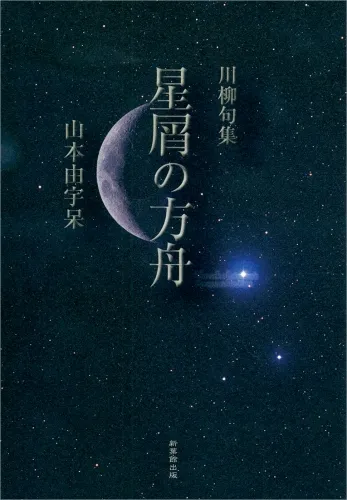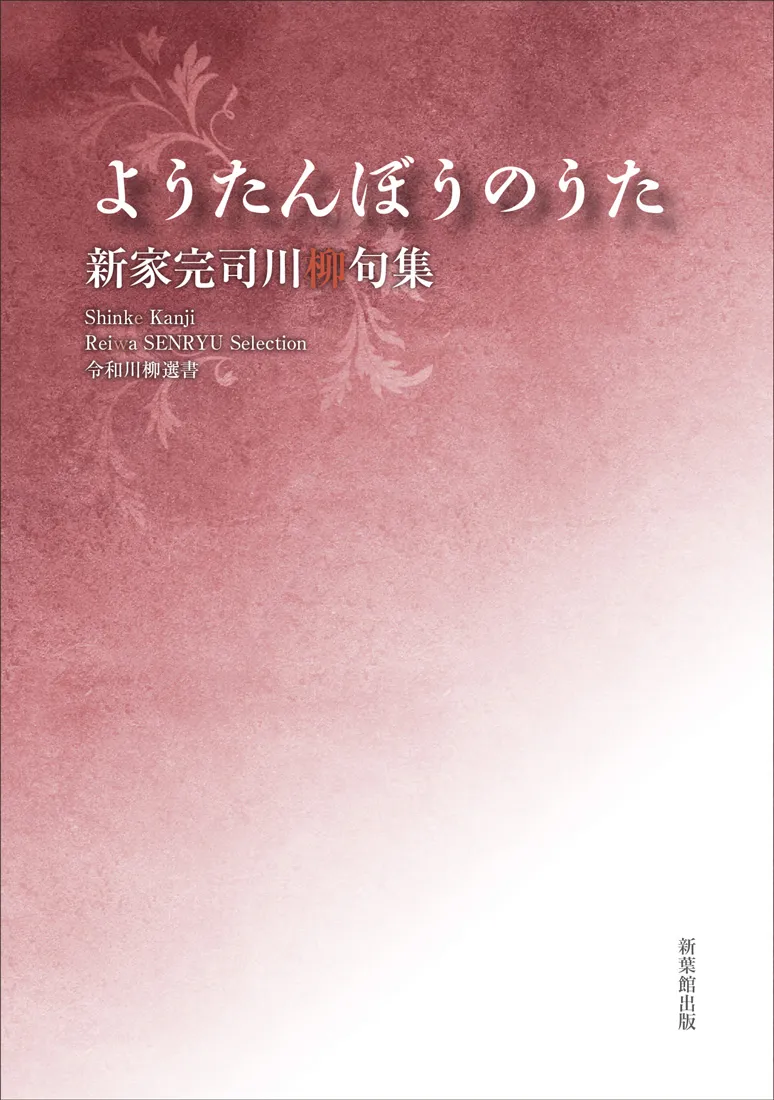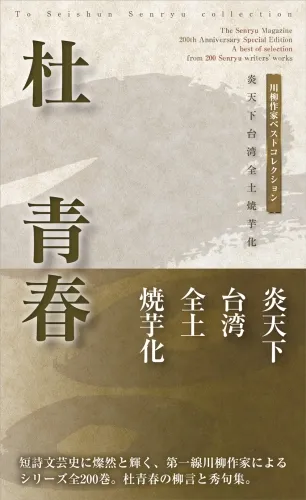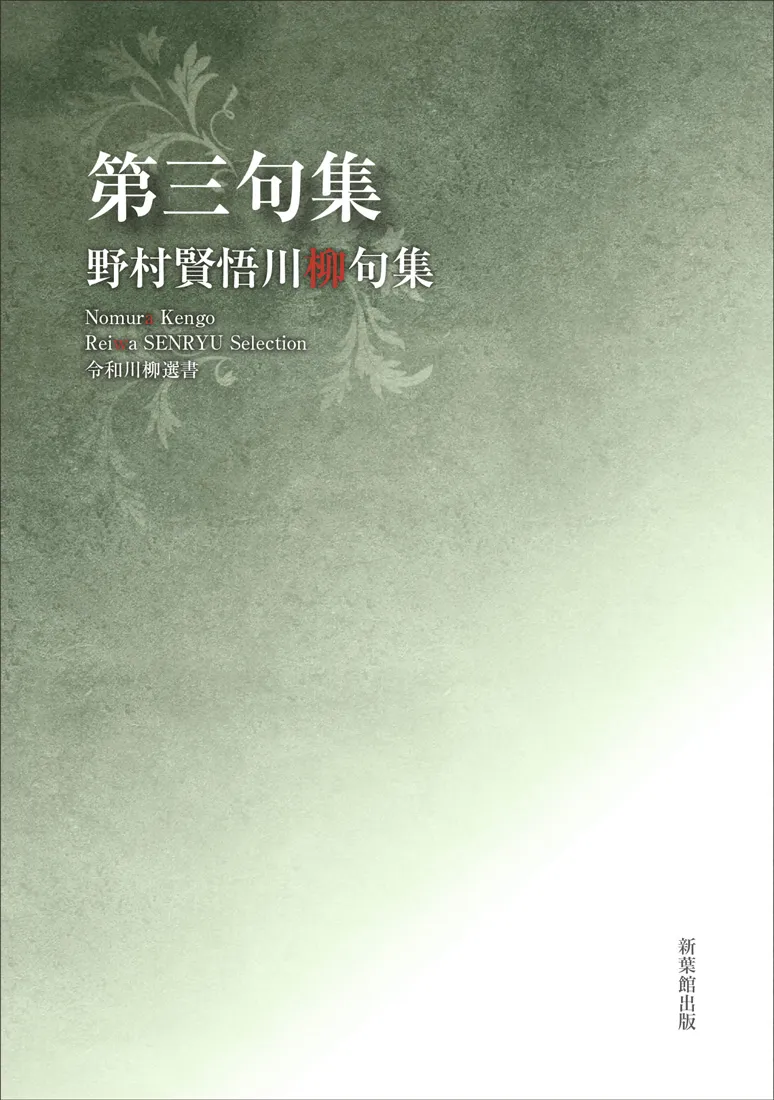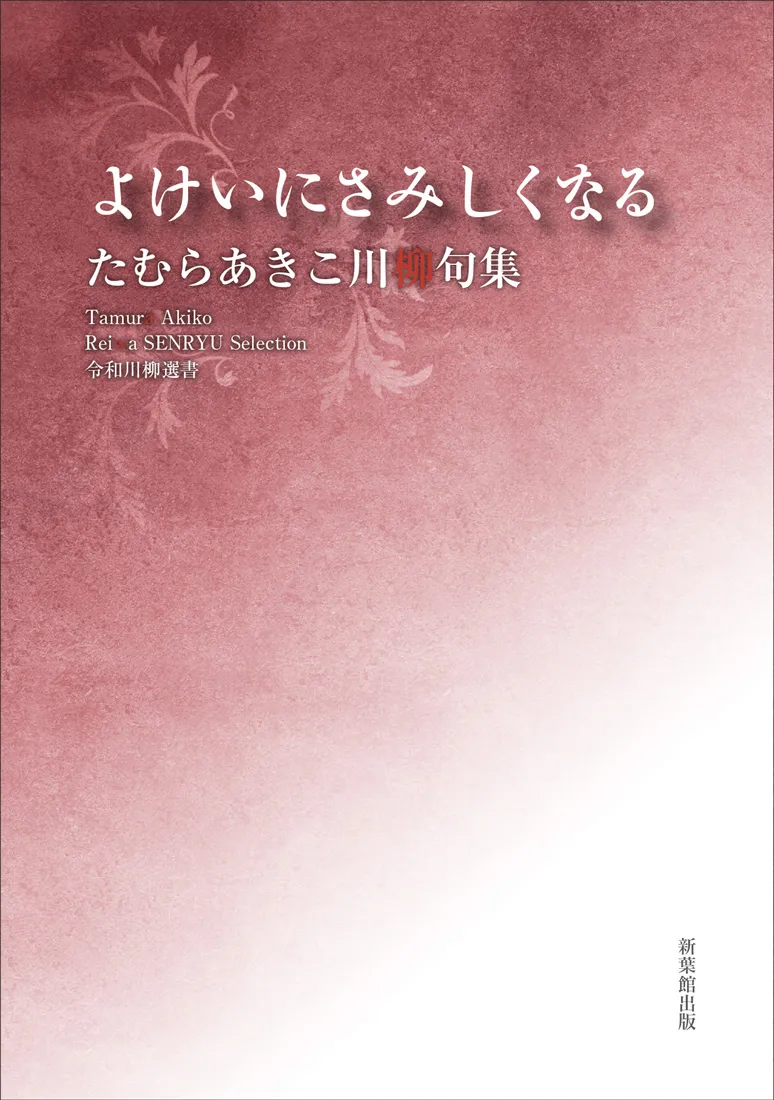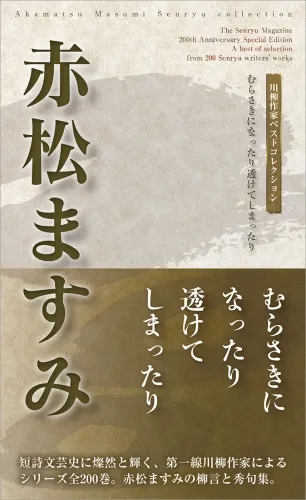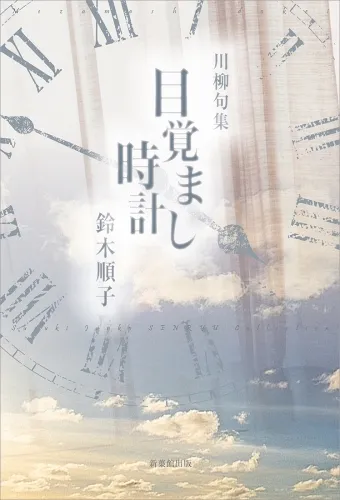11月8日の読売新聞朝刊で、同新聞に掲載された「『移植見送り問題』を巡る一連の報道」(読売新聞東京本社臓器受け入れ断念取材班)に対して、医療分野の優れた報道を表彰する「日本医学ジャーナリスト協会賞」の2024年度の大賞に選ばれたことが報じられていた。記事には、以下のように書かれている。
[取材班は今年1月1日、脳死者から提供された臓器の移植実績が豊富な東京大など3大学病院で23年、人員や病床の不足などを理由に、臓器の受け入れを断念する例が60件超あったことを報じた。その後も、政府や学会、国内外の医療現場や移植を待つ患者、家族らへの取材を重ね、逼迫する移植医療体制の実態を伝えた。]
この一連の報道は私も興味深く読んでいた。そして私立医科大学の事務員として長く勤務した経験から思い出すことがあった。
かなり前のことだが、ある時、外科系の診療科の医局に行く用務があった。それが済んでそこの事務スタッフと雑談していると、デスクにある患者台帳のファイルに目が止まった。手術待ちの外来通院患者のリストだと言う。何十人も名前が記されていた。ベッドが空くまで何か月も要する場合があるとも話してくれた。さらに順番に連絡をとって入院してもらうのだが、あまり待たされると他所の病院に行ってしまうケースも多々あるらしい。待っている間に悪化してしまうことだってあるだろう。これも医療現場の一つの側面なのだと思った。ベッドが空くまでの長い順番待ちというのは致し方ないことなのだろうが、常態化するとそれに馴らされる感覚になるのではないか。何か移植見送り問題に通じるものを感じて思い出されたのである。
事務員としての経験には、附属病院の医療事務部門に配属されていた時期もある。今でこそ大学病院や総合病院に救命救急センターが当たり前のように設置されているが、昭和の頃は急患室が設けられている程度で、休日夜間の医療体制は万全には整っていなかった。その急患室の夜間の電話当番の仕事が、月に1回程度事務員に回ってきていた。いわゆる事務の宿直である。
急患とは原則として附属病院に通院している患者が対象だったので、それ以外の初診は断っていいことになっていた。小児科だけはそうもいかないので、受け入れが可能であれば応じることにしていた。
入職して数年、まだ若かった頃に宿直をしていたら、深夜に電話がかかってきた。眠いのに起こされて渋々受話器をとると、高齢の親が息も絶え絶えで苦しんでいる、連れて行きたいので何とか診察してもらえないかという家族からの依頼だった。更に話しを聞いていくと、いろいろな病院や個人の医院に連絡をとったがすべて断られたと言う。当時は休日夜間の急患のたらい回しということがマスコミで話題となっていたが、まさにその典型的な例である。
当直事務の判断で断ることも出来たが、どうもそれは私には出来ない。心情的に無理である。とりあえず担当になっている内科の若手当直医へ連絡した。そしてその電話を医師当直室に転送し、指示を待つことにした。少し経って当直医から折り返しの電話がかかってきた。内容は、家族の話しを聞いている途中にこの患者は息を引き取ったようだ、だから来院しないということだった。私は、こんなこともあるのかと驚いた。救命救急体制が整う前の日本の医療は、大体どこでもこんな感じだった。今はかなりよくなってきているが、臓器移植については、まだまだ改善の余地がありそうである。読売の記事では、諸外国と比べても日本における移植断念例の数はかなり多いことも併せて報じられていた。
 Loading...
Loading...