福澤諭吉の「学問のすゝめ」をWikipediaで調べると、以下のようなことが記述されている。
[1872年(明治5年2月)初編出版。以降、数年かけて順次刊行され、1876年(明治9年11月25日)十七編出版を以って一応の完成をみた。その後1880年(明治13年)に「合本學問之勸序」という前書きを加え、一冊の本に合本された。
明治維新直後の日本人は、数百年変わらず続いた封建社会と儒教思想しか知らなかった。本書は国民に向かい、日本が中世的な封建社会から、近代民主主義国家に新しく転換したことを述べ、欧米の近代的政治思想、民主主義を構成する理念、市民国家の概念を平易な比喩を多用して説明し、儒教思想を否定して、日本人を封建支配下の無知蒙昧な民衆から、民主主義国家の主権者となるべき、自覚ある市民に意識改革することを意図する。また数章を割いて当時の知識人に語りかけ、日本の独立維持と明治国家の発展は知識人の双肩にかかっていることを説き、自覚を促し、福澤自身がその先頭に立つ決意を表明する。後半の数章で、生活上の心構え等の持論を述べて終わる。
文体は平易ながら、明治維新の動乱を経て新しく開けた新時代への希望と、国家の独立と発展を担う責任を自覚する明治初期の知識人の気概に満ち、当時の日本国民に広く受容された。おそらく近代の啓発書で最も著名で、最も売れた書籍である。最終的には300万部以上売れたとされ、当時の日本の人口が3000万人程であったから実に全国民の10人に1人が買った計算になる。その後も時代をこえてロングセラーとなり、1950年発行の岩崎書店版も数十万部を売り上げた。]
長々と引用したが、最後の段落に注目してほしい。その本の売れ方のすさまじさである。日本の人口が約3000万人の時代に300万部以上売れたと書かれている。300万部という数字がそもそも今では考えられないほどのものだが、当時の書物は知的な財産や宝物みたいなもので、手元に入手できたら有り難がられて必ず読まれたのではないか。いわゆる積ん読というようなこともあまりなかっただろうと想像される。
向学心があっても経済的に本を買えなかった貧しい者もいたことだろう。誰かのものを借りたり回し読みしたりしたのではなかろうか。「全国民の10人に1人が買った計算になる」というが、こういう事情を踏まえると、全国民の10人に1人どころか、それ以上の割合で読まれたと推測される。現代のベストセラーとはかなり異なる読まれ具合だったのではないか。
以前から出版不況と言われているが、今の世で例えば100万部売れた書籍があったとして、それを購入しても読まれないような勿体ないケースは多々あることだろう。そんなことをして眠ったままの開かずの本になったものが、私の部屋にもたくさんある。そんなことを踏まえると、100万部のうち実際に目を通された部数はある程度少な目に見積もられる。せっかく買っても使わない、そういう気まぐれな消費行動は書籍にも該当する。
出版文化も大量生産・大量消費のシステムに組み込まれている時代である。商業主義に乗せられて買わされる本もある。消費への衝動は本の購入でも例外はない。文明開化が始まった明治という時代には、そんな現象は想像すらできなかったかもしれない。
戦後の高度経済成長の経験を経て、贅沢で無駄も多い消費傾向が続く今の世では、価値観の多様化も当たり前になってきた。国民のほとんどが同じ方向へ向かって同じような行動をとるということは少なくなってきた。新刊書が評判になったからといって驚異的なベストセラーになることはもう有り得ないのではないか。
最後に「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずといへり」という冒頭の一節が有名なこの「学問のすゝめ」を私は今更読む気にはなれない。興味が湧かないのは価値観の多様性も私のメンタルの下地にあるのだろう。
 Loading...
Loading...








































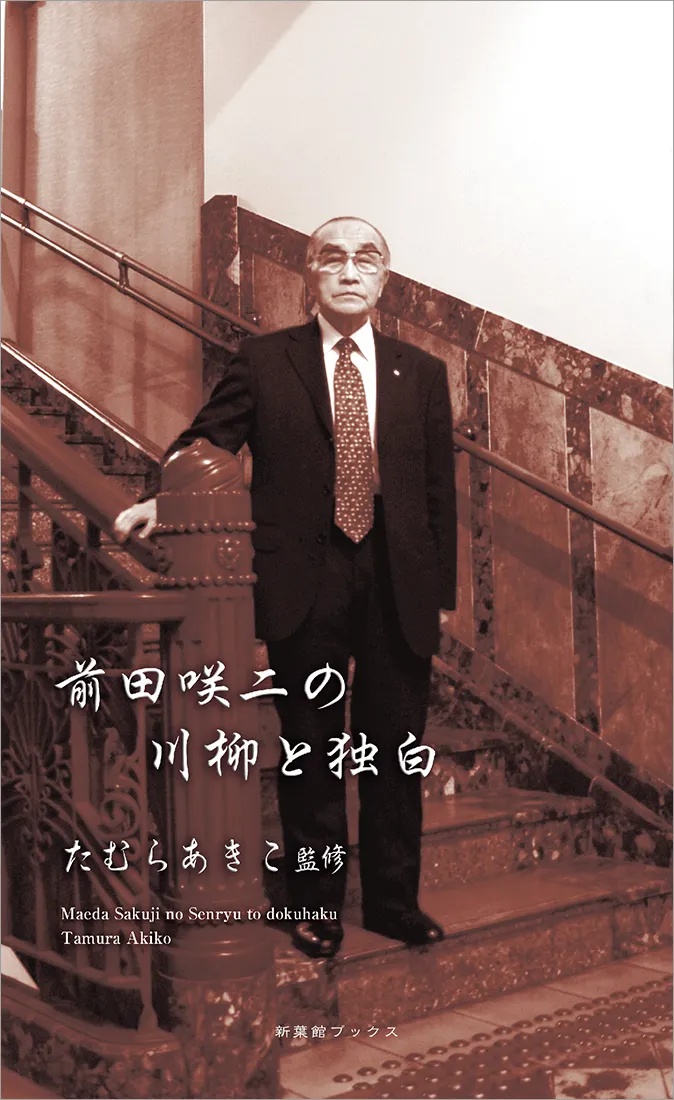
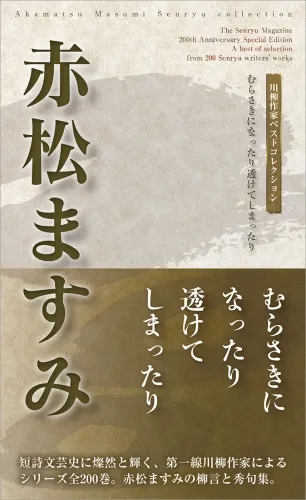
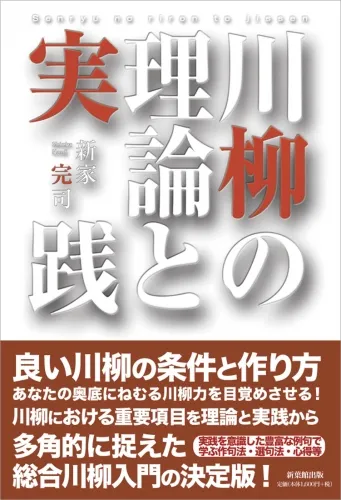
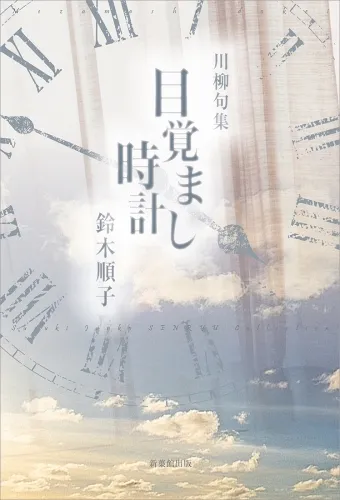
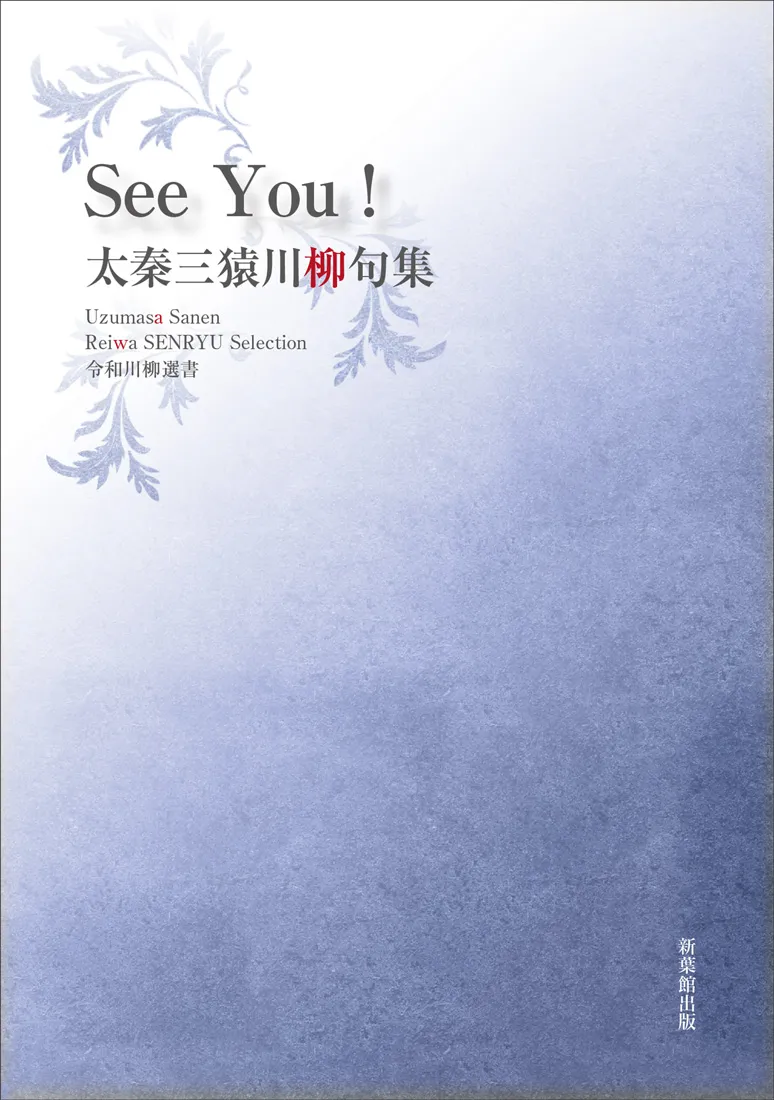
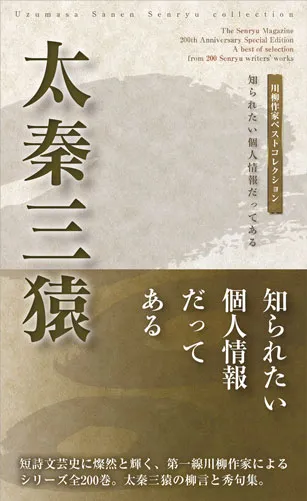
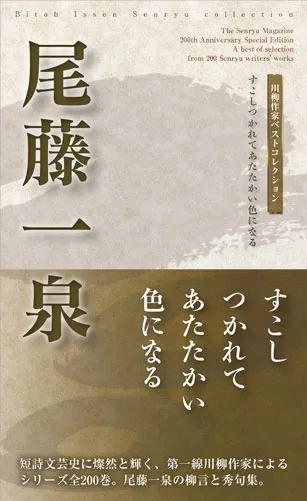
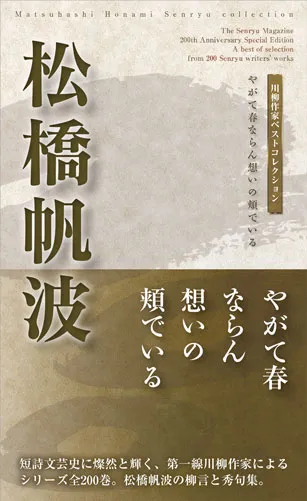
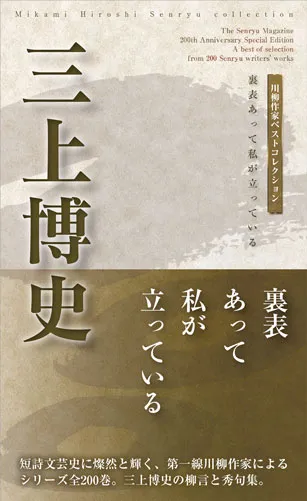





あら、写真、新しくされたのですね!
久美子さん、ご無沙汰しております。コメントありがとうございます。
顎髭の白さがそれなりにサマになってきたかなぁ(笑)…、と一人勝手に思い込みまして、ささやかなリニューアルを施しました。