前回の続きのようになるが、この短歌番組ではある歌人の作品が紹介されていた。その中に「(火葬場で)骨拾う」というフレーズが出てきた。指導講師は「ほねひろう」と読んだ。
これにまたまた私は違和感を持った。火葬場で焼かれた人間の「骨(ほね)」は一般的には「お骨(こつ)」になるのではないか。もちろん「骨(ほね)を拾う」という言い回しはある。「死後の面倒をみる。後始末をしてやる」というような意味合いで使われる場合が多い(例として「骨を拾ってやるから死ぬ気で頑張ってこい」とか)。しかし、火葬場での収骨の場面では「ほね」とは言わない。丁寧に「おこつ」と言う。
作品に出てくるお骨は作者の祖母のものをさしていたが、そもそも祖母のお骨を拾うことを「骨拾う」と「お」を付けないことにも不自然さを感じた。身内のものでも丁寧な言い方になるのが一般的なのではないか。それに気づかない講師の先生にも些か疑問を持った。
火葬された「骨」を訓読みの「ほね」と読まずあえて音読みの「こつ」で呼ぶのは、焼かれて骨(ほね)だけになってしまった死者に対する畏敬の念があるから、こういう音読みの婉曲的な言い回しが派生したのではないかと、私は推理している。国語学や語源については専門家ではないが、「こつ」と「ほね」の使い分けが畏敬の有無でそうなった気がするのである。誰か詳しい方がいたらご教示願いたい。
ちなみに漢和辞典を引くと、「こつ」と読む場合のもう一つの意味として「要領、調子」が挙げられている。「このやり方のコツは…」などと言ったりするが、一般的には片仮名表記で「このやり方の骨は…」などと記したりしない。これは「ほね」と読まれる恐れがあるから敢えてそうするようになったのかもしれない。
さらに余計なことを言えば、「気骨」という言葉がある。これを「きこつ」と読むか「きぼね」と読むかで意味合いは全くことなる。これは文脈から判断するほかない。
という訳で、たかが「骨」の一字にもいろいろと厄介なことが内包されていることを思い知った次第である。
 Loading...
Loading...











































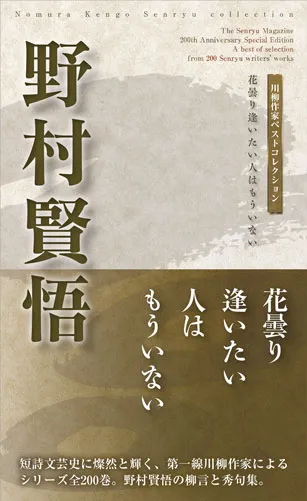
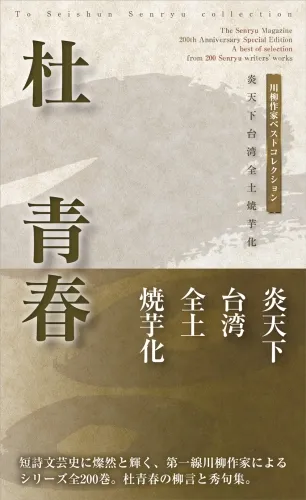
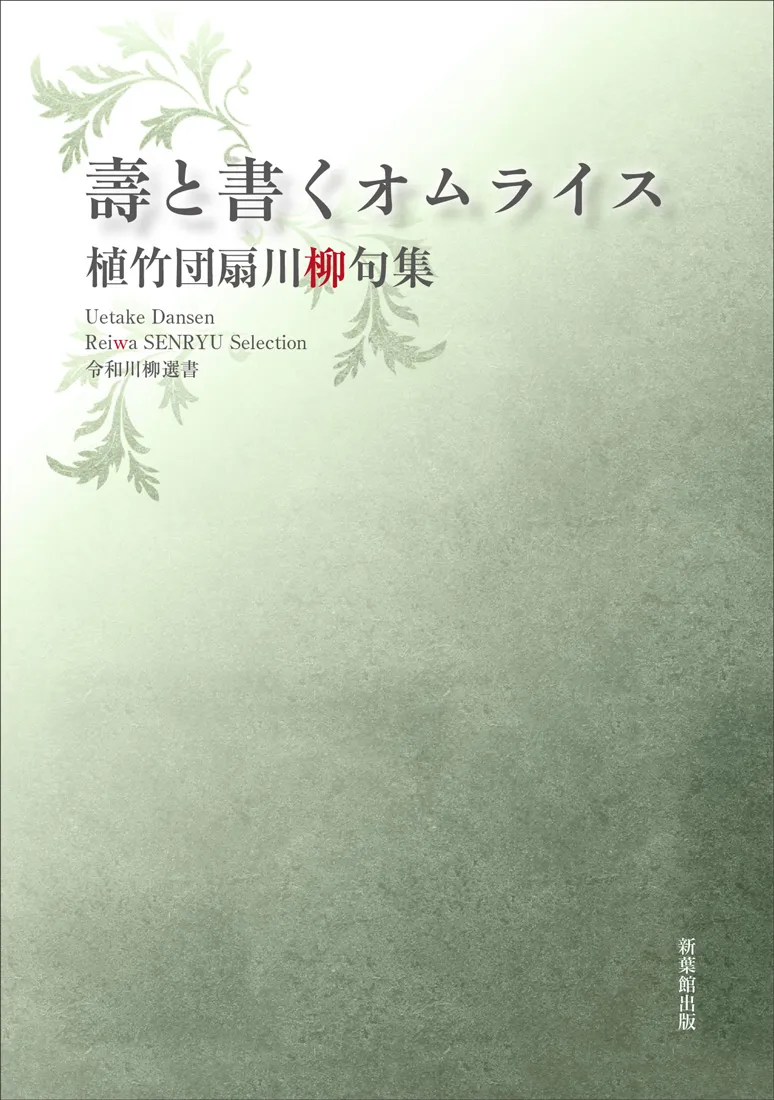
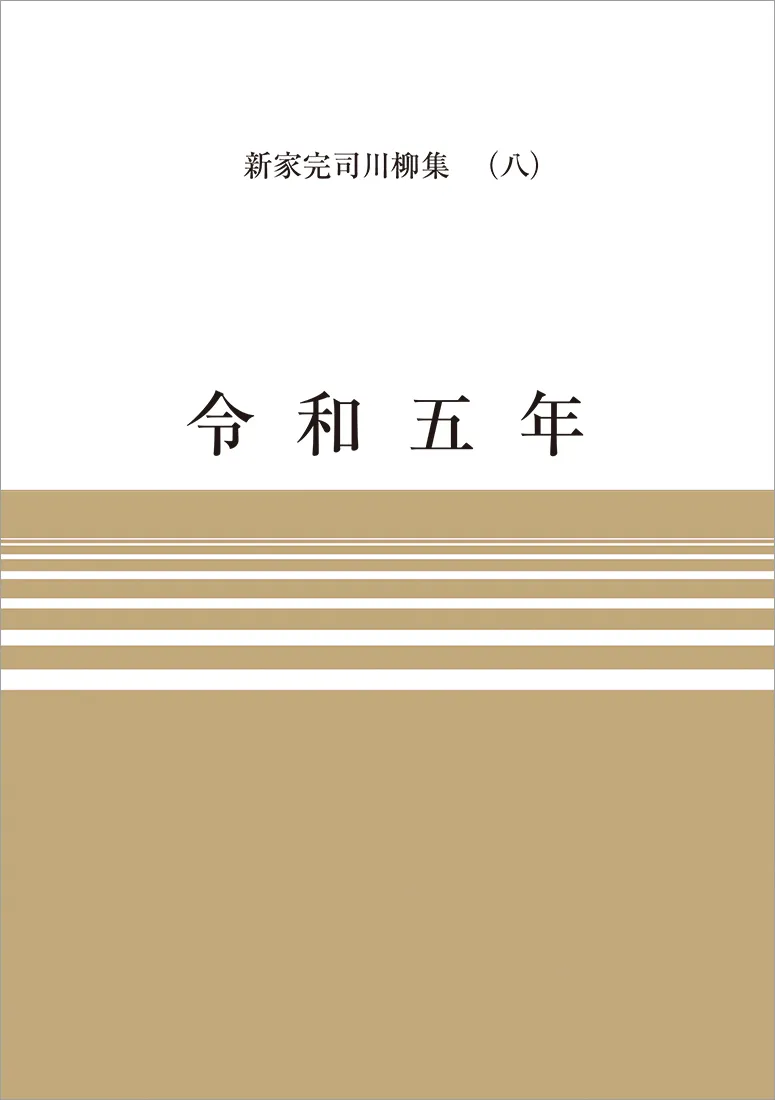
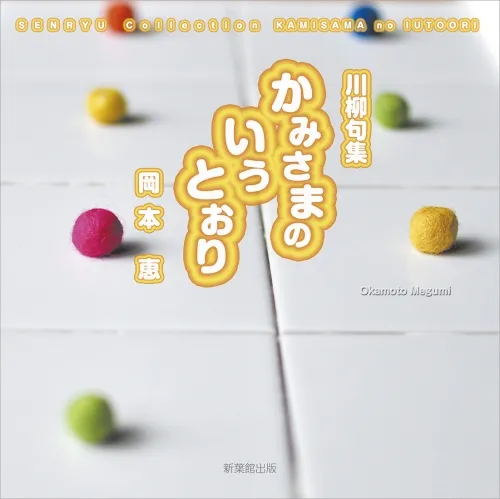

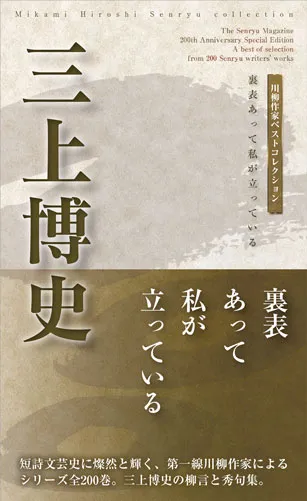
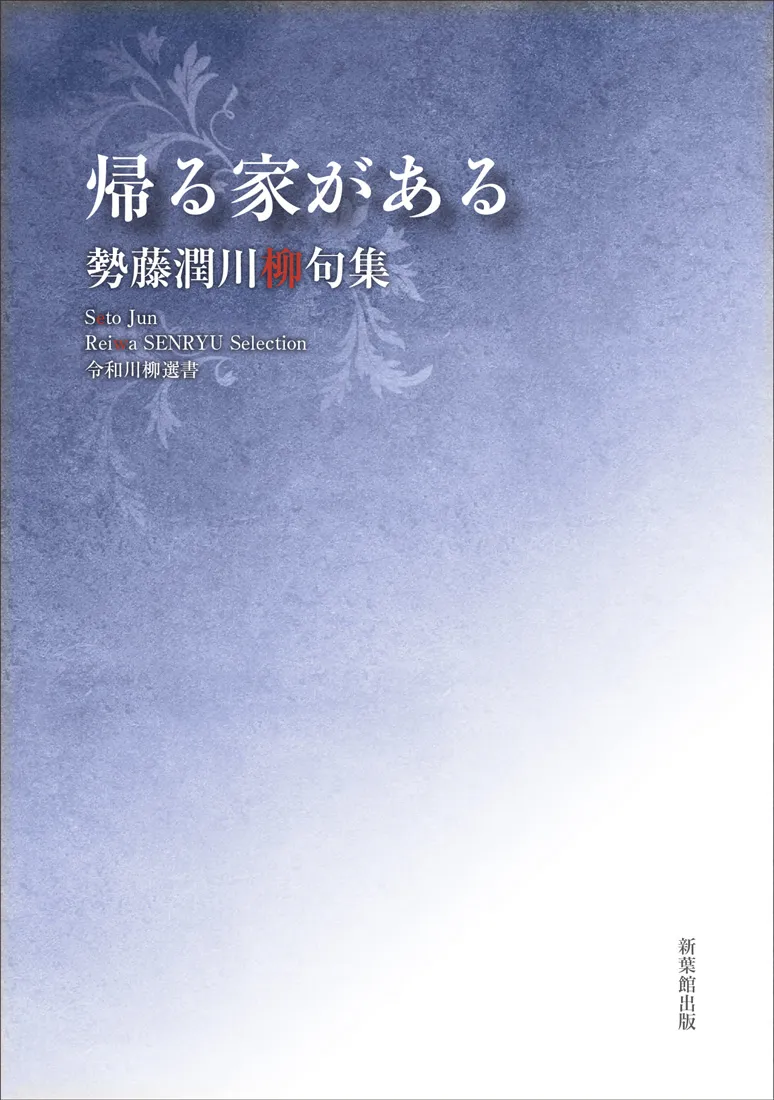
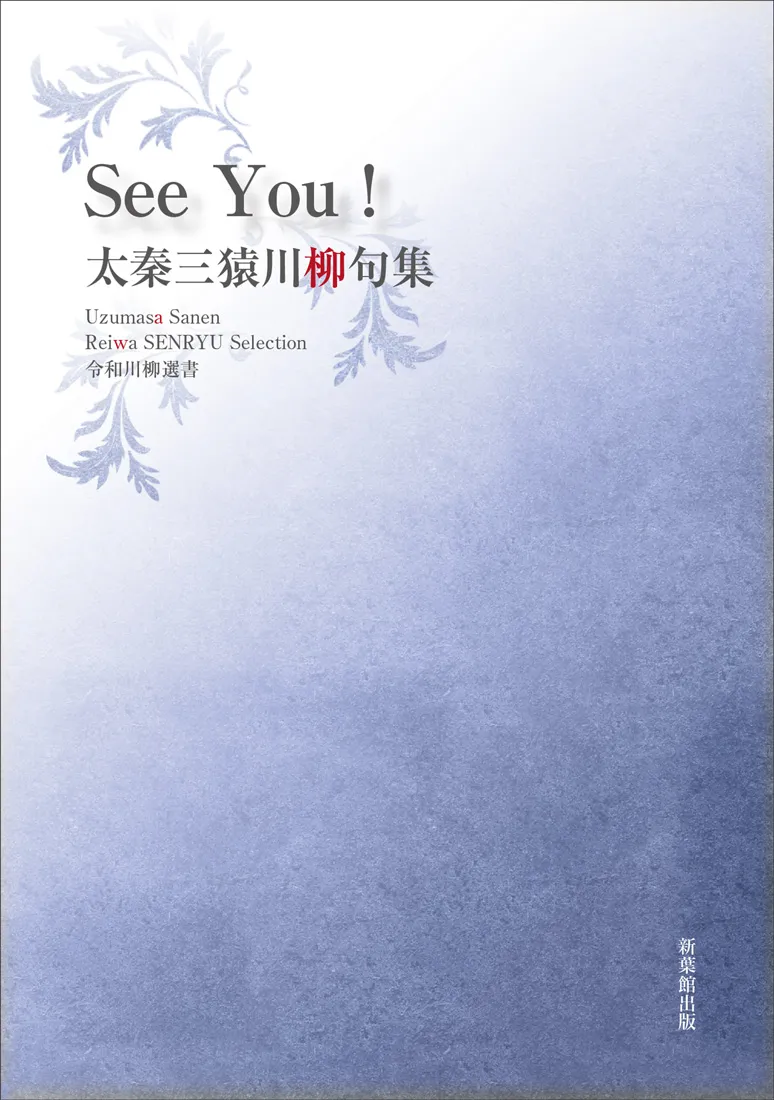
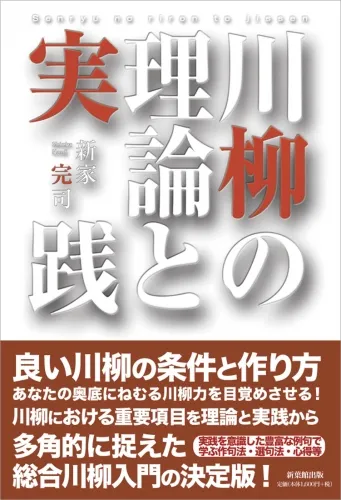




「ほねとこつ」のお話、とても興味深く読ませて頂きました。「骨を折る」も面白い表現ですね。「無駄骨」となるとさらに思いが広がります。日本語から英語へ発想が飛ぶと、さらにややこしくなりますね。身内の(身内に限りませんが)のご遺体をBODY(ボディ)と呼ばれたら腹が立ちませんか?外来語として広く使われている(ボディ)と英語の(BODY)が絡み合うと複雑ですね。〈ことばを感覚としてとらえる〉ことは、大切なことだと考えます。
団扇さん、ありがとうございます。
〈ことばを感覚としてとらえる〉いい言葉です。