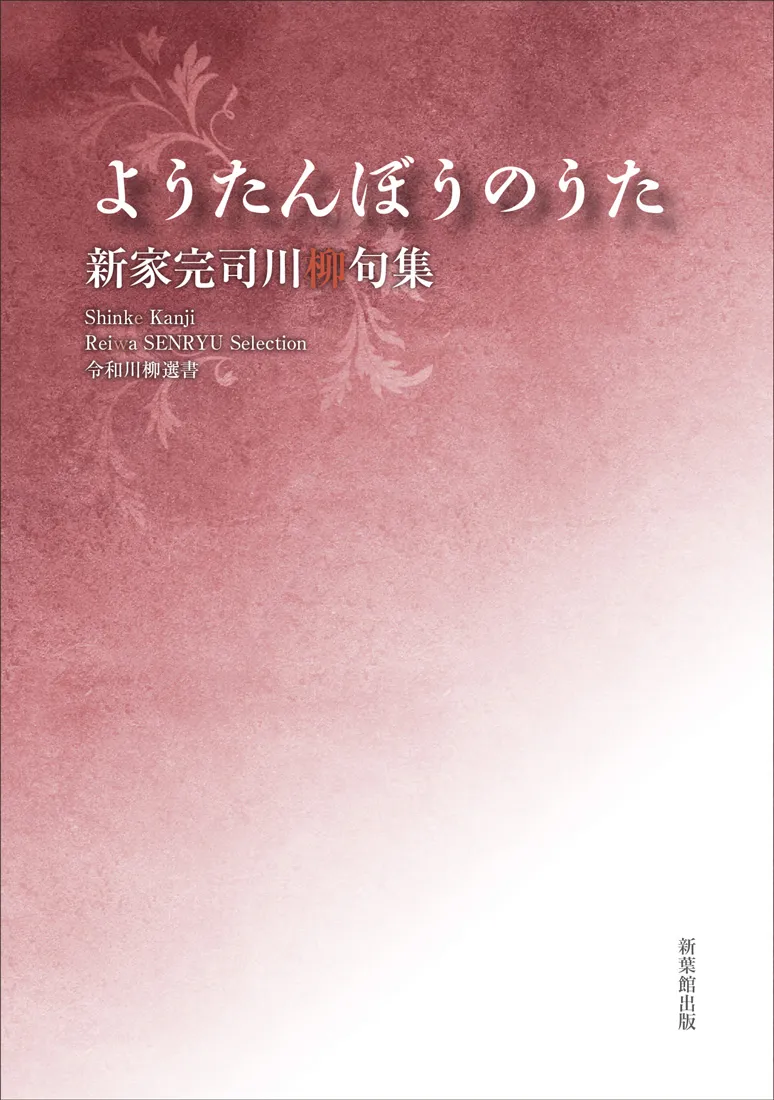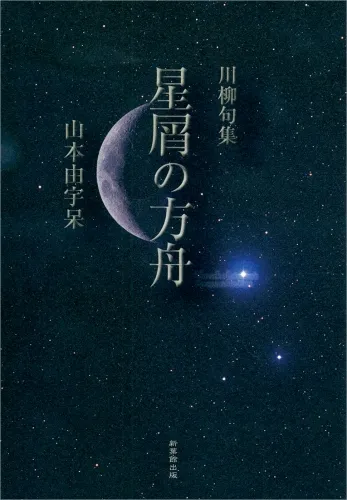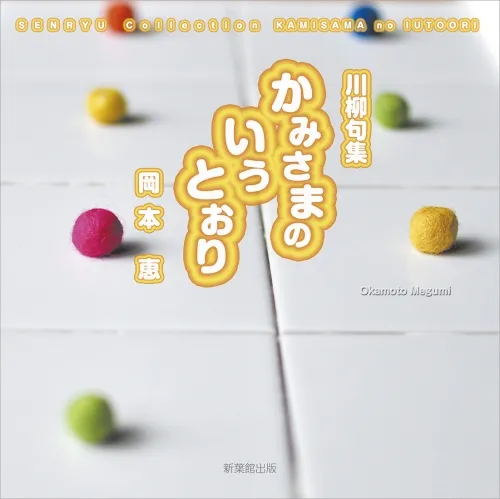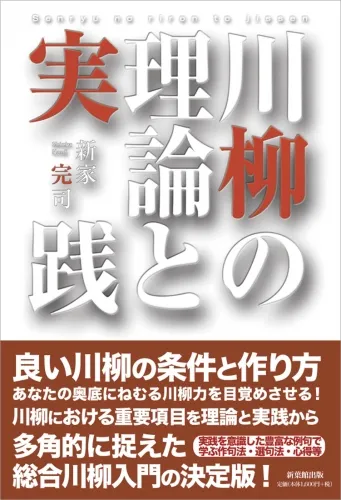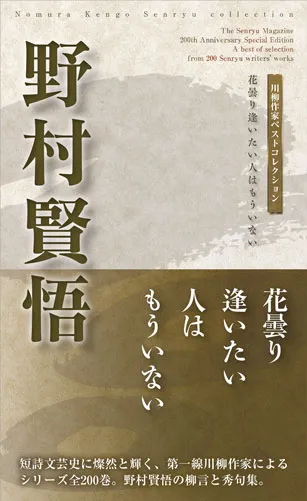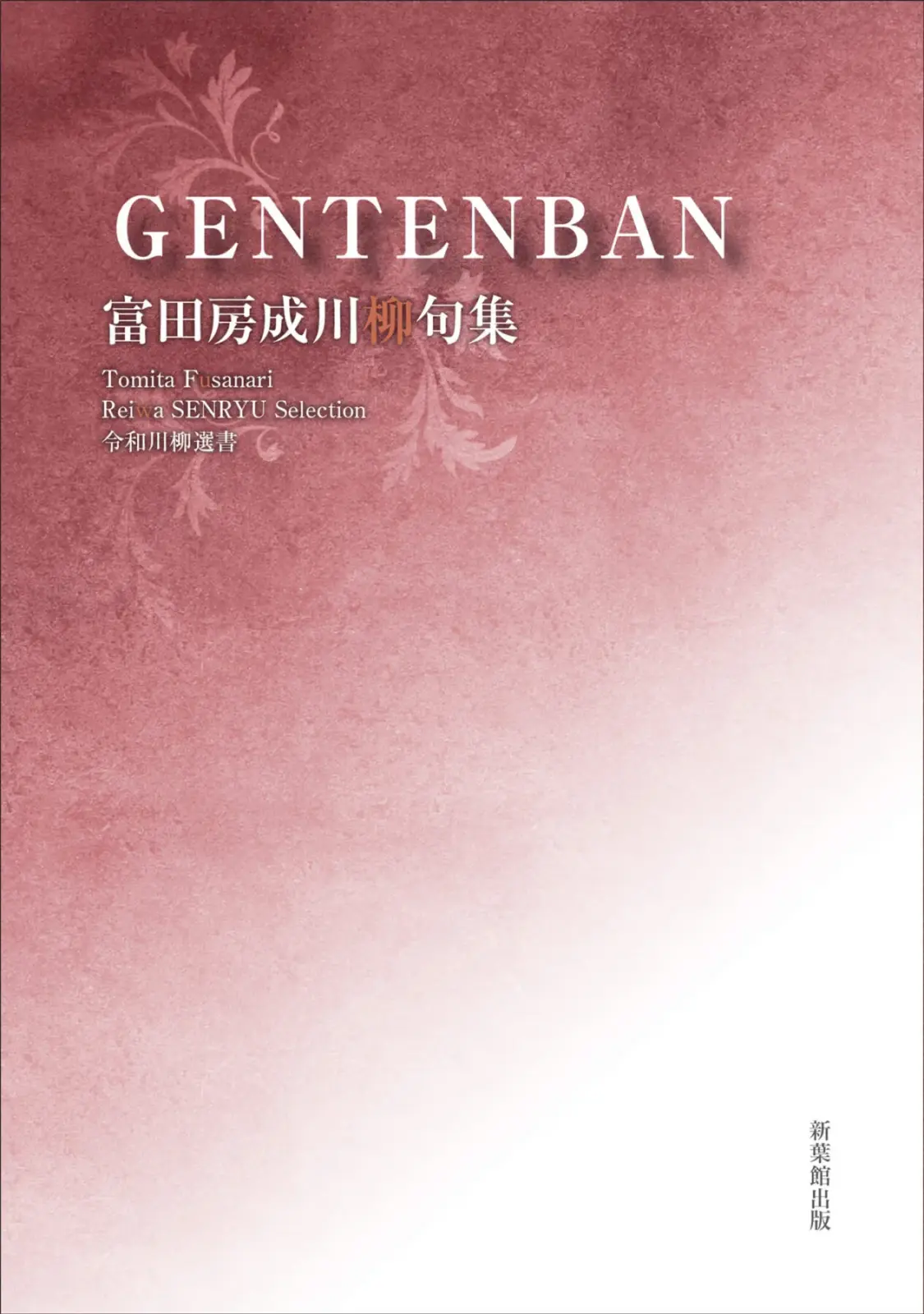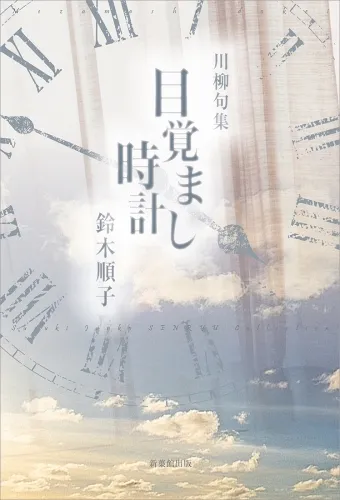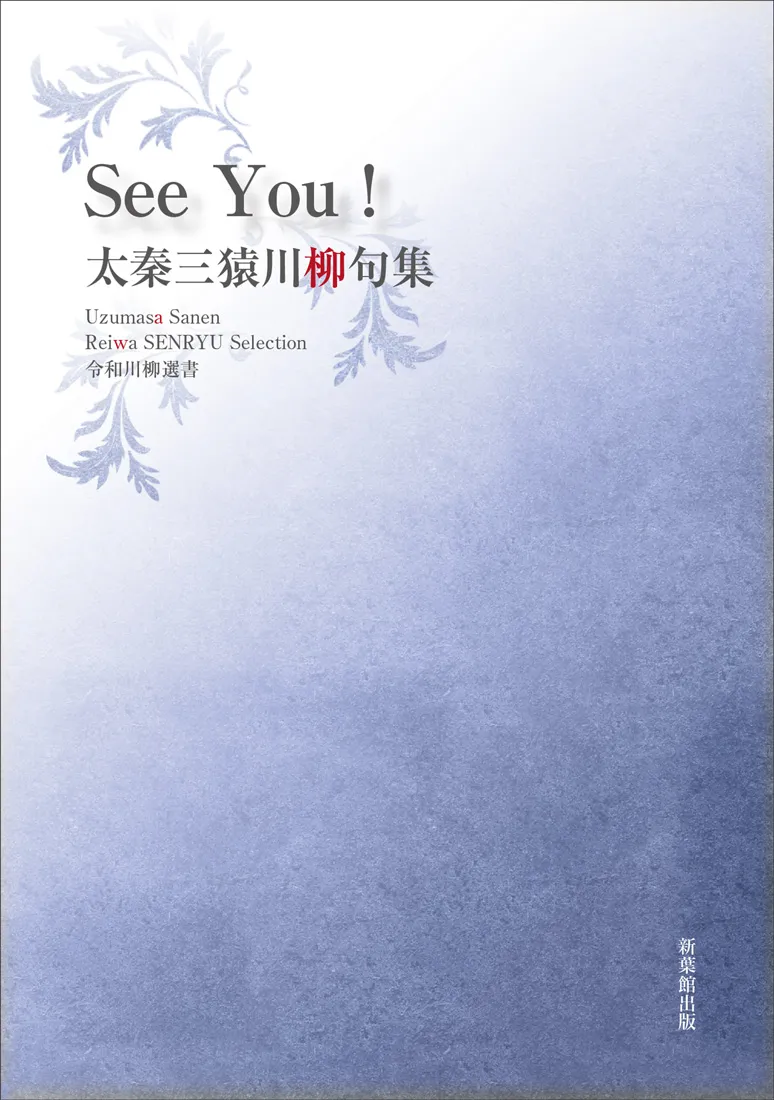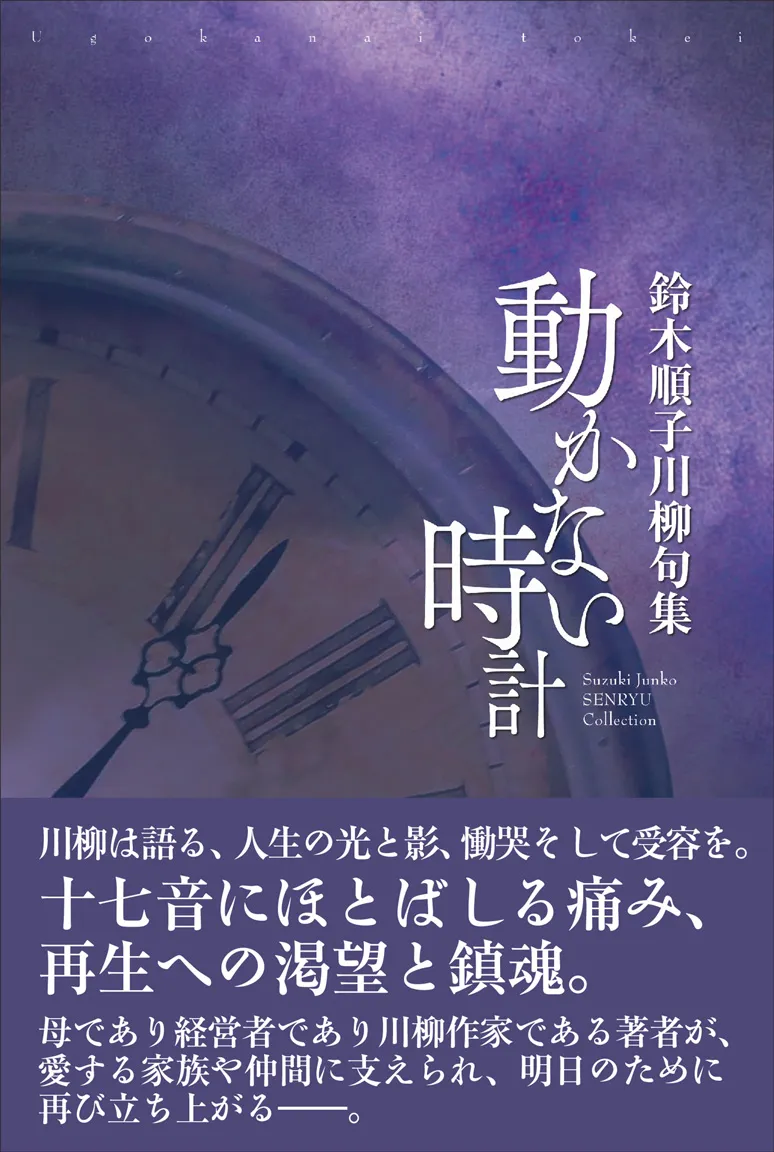昨年の秋、やっと初孫が生まれた友人がいる。70歳近くになって授かったので可愛くて仕方がないと言う。あまりの可愛さにいろいろと孫の将来のことをつい考えてしまうそうだ。
孫が自分と同じ70歳になる2090年代、どんな年号になっているか想像すらつかないが、世の中はどう変わっているか不安にも感じたらしい。そうは言っても平和な時代が長く続いていて欲しいという願いも勿論持っている。
いくら具体的イメージを描いても、決してそのとおりにはなっていないのが未来社会というものである。21世紀末に近づく日本と世界、さらに地球環境は一体どうなっているか。もうこの世に自分は存在していないが、あの世から眺めるだけにしてもいささか心配に思う訳である。
第三次世界大戦や核戦争勃発の恐れ、地球温暖化の更なる進行、エネルギー資源の枯渇、金融に塗れた資本主義経済の行き詰まりなど、世界規模の不安について、友人は熱っぽく語り始める。
それらの話題が尽きてくると、6年先に孫が小学生になることを思い浮かべ、それを踏まえて70年先の孫の孫にあたるような小学生は、当然の如くペーパーレスの教育を受けていて、ランドセルなど背負わなくなっているだろうとなどと話す。その頃の国語の教科書ではもう夏目漱石や芥川龍之介の作品も消えているのではないか。明治大正期の小説もそれ以前のものと一緒に古典として括られ、世間でもあまり読まれなくなっているだろう。いわんや平安文学と言えば必ず登場する枕草子、漢文で必ず習う論語なども、忘却の彼方に行ってしまっているのではないか。そんなことまで言い出す始末である。
友人はどうも国語があまり好きではなかったようである。よく聞くと、中学・高校の国語で習ったものはほとんどつまらなく感じていたらしい。今更ながら思わぬホンネをこぼしたようだった。私も、十年一日、いや五十年一日のような国語の教材にはいささか閉口しているので共感するものがあった。
 Loading...
Loading...