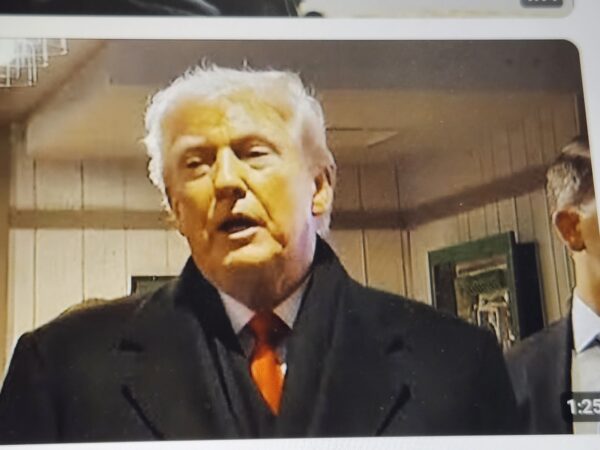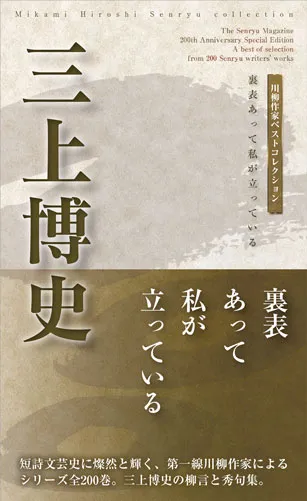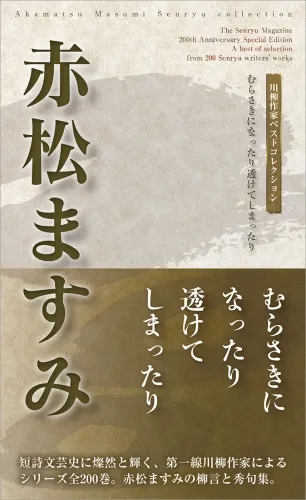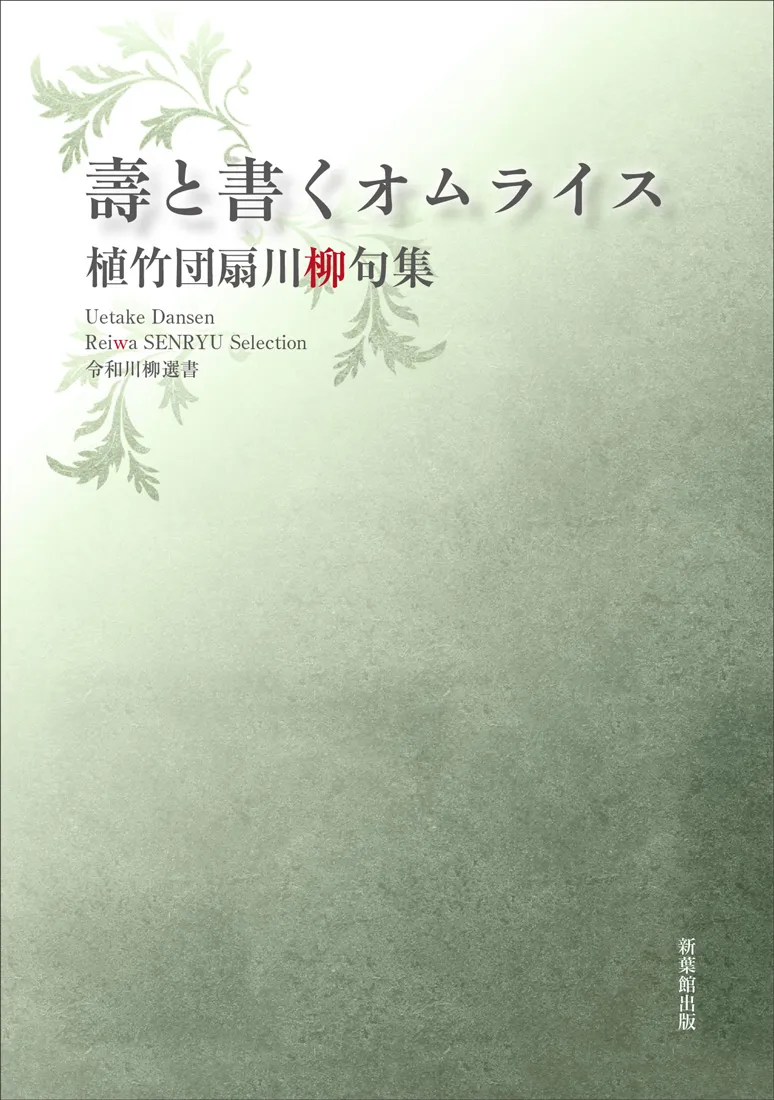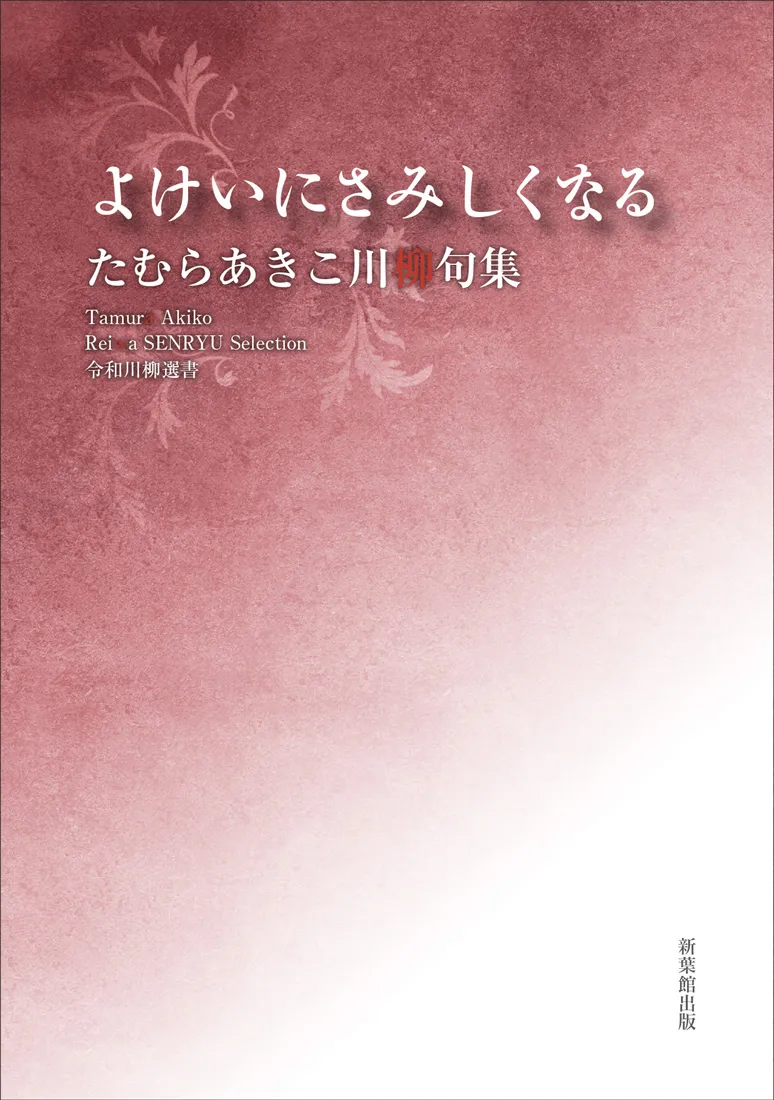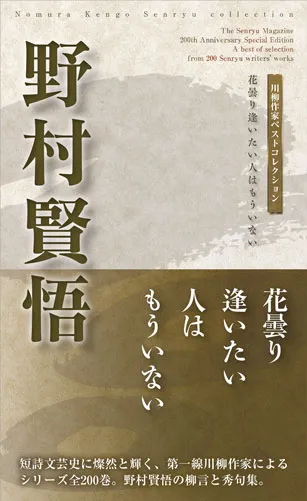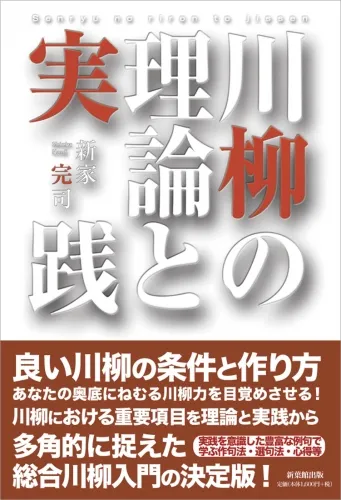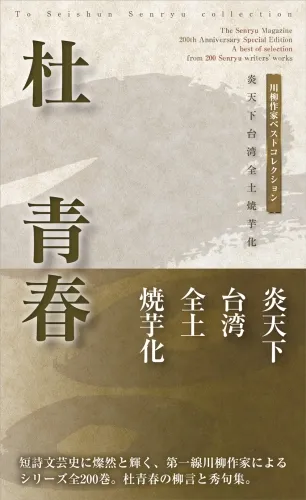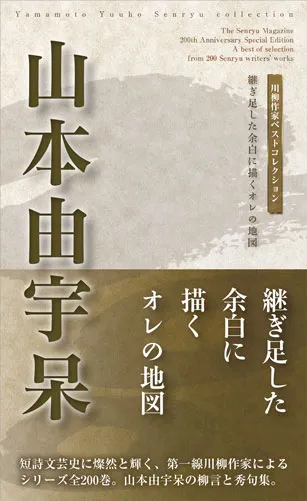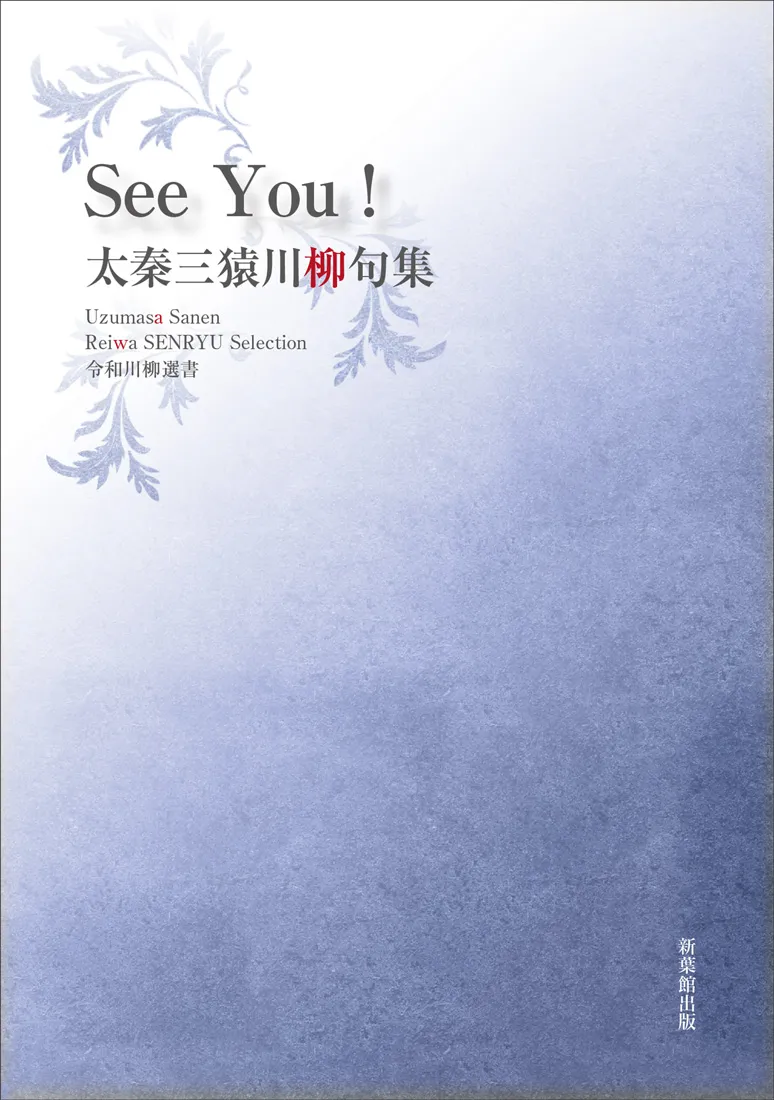一升瓶と缶ビール
川柳作家 三上 博史
私の父親は酒に弱かった。ほとんど飲めなかった。それでも若い頃は少しだけ晩酌していた。飲むのは暑くても寒くても二級の冷や酒。水色の半透明の一升瓶だった。
電気工事関係の会社にずっと勤務していて、夕方帰って来ると食事の前、自分で湯呑に1合の半分、5勺(せき)程度を注いで、つまみもなしにちびりちびりと飲んでいた。今から振り返ると、一日の疲れを取りたかったのだろうと思う。毎日働いて家族を養い、その家族が楽しく暮らせるように頑張った典型的な昭和の親父だった。
そのくらいの飲み方だったので、瓶の中身はなかなか減らない。それでもひと月に1回程度、空き瓶を持って近くの酒屋へ同じ二級酒を買いに行くのが、小さい頃からの私の役目だった。
そんな父親でも、定年退職の日の送別会ではかなり飲んだようで、夜遅く誰かの肩に摑まって帰ってきたことをはっきり憶えている。酔っ払って饒舌になった父親を見たのは初めてだった。その後は、5勺の量も呑まなくなった。
私の方はいける口なので、毎晩ビールなどを飲んでいたが、30歳を過ぎてからは平日には飲まないようにした。その方が翌日の仕事で体が軽く感じられることに気づいたからである。それでも日中のストレスが溜まることもある。夕食前、柿ピーをつまみに缶ビールを開けて飲むことが偶にあった。
缶ビールサラリーマンの日が暮れる 博史
 Loading...
Loading...