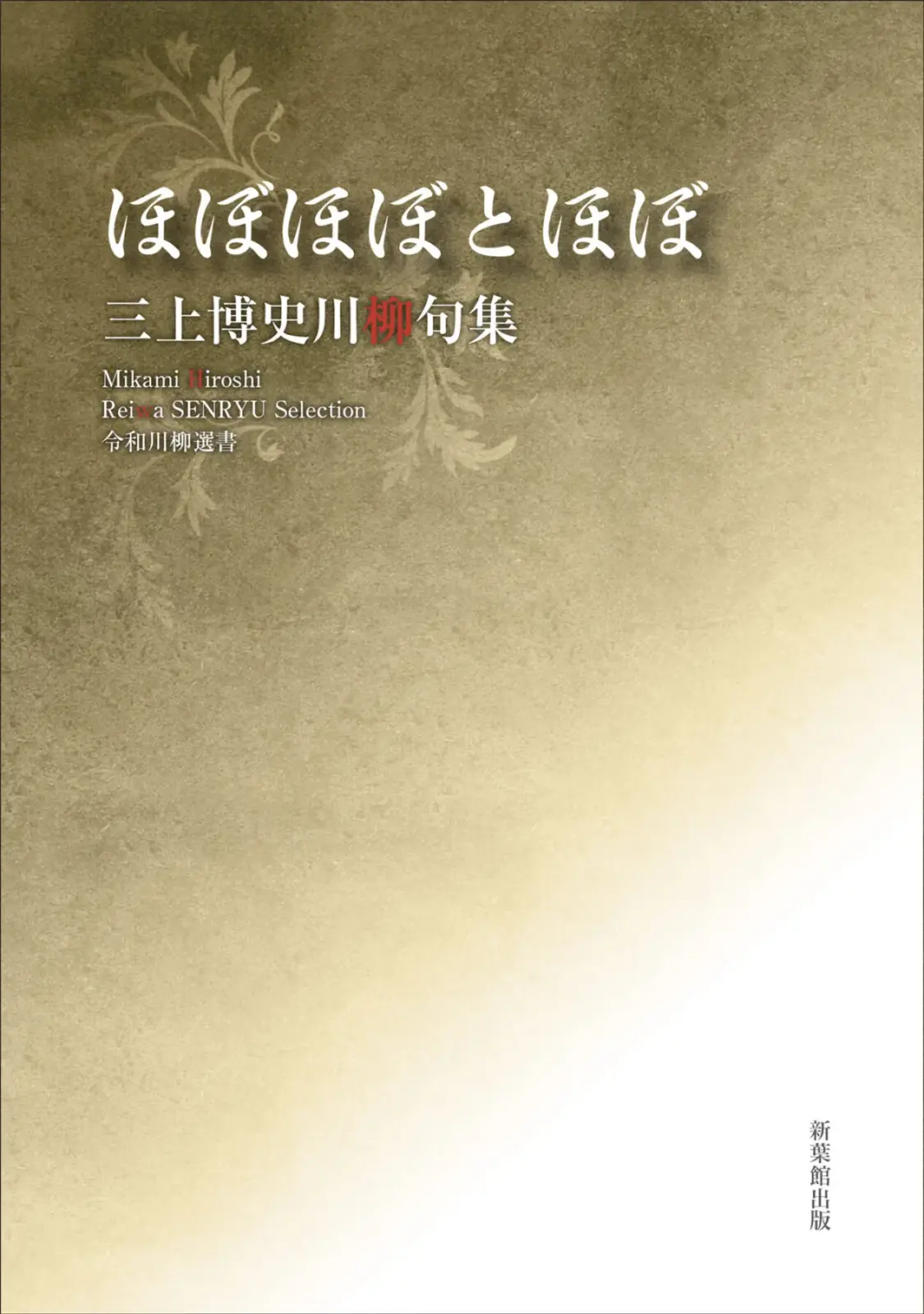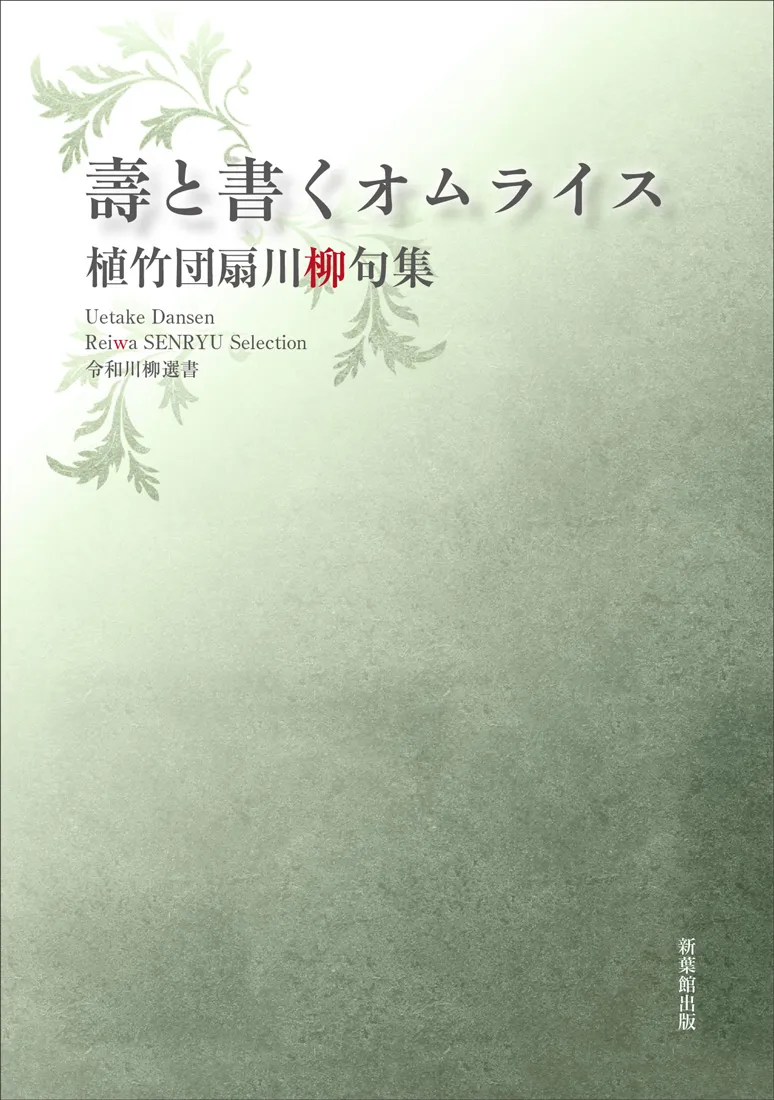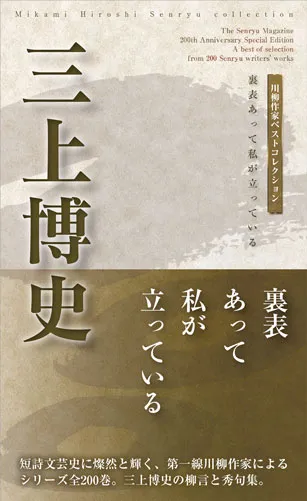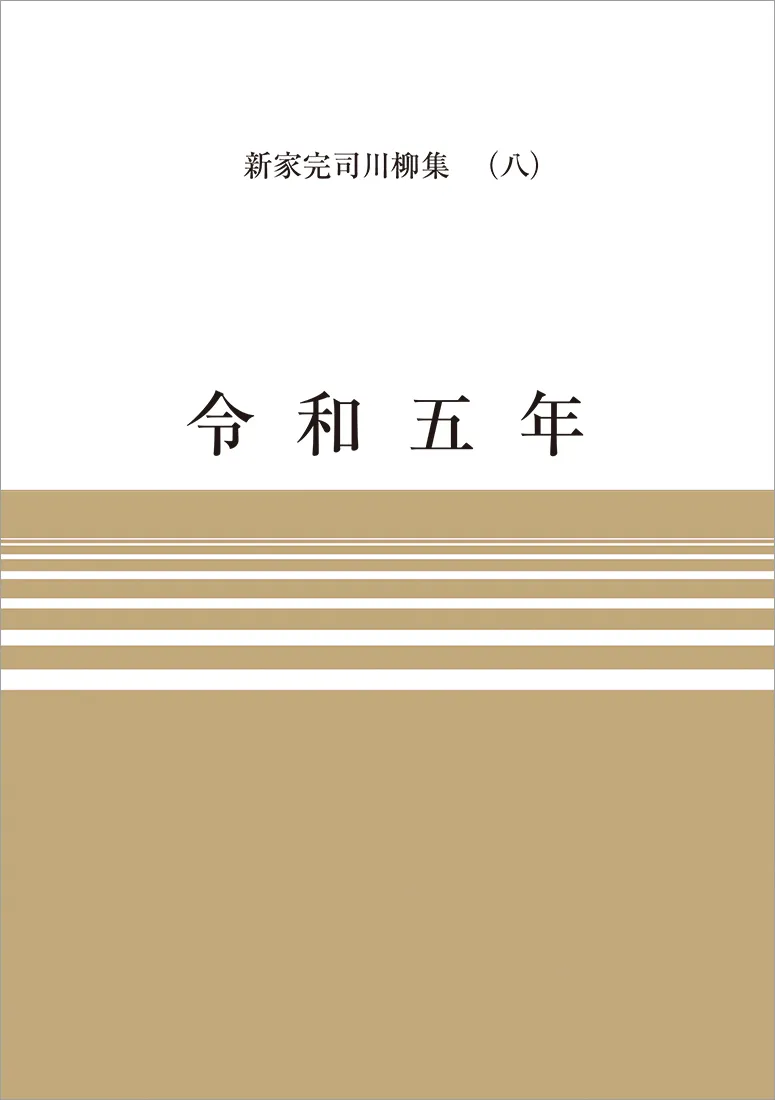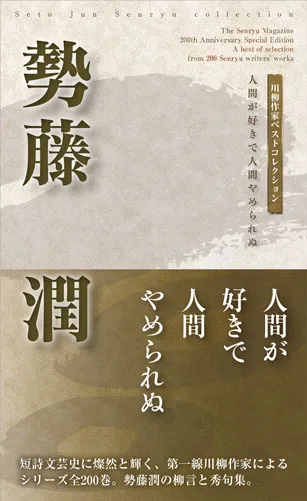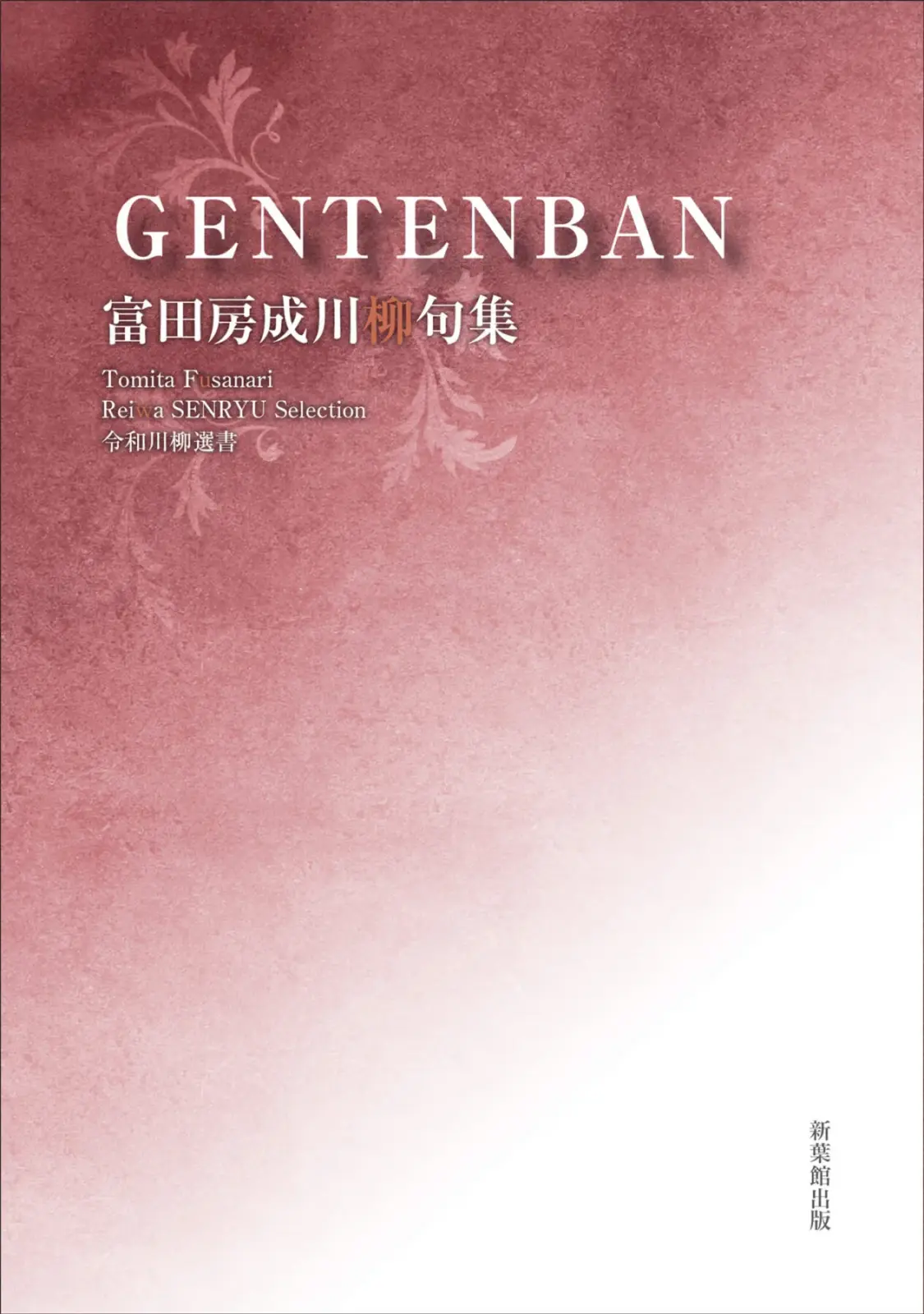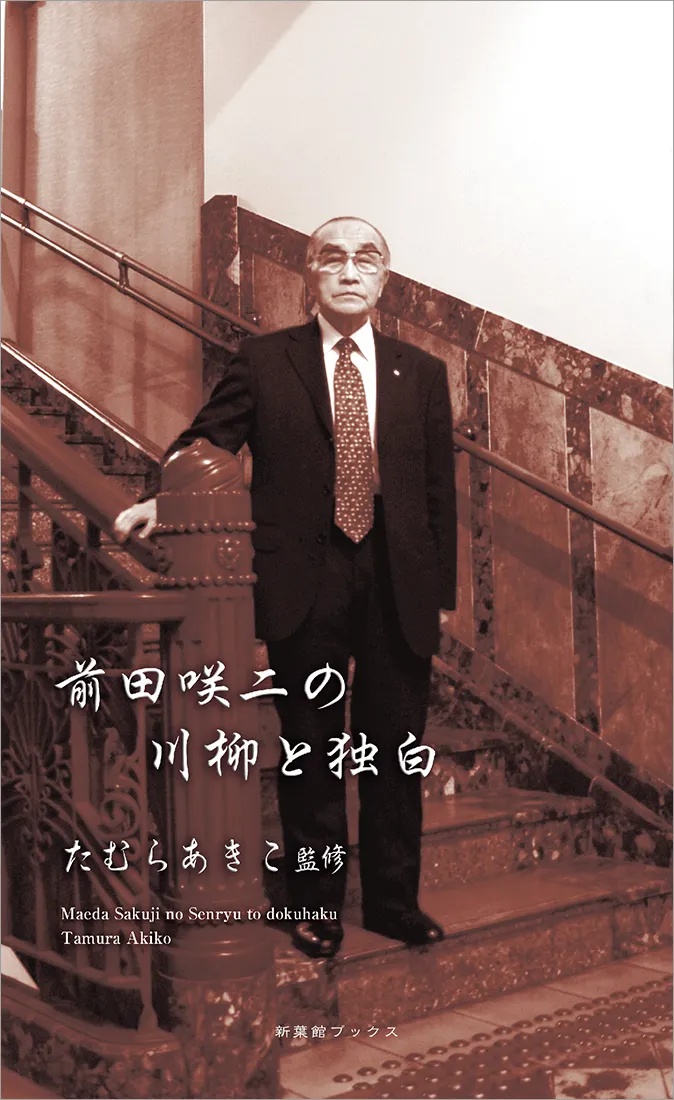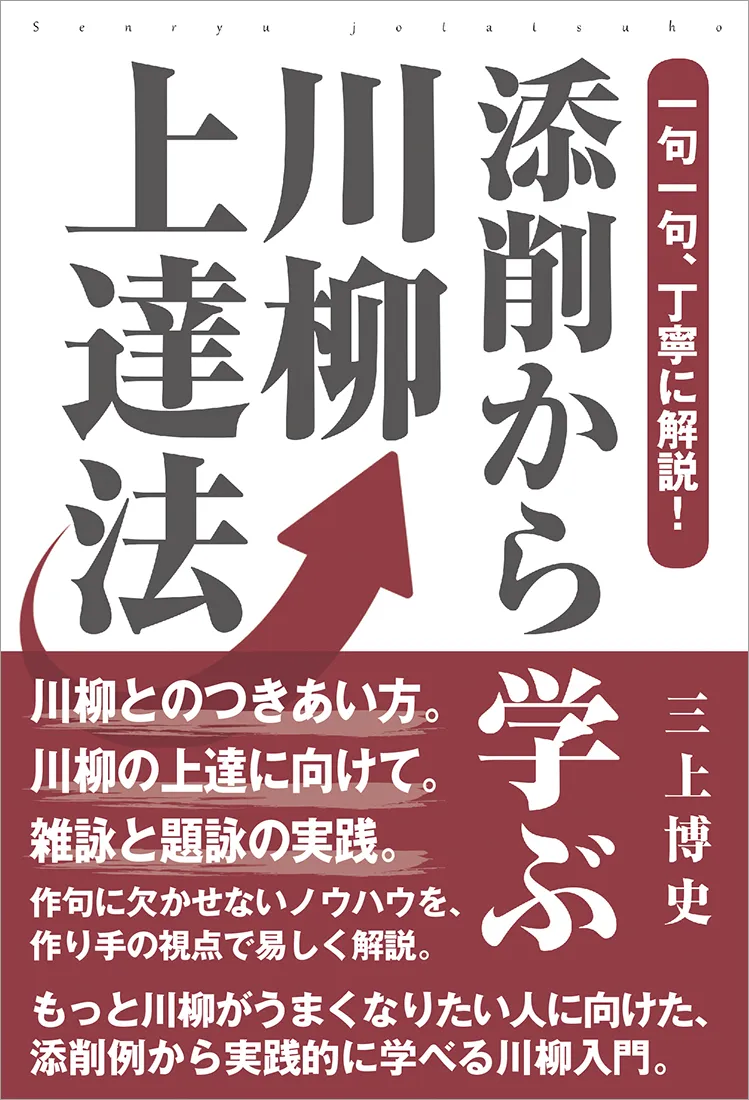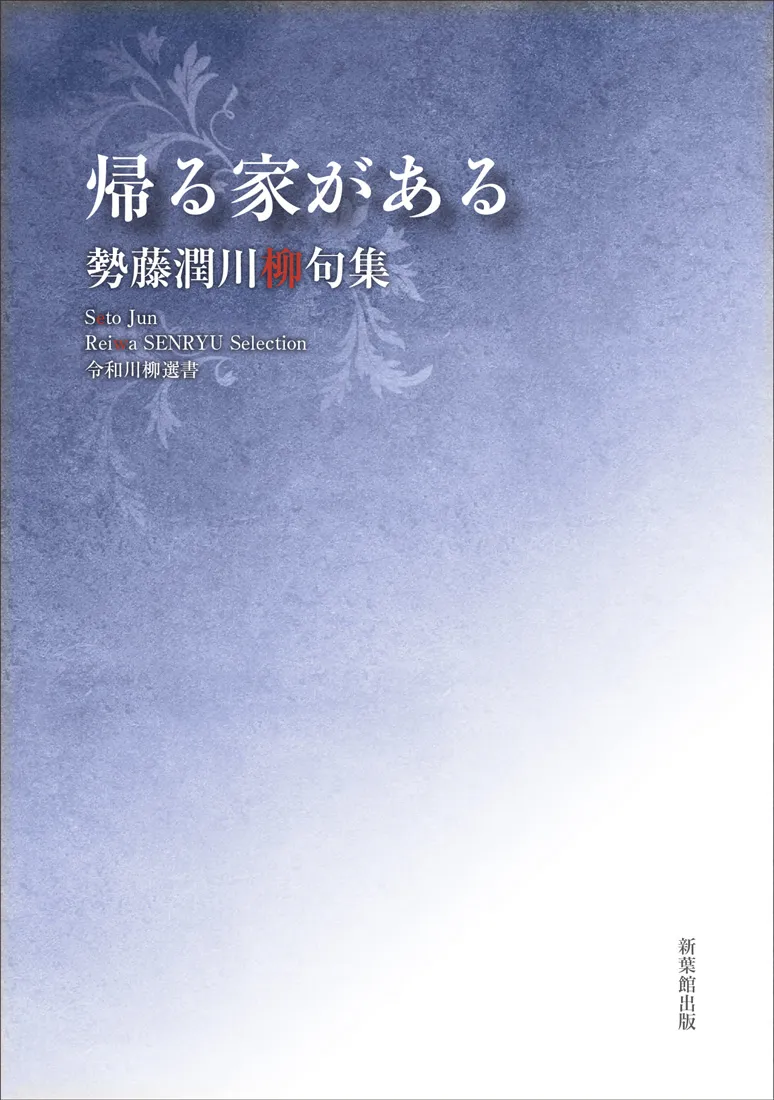三十代から五十代にかけての10数年間、私は誌上大会やコンクールなどへの投句マニアだった。全国どこかでいつもやっているこれらの募集は柳誌などに案内されていて、見つけるとどうしても応募したくなり、作句して毎週のように投函していた。大方は大体1000円程度で参加できるものである。今もあるようだが、ミニレターという確か60円ぐらいの切手が印字された封書が郵便局で売られていて、文具店などで買った封筒に切手を貼るより割安なので、これを毎度利用して小遣いの節約に努めていた。
課題吟がいくつも出されるものは作句数が多くて大変なので、応募は敬遠していた。課題が一つや二つ程度のものは、見つければ必ずと言っていいほど応募していた。結果が載った柳誌が届くとすぐにページを開いて自分の作品が入選・入賞したかどうかを確認した。上位に入っていた時の嬉しさは堪らないものだった。楯やトロフィー、賞状はかなりの数を頂戴して部屋に飾り切れなくなっている。
さて、当時から私には私なりの作句スタイルがあった。休日(わざわざ有給休暇を取る場合もある)の午前中に自室へ籠って句をひねり出すのである。下準備として、国語辞書、類語辞典や漢和辞典などを開いて、出された課題の意味を改めて確認して発想やイメージを広げようと試みる。そして静かに部屋へ籠り座椅子に座る。メモ用紙と鉛筆・消しゴムは離さないで置く。
なかなか句が思いつかない時でも、時間が経過すれば大体いつかは何かの拍子で作句モードにスイッチが入る。そうなるともう自分だけの世界。句の完成形には程遠くても結構な数の着想が湧いてくる。天から降りてくる、と言ったら恰好つけ過ぎか。でも、脳内に何らかのホルモンが分泌されたような感じになっているのは確かである。そんな状態の中で句を詠み続け、応募に必要な数が出来上がりそれなりの満足感を得ると、快い疲労感に襲われる。そして投句作品はすぐには投函せずそのまま数日間熟成させるように眠らせ、それから改めて向き合って推敲する。その後ようやく清書して投函する。このスタイルもずっと変わらず続いた。
自室に籠って作句するやり方は今でも続いているが、誌上大会等への投句は殆どやっていない。いささか飽きてきたというのが正直なところでなのである。しかし作句モードへのスイッチは、雑詠主体となった今でも私の頭の中で機能している。ある程度納得した句が詠めると心地よい脳の疲労感を今も必ず味わっている。だから川柳は止められない。
 Loading...
Loading...