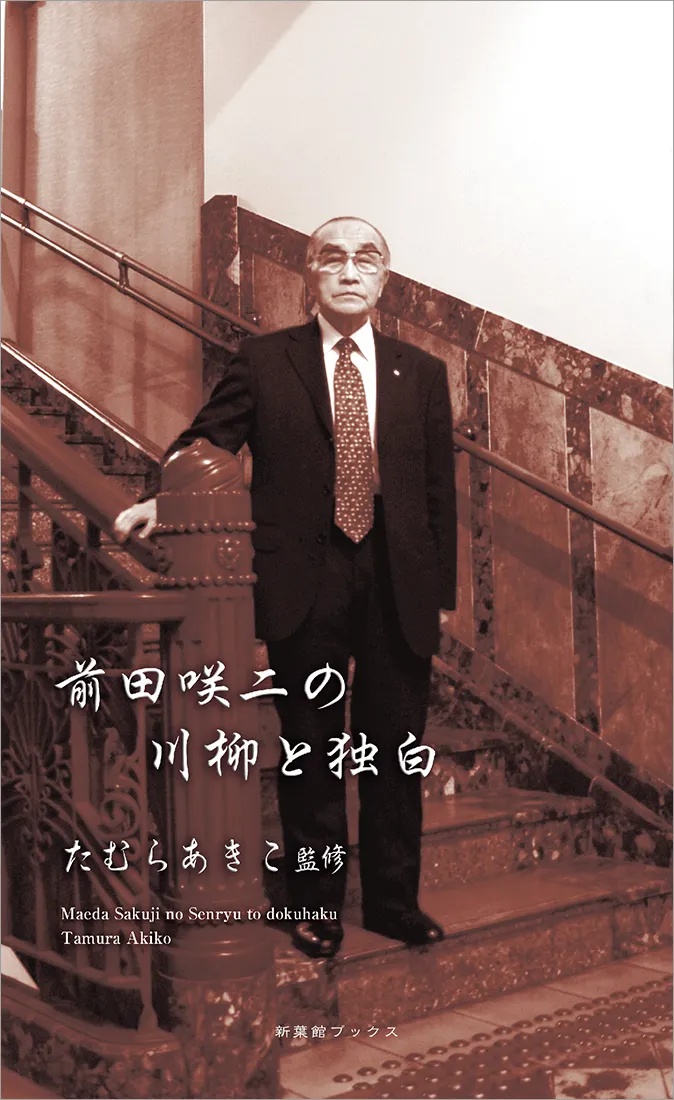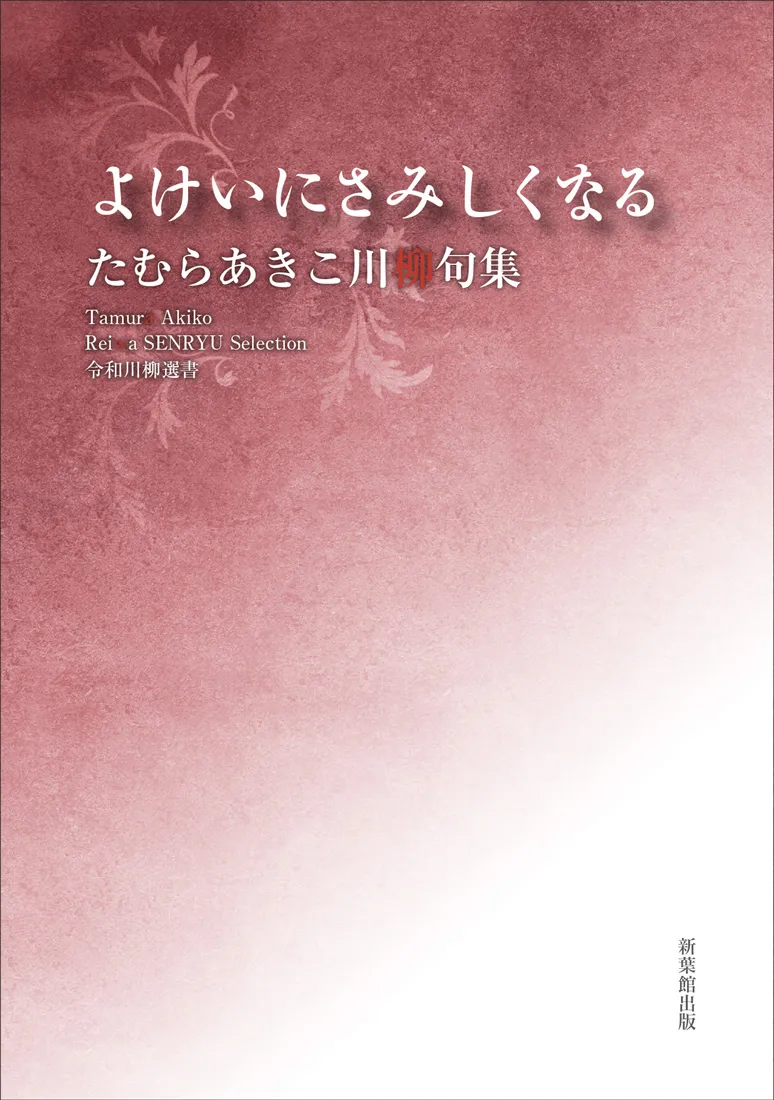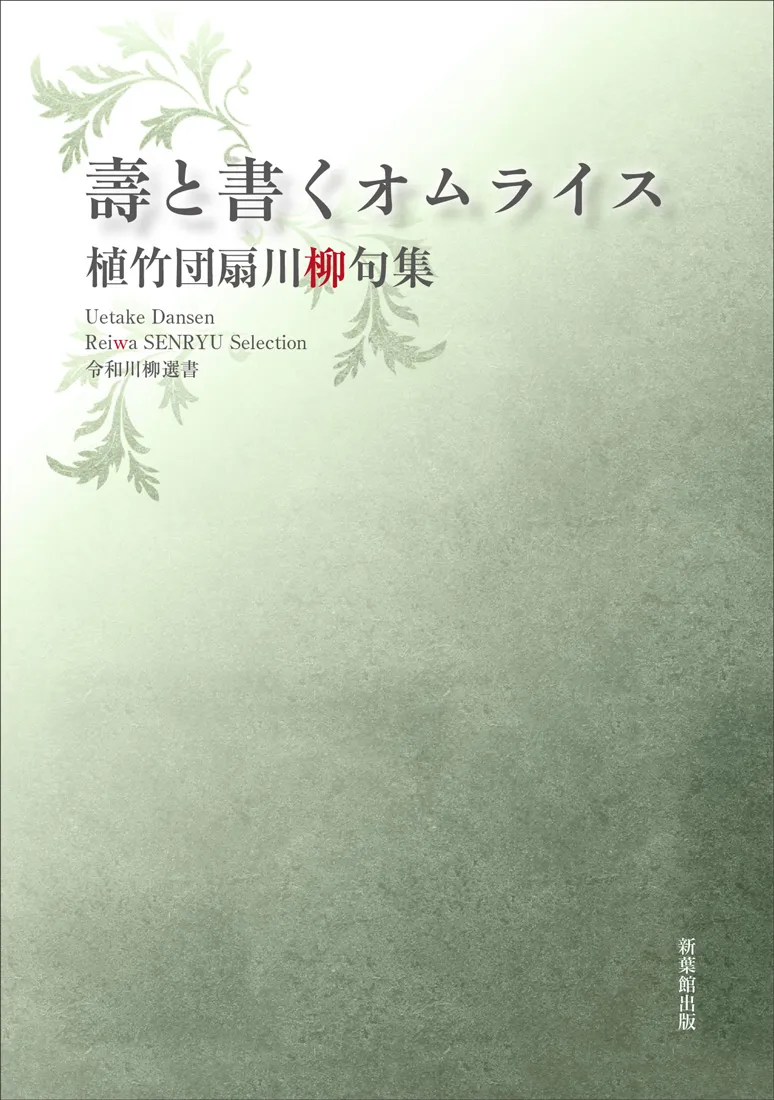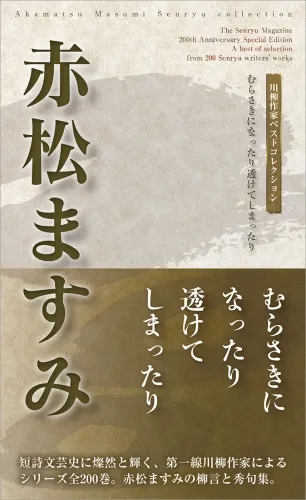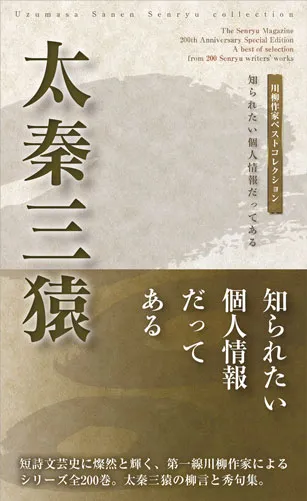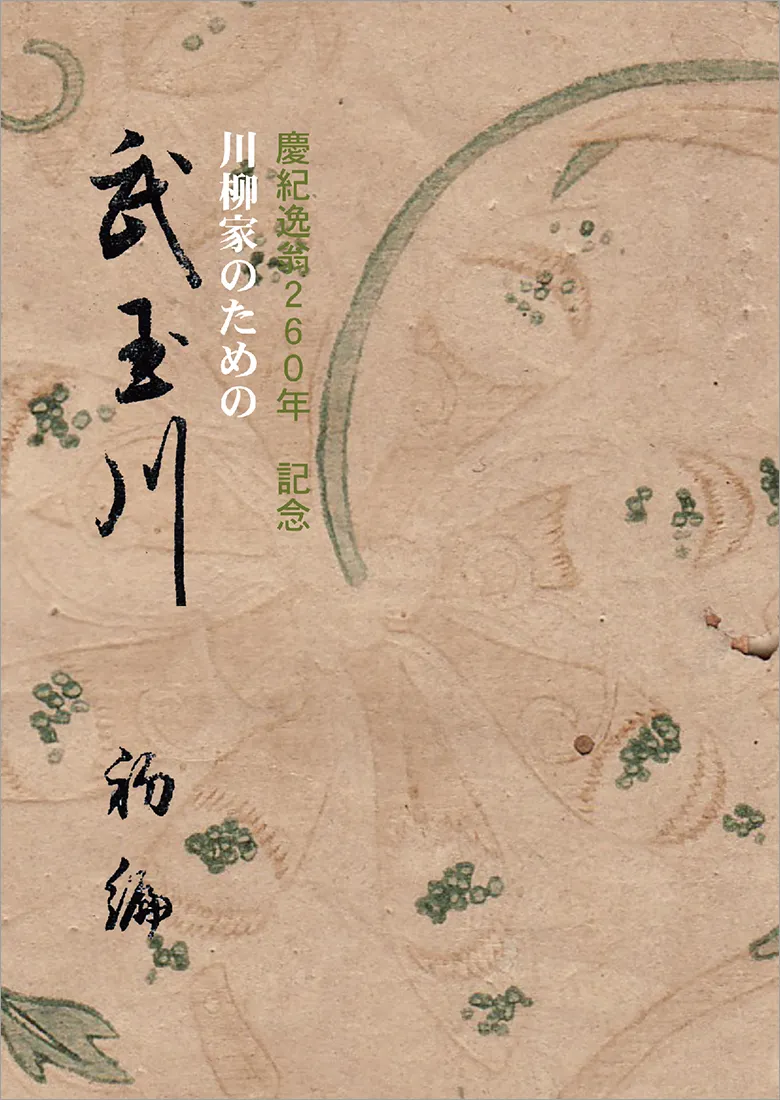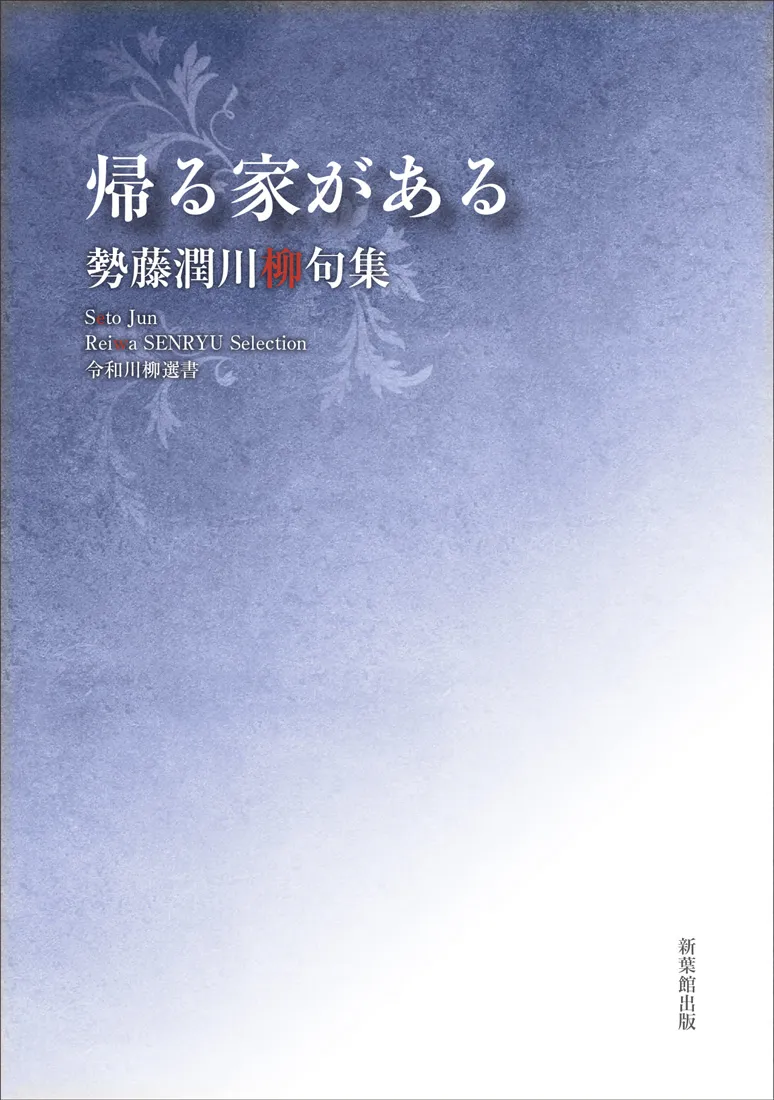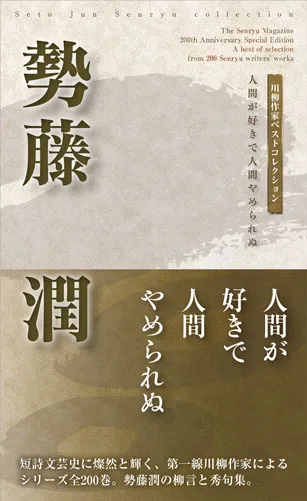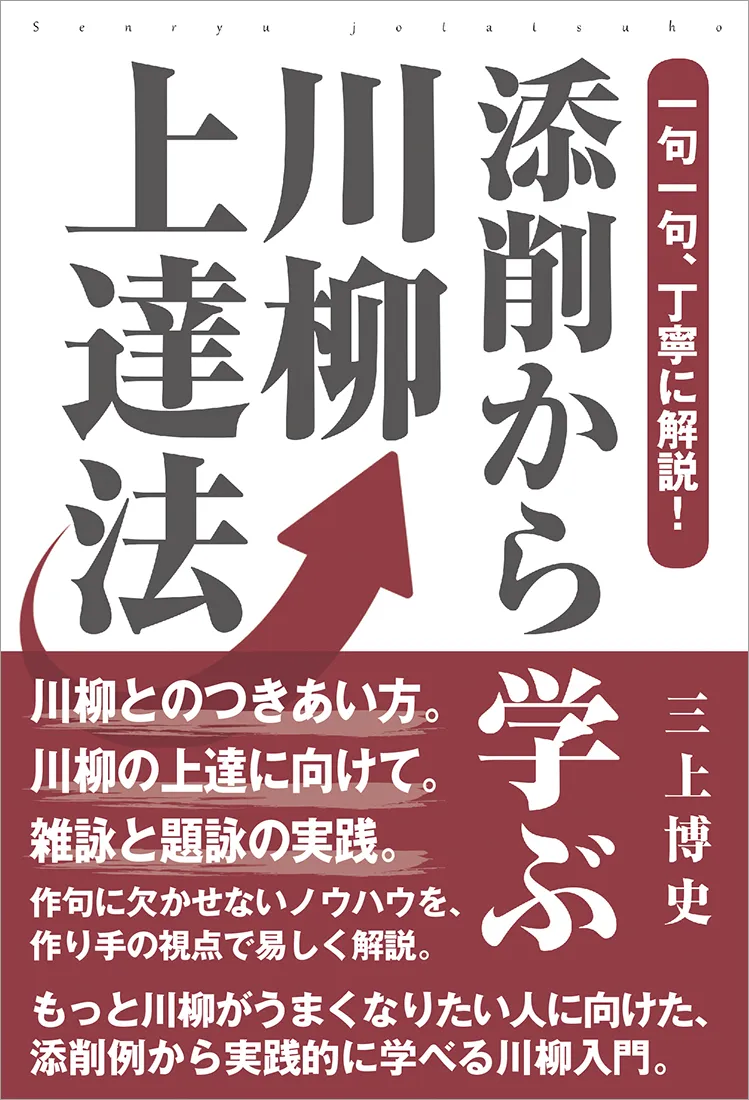学校の音楽室には独特の雰囲気がある。まだ小学生になる前のことだが、近くの小学校の誰もいない1階の音楽室に友達と入り込んだことがある。何かいたずらをしようとした訳ではない。壁に並べて貼られてあるクラシック音楽家の肖像画のモノクロ写真を窓越しに眺めていたら、いろいろな顔つきと表情に対して子供ながら気になりだしたからである。丁寧に一枚一枚を順番に見ていき、西洋人の顔の不思議さに衝撃を受けたことは今も記憶に残っている。なおこの家宅侵入(?)は、一応学校関係者には見つからずに済んだ。
その後引っ越して別の小学校に入学し、さらに中学校へと進んだが、音楽家の肖像画には興味を持ち続けた。バロック音楽から始まりバッハにヘンデル、古典派の時代になるとハイドンやモーツァルト、さらにロマン派のショパンやワーグナーなど、名前を挙げればきりがない。もちろん険しい眉間のベートーベンも目立っていた。そして近代・現代へと続く。日本人は滝廉太郎の顔写真だけだったかもしれない。
これらの音楽家の顔つきに私なりの印象を持ったものだった。微笑んでいるような顔、深刻な表情、あえて横顔になっている人物。バロック・古典派時代の金髪をカールした髪型が地毛ではなく鬘(かつら)であることも後で判った。
音楽の授業ではLP盤に針を落としていろいろなクラシック音楽を聴かされたが、その曲の雰囲気と作曲者の肖像画のイメージがなかなか結び付かない。いや結び付く時も偶にある(正確に言えば勝手に自分が結び付けているだけなのだが…)。柔和に見える顔つきには弦楽合奏曲の穏やかな調べ、厳めしい表情には交響曲の轟くような響きが合致しているように思えた。後から振り返ればそれらはすべて私の頭の中の思い込みではあったが、そもそも子供心とはそんなものなのではないか。この中年のおじさんたちは何を考えてこんな表情を見せているか? そういうことにどうしても考えが及ぶのである。
音楽とは聴覚の世界なのに、それを聴く音楽室には独特の視覚的な雰囲気のイメージ世界が広がってインパクトを与えていた。私は手先が器用な方ではなかったので、楽器を奏でることは苦手な方である。しかし、クラシック音楽に対しては肖像画への興味に端を発して、中学生の頃からLPレコードの収集を地味にやっていた。地味だったのは周りの友だちに同じようなことをしている仲間がいなかったからである。楽器を扱うのは不器用だったが、レコードに針を落として一人聴くことは好きだった。また音楽の教科書についても、載っている楽譜を眺めて音楽記号を覚え、合唱や演奏のルールを勉強することは嫌いではなかった。何につけ理屈っぽかった私には、そういうパズルを解くようなことが少し得意だった記憶が残っている。
話題を少し変える。歴史に残る著名な人物の肖像画の中で、大きな眼を見開いた西郷隆盛のそれが、実はイタリアの画家キヨッソーネが西郷と一度も会っていないのに描き上げたものであるという話しは有名である。実際に似ているのかどうかは怪しいことだろう。しかし、西郷と言えばこの肖像画の写真が必ず使われる。広く伝わっていても、当人はその度に泉下で苦笑いしているかもしれない。
聖徳太子の肖像もかつてはお札になっていたので、そのイメージが強いが、ほんとにそんな顔だったのかはこれもかなり怪しい。聖徳太子二王子像という有名な絵があるが、よく見ると、ヘアスタイルこそ違えど、目元や鼻筋は太子と王子の3人ともかなり似通っている。これも泉下で3人が苦笑いしているかもしれない。
肖像画の「肖」の訓読みは「肖(あやか)る」「肖(かたど)る」「肖(に)る」などがあるが、実物に「あやかって」「かたどった」ものが結果的に「にて」いる場合もあるかもしれない。肖像とはそんな程度のものなのではないのか。
人間の心理として、人の名前を憶えればどうしてもその顔つきや人物像を想像してその存在をさらに具体化したい欲求に駆られる。そういう欲求に応えて、画家に肖像画を描かせることが仕事として成り立っていた。肖像画作成には、描いてもらいたいという当人の意向のほかに、こういう周囲の人間の心理も働いていたのではないだろうか。
そして、そこから浮かび上がって漂う印象がその人物のパーソナリティーにフィードバックされる。そういうプロセスを経て、その人物が伝説化されていく。
画像や映像がなかった時代は、人物像を具体化する際に言葉だけでは物足りないので、何とかさらに一歩踏み込んでイメージを形作りたかったのだろう。人類は遥か昔に誕生した時から顔を持っていたのだから、名前はなくても顔だけは知りたかったのだと私は推定している。顔の無い人間はいない。首の無い人間は不気味である。
 Loading...
Loading...