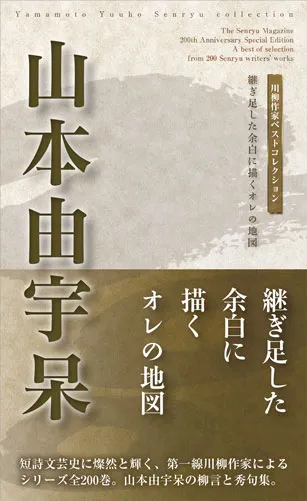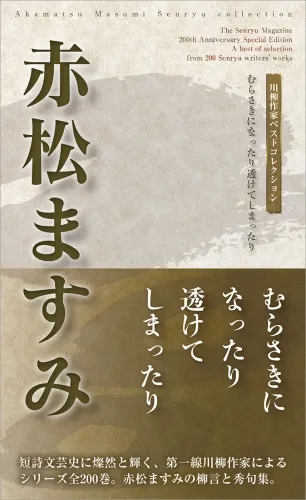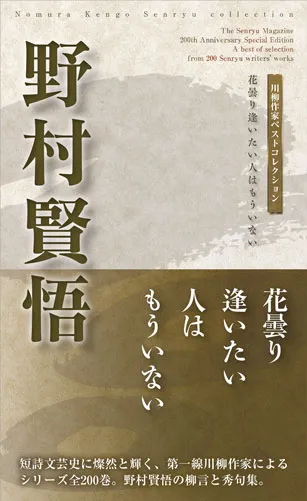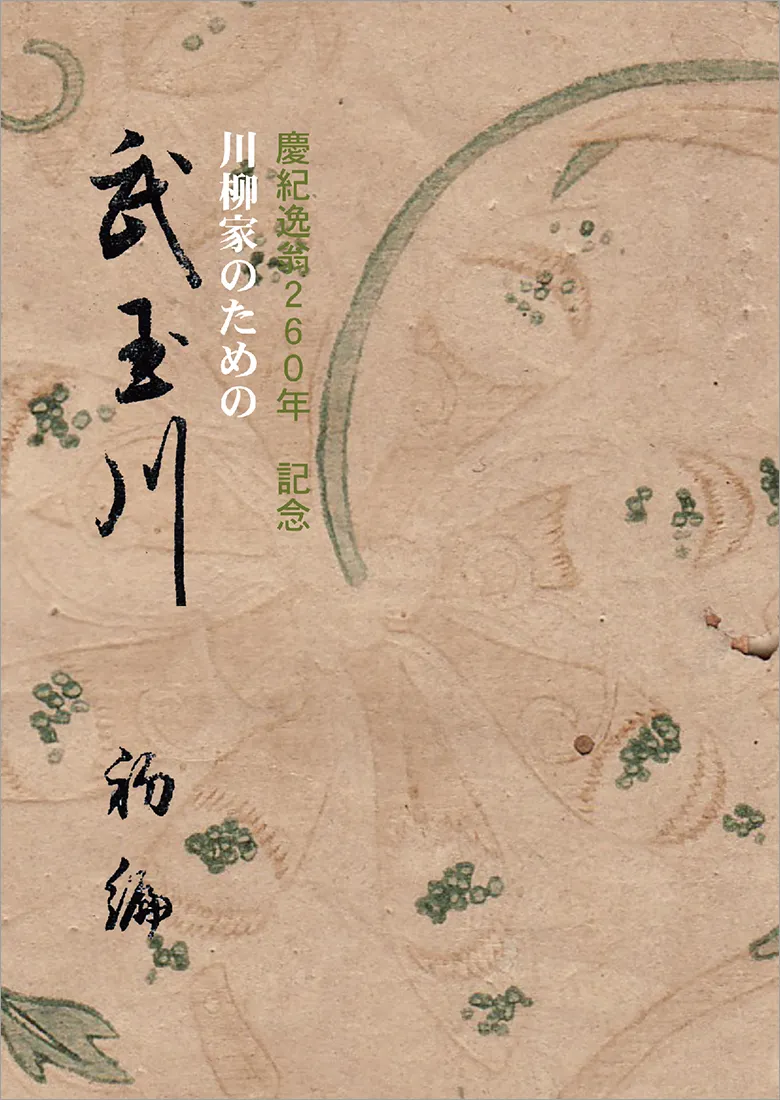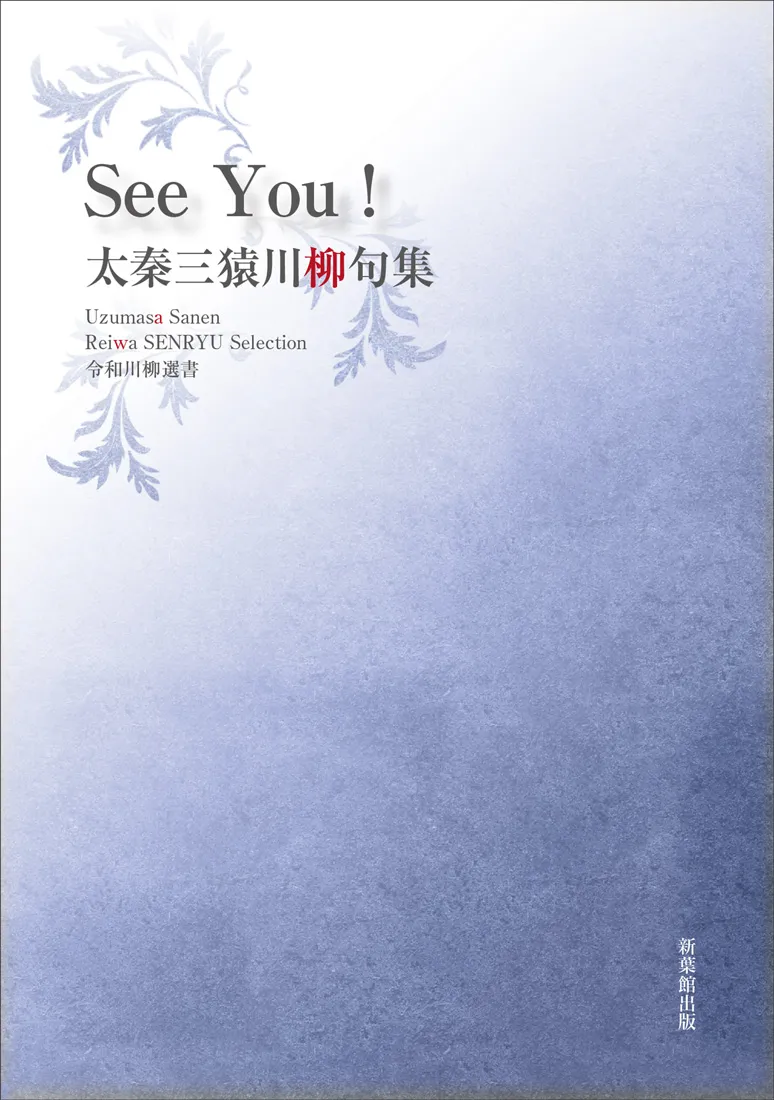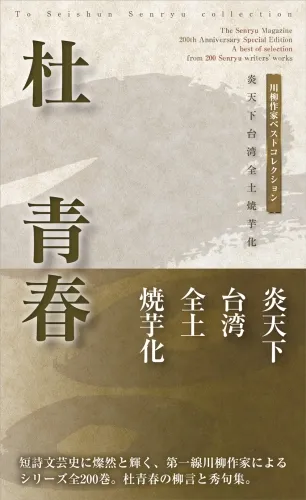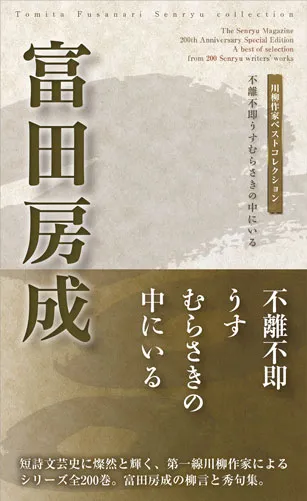高校生の頃、国語(現代国語)の教科書や大学入試の模擬試験に小林秀雄や江藤淳などの評論がよく出されていた。16、7歳の高校生には些か難しいところがある。正直に言えば、私の頭の中ではチンプンカンプンの時もあった。異次元の世界の話題にも思えた。とりあえず試験問題に出るから、そんな理由で晦渋な文章に向き合って何とか馴染もうと格闘していた記憶がある。
そんな中でも唐木順三の無常についての文章は、朧げながら今でも妙に印象が残っている。Wikipediaで無常を調べると、日本人の無常観に関してこんな記述に出くわした。
[「祇園精舎の鐘の声」で始まる軍記物語『平家物語』、西行の「願はくは花の下にて春死なん その如月の望月の頃」に代表される散りゆく桜と人生の儚さ、卜部兼好の随筆『徒然草』、「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」で始まる鴨長明の『方丈記』など、仏教的無常観を抜きに日本の中世文学を語ることはできない。単に「花」と言えば桜を指し、今なお日本人が桜を愛してやまないのは、その美しく儚き散り際に常なき様、万物は流転すること、すなわち無常を感じるからとされる。「永遠なるもの」を追求し、そこに美を感じ取る西洋人の姿勢に対し、日本人の多くは移ろいゆくものにこそ美を感じる傾向を根強く持っているとされる。「無常」「無常観」は、中世以来長い間培ってきた日本人の美意識の特徴の一つと言ってよかろう。]
いまさら唐木順三の著作を読む気にはならないが、人生のターミナルに向けて齢を重ねている現在、「無常」という言葉が心の中で通奏低音ように響く時がある。若い時分は、失望感や喪失感などの経験を通じて「無情」を感じたものだったが、老いてくると「無情」に対してはいくらか悟りの境地みたいなものを抱くようになる。代わりに「無常」が脳裡にしばしば浮かぶようになってくる。
人生を折り返してから久しくなると、耳に入ってくる「むじょう」の響きが変わる。「無情」から「無常」へとパラダイムシフトがなされるようだ。動詞的な世界観において、「do動詞」(他動詞・何事も行動して道を拓く世界)から「be動詞」(自動詞・なるようにしかならない道を歩む世界)へと変容する。老いてくれば、行動範囲が狭まっていろいろな制約を受けるのだから仕方がない。そう観念すると、何事でも寛容になってくる。若者に対抗しても勝ち目はない。もし勝とうとするなら別の切り口で攻める他はない。いや、勝とうとする、攻め込もうとする発想がそもそも野暮ったく思えてくる。かつて流行語となった「老人力」も一つの道具的概念として、改めて身近なものになってくるようである。
 Loading...
Loading...