タイトルに出した前田雀郎のこの句は、栃木県内の川柳愛好者の間では広く知られているものである。私も雀郎作品の中では好きな句の一つになっている。
私の住居遍歴について言えば、小学校入学の頃(昭和38年)に父親が初めて家を新築してそれまでの粗末な生家(六畳間と四畳半の二間程度)から引っ越した。新築した家に暮らし始めてしばらくすると、この句に似た感覚、更にもう一間欲しいという願望が家族4人(父母と姉と私)の間でも湧き起ってきた。中学生ぐらいになるとそれがさらに現実的になり、結局は増築することになった。私の家の住環境は、そういう意味では恵まれた方だったのかもしれない。
昭和30年代、40年代ぐらいまでは日本の住宅事情はあまりよくなく、この句のような思いを抱きながら生活し続けている人が多かったのではないか。借家だけでなく持ち家でも、もう一間欲しいと思いながら暮らし続ける。そしてそんな不満を抱きながら齢を重ね老いていく。人生とはそういうものなのだなぁ、と振り返ってしみじみ実感するのではないか。
さて私の場合その家に今も住んでいるのだが、今では老母との二人暮らし。部屋が余っている状態になってしまった。姉は高校を卒業して早々に家を出た。それからだいぶ経って親父が亡くなった。平成生まれの娘が嫁に行き、使われなくなった娘の部屋は次第に物置みたくなっていった。
こういったことも我が家だけの話しではなく、他所でもそんなふうになっているようだ。2階へ上がるのが億劫になり、あまり出入りしない部屋はいつの間にか埃っぽくなっていく。一生に一間足りないではなく、一生に一間も二間も余ってしまう家に住むのが今風の住宅事情なのだろう。余った部屋に下宿人や居候を住まわせて有効活用するなどという発想は、昭和時代のことである。
空き家問題がいろいろな所で言われている。確かにそのとおりである。街中を散歩していると、何処かで必ず空き家を目にする。その一方でモダンな賃貸用集合住宅はまだあちこちで建てられている。道を歩けば空き家を見つけるご時世に、資産運用のための新築アパートの数はなおも増えている訳である。家族生活の形態がどんどん変化して、子供が社会人になれば親とはもう同居しないのが当たり前になって来た。一人暮らしの淋しさよりその気楽さを選ぶ時代なのである。雀郎が句を詠んだ時代とは隔世の感がある。
齢を重ねても、それなりの夢や希望を持ち続けることは決して悪いことではない。しかし、今の世の中はやる気になれば何でも叶えられる自由と平等は与えられているところがある。だから、そのために例えば本気で家を建てようとするなら、先のことを見通して本当に満足する間取りを考える。始めから一間足りないと感じるような家を建てることなどはしない。
しかしいずれ子供が巣立っていって、部屋が余ることにまでにはなかなか思いが及ばない。そして、自分が死んでも家を引き継ぐ者がいないだろうという予想も立てたがらない。自分が死んだら速やかに処分されるような家を誰が設計できるだろうか。そんなことを想定できる現実的な感覚を持てる人はなかなかいないだろう。
私は衣食住にあまり興味がない方なので、当然今住んでいる家にも執着はない。私がこの世からいなくなったら処分される訳だから、住み続ける限りカネのかかるリフォームなどはほとんど考えていない。
これから日本は空き家社会がどんどん進行していく。廃屋を始末できないまま無惨に放っておくのは、誠に忍びないことである。終活の中で、自宅の取り扱いは盲点のようでもあり、先々のことはある程度は想定していても、だからと言ってなかなか積極的に動こうとはしない、したがらないのではないか。だから空き家はこれからも着実に増えていく訳である。
 Loading...
Loading...











































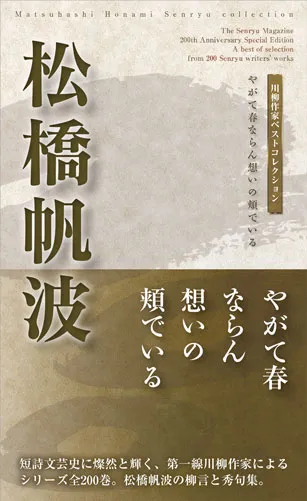
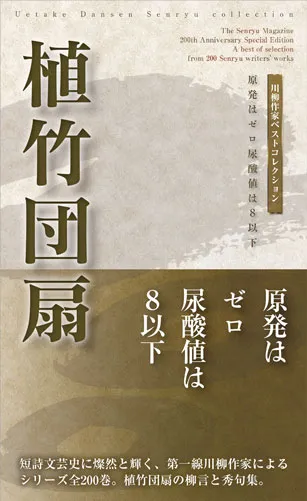
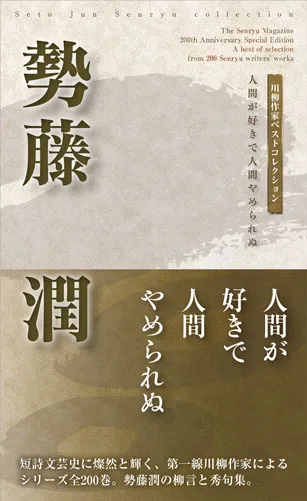
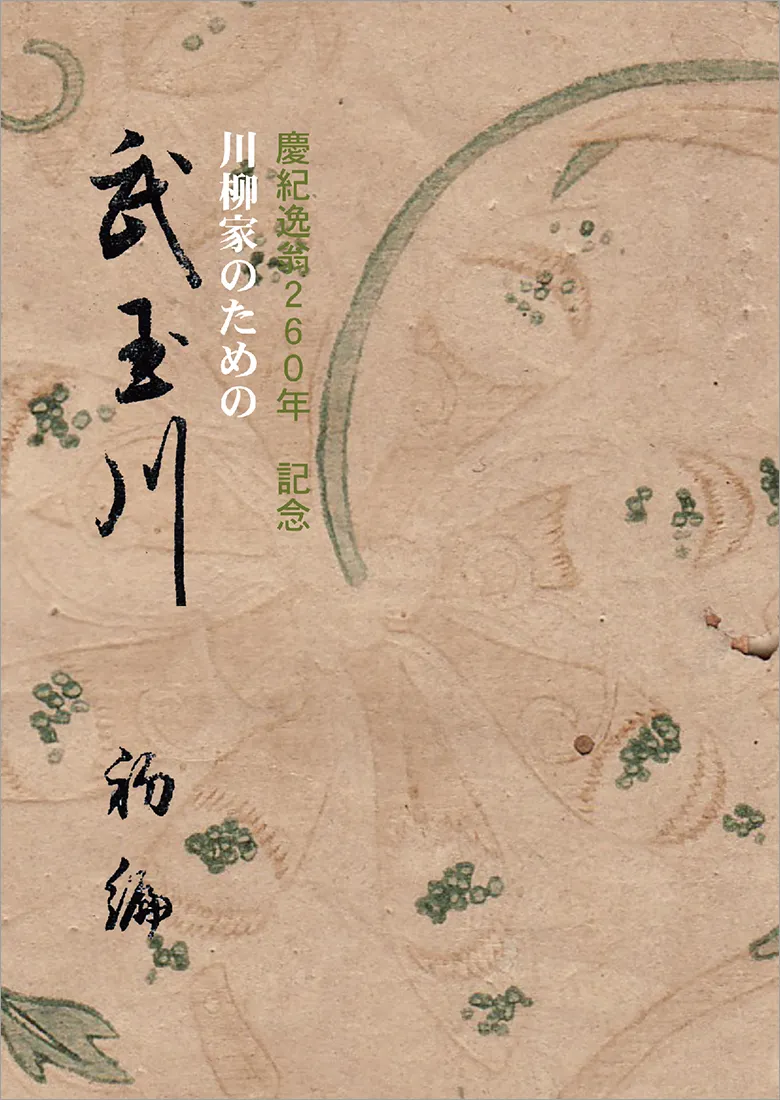
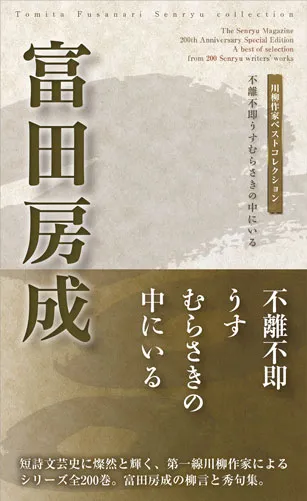
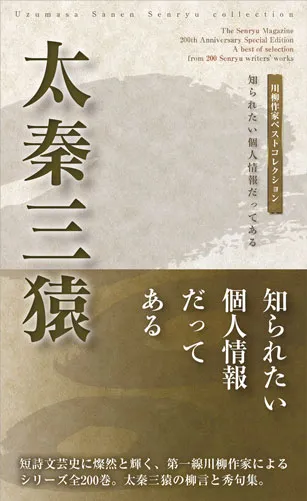
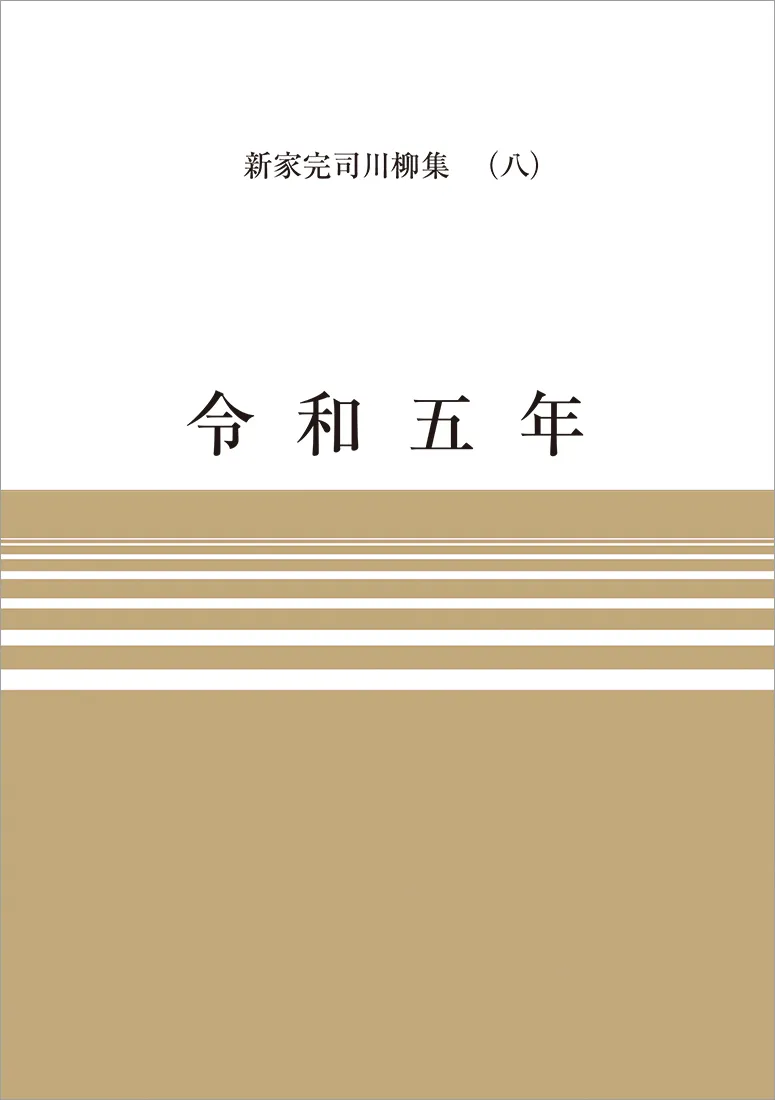
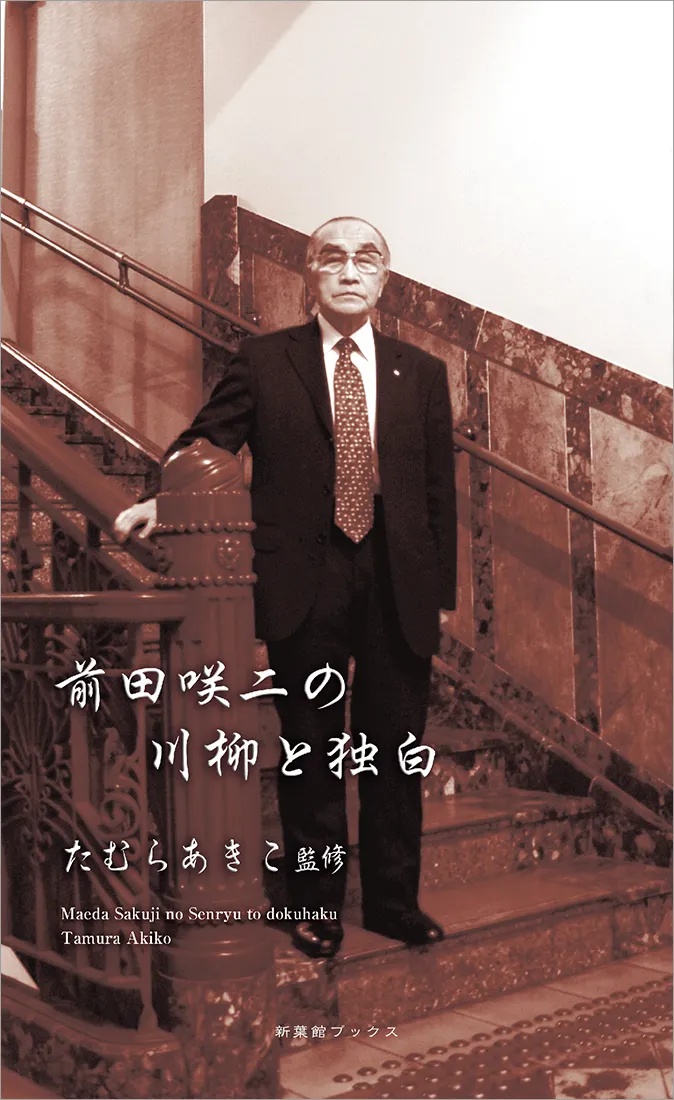
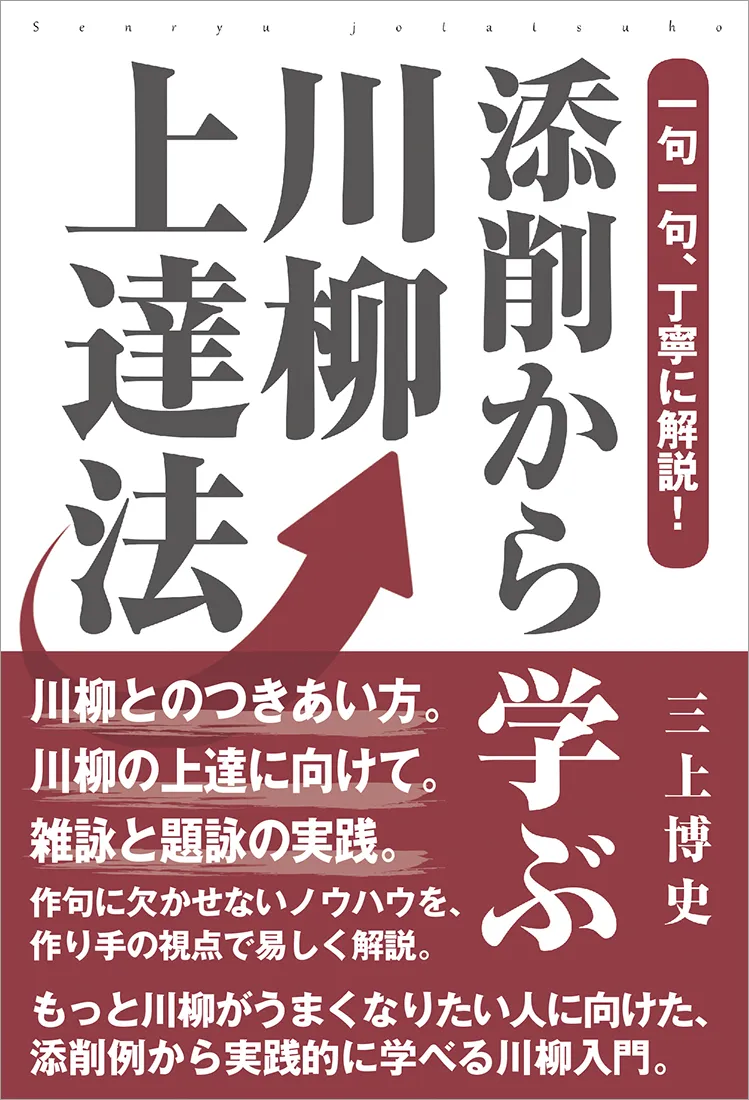
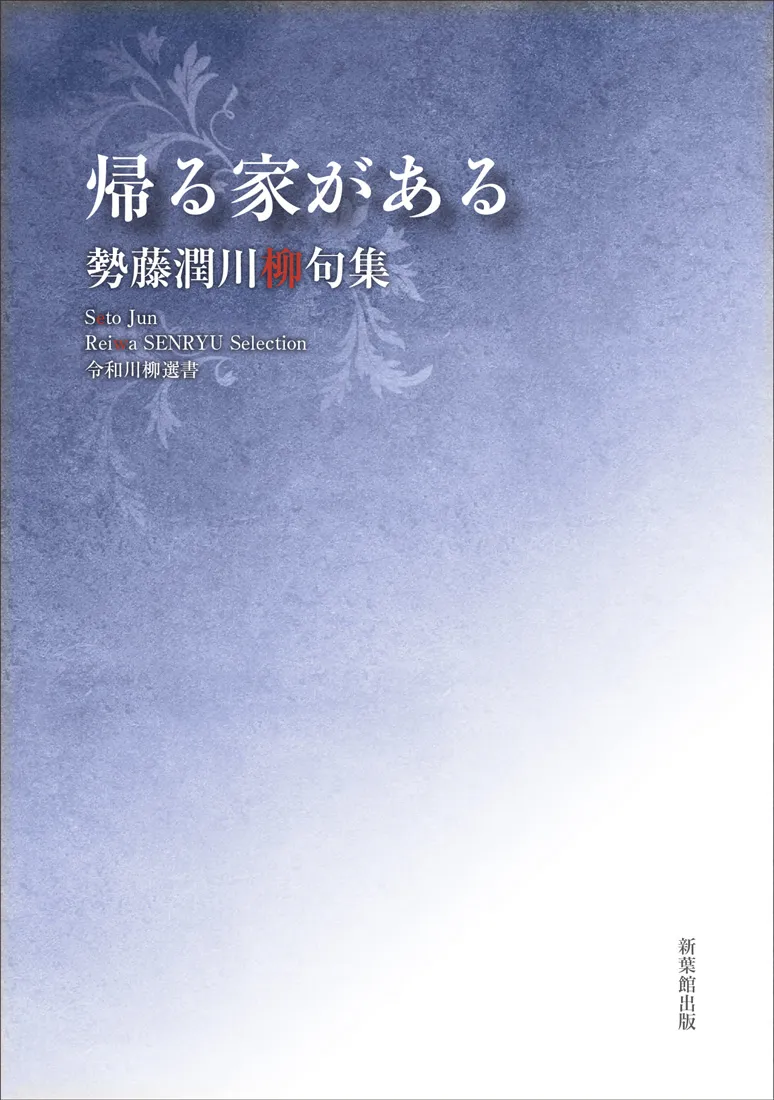




「一生を」、「を」だったともいますが。用件のみにて。
哲男さん、ご指摘ありがとうございます。そのとおりです。訂正いたしました。