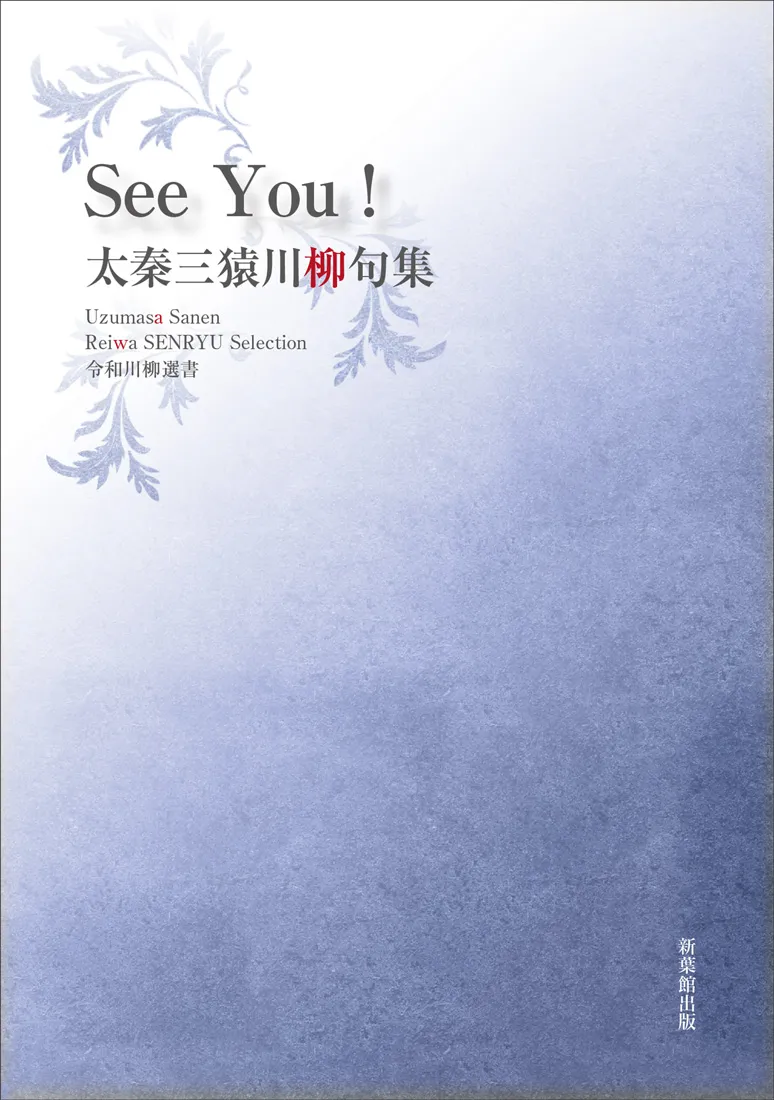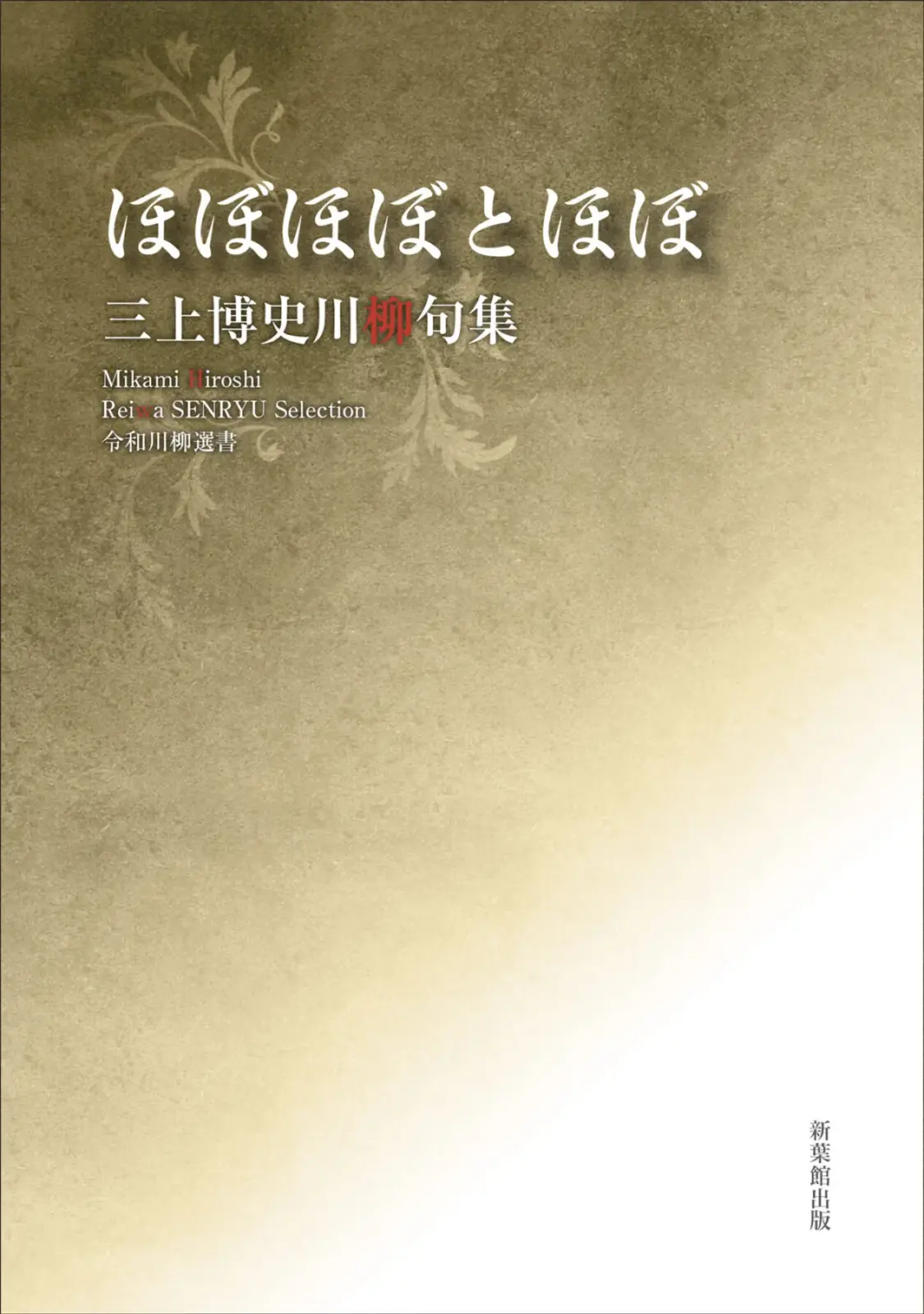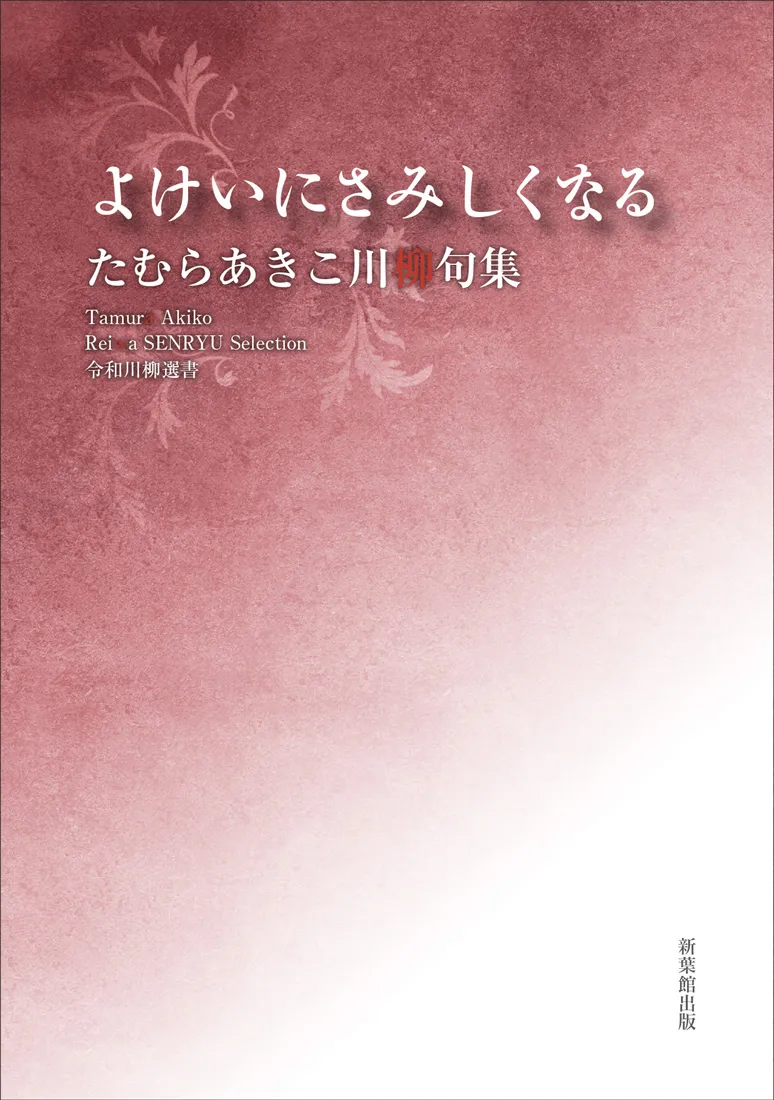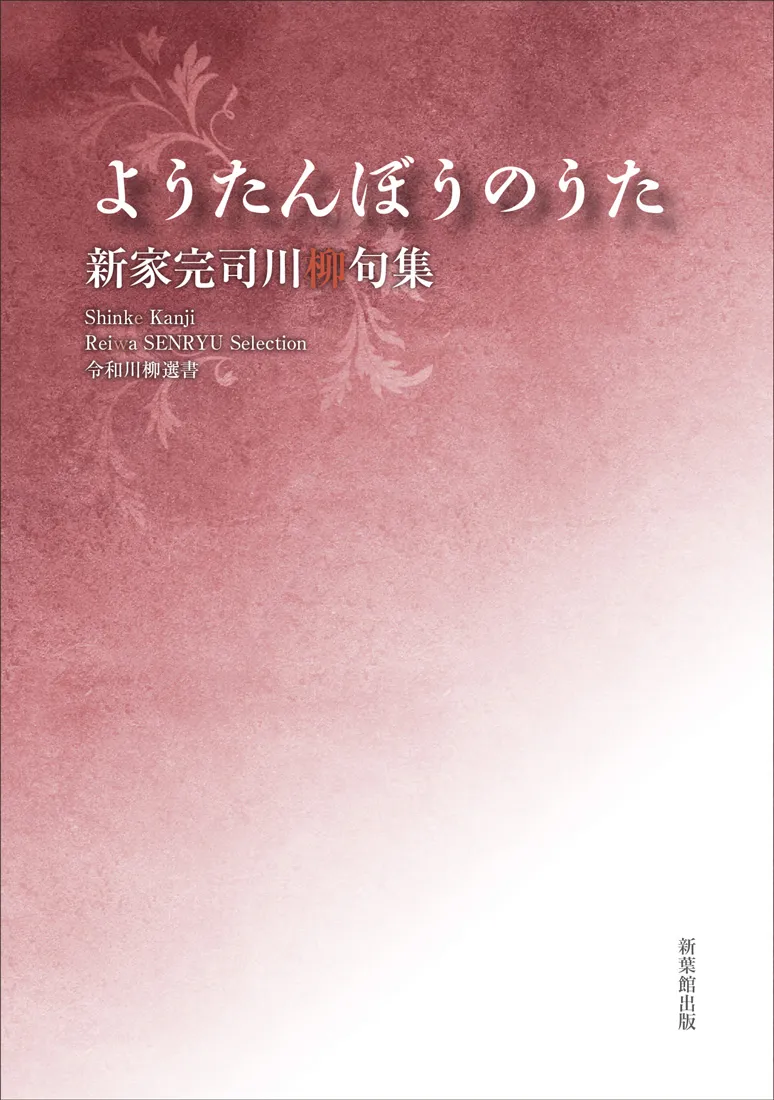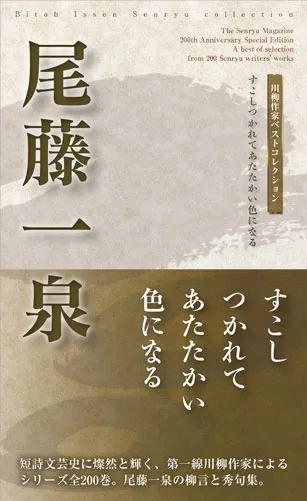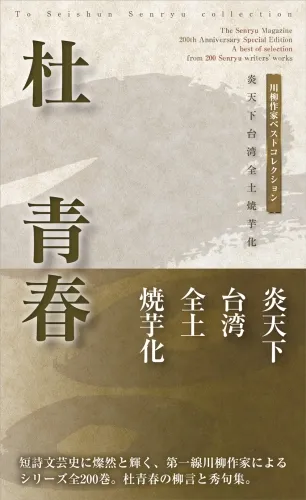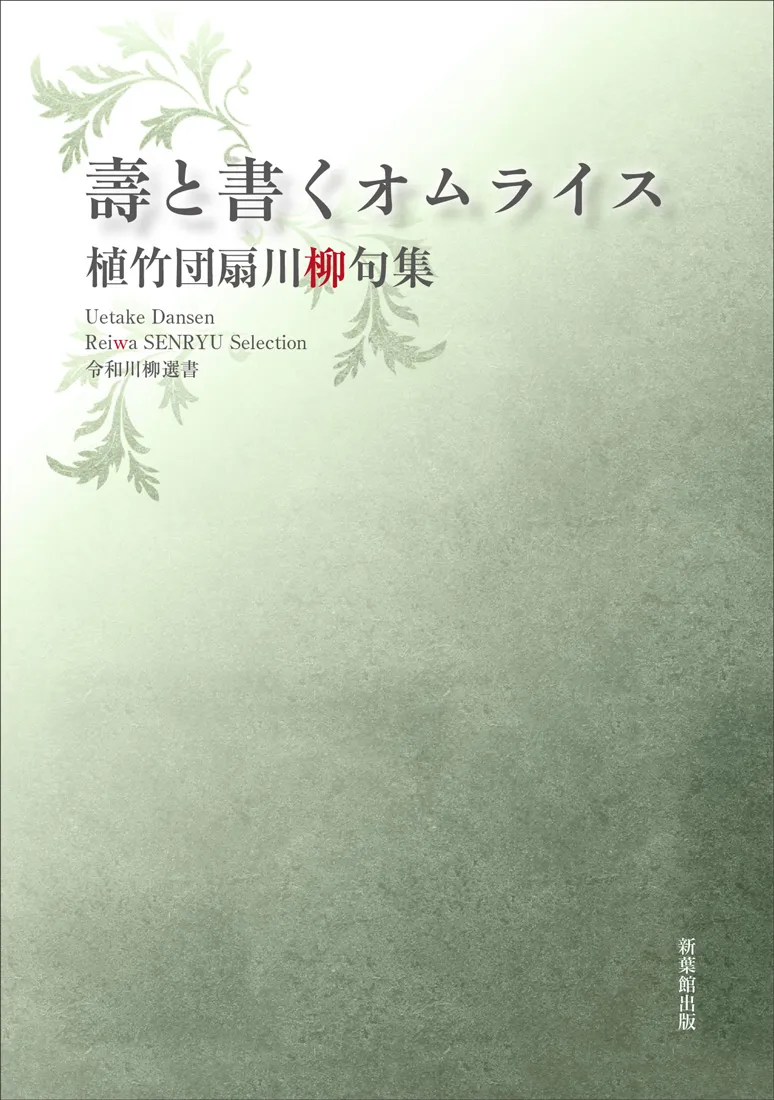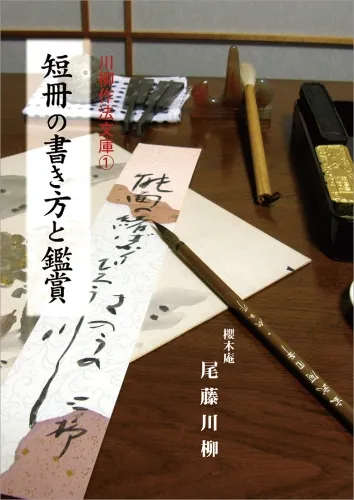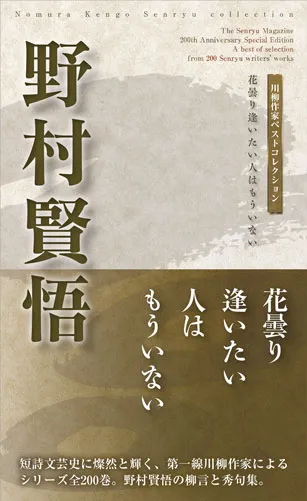先日、私と同世代の元川柳仲間から、自作を収めて上梓した歌集が送られて来た。彼とはお互い遠く離れて住んでいるが、10数年前、東京で開かれたある川柳大会でたまたま知り合った。当時二人とも年齢が50代前半でほぼ同じ(おそらく昭和30年以降の生まれ)。話しをしているうちに息が合って、その後、双方の住まいからの中間地点である東京までそれぞれが出向いて居酒屋などで落ち合い、何度か飲んだことがあった。柳壇の長老支配の実態を愚痴ったり嘆いたりして、二人だけだが大いに盛り上がったものだった。
その頃から既に、そろそろ川柳をやめて短歌に転向するようなことを彼は話していた。短歌をやっていたお母さんの影響もあったのだろう。短歌から川柳へ転向する人は結構多い。かの時実新子もそうだったし、私の地元の川柳仲間にも元は短歌を詠んでいたという方は何人もいる。しかし川柳から短歌へ移ったというケースはあまり例がないのではないか。
さていただいた歌集を早速読み始めてみると、川柳をやめて私と会わなくなってからの10数年の間に詠まれた作品を時系列に並べている。新聞の全国紙の歌壇に入選したものや所属結社の歌誌に載ったものを中心にまとめたようである。
具体的には平成23年3月の東日本大震災の頃に詠んだ作品から始まっている。50代の半ばだろうか。それから60代半ばの現在に至るまでのものが日々の生活を通して素直に詠まれている。読み進めていくと、母親との二人暮らし(おそらく当人は独身だったのだろう)であること、その母親が病に倒れ、看病・介護を続けていた経過が日記を綴っているかのように判ってくる。親子の情愛がひしひしと伝わってくる。そういえば、二人で飲んだ時にもお母さんのことはよく話していたなぁ、と急に思い出した。
読み終えて気づいたのだが、おそらくいろいろあったはずであろう二人暮らしの家庭内の葛藤があまり感じられないことだった。看病や介護をやっていく過程でいろいろなことが起きて、時には大変な思いも経験したことであろう。決して母と息子の良好な関係だけで生活していただけではないはずだ。ところが、親子関係の苦しみやもがきが作品から出てきていない。母親に対して時にはアンビバレントな感情が湧いたこともあっただろうに、それが歌には表わされていない。読後感として、そういうことも滲ませた歌を少しでも詠んでもらいたかった。
石川啄木は、母親のことをいろいろ短歌に詠んだが、実際の親子関係は決して綺麗事では済まなかったことがよく知られている。嫁姑の関係にも辟易していたらしい。そういうリアリティーは作品の中ではすべて捨象されている。それも一つのスタイルなのだろうが、虚構はいつか必ず判明する。作品そのものの評価とは別だとは分かっていても、その印象は一度知ったら拭い去ることは出来ない。
元川柳仲間の短歌作品にも、啄木などとは違う、どろっとした裏の側面も正直に詠み上げてもらいたかった。個人的にはそこはもの足りなく感じた。もちろん一つひとつの作品には短歌としての詩情がうまく描かれていることは確かであり、素直に感銘を受けた。
私が現在一緒に暮らしている老母のことを川柳に詠むなら、必ずそういった葛藤や苦悩を入れ込むだろう。光と影、表と裏の世界、そういった二面性の厚みと深みを詠み込まないと気が済まないのが私の川柳作家としての性分なのである。ただし、直接的な言い回しは使わないだろう。葛藤や苦悩が時間をかけて熟されてから、ぽろっと五七五に吐く。自分の思いが句に昇華されたとまでは言わないが、少なくとも心がいくらか浄化されることだろう。親子関係のことを詠んだ作品だと読み手にうまく伝わらなくてもいい。自分の心情に対して素直に向き合えただけでもいい。そういう作句姿勢が私なのである。
 Loading...
Loading...