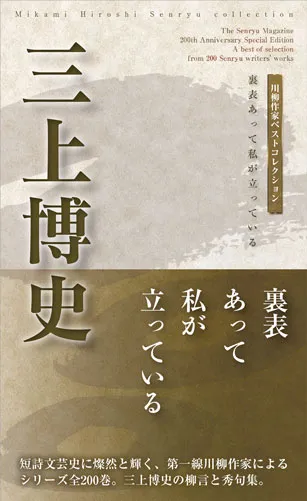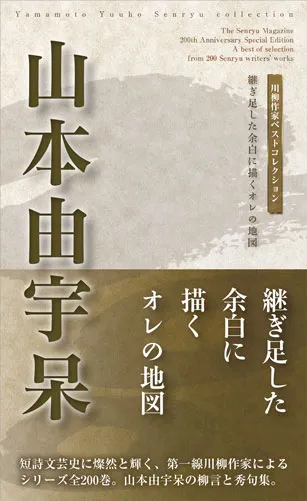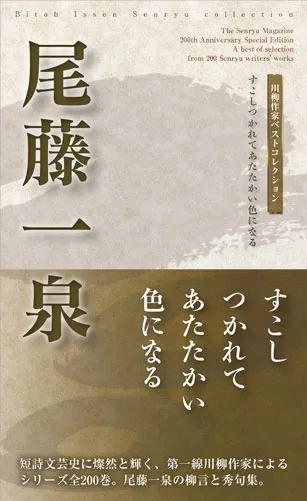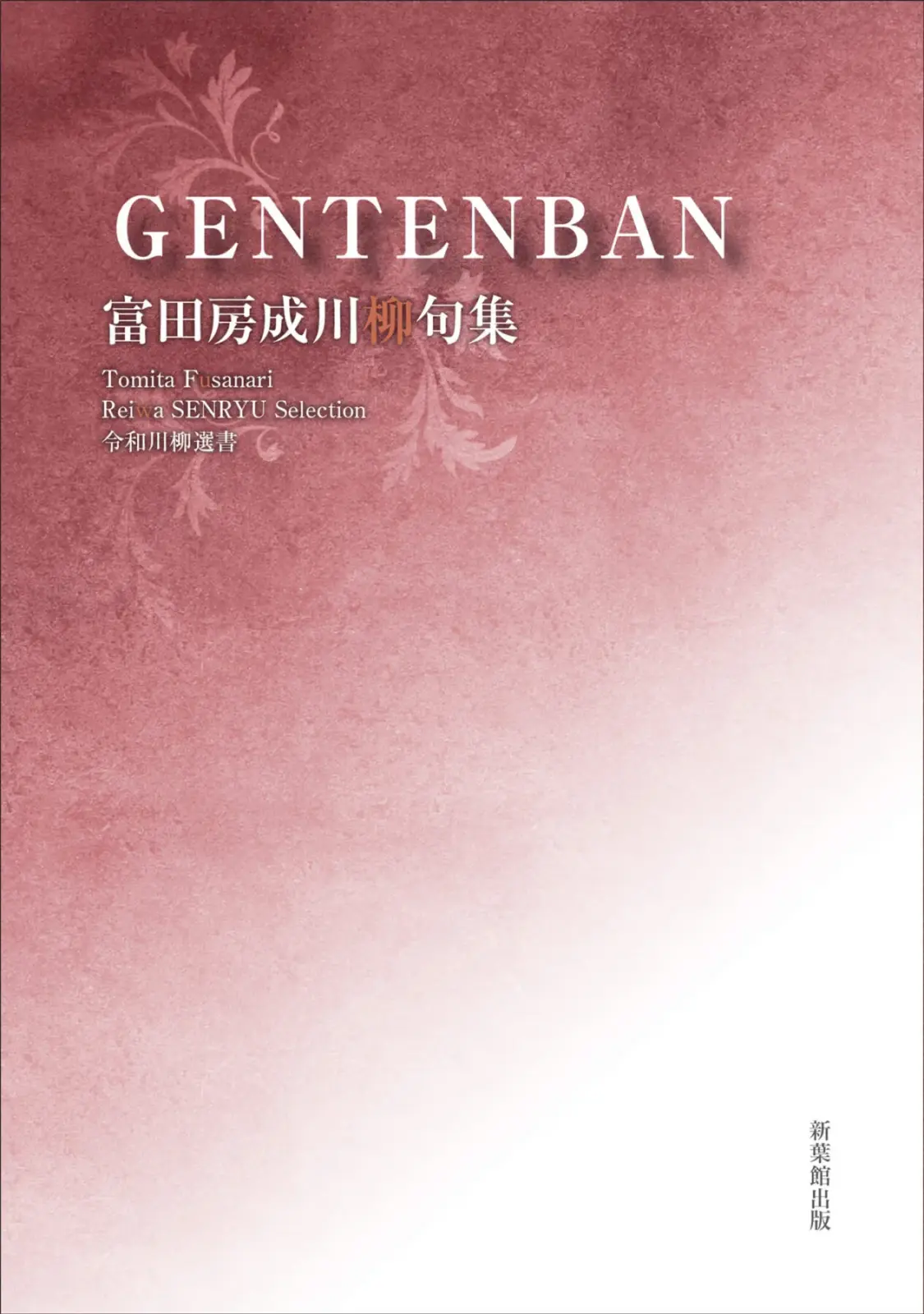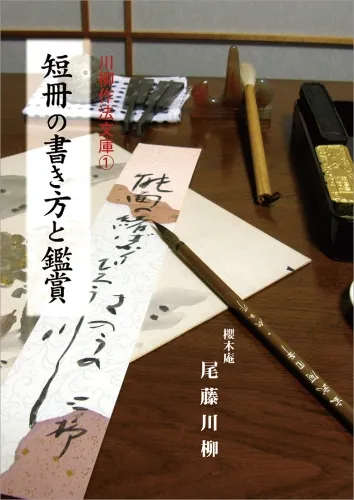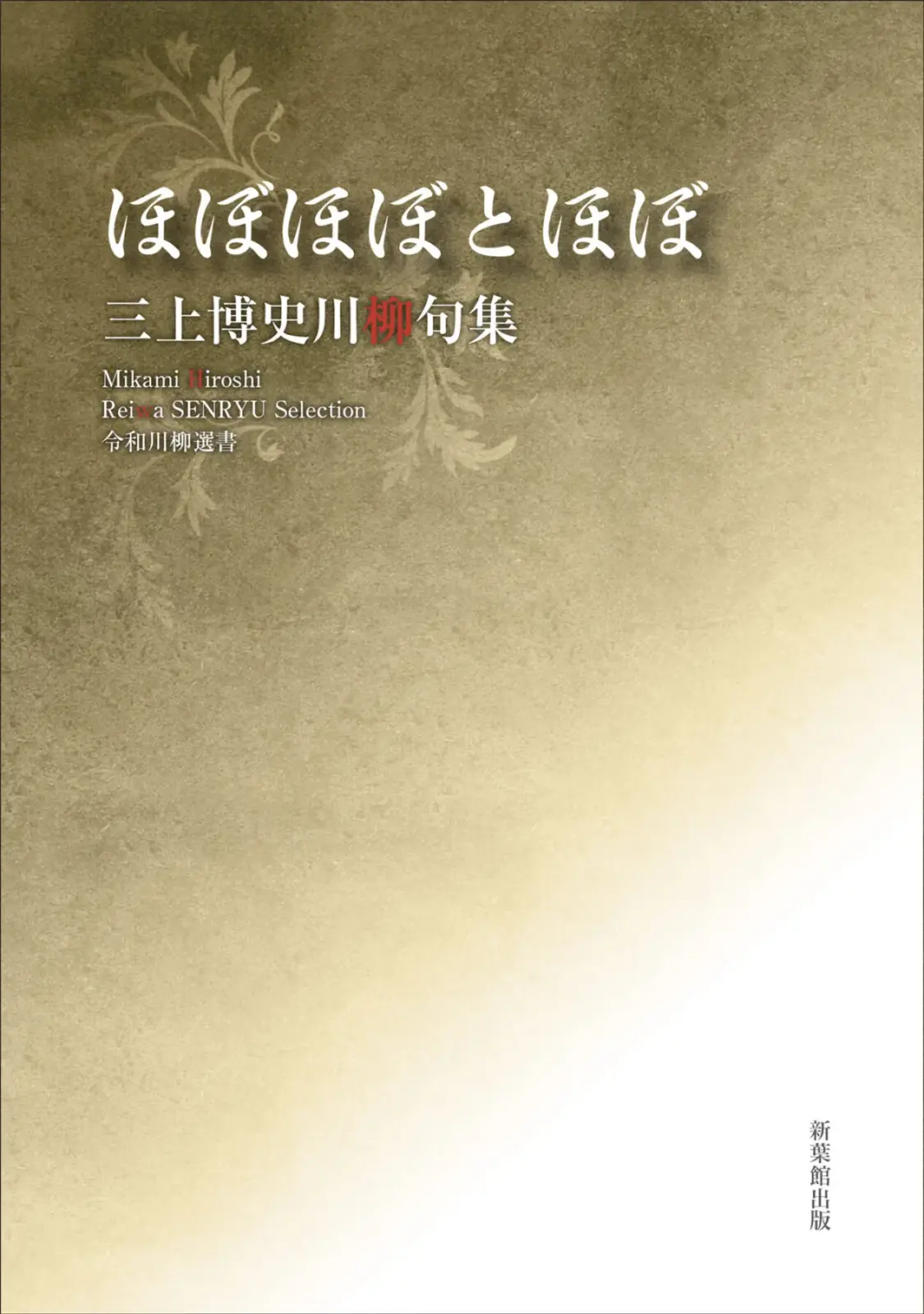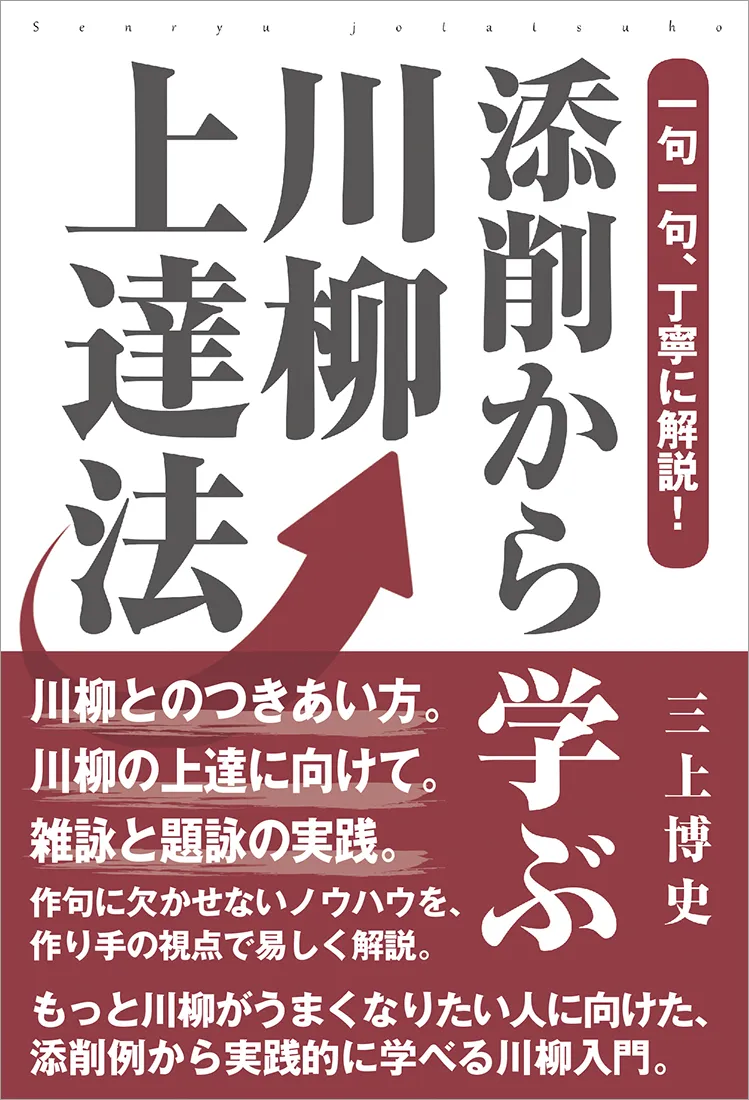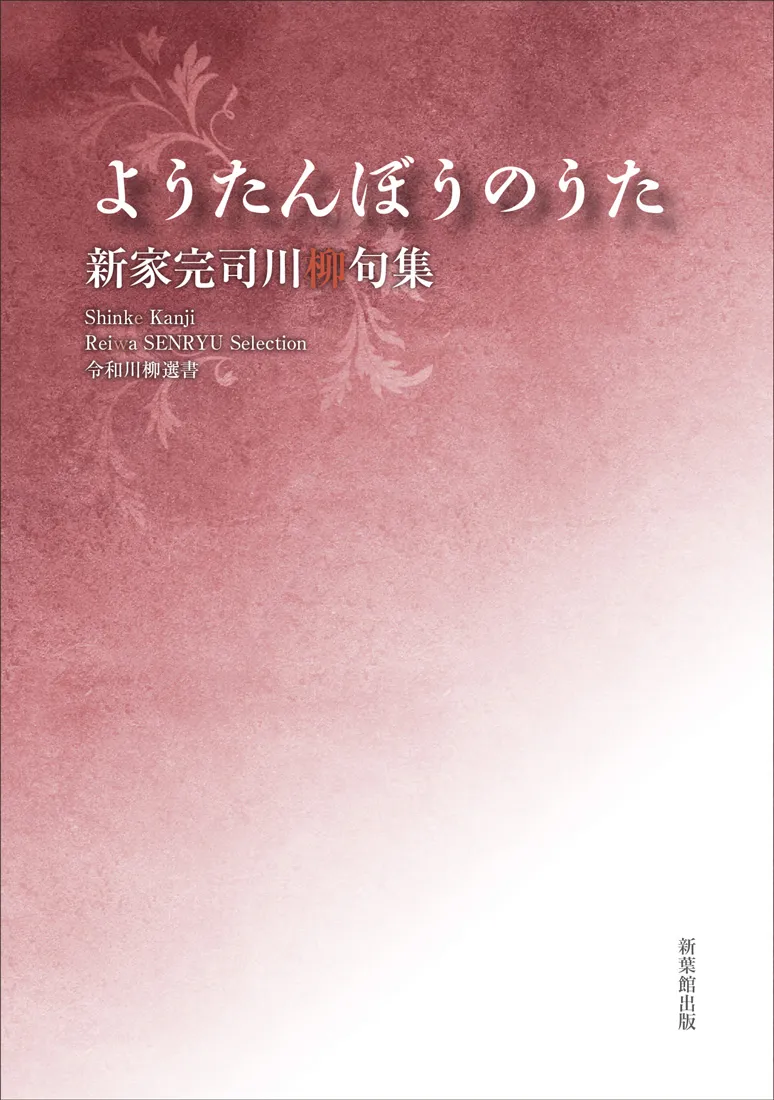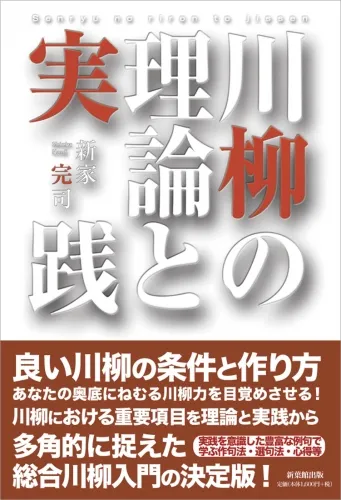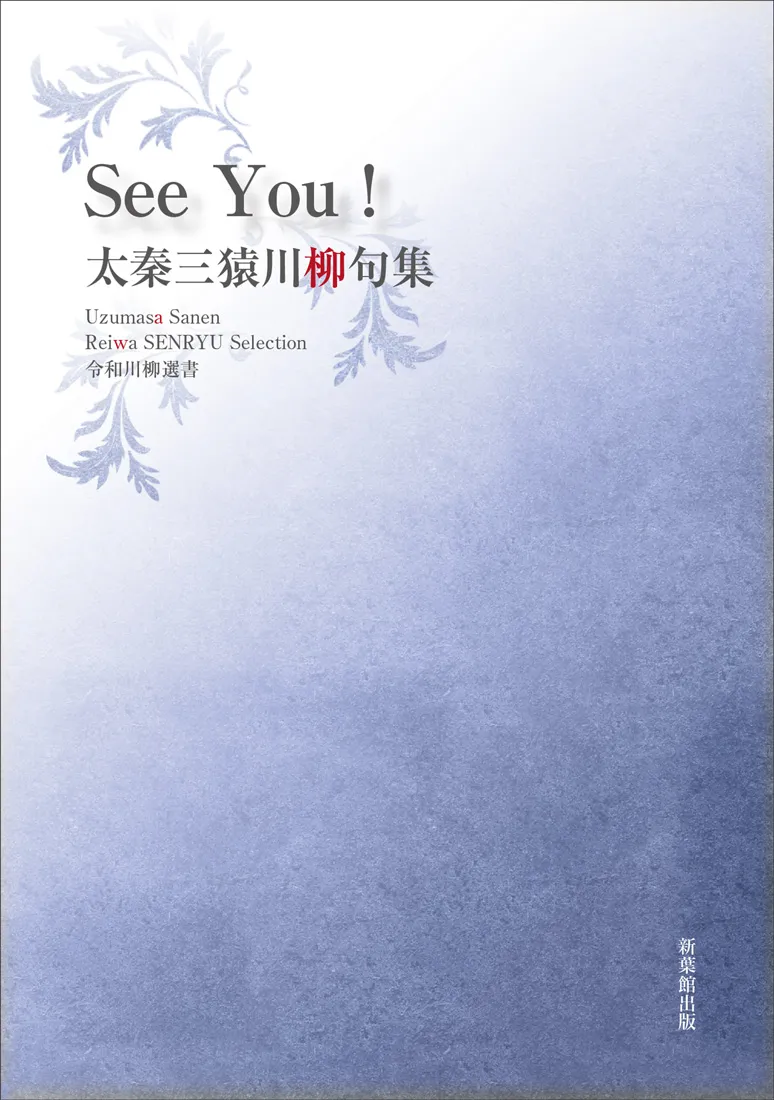月2回ほど通っているコーラスサークルで、以前「サボテンの花」(1975年・作詞作曲:財津和夫)を練習したことがあった。
歌詞を読みながら繰り返し歌ってみると、男の身勝手さが随所に表れていることに気づく。典型的な昭和歌謡なのだと改めて思い知った。
ほんの小さな出来事に 愛は傷ついて
君は部屋をとびだした 真冬の空の下に
編みかけていた手袋と 洗いかけの洗たくもの
シャボンの泡がゆれていた
君の香りがゆれてた
たえまなく降りそそぐこの雪のように
君を愛せばよかった
窓に降りそそぐこの雪のように
二人の愛は流れた
想い出つまったこの部屋を 僕もでてゆこう
ドアに鍵をおろした時 なぜか涙がこぼれた
君が育てたサボテンは 小さな花をつくった
春はもうすぐそこまで
恋は今終った
この永い冬が終るまでに
何かをみつけて生きよう
何かを信じて生きてゆこう
この冬が終るまで
この長い冬がおわるまでに
何かをみつけて生きよう
何かを信じて生きてゆこう
この冬がおわるまで
ラララララ…
ほんの小さな出来事に傷ついて女が部屋を出ていく。これは男にとって突然の出来事のように思えたかもしれないが、些細なことは一つのきっかけに過ぎない。突然というより部屋をとびだす必然性は、女の心の中でスタンバイになっていたのだろう。そのように解釈することが心理学的には妥当である。要するに男の身勝手に対して不満が溜まっていた訳である。世の中には突然の事など何一つない。すべての物事は必然の連鎖(原因と結果)によって起こる。突然と必然の違いは認識(予期)していたかどうかだけである。この歌の場合、なるようにして(なるべくして)なった別れなのである。
降りそそぐ雪のように愛していればこの別れは回避できたと、自分なりに総括するように言っているが、それに続いて、二人の愛は流れたと、客観的に描写しようとしたところは些か責任回避的な印象を与える。まるでお互いに非があったようにも受け取れる。
想い出がつまった部屋を今度は自分も出て行こうとするのはいいが、ドアの鍵をおろして涙がこぼれるのはナルシシズムに少し酔ってはいないか。己の言動を振り返って悔い改めるというようなことはしないのか。
そんな自己中心的な態度だから、案外すぐに前へ向き直ることが出来るのかもしれない。気持ちを切り替えて春を待つ心境になれたのだろう。何だか安易な気もするが…。
以上、私の勝手な解釈である。登場する男に少し手厳し過ぎるかもしれない。でも、どうしてもそう感じてしまう。
いい歌であるが、歌って練習してみると案外難しいところがあった。
 Loading...
Loading...