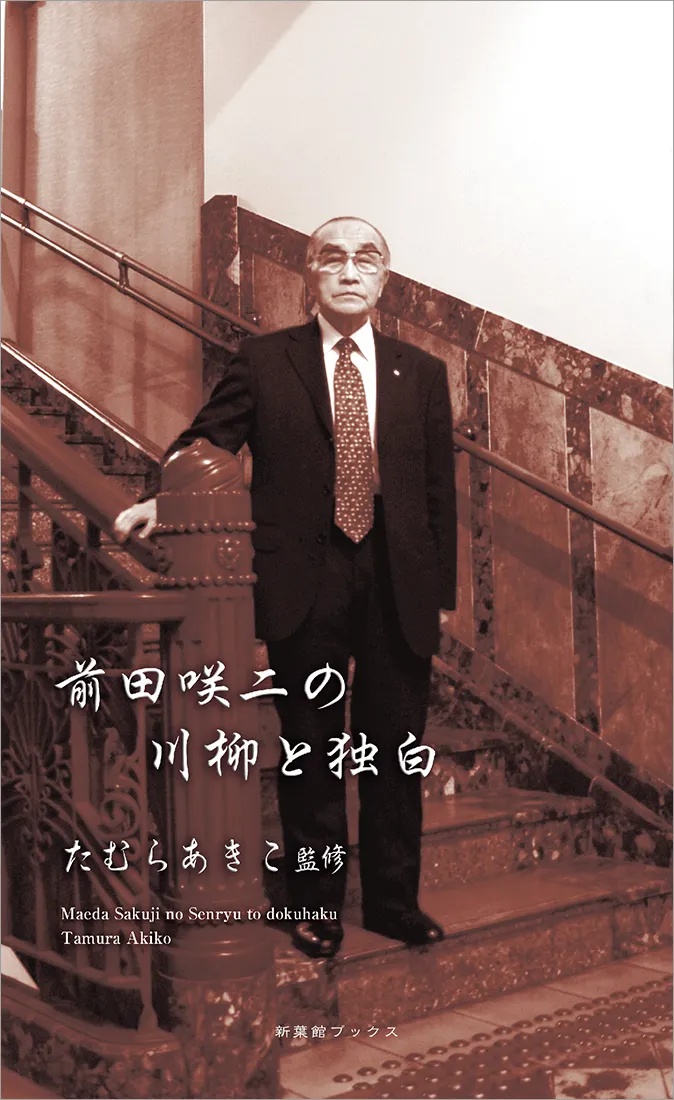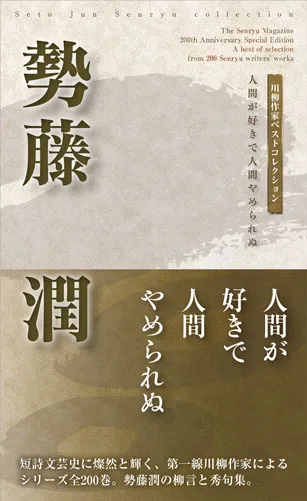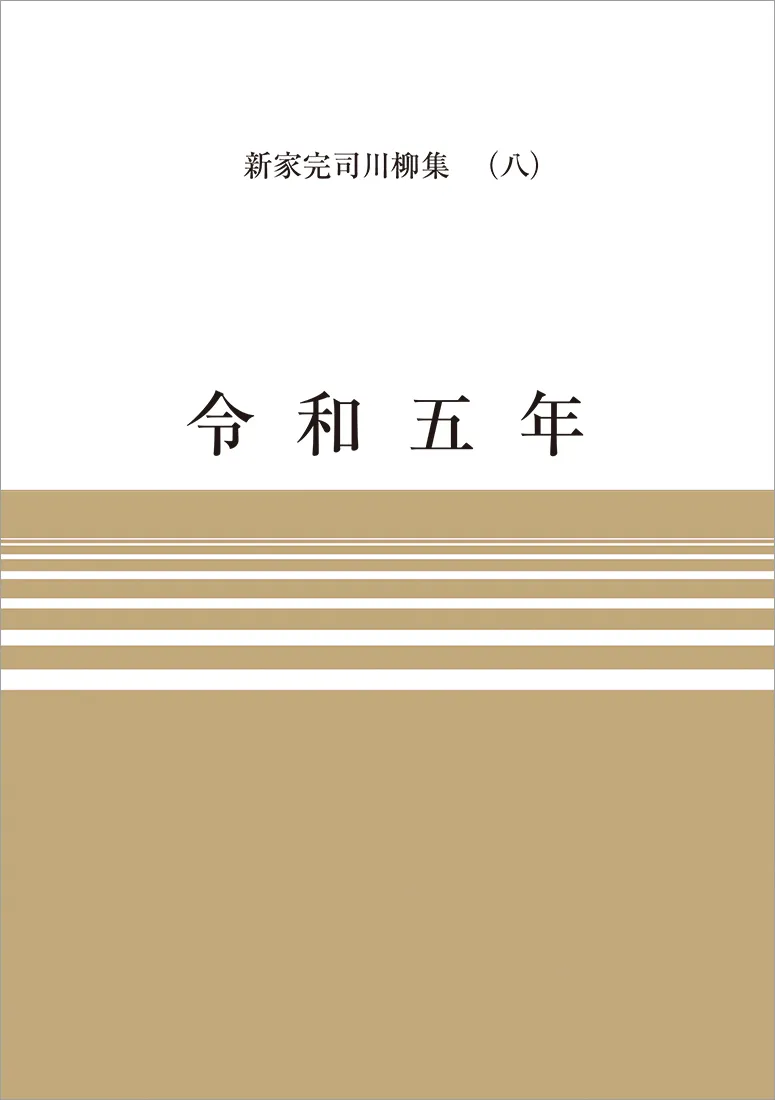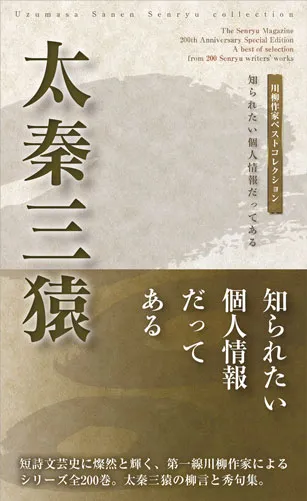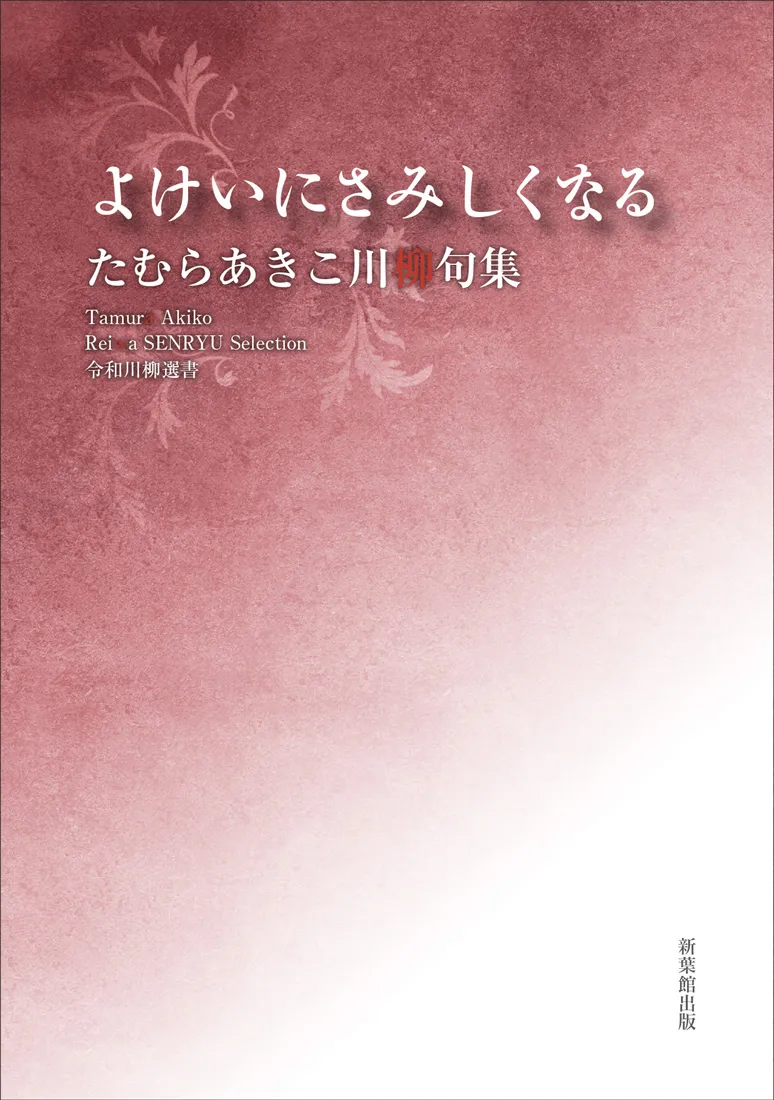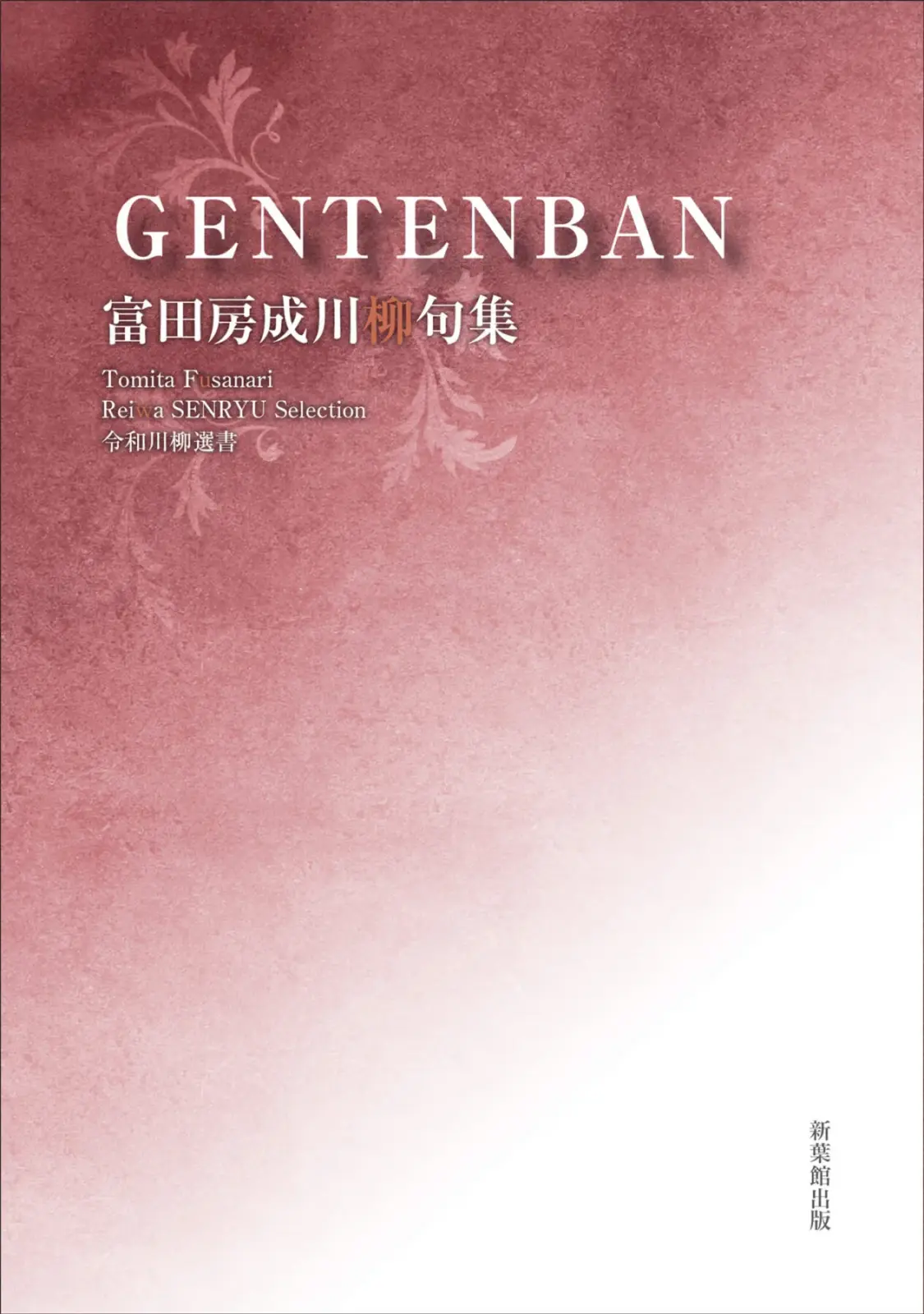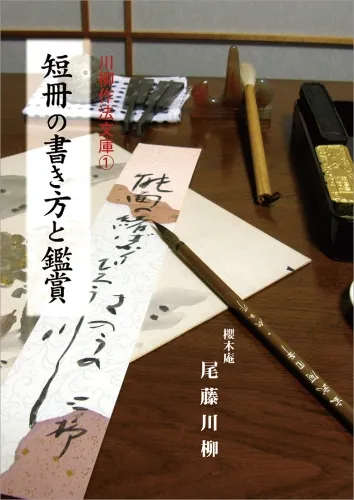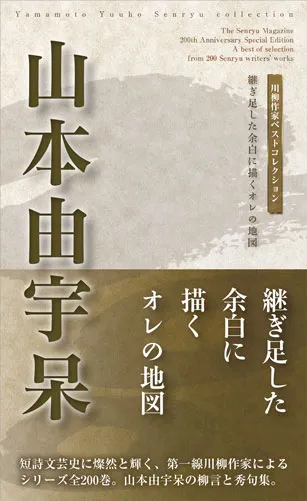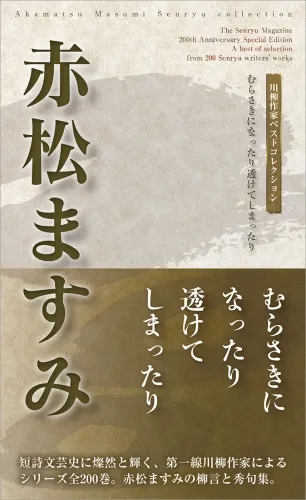あるメジャーな文学賞の選考で、一人の委員がいつも選評の中ですべての候補作品を酷評していた。ひどい時にはタイトルまで、意味が分からないなどと貶すこともあった。毎回そのような厳しい態度をとっていたので、そんなに気に入らないものばかりなら、選考委員を辞退すればいいのに、といつも私は思っていた。
そもそも文芸というものは、いくら客観的に評価しようとしても限界がある。ある作品について絶賛する者がいれば、クソミソに貶める輩も必ずいる。一体どちらが正しいのか、それをはっきりさせることは土台無理である。
人間は誰でも好意的な態度と悪意のある面を併せ持っている。気分がいい時は優しく好意的、不機嫌な時は厳しく悪意的、そういう側面は誰でも持っているはずだ。
川柳作品の選考で膨大な句箋を読まなければならない時がある。最初の粗選は、いかにケチをつけて振り落とそうかという姿勢で私は一枚一枚の句に向き合う。悪意的と言ったら語弊があるが、かなり厳しい見方をするのである。
さらに粗選から規定の入選句に絞り込む場合は、翻って極めて好意的にそれぞれの句と向き合う。急に悩ましくなってくる。選から落とすのに躊躇いが出たりする。そこから特選句を選ぶとなると、悩ましさは倍加される。結局私の好み、私の実感にフィットとするものを選んでいることに気づく時もある。
私の選句作業とは、厳しさと優しさが妙に混ざり合って、それがそれなりにバランスを保っているのである。
件の文学賞の選考委員のように、最初から最後まで全否定ということはあり得ない。
 Loading...
Loading...