大学生の頃、桑原武夫(フランス文学者・京大教授/1904-1988)の論じた第二芸術論のことを知った。学校で教わった俳句や短歌などにあまり面白味を感じていなかったので、なるほどそのとおりだと共感したのである。
1946年に発表された「第二芸術 ―現代俳句について―」(岩波書店の雑誌『世界』に所収)は、戦前の鬼畜米英、国体の護持などの価値観がすべてひっくり返された終戦間もない時期に、現れるべくして現れた怪物のような衝撃だったのかもしれない。
俳句を「第二芸術」として他の芸術と区別すべきと論じ、当時の俳壇に大きな論争を巻き起こした。既に承知している方も多いと思うが、以下、ウィキペディアから改めて紹介する。
〈この論文では桑原はまず作者名を伏せたうえで、大家の作品のなかに無名の作者のものを混ぜた15の俳句作品を並べ、作品からは素人と大家の優劣をつけることができないとする。ここから俳句においては大家の価値はその党派性によって決められるものであるとして批判し、また近代化している現実の人生はもはや俳句という形式には盛り込みえず、「老人や病人が余技とし、消閑の具とするにふさわしい」ものとして、強いて芸術の名を使うのであれば「第二芸術」として区別し、学校教育からは締め出すべきだという結論を導き出している。
桑原の挑発的な論調もあってこの論文は俳人たちの間で多くの反論を引き起こした。主な論者は山口誓子、中村草田男、日野草城、西東三鬼、加藤楸邨などで、山口と桑原は毎日新聞紙上で「往復書簡」のやりとりをしている。反論側の要旨は俳句の党派性などの弊害をある程度認めつつ、桑原の鑑賞力の低さや俳句に対するそもそもの非好意的な態度を批判するもので、中でも中村草田男が激しい反論を行った。戦後の当時は俳人たちも俳句のあり方を模索していた時期であり、この論争はその後社会性俳句運動などが生まれる遠因ともなった。〉
この文章に出合ってから、当時の私は俳句をはじめとする短詩型に改めて全く興味を示さなくなった。俳句や短歌とは、いずれは衰退していく年寄の暇つぶしのものであると、第二芸術論に100%賛同、いや洗脳されたのかもしれない。しかしその後しばらく経って、サラリーマン川柳と出合ったことがきっかけで、俳句と兄弟関係にある川柳にのめり込んでいった。その経緯は「川柳マガジン」(2020年3月号)の『柳豪のひとしずく』に書いたのでここでは省く。
さて、ある偉い裁判官の人が「俳句は単に事実を述べただけのものである」と自分なりに見抜いた。その話しを聞いた時、私は、法律の世界はすべて理屈で成り立っているので、それを職業にしている人から見るとなるほどそう思えるのかと解釈した。また別の時に、ある弁護士の方が、ある川柳鑑賞の文章を読んで「これは事実を説明しただけでそれ以上のものは何もないのではないか」と宣ったのである。句を鑑賞するとは読む方の力量が問われるものであるが、その弁護士はそういった観点から鑑賞文を味わおうとはしなかったのであった。偶然にもこの二つの話しを聞いて、法律家の考え方(合理性)と短詩型文芸とは相容れないところがあるのだなとしみじみ思った次第である。
法律関係の人に短詩型文芸のおもしろさを無理に分かってもらうつもりはないが、短詩型文芸の作品には、事実(記述と言ってもいい)以上のものが常に熱量として内包されている。内包しているから韻文として成り立つのである。そこを自分なりに読み込めないとそもそものおもしろさは味わえない。事実を超えたもの、あえてフィクションとまでは言いたくないが、そういったものと緊張感を響かせているのが韻文なのである。
それが曖昧なままですっきりしないから、華道や茶道などの芸事の流派、家元制度のように師弟関係(師系)が大事にされ、結果的に黴の生えた権威主義に陥って時代遅れの第二芸術と貶められたのではないだろうか。
短歌における俵万智や俳句における黛まどかのように、新風を巻き起こす革新的な作家が出現したのは、そういう伝統・保守性を打破しようとする必然のマグマが溜まっていたと解釈できるだろう。川柳についても同じことが言える。
川柳は、短歌や俳句と違って口語で詠まれ、約束事が少ないことからそもそも自由度が高いと言えるが、価値観や作風について若い世代の感覚を大事にしないと旧態依然のものとして、第二芸術以下の埃っぽい第三芸術に成り下がってしまうかもしれない。川柳の強みは、他の二つと比べて、まず作者ありきの作品鑑賞をしないところにある。無名の作家の作品を掘り起こして評価することも多い。これらの反権威主義的な姿勢はずっと守っていきたい。
改めて言うが、俳句にとっての第二芸術論は川柳に対しても他人事ではない。六大家の作品と無名作品を並べて一般人に良し悪しの判定をさせたら、六大家の方が評価されないこともあるかもしれない。六大家の作品が安易に添削されてしまうかもしれない。キャッチーな言葉に溢れているデジタル情報化社会においてなおも伝統な考え方に拘っていたら、現代川柳が衰微していくことは目に見えている。
AIが俳句を詠む時代がいつか来るだろう。桑原武夫の論考を真似して、AIと著名俳人と無名俳句愛好者の三者の作品(前二者は秀句、後者は駄句)をシャッフルして並べ、その優劣を論じたらAIが圧勝した、なんてことが起きるかもしれない。テレビ番組として企画されてもおかしくないだろう。囲碁や将棋の勝負事の世界だけでなく、小説などの散文を含めた文芸の世界にもAIは必ず侵入してくるはずだ。その時、川柳は原点に立ち返って、穿ち・軽み・可笑しみの三要素を武器に応戦すべきだと考えている。AIに、川柳は俳句より手強いと思わせたい。
 Loading...
Loading...






























































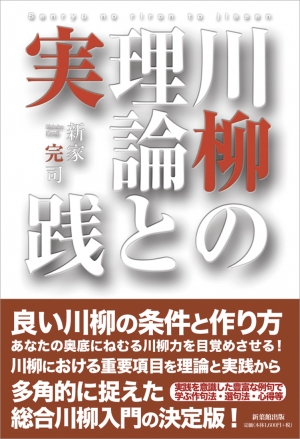


















>AIに、川柳は俳句より手強いと思わせたい。
さいご、笑ってしまいました。
川柳人の意地ですよね、笑。
読み応えのある文章、参考にさせていただいております。
ありがとうございます。
ずうっと思っていたことを書いてみました。